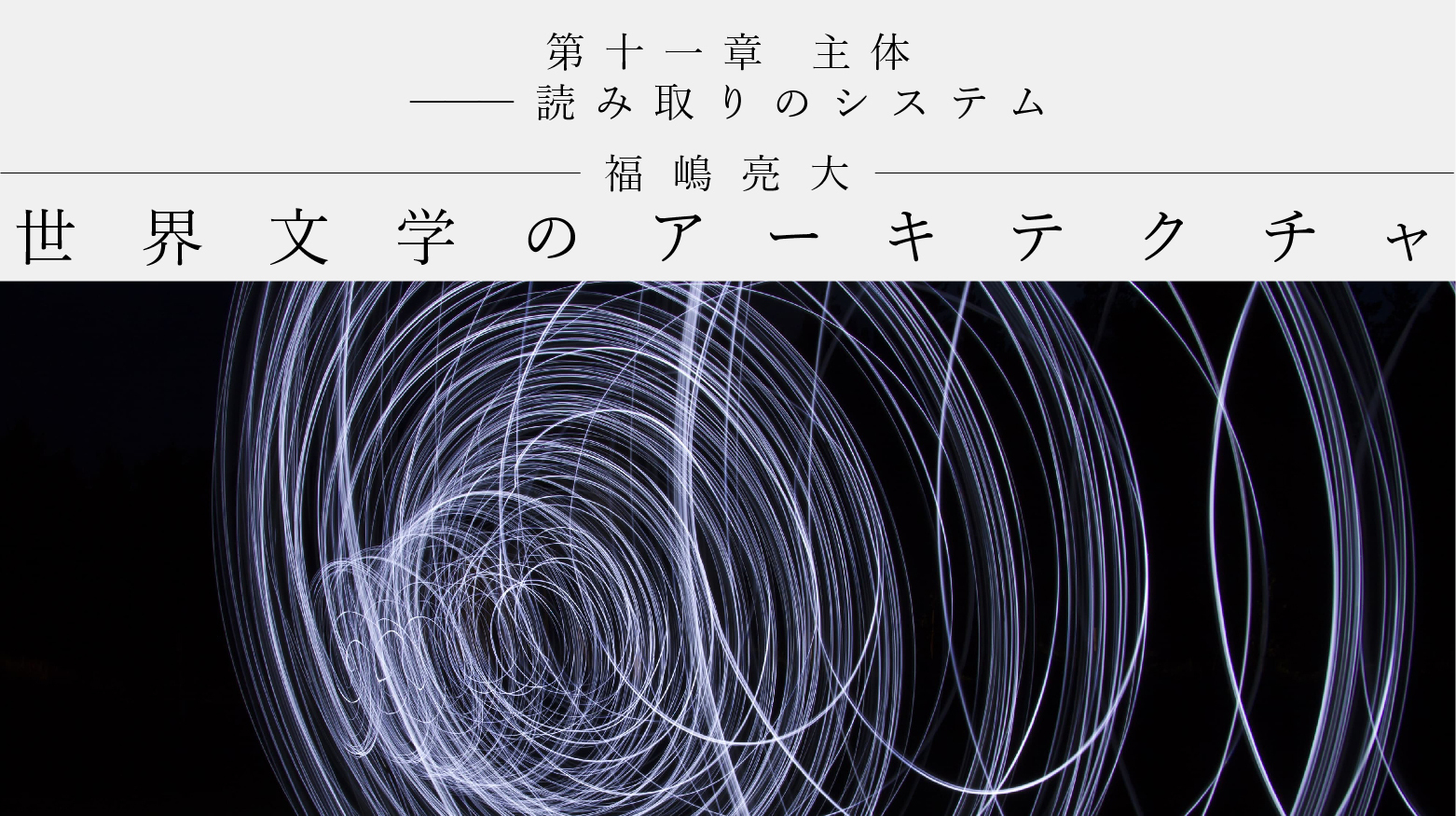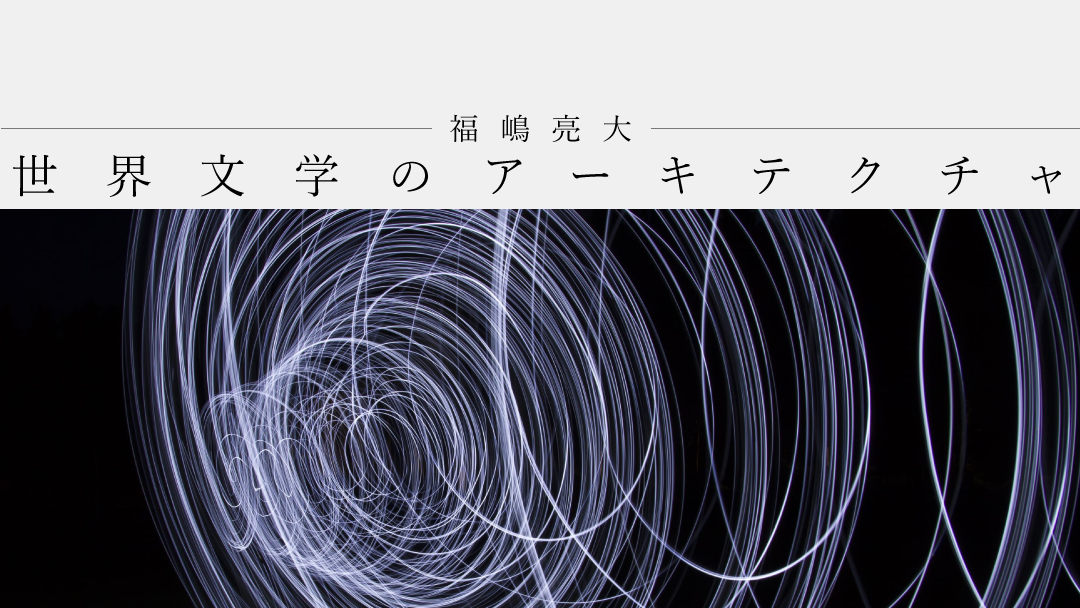
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、一か二か
ルソーが自伝文学『告白』の冒頭で「わたしひとり。わたしは自分の心を感じている。そして人々を知っている。わたしは自分の見た人々の誰とも同じようには作られていない」と大胆不敵に宣言したことを典型として、近代ヨーロッパの文学は唯一無二の創造物である「私」の探究に駆り立てられてきたように思える。故郷喪失に続く冒険を小説の基本的なテーマと見なしたジェルジ・ルカーチも、結局は「一」なる主体をその核に据えていた。
柄谷行人が指摘したように、近代小説の根幹には「内面の発見」がある[1]。これは、他者や環境から区切られた内面が、小説の探究すべき対象になったことを意味する。ルソーの『告白』は、まさに「私」を他に依存しないスタンドアローンな存在に仕立てあげた一種の独立宣言である。
古代文学と比較すると、ルソーの宣言の意義はいっそうはっきりするだろう。例えば、古代のホメロスの叙事詩では、英雄たちの心は閉じた自我のなかに格納されず、環境の作用を強く受けていた。ホメロス的人間とは「周囲のあらゆる力の影響から人間を隔絶する境界をもたない、いわば「開かれた力の場」」なのだ[2]。逆に、カメラ・オブスクラのモデルに近似する近代小説のリアリズムは、自我の感覚の部屋(=カメラ)を、この種のボーダーレスな「力の場」から切り離した。それによって、小説は唯一無二の「私」の自己認識を深める装置として進化してきた。
ルカーチも柄谷も、「一」なる主体を近代小説の主人公の標準的形態として捉えたことに変わりはない。しかし、このモデルには修正の余地がある。というのも、小説的な主体性は実は純粋な「一」ではなく、早期から「二」への傾きを備えていたからである。
その具体例には事欠かない。『ドン・キホーテ』(ドン・キホーテ/サンチョ・パンサ)、『ペルシア人の手紙』(ユズベク/リカ)、『新エロイーズ』(ジュリ/サン゠プルー)、『ラモーの甥』(ラモー/哲学者)、『ロビンソン・クルーソー』(クルーソー/フライデー)、『闇の奥』(クルツ/マーロウ)、『ロリータ』(ハンバート/ロー)、日本文学で言えば夏目漱石の『こころ』(先生/K)、大江健三郎の『万延元年のフットボール』(蜜三郎/鷹四)、村上春樹の『風の歌を聴け』(僕/鼠)等では、単一の主体ではなくカップルが中心化される。さらに、ルソーの『ルソー、ジャン゠ジャックを裁く』、ドストエフスキーの『分身』、E・A・ポーの「ウィリアム・ウィルソン」、E・T・A・ホフマンの『砂男』、オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』をはじめ、自己を二重化する分身(ドッペルゲンガー)のテーマも、特にロマン主義以降に何度も反復されてきた。
だとすれば、小説の主体性を「一」に還元するのは妥当ではない。小説はいわば「二」のウイルスに感染しており、それが折に触れて症状として顕在化するのだ。この「一」と「二」のあいだの振幅は、小説そのものの特性と切り離せない。なぜなら、小説における「私」は他者との接触なしにはあり得ないからである。「小説は演劇ではないのだから、すべての人物を厳密にいって同時に、読者に《見せる》わけにはいかない。小説においては、人物は相互に他の人物を通してみられるのである」(ジャン・プイヨン)[3]。小説の自我(ego)は他我(alter ego)の介入を必要とする。そこに、「一」なる主体が潜在的に「二」への分裂を含む要因がある。
ミハイル・バフチンは、小説における他者の介入に「対話的」という形容を与えた。バフチンの理論では、小説は複数の声の遭遇や衝突の場として了解される。ただ、私は「二」を「対話的」というより「読解的」な問題として考えたい。結論から言えば、近代小説は他者や世界を読むことの発明と不可分だからである。以下では「一」と「二」のあいだをさまよう主体の歴史を整理しながら、小説的主体を《読み取りのシステム》として把握することを試みる。まずは「二」の問題から始めよう。
2、書簡体小説の啓蒙的機能――近況報告あるいは権力のホログラム
一八世紀ヨーロッパを代表する小説が書簡体で書かれたことは、コミュニケーション(自我と他我のカップリング)が近代小説の基盤にあることを示唆する。もともと書簡文学の伝統は、医師ヒポクラテスの名を冠した古代の架空の書簡集(ヒポクラテス・ロマン)や中世の『アベラールとエロイーズ』等にまで遡れるが、一八世紀になるとそれは啓蒙思想の有力な手段として再創造された。
書簡体小説の金字塔と呼ぶべきモンテスキューの『ペルシア人の手紙』は、ヨーロッパとアジアのあいだの異文化コミュニケーションを主題としながら、開明的な貴族ユズベクと若く生気に満ちたリカという二人のペルシア人を対比的に登場させた(第三章参照)。モンテスキューはここでペルシアとフランス、年長者と若者という二組のカップルを交差させたが、それを手紙というテレコミュニケーション・メディアで実行したところに彼の創意工夫がある。
モンテスキューの創作した手紙は、カップルを結びつける一方、その両者の差異や異質性も浮き彫りにする。モンテスキューは異邦人の仮面をかぶり、フランス社会に対してわざと無知のふりをすることによって、その体制に加担せず、悪しき因習を暴露した。バフチンによれば、この「変わり者」の人物像の「分からない」という態度こそが、モンテスキューの発明であった[4]。小説とは分からないこと、不可解であること、愚かであること、変わり者であることを積極的に利用して、社会の自明性を懐疑するジャンルである。『ペルシア人の手紙』の大量の通信は、まさに変わり者=異邦人の態度に根ざしながら、見慣れた社会を見慣れないものに変えた。
さらに、モンテスキューの書簡体の採用には、明確な方法論的な企図があった。彼自身、書簡体小説の利点を具体的に説明している。
そもそも、この種の小説は、たいてい成功を収めるものだ。なぜなら、人物がみずから近況を報告するからである。このやり方は、人が語ることのできるどんな物語よりも、きちんと情念を伝えてくれる。〔…〕書簡集の形式では、役者たちは決まっておらず、扱われる主題は前もってあたためられたどんな意図や計画にも左右されないため、一つの小説に哲学や政治や道徳を盛り込み、全体を秘密の鎖で、ある意味では未知の鎖で束ねるという特権を著者は手に入れたのだ。(「『ペルシア人の手紙』に関するいくつかの考察」)
現代のEメールやインスタントメッセージでも、そのやりとりはほぼ「近況報告」によって占められている。この種の報告では、語りの首尾一貫性や事前の入念の計画性よりも、相手にそのつど情報や感情を伝える即興性が優位に立つ。モンテスキューは架空のペルシア人たちがパリの異文化に出会ったときの新鮮な驚きを擬態し、脱線もおおらかに許容しながら、哲学や政治の話題にフレッシュな生命を与える。思想をその誕生の瞬間に差し戻すこと――それが書簡体小説の効果である。
その一方、モンテスキューは書簡が届くまでの「時差」も巧妙に利用していた。フランスとペルシアの遠さゆえに、ユズベクが故郷に手紙で発する命令は遅延し、有効に機能しない。そのため、彼は絶対的な権力者であるにもかかわらず、ペルシアのハーレムで起こった女たちの叛乱を制御できない。この無力さは、彼が手紙の通信のなかでのみ立ち現れる、いわばホログラム的なヴァーチャル・リアリティ(VR)であることに起因する。
そもそも、パリでアイドルとなった若いリカとは違って、年長のユズベクは消費社会の見かけ(仮象)に騙されないように警戒している。つまり、ユズベクにはオーセンティックなもの(本物)への意識がある。しかし、手紙で語られる自己とは、むしろ記号的な「見かけ」しかないホログラムに似た存在ではなかったか。手紙は他者を操作し、望ましい状況を作り出そうとするが、その戦略はたやすく誤解されたり改竄されたりする。いかなる強大な専制君主であっても、見かけだけの《手紙内存在》として現れるときには、そのリスクを回避できない。ここには本質的な脆弱性がある。
要するに、手紙は権力の増減、権力のキャンセル、権力のねじ曲げの発生する戦場であり、書簡体小説とは権力を乱高下させるゲームなのである。テリー・イーグルトンはそれをうまく説明している。
手紙は、主体の秘密をあかすもっとも生々しい記号であるがゆえに、干渉を受け、捏造され、奪われ、失われ、書き写され、引用され、検閲され、パロディにされ、曲解され、書きなおされ、からかい半分の注釈にさらされ、別のテクストに織り込まれることによって意味の変質をこうむり、書き手が予想だにしなかった目的のために使われる。[5]
現代でも、流出したメールは週刊誌的なゴシップの格好のネタになる。手紙は人間の隠された秘密を生々しく語る一方で、他者によってたやすく曲解されパロディにされ、権力者の威厳を失墜させる。一言で言えば、手紙とは神経過敏なメディアであり、限りなく「私」に近いのに、同時に「他者」の干渉にさらされている。
このような手紙の特性を踏まえると、モンテスキューが書簡体小説を啓蒙のプロジェクトに利用したのも、当然と言えば当然のことに思える。改めてポイントを二つにまとめよう。
第一に、手紙はよそもの(他者)の目から見た即興的でタブーのない近況報告によって、フレッシュな社会批評となる。比較人類学的な思想書『法の精神』の著者らしく、モンテスキューは『ペルシア人の手紙』でも法や文化の相対性を読者に強く意識させる[6]。ヨーロッパからペルシアを観察し、ペルシアからヨーロッパを観察する『ペルシア人の手紙』は、他者に自己を映し出すプロジェクトの記録にほかならない。しかも、このプロジェクトを支える手紙は、しばしば接続不良に見舞われ、混乱を助長するのだ。
第二に、手紙はその送信者を脆弱なホログラムに変える。権力者ですら、その例外ではない。書簡体小説では、他者がいなければ自己もない。つまり、送信者も受信者も、他者の地平のなかに、自己を出現させなければならない。相手からの返信によって、自己がどんな人間かがはじめて了解される。だからこそ、発信者は受信者の思想を占拠し、望ましい自己をそこに出現させようとする。他者を支配することと他者に支配されることが、次第に見分けがたくなること――そこに書簡体小説の特性がある。
3、読むことの公共性――リチャードソンからルソーへ
テリー・イーグルトンが指摘したように、書簡体小説では自己の最も大切で、ある意味で脆い秘密の部分が、たえず親密な他者に向けて流出してゆく。この点で、書簡体小説はかけがえのない真実性への意識を強める効果がある。
一八世紀イギリスの作家サミュエル・リチャードソン(モンテスキューと同じ一六八九年生まれ)は、まさにこの手紙の「現実効果」を利用した。彼の書簡体小説『パミラ』(一七四〇年)、および驚くほど長大な『クラリッサ』(一七四八年)には、女性の心理が詳細に書き込まれている。主人公クラリッサの家族は貴族社会への参入を望み、伯爵のラヴレースに接近するが、クラリッサはその彼に監禁されて売春宿に送られ、ついには凌辱される。それでも節を曲げず、ラヴレースの求婚を断り続けたクラリッサには、しかし病ゆえの死が待ち受けていた。
リチャードソンの『クラリッサ』を絶賛したディドロは、その詳細な細部のもつ豊かな表情を「イリュージョン」と評した[7]。リチャードソンの文体は心理の解像度がきわめて高く、繊細なニュアンスに富んでいた。ディドロがそこに認めたのは、通常の現実を飛び越えた、ほとんど眩暈をもたらすようなハイパーリアリティである。つまり、リチャードソン的な手紙は、いかなる真実らしさも超越する最上の真実性を表現しており、だからこそそれはかえってイリュージョンに近づいたのである。
その一方、イーグルトンによれば、当時有数の印刷業者であったリチャードソンは、新興の商人階層を代表し、貴族に闘争を挑んだ「有機的知識人」であった。彼にとって、小説の出版はたんなる娯楽の提供にとどまらず、女性の読者をも巻き込んだ「対抗‐公共圏」の創設に結びついていた。強烈な感情移入を伴いながら、社会の抑圧や不正を訴える彼の書簡体小説は、貴族の権力を切り崩す戦闘の旗印になった。リチャードソンの言うセンティメント(感傷)は、たんなる感性の敏感さではなく、むしろ「倫理」に近いものとして理解されねばならない[8]。
ゆえに、リチャードソンにおいては「政治と文学」のあいだに矛盾はない。その後も、ルソーの『新エロイーズ』からドストエフスキーの『貧しき人々』に到るまで、書簡体小説のもつ感傷性は、社会の片隅で埋没しかかっている不幸や悲劇を、鋭敏につかみとる倫理とつながっていた。リチャードソンのセンティメンタルな書簡体小説は、社会問題を読者とシェアし、それによって支配層のイデオロギーを相対化しようとする戦略の先駆けだと言えるだろう。
さらに、このリチャードソン的な情緒の倫理は、ルソーの小説においてはシンパシー(共感)を強化する方法論と結びついた。歴史家のロバート・ダーントンは、手紙や本を「読むこと」に熱中する『新エロイーズ』の主人公たちについて、こう述べている。
〔『新エロイーズ』において〕生きることは読むことと区別できず、恋することは恋文を書くことと区別できない。事実、恋人たちは愛し方を教えあうのと全く同じように、読み方を教えあう。サン゠プルーはジュリにこう勧めている。「わずかしか読まず、読んだことについては十分に考えること、あるいは同じことですが、それについておたがいに十分語りあうこと、これがよく消化する方法です」。[9]
ルソーはサン゠プルーの口を借りて、書物との接し方を変えるように読者に助言している。『新エロイーズ』の画期性は、読者をテクストの内部に誘導し、自らのライフスタイルをも変えるように方向づけたことにある。因習的な文学と縁を切りながら、新たな読書法を示すルソー的教育学は、平凡なブルジョアの読者たちに強い共感とともに受け入れられた。ダーントンが言うように、ルソーは「作者と読者、読者とテクストとの関係を変えてしまった」[10]。
実際、『新エロイーズ』の読者はルソーを親しい「友人」と見なし、ジュリとサン゠プルーの悲運に深く同一化した。つまり、通常の距離を壊すようにして、『新エロイーズ』の周囲には新たな精神的共同体が形成されたのである。ここには、シンパシーさらにはテレパシー(遠隔感応)に通じる問題がある[11]。書簡体小説においては、登場人物も読者も《読み取りのシステム》として組織される。この読解の精度があがると、テクストの外の読者は会ったこともないルソーや架空のジュリやサン゠プルーとまで、まるで長年の友人のように、心をテレパシー的に通じあわせるだろう。こうして、『新エロイーズ』では「読み」に向かう心の動きが無尽蔵に拡大し、ついにはテクストの内と外までもがボーダーレスに結びつけられる[12]。
近代小説における「二」のテーマの原点には、作者と読者の関係がある。親密な「友人」のような他者の書いたテクストを読むこと――それは小説の主体性を根拠づけるとともに、読者との共同性の源泉にもなった。リチャードソンやルソーの書簡体小説は、読むというコンタクトの技術を拡散し、手紙の言葉をときに本物以上に本物らしいイリュージョンとして体感させた。この高度な錯覚が、一種のテレパシー的公共圏の創設につながったのである。
4、感覚の鋭いアウトサイダー――世界を読むピカレスクロマン
ここで「一」の小説の系統に目を転じよう。その先駆けとなったのは、一六世紀のスペインで発達したピカレスクロマン(悪漢小説)である。一四九九年に刊行されたフェルナンド・デ・ロハスの悲喜劇『セレスティーナ』を先触れとして、作者不詳の『ラサリーリョ・デ・トルメスの生涯』(一五五三年頃)、マテオ・アレマンの大作『グスマン・デ・アルファラーチェの生涯』(一五九九年)、フランシスコ・デ・ケベード――当時の第一級の知識人であり、その洗練された思索的・技巧的な文体は「刀や銀の指輪のような物体」(ボルヘス)とも評される[13]――の『ブスコンの生涯』(一六二六年)等が、その代表作として挙げられる。
ピカレスクロマンの特徴は、下層階級出身のアウトサイダー(ピカロ)が、自らの生涯にわたる遍歴を一人称で語りながら、社会の諸相を浮かび上がらせたことにある。この一人称的な「視点」の獲得は、小説史の転換点となった。スペインの文献学者フランシスコ・リコによれば、ピカロという視点を得た新しい文学は、伝統的なコードによって世界を了解するのをやめ、特定のとき・特定の場所・特定の人間に基づいて世界を観察し始めた。そのとき、社会的なリアリティは一元化されず、それぞれの視点に応じて変容することが、はっきりしたのである[14]。
ロハスの『セレスティーナ』は形式的には演劇ではあるが、登場人物たちがまさに自らの「視点」から複雑で込み入った心理を語る、近代小説の先駆けとしての一面があった。老女セレスティーナは、男女の色事の仲介業や娼婦のマネジメントをやりながら、さまざまなあやしげなビジネスにも手を出す戦略家である。彼女は道徳的な悪人というよりは、頭脳的な経済人であり、さまざまな悩みも抱えながら、社会のアンダーグラウンドで生き延びるための戦略や計算をたえず思いめぐらす。
このような感覚の鋭さは、その後のピカレスクロマンのアウトサイダーたちも特徴づけている。例えば、『ラサリーリョ・デ・トルメスの生涯』の主人公=語り手のラサリーリョは、もともと黒人奴隷を継父とするが、母とも別れて無一物の孤児となった後、老いた盲人に引き取られる。明敏にして強欲なこの盲人をはじめ、さまざまな主人たち――聖職者や下級貴族――がラサリーリョを受け入れるが、彼はそのいずれをも無遠慮に評価してゆく。社会的な後ろ盾をもたないからこそ、ラサリーリョは一種の変わり者=異邦人として、主人たちの腐敗や無慈悲さ、いかさまを暴くことができる。
バフチンによれば、文学上のピカロ(悪漢)は道化や愚者と同じく「この世界に現にある実人生のなかの、いかなる地位・いかなる立場にも連帯せず同調しない」[15]。つまり、ピカロは地位も財産ももたないからこそ、その行動によって鋭い社会批評を実践する。実際、ラサリーリョの考えでは、人間の才覚は飢えによって研ぎ澄まされる。「飢えは私を導く光明であったと確信しています」[16]。これははるか後のドストエフスキーの書簡体小説『貧しき人々』を思わせる(前章参照)。『ラサリーリョ』がドストエフスキーのはるか以前に「貧しさ」や「もたざること」を認識の方法に高めたことは、特筆に値するだろう。
さらに、『ラサリーリョ』を意識した『グスマン・デ・アルファラーチェの生涯』になると、自伝のスタイルのなかに、より多面的な社会批評が書き込まれた。セルバンテスと同年に生まれ同年に亡くなった作者のマテオ・アレマンは、この大作をいわば賢い不良の文学に仕立てた。語り手=主人公のグスマンをはじめピカロたちは、悪辣な人間というよりも、多くの知識と鋭い感受性を武器にして、社会の欺瞞を見抜く俊敏な批評家である。彼らは言葉を尽くして、知識のすばらしさを褒めたたえる。
いかなる場合でも、富より知の方が優っている。何故なら、仮りに運命の女神あるいは財産が人に背いたとしても、知識は決して人を見捨てたりはしないからです。〔…〕幸運や富など、何かちょっとした出来事によって壊され、奪い去されてしまいますが、消滅したものや見離されてしまったものを、知識はいとも簡単に修復してしまいます。まさに知識こそ、この上なく豊かに開かれた鉱脈であって、望む者はそこから、尽きることも涸れることもない大河の水のごとき無限の財宝を掘り出すことができるのです。[17]
富をもたないピカロたちは、酒場を「公開講座を開いている大学の講堂や教室」のようにして、時事問題について活発な議論を繰り広げる――そのとき、違法者の彼らこそが、酔っぱらった「立法者」に変身するだろう[18]。そもそも、ピカレスクロマンの流行した一六世紀のスペインでは、新世界の植民地獲得をきっかけとして一種の言語革命が進んでいた。この荒波のなかで、ピカロたちはその旺盛な言語の力で、現実を新たに作り出すことに向かったのである[19]。
書簡体小説における読み書きの行為は、手紙というフレームに格納されていた。それに対して、より古い『ラサリーリョ』や『グスマン』のようなピカレスクロマンでは、すでに「読むこと」と「書くこと」の対象は広く外界に及んでいた。ピカロたちはさまざまな主人に仕えては、その綻びや欺瞞をすばやく読み解く――ちょうど現代のネットサーフィンのように。書簡体小説が作者と読者という「二」の構図を守るのに対して、ピカレスクロマンでは「一」の主体が、世界の近況を異邦人の視点から読み、報告し続けることになる。
5、メタピカレスク作家としてのセルバンテス
このようなピカレスクロマンの隆盛に対して、マテオ・アレマンの友人であったセルバンテスは、『模範小説集』(一六一三年)に収めた諸短篇で興味深い反応を示した。例えば「犬の対話」では、シピオンとベルガンサという二匹の犬が、膨大な知識をもつおしゃべりな哲学者となり、スペイン社会の「主人」たちを論評する。セルバンテスはピカロの役割を犬に与えながら「犬に哲学者ぶらせ、この犬の仮面の下でかつてなく本人に近い形で」(ミシェル・ビュトール)語ったのだ[20]。
さらに、「ガラスの学士」は流行のピカレスクロマンの影響を受けつつ、それをパロディにした傑作である。大学生のトマスは重病から回復した後、自らの身体がガラスになったと妄想的に思い込む。ガラスという「繊細にして緻密な物質」と同一化し[21]、いかなる難題にもすぐに的確な答えを出すトマスの狂気じみた知性は、カスティーリャじゅうで話題になり、ありとあらゆる職業が彼の論評の対象になる。しかし、狂気が治療された後、トマスは経済的に困窮して、飛躍を求めて戦争に出るもののあえなく戦死してしまう。トマスの頭脳は『グスマン』のピカロたちと同じく大量の知識を収蔵しているが、その知のコレクションはガラスのように繊細で脆く壊れやすい。セルバンテスはそれを狂気のテーマに即して、巧みに造形した。
セルバンテスの批評性はもっぱら、騎士道文学をパロディにしたメタ騎士道文学の『ドン・キホーテ』に基づいて語られてきた。しかし、彼には『模範小説集』で、ピカロを犬やガラス人間に置き換えた「メタピカレスク」の作家という一面があったことも忘れてはならない[22]。それに『ドン・キホーテ』にしても、騎士道文学だけでなくピカレスクロマンとの差異が重要である。もともと、セルバンテスの物語理論はアレマンに多くを負っており、それなしでは『ドン・キホーテ』のリアリズムもなかった。しかし、セルバンテスが向かおうとしていた新たな文学には、アレマンの『グスマン』のような語りはもはやふさわしくなかったのだ[23]。
実際、『ドン・キホーテ』はピカレスクロマンの「一」の自伝的(一人称的)な主体に対して、伝記的(三人称的)に語られる「二」の主体を創出した。狂気に駆り立てられるドン・キホーテは、サンチョ・パンサとカップリングされるからこそ、ガラスの学士のように自滅することはない。しかも、スペインの哲学者マダリアーガによれば、このカップルは冒険が進むとともに「魂の兄弟愛」を深め、ドン・キホーテはサンチョ化し、サンチョはドン・キホーテ化してゆく[24]。『ドン・キホーテ』は「二」への分裂と「一」への融合という運動を内包していた。
セルバンテスはピカレスクロマンの臨界点において、螺旋状の運動を加速させた。彼のメタピカレスクにおいては「一」に収納しきれないエネルギーが渦巻いている。「ガラスの学士」ではその過剰なエネルギーが主人公を自己破壊的な狂気へと導き、「犬の対話」ではそれがおしゃべりな犬たちの会話に変換され、『ドン・キホーテ』は『ドン・キホーテ』という書物そのものを増殖させる。ピカロの冒険は、スペイン社会の「主人」たちへの批評の旅であった。それに対して、ドン・キホーテの冒険はただ社会をサーフィンするだけでなく、しばしば自らの観念に対する自己言及のゲームへとねじ曲げられる。
もとより、冒険は決して無条件に成立するのではなく、それにふさわしい《世界》を必要とする。一八世紀の初期グローバリゼーションは、冒険の舞台となる《世界》を大西洋およびアメリカと関連づけ、ロビンソン・クルーソーやガリヴァーのような小説的形象を生み出したが、それは過剰なエネルギーを逃がす場所としての外部=海が発明されたことと等しい。逆に、それ以前のセルバンテスは過渡期の作家であり、海の手前に留まった。彼のメタ騎士道文学やメタピカレスクロマンは、いわば内部に向かってとぐろを巻くようにして、観念の激しい運動を閉じ込めた。このバロック的な迷宮は、一六世紀のピカレスクロマンと一八世紀の近代小説の「あいだ」に生まれた奇観なのだ。
6、教師あり学習――ゲーテのビルドゥングスロマン
もっとも、セルバンテス以降もピカレスクロマンの影響力は持続し、一八世紀のヨーロッパではときに女性のピカロも登場した。デフォーの『モル・フランダース』にせよ、サドの『ジュリエット物語あるいは悪徳の栄え』にせよ、その主人公はいわば不良の女性である。特に、悪の快楽に染まったジュリエットは、美徳を象徴する妹ジュスティーヌとは対照的に、ヨーロッパの各地を旅して破壊の限りを尽くす。ジュリエット一行が道中で目の当たりにしたイタリアの火山は、まさにその放埓なエネルギーの象徴であった。
その反面、ピカレスクロマンの主人公には成長や発展の契機は乏しかった。一人称の視点を備えたピカロは、さまざまな社会環境を遍歴するが、それはしばしば単調でパノラマ的な反復に陥った。場面が劇的に変化しても、主人公はそこをサーフィンするだけで内面的な成長にはつながらない――それはピカレスクロマンだけではなく、クルーソーやガリヴァーのような一八世紀型の主人公全般に当てはまる傾向である。
この限界を超えるようにして、一八世紀後半以降になるとドイツ語でビルドゥングスロマン(Bildungsroman/「教養小説」や「成長小説」と訳される)と総称されるジャンルが、精神的な「発展」のテーマを浮上させた。人間の隠れたポテンシャルを探り当て、生物のように成長させて自律的な存在に到らせること――それがビルドゥングスロマンの企てである。その中心地のドイツでは、一七世紀のグリンメルスハウゼンの『阿呆物語』をはじめ、一八世紀後半にヴィーラントの『アガトン物語』やノヴァーリスの『青い花』が現れた。なかでも、ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』(一七九六年)は、ビルドゥングスロマンの標準的形態として評価されてきた。
ジャンル論的な観点から言えば、ゲーテが『ヴィルヘルム・マイスター』以前に、書簡体小説からの離脱を促したことが重要である。彼の初期のベストセラー『若きウェルテルの悩み』(一七七四年)は、形式的には書簡体小説であるものの、その内容は激情型のウェルテルの一方的な語りによって占拠されており、書簡相手とのコミュニケーションを欠く。ウェルテルは他者の書簡を読む代わりに、たとえ話をたびたび用いて、自らの語りの意味を重層化することを試みる。つまり、彼の手紙はあくまで自己内対話の記録なのである。
ゆえに『ウェルテル』は「書簡体構造の崩壊」を鮮明にする一人称の告白小説に近づく[25]。書簡体小説の時代の終わりを、これほどはっきり示した作品は他にない。加えて、ウェルテルはピカレスクロマンを導く下層のアウトサイダーでもなかった――ルカーチが言うように、ウェルテルはむしろ「高貴な情熱」を純粋化した挙句に、社会の法体系と矛盾してしまうのだから[26]。要するに、ゲーテはウェルテルに、それまでの文学形式には収容しきれない人間像を託したと言えるだろう。
この『ウェルテル』の実験の二〇年後に現れたのが、大作『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』であり、そこで後にビルドゥングスロマンと称される文学形式が開示された。ウェルテルが自己破壊的な情動に囚われたのと違って、ヴィルヘルムはむしろ世界に沿って記憶や経験を組織的に蓄積し、それを自己形成のプログラムとして利用する。コンピュータ・アルゴリズムの比喩を使えば、ビルドゥングスロマンとは「教師あり学習」(supervised learning)のプロセスを再現した文学として理解できる。ヴィルヘルムはまさに世界=教師から学習し、精神を段階的に建設してゆく「教養(ビルドゥング)」の企てに自らを差し向けた。
もとより、教養とはまばらな知識の集まりではなく、自律性の獲得に向けた組織的で終わりのない知的運動を指す。バフチンによれば、ゲーテにとって、この教養的な人間形成のモデルになったのが、自然環境に含まれる「有機的」な「歴史的時間」であった。「空間のなかに時間を見るゲーテの驚くべき能力」は、生き生きとしたリズムで脈動する自然を捉える[27]。ゲーテ的な人間は、この自然のダイナミックな時間と共鳴するようにして、自らのうちなる生成力を発見する。教養とは死んだ知識の収蔵ではなく、世界に内在する生成力の発見に等しい。
主人公の自律性の獲得を描くビルドゥングスロマンは、ふつうに見れば「一」の文学である。しかし、主体が世界=教師とペアリングされて成長するという意味では、そこには潜在的な「二」の文学の要素がある。バフチンが言うように、ゲーテはこのペアリングを「見ること」つまり鋭敏な視覚の力によって可能にした。
7、教養の廃墟からの成長――ブロンテの『嵐が丘』
それにしても、なぜドイツでビルドゥングスロマンが発達したのか。そこにはドイツ特有の政治状況がある。フランスと違ってドイツには革命がなく、しかも多くの領邦国家が分立していた。ゆえに、ドイツの統合に向けては、精神的な次元での「文化国家」のアイデンティティに訴えるしかなかった。そのとき、未成熟な状態からの成長を描くビルドゥングスロマンは、一つの成熟した精神的=文化的共同体に向かうための格好の道標になった[28]。
このような政治的動機を潜ませたドイツの文芸を中心にするとき、ビルドゥングスロマンはきわめて男性的なジャンルとして現れてくる。ただ、この見方がジェンダー的な偏向を含むのは明らかだろう。
そもそも、小説的主体の歴史が男性に還元されないことは、スペインの『セレスティーナ』をはじめ、デフォーやサドらの描いた女性のピカレスクロマンからも分かる。彼女らは社会的規範を出し抜く戦略家であり、モル・フランダースのように、大西洋を渡ることも辞さない旺盛な活動力を備えていた。その一方、リチャードソンやルソーの書簡体小説も、女性の心理という豊饒な鉱脈の発見なしにはあり得なかった(この両者が幼少期から女性との接触の機会が多かったことは興味深い)。近代小説の原史において、女性の関与が不可欠であったことは、改めて思い出されるべきである。
ビルドゥングスロマンの進化についても、すでにゲーテ以前に女性作家が関わっていた。女性作家による女性を主人公とするビルドゥングスロマンの先例としては、フランスのラファイエット夫人の『クレーヴの奥方』(一六七八年)やイギリスのイライザ・ヘイウッドの『ベッツイ・ソートレス嬢の物語』(一七五一年)等が挙げられる。その後、アメリカではルイーザ・メイ・オルコットの『若草物語』(一八六八年)からマーガレット・ミッチェルの『風と共に去りぬ』(一九三六年)まで、広義のビルドゥングスロマンに数え入れられる小説が、商業的にも大きな成功を収めた。
ただ、私はここであえて、女性作家の書いた変則的なビルドゥングスロマンを、特異な事例として導入しておきたい。それはエミリ・ブロンテの『嵐が丘』(一八四七年)である。
周知のように、この小説はもはやふつうの意味でのビルドゥングスロマンの可能性が崩壊した、荒涼とした丘陵と渓谷を舞台にしている。孤児ヒースクリフの形象はアイルランド大飢饉の惨禍に通じるが(第五章参照)、この亡霊的なヒースクリフ自身も、同じ魂をもつ死んだ恋人キャサリン・アーンショウの亡霊に憑かれる。ヒースクリフの狂気は、望まない結婚を経て死に到った不幸な女性の狂気と重なりあう。その意味で、『嵐が丘』とは「二」の小説、つまりきわめて荒々しく凶暴な男性が、実は女性にハイジャックされているという両性具有的な作品である。
そして、この二乗された亡霊は暴風のように吹き荒れ、人間どうしの絆を断ち切り、幼い家族を虐待し、ついにヒースクリフ自身の破滅へと到る。彼の前代未聞の過剰なドメスティック・ヴァイオレンスは、ゴシック小説の伝統に即しつつも、それをはるかに超えるような不可解な印象を与える。語り手の家政婦ネリー・ディーンは、本名も年齢も不詳のヒースクリフについて「いったいあの人は、どこから来たのだろう?」と夢うつつでつぶやく[29]。ヒースクリフにはいかなる社会的属性もない。彼は、社会に場をもたない異邦人であり、彼の住まう「嵐が丘」はいわば亡霊たちのアセンブリ(集会)の場なのである。
キャサリンの亡霊と一人対話するヒースクリフの表情は「極端な楽しみと苦痛」にさいなまれ、苦しみのなかで恍惚としている[30]。このぞっとするような光景には、いかなる出口もない。内面的な成長の可能性をもたないヒースクリフは、ビルドゥングスロマンの枠組みから完全に外れた存在である。
煽情的なゴシック小説の流行を嫌った一九世紀初頭のワーズワースは、湖水地方のなめらかな自然の運動を教師としながら、自らの詩(特に『序曲』)に一種のビルドゥングスロマンの性格を与えた。The Tables Turned(形勢逆転)という詩では、書物を捨てて、光を浴びて鳥のさえずりを聴き、自然を先生にせよというまっすぐなメッセージが発せられる[31]。ワーズワースにとって、自然は書物を超えた書物、学校を超えた学校であった。しかし、その半世紀後の『嵐が丘』になると、自然=教師はその暴力的な顔をむき出しにする。ヒースクリフ(ヒースの茂る荒野の崖)という名前そのものが、破局的な自然の記号にほかならない。
しかし、ここで注目に値するのは、ヒースクリフの異様な暴力と謀略の支配のなかでも、自らの精神的な独立をめざした女性がいたことである。それが亡きキャサリンの娘キャシーである。一八歳のキャシーは二三歳のヘアトン(キャサリンの甥だが、同居するヒースクリフに虐待されてまともな教育を受けられず、すっかり退嬰的な気分に沈み込んでいる)を抱き込み、「嵐が丘」という屋敷――ゴシック小説を特徴づける不気味な「城」の等価物――でのサバイバルを企てる。その際、キャシーとヘアトンを結びつけるのは、ヒースクリフの忌み嫌った書物である。
「本があったときには、いつでも読んでいたわ」とキャシーは言いました。「でも、ヒースクリフさんは本を読まないの。だから、あたしの本も捨てちゃうような真似をするのよ。〔…〕それにねヘアトン、あたし、あなたの部屋に隠してある本を偶然見つけたのよ……ラテン語やギリシャ語の本に、物語や詩の本。みんな、あたしの昔の友達だったわ〔…〕」。[32]
キャシーはヘアトンに本をプレゼントし、二人で仲良く読書する。この自己教育によって、二人の敵対性は消滅し、親密な同盟関係が設立され、ヒースクリフの暴力の防波堤となる。ここで重要なのは、二人がともにキャサリンの亡霊を背負っていたことである。ネリーの報告によれば「二人の目はほんとうにそっくりでございますよ。亡くなったキャサリン・アーンショウの目なのです」[33]。キャサリンの亡霊はヒースクリフに苦痛に満ちた恍惚を味わわせる一方、若いカップルには連帯の可能性を与えた。ヒースクリフを過去に閉じ込める亡霊は、キャシーとヘアトンにとっては、むしろ唯一の活路として現れる。ブロンテがここに世代的な差異を導入したことは明らかだろう[34]。
こうして、キャシーは「嵐が丘」という恐るべき紛争地帯において、読む行為をヘアトンに感染させながら、自己を戦略的に立て直そうとする。ビルドゥングスロマンを粉砕するほどの過剰な暴力の吹き荒れる閉域で、いかなる成長の物語を描くか――ブロンテはこの難題に「読む主体」の複数化によって応じたのだ。
8、アイロニーとその限界
ただ、いずれにせよ、ビルドゥングスロマンのモデルが脆弱性を抱え込んでいたのは確かである。主体を成長させる学習環境は、必ずしも安定していない。例えば、未熟な子どもを主体化するはずの教師が、予期せぬ誤作動を起こせばどうなるか――その場合、セルバンテスの「ガラスの学士」のように、いったん「一」に統合されたかに思えた主体が、ただちにひび割れてしまうことも十分あり得るだろう。
実際、ビルドゥングスロマンの脆弱さは、ゲーテに続くフリードリヒ・シュレーゲルやノヴァーリスらドイツ・ロマン主義者によって早くも自覚されていた。ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』の企てに共鳴しつつも、それを不十分と見なした彼らは、新たな思想の拠点をアイロニーに求めた。
平たく言えば、アイロニーとは一階の自己のふるまいを、超越論的な二階の自己の「反省」によって管理・修正しようとする自己二重化のプログラムである。さまざまな予測不可能な経験にさらされる主体を、メタレベルからたえずモニタリングすること、つまり世界の諸事象に没入してはアクシデントに直面する自我を、ときにクールに突き放して観察すること――この往復運動がアイロニーの真骨頂である。アイロニーとは、自己の脆弱性を修正するプログラムだと言い換えてもよい。
シュレーゲルは「二」を「一」のなかに折り畳むアイロニカルな反省を、文学の中心的問題に格上げした。メタレベルのチェック機能が保たれていれば、たとえカオスに呑み込まれても自己は崩壊せずに済む。裏返して言えば、二階の大人の反省や修正の機会が保証されていれば、一階の子どもは遠慮なくいくらでも過激になれるだろう。ロマン主義的なアイロニーの理論によれば、自己を二階の反省によって超越すること(=自己超出)だけが、真に自己自身であるための秘訣なのである[35]。
しかし、アイロニーも万能ではない。例えば、一階の自己にかかる負荷やショックが飛躍的に増大し、アイロニカルな自己二重化では処理しきれないほどの水準に達すればどうなるか。要は、一階がつぶれてしまえば、二階の自我も成立しようがないのではないか。ヴァルター・ベンヤミンが大戦間期に問題にしたのは、まさにこのことである。彼の興味深い観察によれば、第一次大戦の戦場から帰還した兵士たちは、自らの苛酷な経験を物語る術をもたず、ただ押し黙ったままであった。あまりにも強烈な破壊と爆発は、彼らの経験を増やすどころか、かえって極端に貧困化してしまったのだ[36]。
ゆえに、世界戦争の帰還兵たちは、ゲーテ的な教養=成長からもシュレーゲル的なロマンティック・アイロニーからも疎外されている。一階の自己(経験)の麻痺してしまった彼らの存在様式を先取りしていたのは、E・A・ポーの『ピム』におけるゾンビ的存在だろう。強烈なショックを受けて、修復不可能なダメージを負ったゾンビは、もはや出来事の意味を了解するだけの思考も知覚ももたない。自己をモニターするメタレベルの認識を麻痺させたまま、痛覚のない肉を痙攣的に動かし続けるゾンビ――このおぞましい絶滅の情景は、やがてエントロピーの最大化した最果ての白色の世界を呼び覚ます(前章参照)。そこにはもはや成長やアイロニーの余地はない。ポーの物語が描いたのは、小説の主体の基盤そのものが喪失される可能性なのである。
9、ピカレスクロマンのリバイバル?
二〇世紀の世界戦争を経て、一九世紀のビルドゥングスロマンは過去のものになった。ゲーテ的な生成や発展のプログラムを中断し、アイロニーも蒸発させる強烈な爆発やショックに襲われたとき、ヨーロッパ小説の主体はついに「一」から「零」へと滑落した。一九五〇年代のサミュエル・ベケットやロブ゠グリエのテクストは、もはやショックを受ける人間そのものも消え失せた小説、つまり主人公らしい主人公が絶滅した反小説(アンチ・ロマン/後にヌーヴォー・ロマンと呼ばれる)の実例となっている。
ただし、二一世紀のわれわれは、これら反小説の《零度の主体》が小説の可能性をすべて食べ尽くしたわけでないことも知っている。主体の歴史には、ビルドゥングスロマンとは別の生き延び方があった。ビルドゥングスロマンを文学の標準的形態とするのをやめれば、それ以前にあった別の主体性の文学、つまりピカレスクロマンや書簡体小説の遺産を再評価することも可能になるだろう。
特に、ピカレスクロマンが重要なのは、ヨーロッパ以外の文学でも類似した形式があったからである。例えば、東アジアの文芸においては、中国の『水滸伝』から日本の上田秋成の「樊噲」(『春雨物語』所収)に到るまで、法や規範を侵犯するアウトサイダー――『水滸伝』ではむしろ「好漢」と呼ばれる――を主役にした冒険小説が、プロト近代文学の里程標となった(第五章参照)。スペインの『ラサリーリョ』や『グスマン』と同じく、これらの東アジアのピカレスクロマンでも、違法者こそが社会の裏側に隠れた欺瞞やごまかしを暴くことになる。
かたやアメリカ大陸でも、ピカレスクの伝統を引き継ぐマーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』(一八八五年)という記念碑的小説があり、ナボコフの自動車旅行文学『ロリータ』(一九五五年)も、ロードサイドの社会的諸相をサーフィンするピカレスクな要素を含んだ。さらに、二〇世紀後半になると、ラテンアメリカ文学のブームのなかでロハスの『セレスティーナ』が再発見されて、カルロス・フエンテスの『アウラ』、ガルシア゠マルケスの『エレンディラ』、セベロ・サルドゥイの『コブラ』等が『セレスティーナ』の遺産の相続者として現れた[37]。
私には、ゲーテ的なビルドゥングスロマンは文学史の一時期にのみ流行した限定的な形態であったように思える。むしろ、主人をたえず取り替えながらメタモルフォーゼ(変容)を繰り返すピカレスクロマンのほうが、小説の主体の歴史においてより標準的な形態ではないか。そして、それは二〇世紀の《零度の主体》のデッドエンドから脱け出す手がかりにもなり得たのではないか。実際、ピカレスクロマンに類似した形式は、二〇世紀の世界戦争のなかで再生されたように思える。本章の締めくくりに、その実例をレイモンド・チャンドラーの探偵小説から引き出しておきたい。
10、世界の終わりで探索する――レイモンド・チャンドラーの探偵小説
多くの探偵小説には、ビルドゥングスロマンのような内面的な成長の物語が欠けている。このジャンルの重要性はむしろ、ビルドゥングスロマン以前の主体性の形式を再来させたことにあった。ポイントを挙げよう。
第一に、探偵はピカレスクロマンの主人公と同じく「発展」や「成長」がなく、たいてい富ももたないが、知識や鋭敏さにかけては誰よりも秀でている。探偵のプロトタイプとなったポーのオーギュスト・デュパンは、生家の没落の後、わずかな資産をやりくりして生計を立てている(「モルグ街の殺人」)。労働者でも資本家でもなく、鋭い分析的知性の行使に熱中する快楽主義者――それがポー以来の典型的な探偵像である。
第二に、犯罪を探る性質上、探偵はピカロと同じく、社会のアンダーグラウンドと頻繁に接する。探偵にはたいてい家族がおらず、一匹狼である。探偵はこの束縛のない「変わり者」の視点から、しばしば社会を形作っている主人たちの欺瞞を明らかにする。それが探偵小説に社会批評性を与える。
第三に、探偵小説は本質的に「二」の小説であり、犯罪者と探偵というカップルが不可欠である。このカップルは、書簡体小説における作者と読者の関係によく似ている。探偵は手紙をやりとりする代わりに、犯罪者=作者の痕跡を「読むこと」に集中する。探偵が読むのは、ふつうの人間の気づかない痕跡であり、そのため犯罪者と探偵は秘密を共有するカップルに近づいてゆく。
もとより「探索すること」は脳の基本的な機能である。探偵小説はこの機能を最大限に生かしながら、群集のなかから一人の犯人を特定する。探偵小説の本質は、現実のミメーシスではなく、頭脳のミメーシスにある。ゲーテのビルドゥングスロマンが生物学な時間に沿って、成長する主体を象ったとしたら、探偵小説は脳の機能に沿って、探索する主体を描き出した。
その場合、ポーの探偵デュパンやコナン・ドイルの探偵シャーロック・ホームズが三人称的に描かれたのに対して、二〇世紀アメリカ西海岸のハードボイルド探偵小説家たち――レイモンド・チャンドラー、ダシール・ハメット、ロス・マクドナルドら――が、一人称的な語りによって、リアルタイムの「探索」に読者を巻き込んだのは重要な発明であった。それはまさに、スペインのピカレスクロマンが一人称の「視点」を発明したことを彷彿とさせる。
チャンドラーの小説では、社会の各部はバラバラに存在していて、それらはただロサンゼルスを拠点とする私立探偵フィリップ・マーロウの探索と移動によって、つかのま統合されるだけである。マーロウの関与する事件は、たいていそれほど人目を惹く事件ではなく、事実上社会から打ち捨てられており、たいした見返りもない。そのため、チャンドラーの探偵小説には、解体的な要素と個人的な要素が同居している。
特に、一九五三年に刊行された『ロング・グッドバイ』では、世界戦争後の底なしの廃墟感覚が、テリー・レノックスという人物を通じて浮上してくる。ナチス・ドイツとの戦争で顔に傷を負って帰国したレノックスは、マーロウと友人になるが、やがて失踪して妻殺しの容疑がかけられる。後日マーロウのもとには、彼がメキシコで自殺したというニュースが届けられる。この不可解な「レノックス事件」は公的な興味をひかず、ほとんどマーロウの個人的な探索によって、かろうじて存在するだけである。
マーロウはこの事件と並行して、ロサンゼルス郊外のアイドル・ヴァレー(サンフェルナンド・ヴァレーがモデル?)に住まう売れっ子小説家――フィッツジェラルドに憧れている――とその妻と関わりをもつ。アイドル・ヴァレーは「社会のいちばん上の段に属する、くもりなくこぎれいな、選び抜かれた人種だけが住人として受け入れられる」楽園のような高級住宅地だが[38]、この清潔なゲーテッド・コミュニティで小説家は殺されてしまう。
マーロウの探索を経て、何不自由なく繁栄を謳歌している、この申し分のない富裕層の住む地区こそ、暗い荒廃に蝕まれていたことが明らかになってゆく。そして、この殺人事件の解決とともに、帰還兵レノックスの正体が浮かび上がる。レノックスは人生の抜け殻となり、かつては「何か」をもっていた心も無に帰してしまった。マーロウの探索は結果的に、この空虚をきわめて綿密かつ正確に描き直したのである。
チャンドラーを高く評価する批評家のフレドリック・ジェイムソンは、探偵小説にピカレスクロマンとの類似性を認めつつ、それがアメリカで果たす機能に注目している。社会が緊密に組織化されたパリとは異なり、チャンドラーの描くロサンゼルスは水平的に広がり、社会の各要素は相互に隔たった断片と化している。マーロウはそこでは純粋な思索にふけってはいられず、一つの社会的現実から別の社会的現実へと、ずっと探索するように駆り立てられる。この推力のなかで、ギャングやアルコール中毒者からアイドル・ヴァレーの上流階層までを含む社会の全体性が仮構される[39]。
チャンドラーは同世代であるジョイスやウルフのようなイギリスのモダニストと同じく、主人公に都市をさまよわせながら、社会に散らばった断片的な出来事を収集した(チャンドラー自身、幼少期にはイギリスで暮らしていた)。この「全体性の捜査」(ジェイムソン)は、ドライな感傷性とともになされる。かつてリチャードソンやルソーの新興ブルジョワ向けの書簡体小説が、その感傷性によって貴族社会の罪を発見したように、チャンドラーも大衆向けのパルプフィクションの系譜に連なりながら、感傷性と倫理性を交わらせた。
〔…〕犯罪に満ちた夜の中で、人々は死んでいく。手足を切断されたり、飛んでくるガラスで切られたり、ハンドルに叩きつけられたり、重いタイヤに踏まれたりして。人々は殴られ、強奪され、首を絞められ、レイプされ、命を奪われる。人々は腹を減らせ、病気を患い、退屈し、孤独や後悔や恐怖で自暴自棄になり、怒り、残酷になり、熱に浮かされ、身を震わせてすすり泣く。都会なんてどこも同じだ。都市は豊かで、活気に満ち、誇りを抱いている。その一方で都市は失われ、叩きのめされ、どこまでも空っぽだ
人がそこでどのような位置を占め、どれほどの成果を手にしているかで、その相貌は一変する。私には手にするものもなく、またとくに何かを求めているのでもなかった。[40]
私立探偵のマーロウには社会的な所属はもとより、富もアイデンティティもない。この「もたざる主体」を読み取りのシステムとして、空虚な都市に送り込むこと――チャンドラーにとって、それは世界戦争後にほとんど唯一可能な主体化の経路であった。ピカロのように鋭敏な「読む主体」であるマーロウは、埋没してしまった他者の痕跡を探索し、読み続ける。チャンドラーはそこに、《世界の終わり》の空虚を生き延びる手法を見出したのである。
[1]柄谷行人『定本 日本近代文学の起源』(岩波現代文庫、二〇〇八年)第二章参照。
[2]ベネット・サイモン『ギリシア文明と狂気』(石渡隆司他訳、人文書院、一九八九年)四五頁。
[3]ジャン・プイヨン『現象学的文学論』(小島輝正訳、ぺりかん社、一九六六年)二五頁。
[4]「小説における時間と時空間の諸形式」(北岡誠司訳)『ミハイル・バフチン全著作』(第五巻、水声社、二〇〇一年)二六七頁。
[5]T・イーグルトン『クラリッサの凌辱』(大橋洋一訳、岩波書店、一九九九年)九一頁。
[6]モンテスキューには法の局所性・相対性の認識がある。『法の精神』によれば、学者はそれぞれの国の気候風土や民族の生活様式に応じて、つまり「事物の秩序」に沿って、望ましい法律を探究せねばならない。アラン・シュピオ『法的人間 ホモ・ジュリディクス』(橋本一径他訳、勁草書房、二〇一八年)一〇九頁。
[7]「リチャードソン頌」『ディドロ著作集』(第四巻)五六頁。
[8]イーグルトン前掲書、五、一二、二八頁。その一方、貴族を主人公とした書簡体小説としては、フランスのラクロの『危険な関係』(一七八二年)が名高い。リチャードソンやルソーの書簡体小説が平民のセンティメンタリズムに根ざしたのとは逆に、『危険な関係』では戦略家の貴族たちが、他者を操作・利用しようとする謀略を互いに手紙で仕掛けあう。彼らの自己は、この謀略の渦巻きのなかで創出されるのだ。
[9]ロバート・ダーントン『猫の大虐殺』(海保真夫+鷲見洋一訳、岩波書店、一九九〇年)一八三頁。
[10]同上、一八四頁。
[11]ルソー的なシンパシーないしテレパシーの問題を再来させたのは、若き日の恋愛の最中に「テレパシーというものを確信していた」(一八二七年一〇月七日)と、後にエッカーマンに告白したゲーテである。ゲーテの文学はテレパシーと密接な関係がある。それは、精神的なインフルエンザのように若者に感染した『若きウェルテルの悩み』のみならず、四人の男女の情動の化学反応を記録した長篇小説『親和力』(一八〇九年)にも見出せる。
[12]なお、ポール・ド・マンをはじめ「読むこと」をめぐる理論は、しばしばテクストの解釈が単一の決定的な意味に帰着しないことを強調してきた。ただ、私がここで重視するのは、ド・マン的な「読むことの不可能性」ではなく、むしろ「読むことの感染性」である。近代小説の社会学的基盤には、読むことを特権化しつつ一般化したリチャードソンらの戦略があった。
[13]J・L・ボルヘス『序文つき序文集』(牛島信明他訳、国書刊行会、二〇〇一年)二四〇頁。
[14]Francisco Rico, The Spanish Picaresque Novel and the Point of View, Cambridge University Press, 1984, p.16.
[15]バフチン前掲書、二六〇頁。
[16]「ラサリーリョ・デ・トルメスの生涯」(牛島信明訳)『ピカレスク小説名作選』(国書刊行会、一九九七年)四三頁。なお、『ラサリーリョ』は今や出世したラサリーリョが、上司に提出した自己弁明の手紙として書かれている。もともと、ルネッサンス期のペトラルカをはじめ、文人たちは書簡文学を自伝的に用いてきたが、『ラサリーリョ』はこの伝統に接ぎ木された作品である。Rico, op.cit., p.3.
[17]マテオ・アレマン「グスマン・デ・アルファラーチェ(抄)」(牛島信明訳)『バロックの箱』(筑摩書房、一九九一年)一〇二頁。
[18]同上、一一〇頁。テリー・イーグルトンは『テロリズム 聖なる恐怖』(大橋洋一訳、岩波書店、二〇一一年)で、法を新たに創設する「立法者」が、既存の法の適用をすり抜ける「違法者」でもあることを強調しているが(六頁)、これはアレマンの描いたピカロたちの特性にも当てはまる。
[19]Roberto Gonzalez Echevarria, Celestina’s Brood: Continuities of the Baroque in Spanish and Latin American Literature, Duke University Press, 1993, p.50.
[20]ミシェル・ビュトール『レペルトワールⅡ』(石橋正孝監訳、幻戯書房、二〇二一年)一五〇頁。
[21]「ガラスの学士」『セルバンテス短篇集』(牛島信明訳、岩波文庫、一九八八年)。
[22]Echevarria, op.cit., p.54.
[23]Chad M. Gasta, “Cervantes and the picaresque”, in J. A. Garrido Ardila ed., The Picaresque Novel in Western Literature, Cambridge University Press, 2015, p.100.
[24]サルバドール・デ・マダリアーガ『ドン・キホーテの心理学』(牛島信明訳、晶文社、一九九二年)二一三頁。むろん、ドン・キホーテとサンチョという「兄弟」の傍らには、ロシナンテ――あらゆる駄馬のなかで最高位の駄馬と称される――がいた。セルバンテスの画期性は、物語の舞台に動物をエントリーさせ、人間たちの生を活気づけたことにある(逆に『ガリヴァー旅行記』の馬の国では、動物は人間を絶滅させることも辞さない)。もし人間だけの旅であれば、『ドン・キホーテ』の面白さは半減したに違いない。
[25]モース・ペッカム『悲劇のヴィジョンを超えて』(高柳俊一他訳、上智大学出版、二〇一四年)九四頁。
[26]「ゲーテとその時代」(菊森英夫訳)『ルカーチ著作集4』(白水社、一九八六年)八八頁。
[27]「教養小説とそのリアリズム史上の意義」(佐々木寛訳)バフチン前掲書、九七頁。
[28]Todd Kontje, “The German Tradition of the Bildungsroman”, in Sarah Graham ed., A History of the Bildungsroman, Cambridge University Press, 2019.
[29]E・ブロンテ『嵐が丘』(下巻、小野寺健訳、光文社古典新訳文庫、二〇一〇年)三九四頁。
[30]同上、三九七頁。
[31]Jonathan Bate, Radical Wordsworth, William Collins, 2020, p.201.
[32]ブロンテ前掲書、三二九頁。
[33]同上、三七六頁。
[34]Kate Ferguson Ellis, The Contested Castle: Gothic Novels and the Subversion of Domestic Ideology, University of Illinois Press, 1989, p.218.
[35]ヴィンフリート・メニングハウス『無限の二重化』(伊藤秀一訳、法政大学出版局、一九九二年)二八四頁。
[36]「物語作者」『ベンヤミン・コレクション2』二八五頁。
[37]後世への『セレスティーナ』の影響を論じたロベルト・ゴンザレス・エチェバリアは、この作品が「スペイン語圏の文学上のモダニズムの先駆者」であり、近代小説の「種子」になったことを強調している。Echevarria, op.cit, p.10.
[38]レイモンド・チャンドラー『ロング・グッドバイ』(村上春樹訳、ハヤカワ文庫、二〇一〇年)三九〇頁。
[39]Fredric Jameson, Raymond Chandler: The Detections of Totality, Verso, 2016, pp.7, 24.
[40]チャンドラー前掲書、四二八頁。
(続く)
この記事は、PLANETSのメルマガで2024年3月14日、3月19日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2024年5月2日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。