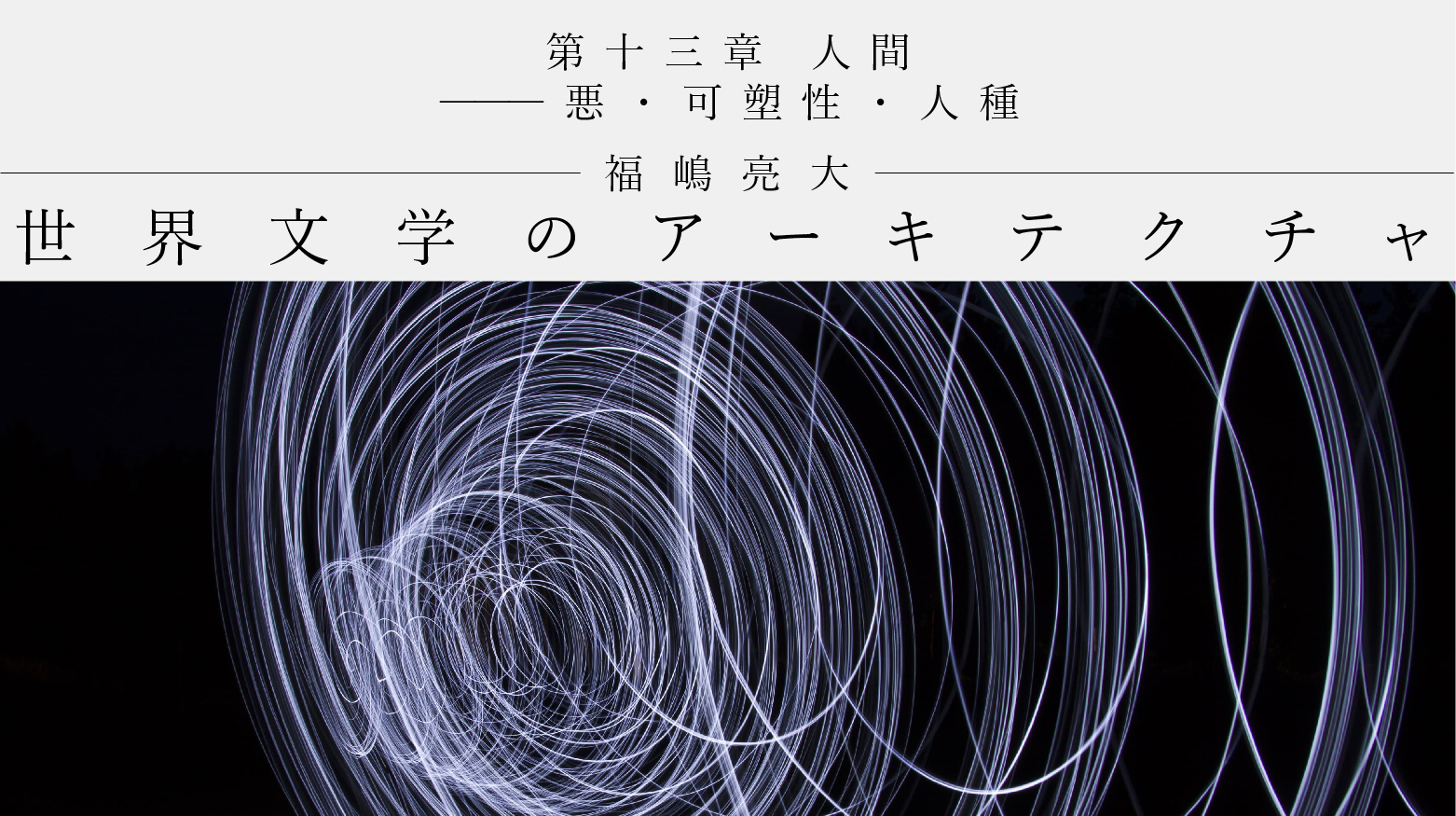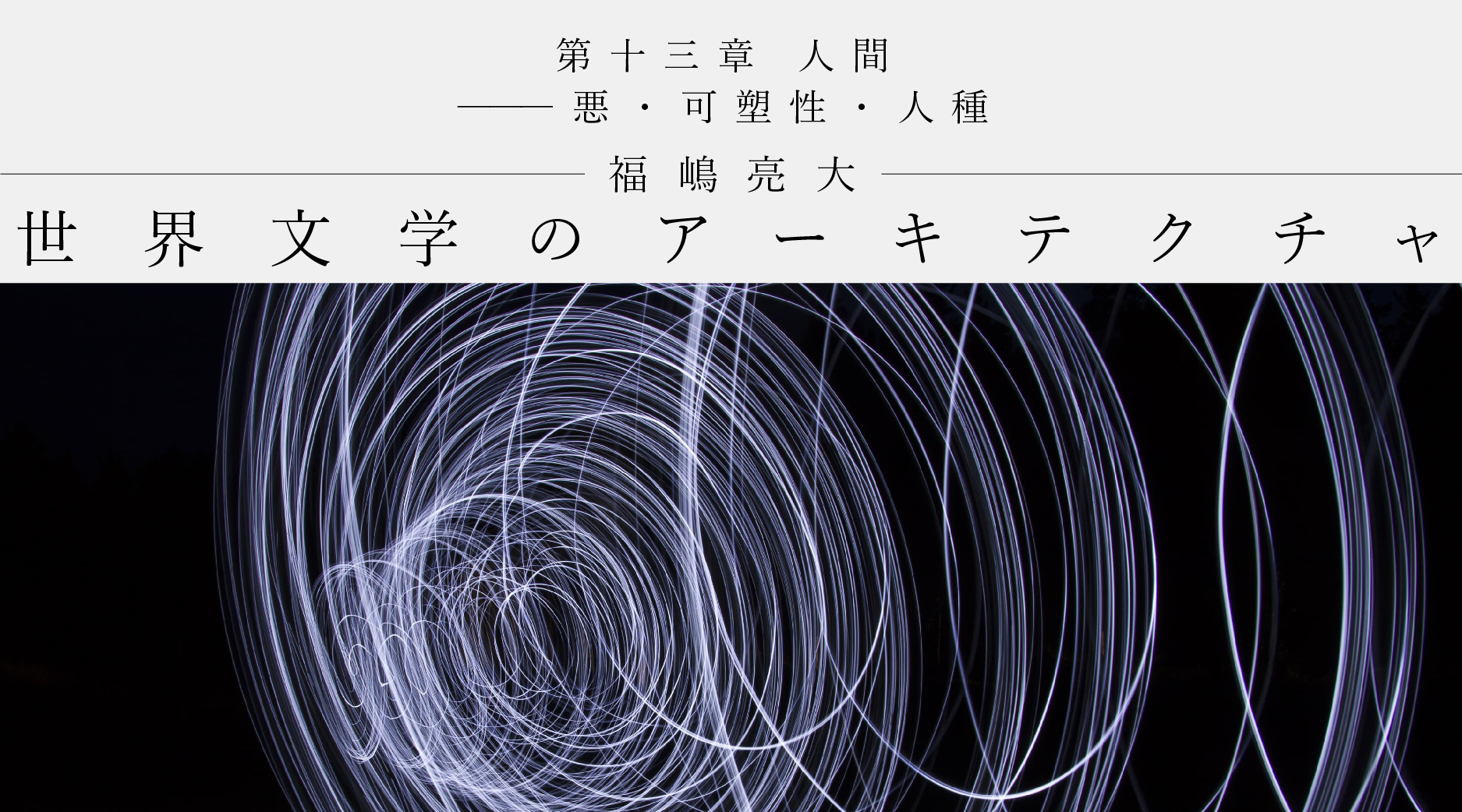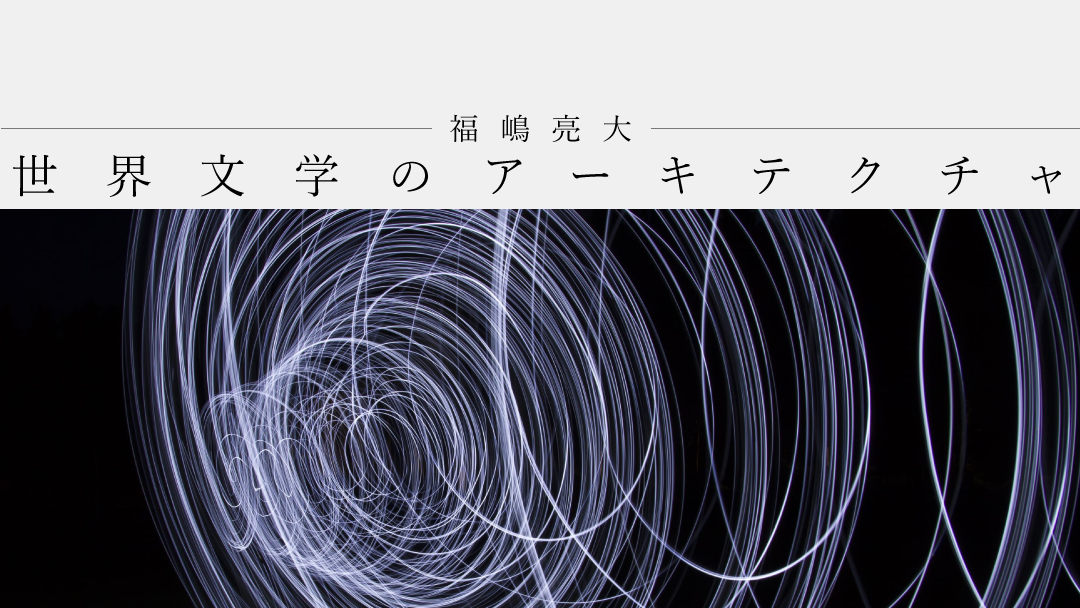
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、悪の発明――ラス・カサス的問題
文学にとって世界とは何か。私は歴史的な見地から、その問いを初期グローバリゼーションと紐づけた。世界とはたんに空間的な広さを指す概念ではなく、異質なものとの接近遭遇がたえず起こる場である。異なる歴史、異なる習俗、異なる人間との関係の集合体としての〈世界〉――その成立に欠かせなかったのが、アメリカ大陸へのヨーロッパ人の進出であり、「万物の商品化」を加速させる資本主義のプログラムであった。「世界文学とは新世界文学である」(第七章)という私のテーゼは、異質なものとの関係の無尽蔵の発生を、その根拠としている。
その一方、グローバリゼーションの発端にはおぞましい暴力がある。一六世紀スペインの神学者ラス・カサスの『インディオの破壊についての簡潔な報告』は、まさにその暴力を告発した文書である。先住民――ヨーロッパ人の誤認のせいで「インディオ」と呼ばれた――の虐殺のカタログと呼ぶべきその記録は、ヨーロッパの発明した「世界」が、他者との対話や競合ではなく、搾取と破壊から始まったことを証言している。
ラス・カサスによれば、コロンブスがアメリカ大陸に到着した一五世紀末に「まったく新しい、過去のいずれにも似ても似つかない」時代の扉が開いたが、それはただちに黄金に目のくらんだキリスト教徒たちによる、先住民のインディオの殺戮へと到った。スペイン領植民地におけるエンコミエンダ制(先住民を労働力として使役する権利を征服者に認めた制度)を神への違反として厳しく批判した他のドミニコ会士とともに、ラス・カサスは「人間の破壊」という激越な言葉を使って、スペインの植民地政策の非合法性を訴えた。彼が批判したのは、インディオを「絶滅」させることも厭わない残酷さであり、それを促した数々の社会的不正である[1]。
ラス・カサスは新大陸で受けた精神的な衝撃を、神学的かつ法学的な枠組みのなかで厳密に思考し直した。二〇世紀ペルーの神学者グスタボ・グティエレスによれば、ラス・カサスの企ては「掠奪と不正の上に築かれた社会で福音を宣べ伝えること」にあった。彼は聖書の教えに従い、断固として貧しきものたち、つまり先住民(インディオ)の側に立った。本来、キリストの教えでは、神と富に同時に仕えることはできない。キリスト教徒たちはインディオを、異教の神々をあがめる偶像崇拝者として蔑んだが、ラス・カサスに言わせれば、富(マモン)を行動の基準とし、富にすべてを捧げた自称キリスト教徒たちこそが、本物の神をフェイクの神に取り替えた最悪の偶像崇拝者にほかならない[2]。
黄金という「偶像」に惑溺したキリスト教徒が、おぞましいジェノサイドに駆り立てられる――この植民地でのトラウマ的な「人間の破壊」は、悪の新たな形態の出現、つまり悪の発明と呼ぶにふさわしい。ラス・カサスは大部の『インディアス史』において、この数々の邪悪な行為を歴史家として緻密に再現する一方、『インディアス文明誌』では非ヨーロッパ人のインディオがいかに理性的な人間であるかを、主にアリストテレスの哲学に拠りながら論証しようとした。そこには、人類社会のさまざまな差異とその深層の同一性をスキャン(走査)する文化人類学的な要素がある[3]。
アリストテレスの考えでは、あらゆる人間は政治的動物である。ラス・カサスが論証したのは、それはインディオも例外ではないということである。ラス・カサスに続いて、ホセ・アコスタの驚異的な著作『新大陸自然文化史』(一五九〇年)になると、アリストテレス哲学の限界が厳しく指摘され、あわせてアメリカ大陸の自然誌(気象、動植物、鉱物等)およびインディオの多様な文化についての詳細な分析が記された。それは、ヨーロッパ人に根強くあった新世界=怪物の住む土地という迷信を解体し、理性的な人間の住む範囲をヨーロッパ以外にも広げる企てであった[4]。《世界》に直面したスペイン人は、人間を破壊する暴力と、人間を発見する体系的な知を、ともに進行させたのである。
2、リハビリテーションの技法としての小説
ところで、新世界が「まったく新しい時代」を開いたと言われるのは、それが「旧世界」にも無数の変化をもたらしたからである。スペイン史の泰斗ジョン・エリオットによれば「アメリカを発見したことによって、ヨーロッパは自らを発見した」。アメリカは大量の新しい事実を、ヨーロッパの人間に示した。アメリカはたんに「新しい」世界であるばかりか、自然や文化に関してもヨーロッパとは「違った」世界であった[5]。ゆえに、ヨーロッパ人は新世界の人間や風土を理解するのに、自らの認識の土台――聖書やアリストテレスの哲学も含めて――に遡り、理性や信仰の問題を根本的に再検討するように強いられたのである。
新世界との出会いは、旧世界=ヨーロッパの自己認識に少なからぬ影響を及ぼした。そして、このヨーロッパにおける自己の再発見は、小説の認識の基盤にも重大な作用を及ぼしたように思える。繰り返せば、新しい「世界」の成立は、新しい「悪」の発明でもあった。それは人間――というより人間以下とされた存在――を組織的に破壊するという悪であり、富の増進のために貧者を資源として酷使するという悪である。
このようなジェノサイドの光景は、ヨーロッパの近代小説において変奏された。デフォーの『ペスト』やスウィフトの『ガリヴァー旅行記』、そしてサドの一連のリベルタン小説から、ドストエフスキーの『死の家の記録』、コンラッドの『闇の奥』、ソ連の強制収容所(ラーゲリ)を告発したソルジェニーツィンの『収容所群島』等に到る小説は、人間のシステマティックな「破壊」というラス・カサス的問題を執拗に反復してきた(第十章参照)。ここからは、近代ヨーロッパの発明した「世界」および「世界文学」が、人間の脆弱さや傷つきやすさへのオブセッションを抱いてきたことがうかがえる。
その反面、近代小説はラス・カサスの言説と同じく、富の発明した悪への批判、つまり富の有害さの暴露という一面をもった。われわれはここで、小説が悪からのリハビリテーションという仕事を自ら背負い込んだことに、注意を払っておこう。
現に、ラス・カサスの告発からほどなくして、フェリペ二世の統治時代(一六世紀半ば)のスペインではピカレスクロマンが流行し、無一物の「貧しきもの」の視点から、社会の富める主人たちの欺瞞があばかれた(第十一章参照)。スペインは新大陸から膨大な富が流入していたのに、財政的には赤字が膨らみ、苦境にあった。この繁栄のなかの危機を背景として、当時のスペイン社会では上から下まで、貧しきピカロの精神が浸透し、スペイン人の「人生哲学」を形成するまでになった[6]。財貨を軽蔑し、名誉を求める遍歴の騎士ドン・キホーテは、まさにこの哲学の延長線上に位置している。新世界に最初に進出したスペインが、小説の原初的なプログラムとして富=偶像への批判を明確化したことは、その後の小説の進化を方向づけるものであった。
さらに、『ロビンソン・クルーソー』や『ブーガンヴィル航海記補遺』で新世界と旧世界の対話的なつながりを創出した一八世紀のデフォーやディドロの言説は、アメリカ大陸におけるスペインの暴虐、いわゆる「黒い伝説」への厳しい批判を含んでいた。異文化の人間との友好的な対話を描いたデフォーやディドロは、スペインの悪魔的な「進出」と自らを差異化しようとする――そのとき彼らの小説は、ヨーロッパ人の発明したトラウマ的な悪からのリハビリテーションの場になった。
3、諸世界性と可塑性――スウィフト再訪
新世界の発見に関わるもう一つの重要なポイントは、旧世界の流動性が高まったことである。『ドン・キホーテ』の冒険の範囲は主に「旧世界」に留まっていたが、その直前にはホセ・アコスタのような卓越した学者が、新大陸の自然や文化を体系的に伝えていた。そのような幅広い知識は、閉鎖的・定住的な共同体を超えるノマド的な欲動を喚起したのではないか。実際、スペインのピカレスクロマンや『ドン・キホーテ』に見られる「放浪癖」は、新大陸の発見によって加速された。ジョン・エリオットは次のように指摘している。
新大陸の発見と開発のひとつの結果が、セビーリャにおける社会的流動性の増大であったとすれば、それがもたらしたいまひとつの結果は、過去何世紀にもわたって放浪癖をつよく示していたこの国民のあいだに、よりいっそう地理的流動性を強めたことである。[7]
この「地理的流動性」の上昇は、一六世紀スペインの小説のみならず一八世紀イギリスのデフォーやスウィフト、ローレンス・スターンらの小説の酵母にもなった。ここでは特に、スウィフトの『ガリヴァー旅行記』の末尾に注目しよう。フウイヌムの治める「馬の国」からイギリスに帰還したガリヴァーは、著名なスペイン人コンキスタドール(征服者)エルナン・コルテスを引きあいに出しながら、自らの旅した諸世界の征服がいかに困難かを雄弁に語った。
私が語った国々を征服するといっても、フェルディナンド・コルテスがアメリカ大陸に住む裸の者たちを征服したようなわけに行くでしょうか。[…]フウイヌム国は、たしかに戦争という術にはまったく無知であって、戦闘態勢が整っているとは言えそうにありませんし、特に飛び道具に対してはまったく無防備に思えます。しかし、かりに私が大臣であったなら、ぜひフウイヌムに侵攻を、などとはとうてい進言できません。フウイヌムの方々の思慮深さ、一致団結ぶり、恐れを知らぬ豪胆さ、そして愛国心をもってすれば、戦の技の不足すべてを補って余りあると思うからです。彼らが二万頭、欧州の軍の只中に突入してきて、隊列を混乱させ、馬車を転覆させ、後ろ足のひずめの恐ろしい蹴りによって兵士たちの顔を見る影もなく叩きのめしてしまう……そんなさまを想像していただきたい。(四五三頁)
スウィフトはここでガリヴァーの口を借りて、過去のアメリカでの軍事的征服が、いずれヨーロッパに跳ね返ってくる可能性を示唆している。仮にこのような反転が生じれば、虚弱なヤフーと同じく、旧世界のヨーロッパ人もただちに絶滅の危機に瀕する。高度な理性と忠誠心を備えた「新世界」の馬たち――その姿はラス・カサスやホセ・アコスタが詳細に記述した理性的なインディオの変奏のようにも思える――は、ヨーロッパの優越性を文字通りキックして叩きのめすだろう[8]。ヨーロッパが自らの発見した怪物=アメリカに圧倒されるというフランケンシュタイン的な未来を、スウィフトは予感していたように思える。
このような文章が書かれたのは、スウィフトが諸世界性の作家であったことと切り離せない。『ガリヴァー旅行記』が提示したのは、世界がキリスト教の教義のもとで一つにならず、むしろ複数形の、しかもそれぞれに隔離された「諸世界」になった状況である。ガリヴァーはどの特定の国家にも帰属せず、諸世界の狭間をさまよい続ける。この永遠の遍歴者のまなざしのもとでは、人間の身体の形状は安定せず、いわばフォトショップの画像のように操作や加工が施される。
ガリヴァーがリリパットやブロブディンナグ、馬の国のような極端な諸世界を横断するとき、人間は身体的にも知的にも、いかようにでも変化し得る不確定な存在、つまり可塑的な存在として現れてくる。そして、小説末尾での、スペイン人コルテスへのさりげない言及からうかがえるのは、スウィフトがこの諸世界性の原点に、新世界における悪=ジェノサイドを置いたことである。辺境のアイルランドに生まれたスウィフトは、特定のアイデンティティに帰属する代わりに、むしろ人間の可塑性をクールに、しかもグロテスクに誇張した。彼が人口問題の解決のために、アイルランド貧民の子を食肉に供すればよいという露悪的な提案をしたことを、ここで思い出すべきだろう。
私の考えでは、近代小説は二つの相補的なプログラムを内包していた。一つは『ペスト』や『ガリヴァー旅行記』のプログラム、つまり人類の終わりなき変容という悪の深淵を覗き込むことであり、もう一つは『ロビンソン・クルーソー』のプログラム、つまり人類がほぼ消え失せた絶滅の瀬戸際で、人間と社会を新たに再創造することである。このプログラムが進行するうちに、ラス・カサスの時代であれば神学や法学に属した問題を、文学がやがて積極的に引き受けるようになる。現に、「貧しきもの」や「もたざるもの」の側に立つラス・カサス的な精神は、一九世紀になると神学者以上に、ロシアのドストエフスキーやトルストイにおいて再創造されることになった。
4、悪とは無制限の悪化である――ベケットとバラード
〈世界〉とは何か。それは異質な世界どうしの相互作用を生じさせるインターフェースである。諸世界のあいだのギャップこそが〈世界〉を――異質なものとの関係が無尽蔵に発生する場を――生み出す。この〈世界〉を背景とする文学を〈世界文学〉と呼ぼう。一八世紀ヨーロッパのモンテスキュー、ヴォルテール、デフォー、スウィフト、ディドロらが飛躍させた近代小説は、最初からこの意味での〈世界文学〉、つまり諸世界性の文学であった。
この諸世界の相互干渉のなかで、人間は可塑的な存在として立ち現れる。『ガリヴァー旅行記』はこの人間の揺らぎを、まるでポップアップ絵本のように、外見(仮象)の揺らぎとしてユーモラスに示すとともに、それがジェノサイドを容易化することも示唆した。〈世界〉の発端に悪の発明があった以上、『ガリヴァー旅行記』をはじめとする近代小説=世界文学の歴史は、悪をなす人間とは何か、あるいは不条理な悪にさらされるとはどういうことかという検証作業を避けられなかった。
その作業が徹底されるとき、人間はたんに物理的に破壊されるだけでなく、その存在の条件もタブーなく吟味されることになる。小説の中心には常に人間がいるが、その人間の存在の仕方は決して不変ではない。一八世紀のイギリスおよびフランスの思想家=小説家たちは、小説というジャンルを、人間がどこまで変わり得るかをテストする不穏な実験の場に仕立てた。そして、この企てが二〇世紀になっていっそう加速したとき、悪は《無制限の悪化》という不気味な様相を呈することになった。
二度の世界戦争の起こった二〇世紀は、人間のシステマティックな破壊というラス・カサス的問題を再来させた。しかも、そこでは、人間の存在論的なステータスがいかに不安定で、いかに変わりやすいかという意識が際立たせられた。人間をそのままの状態で安置せず、その存在の条件にたえず干渉し続けること、場合によってはその条件をとことん「悪化」させること――この強力な介入のプログラムが文学、哲学、アートなどの諸領域で活気づいたのである[9]。
要するに、人間を別様に思考すること。それこそが二〇世紀思想の核心にほかならない。この企ての文学上の極限が、サミュエル・ベケットの《零度の主体》である(第十一章)。ベケットの場合、この企ては言語を別様に思考することと切り離せなかった。
この問題にアプローチするには、ベケットをその師ジェイムズ・ジョイスと比較するのがよいだろう。ジョイスの小説では、言語は社会的な流通のなかで、ウイルスのように変異しながら無限に増殖してゆく。その特性は、『ユリシーズ』のユダヤ系の主人公レオポルド・ブルームの関わる広告とよく似ている。ジョイス自身、広告のコレクターであり、宣伝標語の駄洒落を好んでいた。ジェニファー・ウィキーによれば「広告こそがモダニズムの、なかんずくはジョイスの『ユリシーズ』にとっての、模範的な言語体系なのである」[10]。まるで輪廻転生を思わせる広告のメッセージの迷宮的な反復と増殖こそが、『ユリシーズ』の言語ゲームの基盤となった。
それに対して、ベケット的人間は広告をとるどころか、職業ももたず、常にみすぼらしい欠乏状態にある。しかも、この人間(?)は、発話するごとにエラーを宣告される。「言うこと、それは言い間違えること」というベケットの有名な逆説は、「言うこと」がもはや「言われること」と決して一致しない状態で発せられる。言語と現実が必ず不一致に終わるのであれば、ベケット的人間はひたすら「言い間違え」を続けるしかない。ゆえに、哲学者のアラン・バディウが指摘するように、その人間は小説ともども、終わりなき「悪化」のプログラムという様相を呈するだろう[11]。
ベケットの小説とは、免れがたい失敗の膨大な履歴である。もっと良く間違えるか、あるいはもっと悪く間違えるか――この不毛な空回りをひたすら続行するベケット的人間は、あらゆる社会的属性を取り消され、言語からも見捨てられ、名前を所有する権利も失う。この脱人間的人間にとって、言語はもはやガラクタにすぎず、意味や文化を与える拠りどころにはならない。そのため、ベケットの小説では、人間の存在の地盤は一瞬ごとに崩壊し続けることになる[12]。世界の諸相を広告的にアーカイヴしようとするジョイス的な全体化の欲望は、ベケットにおいて極限的な貧しさと絶対的な失敗に反転するのだ。
その後、J・G・バラードの一九六〇年代のSFになると、属性を失った人間が物質化されるという新しい次元が開かれる。旱魃や暴風のような異常気象に巻き込まれた人間は、その心も含めて鉱物的なモノへと変質する(第九章参照)。しかも、この変身はもはや意外さや驚きを伴わない。コンラッドであれジョイスであれヴァージニア・ウルフであれ、モダニズムの小説にはまだショックを受け入れる主体があった。しかし、第二次大戦後のバラードの小説では、ショックを受ける主体すら蒸発してしまっている。主体は完全にインターフェースとなり、都市生態系との関係の束に還元される――この過剰な接続の情景こそがバラードの言う「夢」なのである[13]。
ベケットの場合、人間は世界とは端的に無関係であり、その無関係さが近似的に「間違い」と言い表される。逆に、バラードの場合、人間は狂った生態系に狂ったように接続されてゆく。ただ、いずれの小説でも、人間が人間的意味のフィールドの外で、ひたすら悪化の一途をたどることに違いはない。メアリー・シェリーの魅力的な短篇小説のタイトルを借りるならば、彼らは人間を「死すべき不死の者(The mortal immortal)」――人間としては死に続け、そのことによって生態系のなかで不死であり続ける存在――に作り変えた。この不可解な「夢」のなかでは、人間の可塑性はとめどなく増大してゆくだろう。
5、実験としての自然主義
スペインの征服者たちは、新世界のインディオを人間以下の野蛮な対象と見なして「破壊」したが、二〇世紀半ばの文学になると、ベケットやバラードのような旧世界のヨーロッパ人こそが、自らの「人間の条件」を根こそぎ解体してしまう。それによって、人間の可塑性と小説の可塑性はともに極限へと近づいた。人間だけが人間以外のものになれる能力をもつ、あるいは小説だけが小説以外のものになれる能力をもつ――この不思議な逆説が二〇世紀文学の根底に横たわっている。
破壊から可塑性へ――この推移はアンチヒューマンないしポストヒューマンな次元を押し広げたが、それは二〇世紀になって唐突に現れたわけでもない。先述した一八世紀の小説群に続いて、一九世紀前半のシェリーの『フランケンシュタイン』やゲーテの『ファウスト』には、人間の可塑性のテーマがはっきり刻印されているのだから。
ただ、われわれはシェリーとゲーテの違いにも留意するべきだろう。フランケンシュタインが自らの手で人間を制作したのと違って、ファウストは知識の追求に駆り立てられていたにもかかわらず、ホムンクルスの創造にはなぜか関与しなかった。ゲーテが示唆したのは、人間の限界を超えた新しい存在は、知的なコントロールの利かないところで偶発的に生じるということである。人間から人間以外のものへの推移は、厳密に計画できず、サイコロをふるような偶然性を伴っている。後のヴァージニア・ウルフの隠喩を用いて言えば、人間(人生)の周りには、人間以外のもの(非人称的なもの)の領域がぼんやりとした光の暈のようなアンビエントな状態で広がっており、そこへの推移は確率的に生じることになる。
その一方、一八六〇年代以降に台頭したフランスの自然主義の旗手エミール・ゾラになると、この偶発的な変容を管理する方向に向かった。ゾラが企てたのは、小説を人間の実験室に仕立てることである。
ゾラの代表的な評論「実験小説論」は、生理学者クロード・ベルナールの『実験医学研究序説』を模範としながら、文学も「実験的方法」の採用によって科学に近づくべきだと主張した。ゾラによれば「わたしたちはある情熱がある社会環境でどんなふうに働くかを実験によって示す実験的人間探究家なのである」。ゾラは観察と実験によって「人間機械を分解して再度組み立てなおす」ことを推奨した。この文学上のオペレーション(操作/手術)は、人間を支配する感情のメカニズムを制御し、管理し、最終的には無害化するための企てにほかならない[14]。
ゾラの自然主義は、心や社会を素朴に再現するというより、むしろそれらを存立させる条件に強く働きかけ、その干渉によって人間の隠れた次元を明るみに出そうとする実験文学であった。彼は感情をいったん部品単位にオーバーホール(分解)し、その後に再構築することを推奨した。その思想的背景には、ベルナールの医学に加えてダーウィンの進化論があった。人間性を不変のものではなく、むしろ自然淘汰の所産と見なす進化論は、自然主義の実験に強い推進力を与えたのである。
こうして、多くの重要な科学的発見の相次いだ一九世紀を通じて、文学における人間は可塑的な対象に仕上げられていった。ゾラをはじめ自然主義者は芸術家・娼婦・軍人という三つの人間類型を好んだが[15]、それは芸術・娼館・軍隊という特殊な閉域が、人間の実験を遂行しつつ管理するのにふさわしかったからである。人間は不可触の聖域ではなく、むしろ解体・構築されるべき機械に近づいた。ゆえに、自然主義はその名に反して、反自然主義や人工主義と呼ばれるべき要素をもっている。このようなゾラふうの「人間機械論」が、二〇世紀になるとSFにおいて一挙に花開いたのは、言うまでもない。
このような可塑性の強調は、一面において自由の拡大につながるだろう。ゾラはまさに環境の圧力からの解放をめざして、文学の科学化を構想した。しかし、この可塑性の高まりは、人間やその言葉が、いかに外的な圧力によって容易に変形されるかも示している。繰り返せば、ベケットやバラードの小説から浮かび上がるのは、誰もあらがうことのできない強烈な力にさらされ、根本的に変容してしまった人間、つまり人間以外のものにしかなれない人間であった。ならば、可塑性というテーマには、暴力と自由、人間性の破壊とそこからのリハビリテーションがともに内包されているのではないか。
私の考えでは、二〇世紀文学の根本問題は、まさに人間の可塑性のもつ両義性にある。そのことを、イギリス人作家ジョージ・オーウェルが一九四九年に刊行した『一九八四年』(引用は高橋和久訳[ハヤカワ文庫/トマス・ピンチョンによる文庫解説も含む]に拠り、頁数を記す)、およびその三年後に出たアメリカの黒人作家ラルフ・エリスンの『見えない人間』(引用は松本昇訳[白水社]に拠り、頁数を記す)から改めて検討してみよう。
6、可塑性を利用する芸術家――オーウェルの『一九八四年』
架空の全体主義国家オセアニアを舞台とする『一九八四年』では、戦時下の党を率いるビッグ・ブラザーが、テレスクリーンを用いて社会の全体をくまなく監視している。真理省記録局に勤務するウィンストン・スミスは、過去の文書の改竄に従事しているが、やがて魅力的な女性ジュリアと出会ったことをきっかけに党の禁を破る。彼女との性的関係だけが、この息苦しい社会での唯一の避難所となるのだ。しかし、それは本人があらかじめ予想していたように、破局を迎える。逮捕されたウィンストンは、オブライエンの狡猾な拷問によって、心から党への愛を誓う人間に作り変えられてゆく。
もとより、このような常時監視システムにどれほどリアリティがあるかは、検討の余地がある。例えば、アンソニー・バージェスはオーウェルを批評した『一九八五年』のなかで、アメリカがベトナム戦争を遂行しながら、同時にそれを娯楽的なテレビ番組として国民に消費させたことを皮肉っぽく指摘し、オーウェルの社会像の限界を言い当てている[16]。実際、物質的窮乏を国民に強いる架空のオセアニアと異なり、戦後の現実の先進国は、むしろ豊かさや娯楽を統治の手段とした。この点に限っては、同じイギリス人作家オルダス・ハックスリーの『すばらしき新世界』(一九三二年)の描いた管理社会――人間を生物的次元で巧妙にコントロールする快適なユートピア――のほうが、『一九八四年』よりも明らかに予見的であった。
ただ、『一九八四年』にはもう一つの重要なテーマがある。それは、思考および言語の可塑性に関わる問題である。オーウェルが描いたのは、人間を単一のイデオロギーに盲目的に従わせる単純なメカニズムではない。ウィンストンやオブライエンを含めて、オセアニアの人間たちは二重思考(doublethink)の実践者として描かれる。それは党の支配のもとでは民主主義はないと知りながら、党が民主主義の擁護者であると信じる思考様式である。嘘をつくことと信じることを、何ら矛盾なく両立させるアイロニーが浸透したとき、ひとびとは自ら進んで思考を柔軟に調整し、全体主義社会に適応するようになる。
オーウェルはこのアイロニカルな思考様式を、「ニュースピーク」と呼ばれる新しいタイプの人工言語と連携させた。言語が単純化されて、繊細なニュアンスを失えば、思考を社会にあわせて調整し、過去の出来事を都合よく訂正することも容易になるだろう。ウィンストンはまさにそのことに強い恐怖を覚えている。「もし党が過去に手を突っ込み、この出来事でもあの出来事でも、それは実際には起こっていないと言えるのだとしたら、それこそ、単なる拷問や死以上に恐ろしいことではなかろうか」(五五頁)。「歴史は止まってしまったんだ。果てしなく続く現在の他には何も存在しない。そしてその現在のなかでは党が常に正しいんだ」(二三九頁)。
こうして、思考も言語もまさにその柔軟な可塑性ゆえに、党への抵抗力を奪われる。ウィンストンを執拗に虐待するオブライエンは、この仕組みを正しく理解していた。彼の振る舞いは、ある意味ではきわめて洗練されている。かつてスペイン人の征服者が多数のインディオを「破壊」したとすれば、オブライエンは一人の人間のもつ多数の思考を入念に滅ぼした後、別の形態に作り変えるのだ。彼がウィンストンら囚人を閉じ込め、徹底的に洗脳する密室は、まるでゾラ的な実験室のグロテスクなヴァージョンのように見える。そして、このような思考の実験的なジェノサイドが可能なのは、オブライエンが人間の可塑性を熟知しているためである。
われわれが人生をすべてのレベルでコントロールしているのだよ、ウィンストン。君は人間性と呼ばれるような何かが存在し、それがわれわれのやることに憤慨して、われわれに敵対するだろうと思っている。だがわれわれが人間性を作っているのだ。人間というのは金属と同じで、打てばありとあらゆるかたちに変形できる。(四一七‐八頁)
哲学者のリチャード・ローティは『一九八四年』を分析するなかで、オブライエンに「オーウェルの青年時代におけるイギリス知識人の典型的な特徴のすべて」が与えられていると見なし、そこにオーウェルの世代の知的アイドルであったジョージ・バーナード・ショーの面影を認めている。洗練された知識人オブライエンは、その美的な趣味と知的な能力を最大限に発揮して、犯罪者を矯正する卓越した拷問官になった。ローティによれば、オブライエンが知的でありつつ残酷であることは、何ら不思議なことではない。なぜなら「知的な天分――知性、判断力、他への関心、想像力、美への趣味――は性的な本能と同じように可塑的で柔軟なもの」であり「人間の手と同じように、多種多様な形をとりうる」からである[17]。そのことを最も明瞭に自覚していたのがオブライエンなのだ。
そもそも、『一九八四年』は最初から、人間の感情を可塑的なもの、つまり抽象的で無軌道なものとして描いていた。テレスクリーンから定期的に流れる「二分間憎悪」という奇妙なイベント――「人民の敵」とされるエマニュエル・ゴールドスタインへの糾弾が二分間続けられる――のもたらす群衆の熱狂のなかで、ウィンストンの怒りの感情の向かう先は「鉛管工の使うガスバーナーの炎のように」めまぐるしく転換する。
ウィンストンにしても、ある瞬間の怒りはゴールドスタインには少しも向かわず、それどころか、〈ビッグ・ブラザー〉や党や警察に向けられる。そして、そうしたときにはスクリーンに映っている孤独で皆の嘲笑の的である異端者、虚偽の世界における真実と正気の唯一の守護者へと気持ちが傾くのである。ところがその次には、あっという間にまわりの人間と同化し、ゴールドスタインについて言われていることはすべて真実だと思えてくる。そうした瞬間には、彼が密かに抱いている〈ビッグ・ブラザー〉への嫌悪感は敬愛の念へと変化し、〈ビッグ・ブラザー〉は恐れを知らぬ無敵の擁護者として辺りを睥睨する存在であり、アジア人の大群に立ちはだかる巌のように思えてくる。(二六頁)
ここには、ドストエフスキーの登場人物を思わせる二日酔い的な混乱がある。ウィンストンはオブライエンに拷問される前に、すでに変わりやすい感情に支配されていた。「二分間憎悪」においては、ただ感情の激しいアップダウンだけがあり、怒りの矛先は瞬時に切り替えられる――しかも、このアドレス変更はほとんど当人の自覚なしに生じるのだ。この場面は架空の全体主義社会の描写にとどまらず、現実の大衆社会の集合的感情を絵解きしたものにも思える。怒りは群衆の連帯を支える。しかし、それは短時間のイベントに回収され、その怒りの軌道も簡単に変わるのである。
われわれはここで、オーウェルが『ガリヴァー旅行記』についての優れた批評家であったことを思い出そう(第十章参照)。スウィフトが人間の可塑性を強調したように、オーウェルもアイロニカルな二重思考と単純化されたニュースピークという装置のなかで、人間性がいかに変わりやすいかを示した。オブライエンは自らの思考を一切傷つけることなく、きわめて繊細なやり方で党のイデオロギーに順応する。そして、彼はまさにその同じ技術を用いて、ウィンストンの思考を計画的に訂正した。
オーウェルはもともと、原案では『一九八四年』を『ヨーロッパ最後の人間』と題していたが、この形容はウィンストン以上にオブライエンに当てはまるのではないか。オブライエンは知性的であることと残酷であることを、良心の呵責なく両立させる「最後の人間」(ニーチェの言う末人)である。ローティが言うように、人間の「知的な天分」はそれほどに「可塑的」なのであり、そしてこの可塑性を知り尽くした知識人こそが不正を遂行するのだ。このような暗いヴィジョンをもつ小説家にとって「人生にたいする純粋に美学的な態度」はもはやあり得ない。晩年のオーウェルが「政治による文学にたいする侵犯」を積極的に招き寄せようとしたのは、そのためである[18]。文学もまた、政治による介入を受け入れざるを得ないのだ。
7、可視的な透明人間――オーウェルからラルフ・エリスンへ
ところで、テレスクリーンという装置に象徴されるように、オーウェルは社会の全面的な可視化を想定していた。ウィンストンとオブライエンもまた、お互いの姿をしっかり視認している。そして、このあらゆる私的な秘密を視覚的にあばく透明社会のメカニズムが、思考や言語の管理とコントロールを徹底し、全体主義体制からの逃走を失敗に終わらせる。
しかし、『一九八四年』からまもなくして、一九五二年に刊行されたアメリカの黒人作家ラルフ・エリスンの『見えない人間』では、オーウェル的監視社会とは正反対の状況が描かれている。ウィンストンやジュリアが全面的な可視化にさらされていたとしたら、エリスンの捉えたアメリカ社会の黒人は、むしろ不可視(invisible)だと見なされる。『一九八四年』と『見えない人間』のこの興味深いコントラストは、アフリカ系アメリカ人がヨーロッパの白人とは異なる文学的課題を背負ってきたことを示唆している。
トマス・ピンチョンが『一九八四年』に関する評論で注目したように、オーウェルの描く近未来の国家ではすでに人種差別は撤廃されており、ユダヤ人や黒人、インディオにも入党の資格が与えられていた。ただ、ピンチョンによれば、この「ありそうもない人種的寛容」は、小説のリアリティをいくぶんか損なっている(四九八頁)。逆に、エリスンはアメリカの人種差別の存在を前提として、そこで生じる認識の偏向を問題にした。『見えない人間』の主人公のブルー(憂鬱)な黒人青年――その名は最後まで明かされない――は、その語りの冒頭から白人の「内的な眼」の歪みを批評する。
僕は見えない人間である。かといって、エドガー・アラン・ポーにつきまとった亡霊のたぐいではないし、ハリウッド映画に出てくる心霊体(エクトプラズム)でもない。実体を備えた人間だ。筋肉もあれば骨もあるし、繊維もあれば肉体もある。〔…〕人は、僕の近くに来ると、僕の周囲のものや彼ら自身を、あるいは彼らの想像の産物だけを――要するに、僕以外のものだけを見るんだ。(上・二九頁)
ルイ・アームストロングの歌(どうしておれはこんなに黒くて/こんなにブルーなのか)を聴き、マリファナを吸いながら、彼は「時間の裂け目」に滑り込む。「言いわけになるが、不可視性のせいで僕には人と少し違った時間の感覚があって、完全にリズムにのるというわけにはいかない。進みすぎる時もあれば、遅れすぎる時もある。気づかないほどの時間の速い流れではなく、僕には節目が、つまり時間がぴたりと止まったり先にサッと進んだりする瞬間が分かるのだ」(上・三五頁)。
ときに加速し、ときに遅延する主人公の語りは、人生の時間に麻薬的な抑揚を与えている。この不安定なアゴーギク(テンポの変動)のもとで、『見えない人間』は黒人青年の語る長大な「自伝」の様相を呈する。彼はもともと南部のアラバマ州の大学――ツタで覆われ、スイカズラやマグノリアの花の咲く美しい田園として描かれる――の学生であったが、北部出身の白人理事ノートンをうっかり旧奴隷地区、さらには戦争神経症を患った黒人帰還兵の集う酒場に案内するという失態のせいで、大学を追放され、ニューヨークに移住する。ここには大学の欺瞞的なあり方とともに、聖書の「楽園追放」が意識されているのは明らかだろう[19]。
その後、彼はちょうど拷問を受けるウィンストンのように、病院で電気ショックを与えられるという苦難を経て、『一九八四年』の地下抵抗組織「ブラザー同盟」ならぬ「ブラザーフッド同盟」――黒人の自由と能力を解放するために民衆運動の組織をめざすサークル――に参加し、演説の才能を発揮する。しかし、警官に不当に射殺された黒人を弁護したことで、彼とブラザーフッド同盟の関係は悪化してしまう。やがて白人警察に追われるうちにマンホールのなかの黒い石炭の山に転落した彼は、白人専用ビルの地下室の人間、つまり孤独な「見えない人間」となり、ドストエフスキーの『地下室の手記』の自意識過剰な主人公のように、自らの人生を回顧するノートを書くのである。
エリスンはニューヨークの無名の黒人青年を、いわば可視的な透明人間(The visible invisible)として描いた。黒人はその肌の色、つまり可視的・表面的な情報で差別される。そして、まさにそのことによって黒人の状況そのものが不可視化されるというのが、エリスンの提示した逆説であった。それは、全面的な可視化を恐怖と見なすオーウェルの『一九八四年』には欠けていた問題である。
8、新世界のなかの旧世界
では、ラルフ・エリスンは、この不可視化された領域にいかにアクセスしたのか。ここで特筆すべきは、彼が特異な語りの技法を駆使したことである。
なかでも、太陽の照りつける旧奴隷地区で、白人のノートンに向けて自らの人生の罪を語る黒人の農民トゥルーブラッドの長広舌は、忘れがたい印象を与える。ブルースの歌手であり、恐ろしく雄弁な語り手でもあるトゥルーブラッドは、白人が黒人から何を聞きたがっているかを敏感に察知し、自らの犯した近親相姦(娘との性交)の話を淀みなく語る。この呪文のような自伝的な語りを、ノートンとともに聞かされた主人公は「屈辱感と恍惚感の狭間」で心をかき乱される(上・一一五頁)。
著名な黒人文化研究者のヒューストン・ベイカー・ジュニアが指摘したように「トゥルーブラッドの話は、聞き手の期待に応えてきわめて性的である」。つまり、トゥルーブラッドの語り口とその内容は、主流のアメリカ社会で公認され流通している「商品」であり、黒人=性的人間というイメージに順応している[20]。『見えない人間』では、主人公を含めて黒人たちがそれぞれの立場から「自伝的」に語るが、それは商品化=性化されたレイシズムによって制約されている。
ただ、その一方で、主人公やトゥルーブラッドの語りはまさに「時間の裂け目」で、事象を際限なく引き延ばす力をもつようにも思える。その語りはたとえ白人向けの商品であるとしても、常軌を逸した異様な商品である。白人が偏向したまなざしで黒人を見る――そしてそれによって見ない――のだとしたら、エリスンはその不可視の領域に、尽きることのない音と語りの響きを与えようとした。
トゥルーブラッドの語りが、ブルースの伝統に属することは重要である。エリスン自身は「ブルースは叙情的に表現された個人の破局の自伝的記録である」と指摘した[21]。ブルースは残酷な仕打ちを、叙情的な歌に移し替えることによって、その苦痛からの超越を求める。エリスンにとって、自伝的なブルースはまさに「屈辱」と「恍惚」を、いつ終わるとも知れない持続する時間のなかで体験させる。黒人の語りは、確かに白人の欲望に基づいてアレンジされるが、それはたんなる順応を超えて《時間の可塑性》を際立たせるのだ。
それにしても、ブルースによって拡大された「時間の裂け目」は、もとはいかに生じたのだろうか。それは二つの世界の大規模な接触によってである。歴史的に見れば、エリスンの文学の背景には黒人たちの「大移住」(great migration)、つまり一九一〇年代半ば以降に進んだ、前例のない規模の移住があった。かつて奴隷の境遇にあり、移動の自由を制限されていた黒人が、二〇世紀前半になると、都市に大挙して向かうようになったのである。エリスン、リチャード・ライト、ジェームズ・ボールドウィンらの黒人文学は、いずれも南部の田舎の黒人が北部の都市に移住した、この大変動の産物である。この特異な現象は、一七世紀のヨーロッパ人の植民者がアメリカに移住したことの反復でもあった[22]。つまり、アメリカ誕生の神話が、黒人の移動によって再演されたのである。
もとより、南部とは、アメリカという「新世界」において再創造された「旧世界」である。しかも、それは、ヨーロッパ=旧世界よりも古い旧世界なのだ。私は先ほど「諸世界のあいだのギャップこそが〈世界〉を生み出す」と述べたが、アメリカは一国のなかに、時差を含んだ諸世界がある。『見えない人間』のニューヨークは、新旧二つの世界のコンタクト・ゾーンとして描き出される。
このような諸世界性は、『見えない人間』を『一九八四年』と差異化する要因にもなった。オーウェルが描いたのは、単一の世界である。オセアニアの外部は、事実上存在していない。三つの超大国はいずれもピラミッド型の全体主義社会であり、経済のために戦争を続けている点でも共通する。米ソの冷戦(cold war)という言葉の生みの親にふさわしく、オーウェルはウィンストンとオブライエンという二者を鏡像のように向きあわせたが、それは『一九八四年』の世界が単一化されていることと切り離せない。
それに対して、ラルフ・エリスンの『見えない人間』は地上と地下、白人と黒人、北部と南部という二つの世界に分裂している。つまり、同一に思える世界は、実際には一つでなく、そこにはさまざまな「裂け目」がある。エリスンの主人公は、この時間的・空間的なギャップに潜り込むことによって「見えない人間」となった。エリスンが取り組んだのは、黒人の生を、社会的現実を超えた「超現実」に置き直そうとする一種のシュルレアリスム的な企てである[23]。それはただの空想ではない。大規模な移住は、それ自体が超現実的な現実を生み出すのだから。
9、人間を資源化するレイシズム
私は本章を、新世界におけるインディオの「破壊」という衝撃的な事件から始めた。ただ、アメリカの先住民がヨーロッパ人を理性や信仰に改めて向きあわせたのに対して、アフリカの黒人はそのような大規模な議論を引き起こさなかった。ラス・カサスでさえ、当初はアメリカ大陸のインディオの状況を改善するために黒人奴隷の導入を推奨していた――もっとも、彼は後年、アフリカでポルトガル人が黒人奴隷を不正に捕虜にしていたことを知り、過去の自分の不適切な発言を、深い悔恨の念とともに改めたのだが[24]。
ここからは、アフリカの黒人の苦境がインディオ以上に軽視されていたことがうかがえる。この苦境を固定化する言説がレイシズムである。エリスンはあるエッセイで、黒人が「制度化された非人間化の過程を辿るべく選ばれた人間的「天然」資源と認識されるようになった」と指摘している[25]。人種差別は確かにヒエラルキーを固定化し、黒人を資源として扱うことを追認する言説であった。二〇世紀アメリカの黒人の「大移住」は、この固定的な枠組みを揺るがすだけの社会的なインパクトをもったが、それはレイシズムの消滅を意味しなかった。ここには根深い構造的問題がある。
もとより、主人は、奴隷がいなければ主人たり得ない。奴隷を再生産しなければ、主人の地位を保つことはできない。レイシズムはこの構造を持続させるために導入される。イマニュエル・ウォーラーステインは、偽装しにくい「肌の色」を都合の良いレッテルとして利用するレイシズムが、資本主義のシステムの支柱になったことを指摘した。
人種差別は決して単純な現象ではなかった。いわば、世界システム全体のなかでの相対的ステイタスを画するひとつの区分線があった。すなわち、「肌の色」による区分線なるものがそれである。〔…〕
人種差別こそが史的システムとしての資本主義の唯一のイデオロギー的支柱であったし、それはまた、適当な労働力をつくりあげ、再生産してゆく上でもっとも重要なものであった。[26]
ウォーラーステインはここで表層(可視的なもの)と深層(不可視なもの)、この二つの作用から人種差別を理解しようとしている。前者は記号的なレッテル、ルックス(仮象)としての「色」である。それに対して、後者はカラー・ラインをたえず引き直し、主人を支える従属者(奴隷)を供給し続ける世界システムの構造である。歴史家エリック・ウィリアムズ――トリニダード・トバゴの初代首相であり、一九一四年生まれのエリスンと同世代でもある――の有名な見解を思い出すならば、人種差別から奴隷制が生まれたのではなく、逆に人種差別が奴隷制に由来する[27]。ウォーラーステインやウィリアムズの考えでは、奴隷制という経済問題が、黒人の資源化を正当化するレイシズムの原因なのである。
このような構造的な問題は、たんに良心の力だけで変更することはできない。確かに「肌の色」はたかだか表層的なレッテルにすぎないが、それを認識したからと言って、ヒエラルキーがただちに壊れるわけではない。それどころか、肌の色という外見を人間の奥深い本質と見なす言説は、ゲーテのようなヨーロッパの偉大な教養人によって強化された。ゲーテは『色彩論』(一八一〇年)で、色彩を求めてやまない人間の内的欲求を指摘しながら、肌や髪の色がいかに人間の根源に結びついているかを例示した。彼によれば、ブロンドの髪と褐色の髪の人間とでは、その性格に「著しい相違」がある。そして、最も優れた色は白である。
これまでに見聞したすべてのことがらの結果として、われわれはあえて次のように主張したい。白人、すなわちその表面が白色から黄色味や褐色や赤味を帯びた色への変化を示している人間、要するにその表面が最も未決定の色に見え、何かある特殊な色彩に傾くことがほとんどない人間は最も美しい、と。[28]
ゲーテの考える白は、まさに貨幣に似ている。つまり、白とは何にでも交換できる能力を備えた色、単色でありながら無限に変化し得る色であり、ゆえに白い人間は他のいかなる人種よりも美的に優越している。しかし、このような無限の可塑性や柔軟性――繰り返せば『一九八四年』はそれをむしろ悪夢に変えたのだが――が強調されるとき、資源として固定された黒人の現実は隠蔽されざるを得ない。
ただ、その一方、ゲーテは『ファウスト』では、無限の変身能力を備えたメフィストフェレスを黒い犬に変化させていた。ゲーテが理論的には白を特権化しながらも、文学では黒い悪魔に白と同等の力を与えたのは興味深い。白い主人ファウストは黒いメフィストフェレスがいなければ、生まれ変わることができなかった。二〇世紀のラルフ・エリスンは、この白と黒の織りなす色彩の政治に対して、「人目につくのに見えない」という新たな逆説を付け加えたと言ってよい。
10、世界文学の影――デフォーとイクイアーノ
私は〈世界文学〉を諸世界の狭間の文学として捉えた。この観点からは、四〇〇年の文学史が大きな弧を描いているように思える。一六世紀に旧世界の征服者が新世界の人間(インディオ)と接触したとき、文学の世界性が萌芽した。そして、この世界で物言わぬ「資源」として影に隠された黒人が、二〇世紀のアメリカ文学において諸世界性を再生させた。
二〇世紀半ばに現れたオーウェル、ベケット、バラードの小説は、たとえどれだけ異様に見えたとしても、ヨーロッパ文学の進化史の延長線上で了解できる。彼らの文学はスウィフト、シェリー、ゲーテ、ゾラらが人間の可塑性を拡大し、人間を人間以外のものに接近させようとする、その企ての果てに現れた。しかし、このような「実験」の背後で、黒人ははじめから非人間的な資源として歪められていたのではなかったか。
このように言うのは、一九世紀以前にはむしろ黒人を主体とする文学の予兆があったからである。もとより、文学史における黒人の表象の全貌をつかむのは不可能だとしても、いくつかの興味深い例を挙げられる。それはシェイクスピアの『オセロー』のように黒人(ムーア人)を主人公とする戯曲ばかりではない。
ロンドンではフランス革命と同年の一七八九年に、現在のナイジェリア生まれの元黒人奴隷オラウダ・イクイアーノが英語で記した自伝『アフリカ人、オラウダ・イクイアーノことグスタヴス・ヴァッサの生涯の興味深い物語』が刊行された。イクイアーノは故郷アフリカのしきたりやその清潔好きの習慣を紹介した後、拉致されて奴隷船の「積み荷」にされるという受難の経験を語る。つまり、肌の色の異なる恐るべき怪物たちによって、彼はまっとうな人間的な生活から、処分可能なモノへと強制的に変化させられた。
その後、イクイアーノは船旅の途中で目にした西インド諸島での奴隷の処遇の悲惨さや白人詐欺師のずる賢さを詳しく述べる。しかし、彼がただ騙される一方であったわけではない。イクイアーノはやがてキリスト教に改宗するとともに、経済的な成功を収める。彼の自伝的な語りは、神の摂理によって自由を獲得し、救済されるというストーリーに沿って進められてゆく。
ヒューストン・ベイカー・ジュニアによれば、イクイアーノの信仰のドラマを動かすのは「奴隷の経済学」である。というのも、売買される「動産」であったイクイアーノは、やがて自らが商品を扱う商人に成長するからだ。彼の自伝的なテクストは「世俗的な商人の日記」のように、取引を記録した帳簿に似ている[29]。彼にとって、自由は買い取られるべき商品と同じであり、取引の履歴こそが、彼のアイデンティティの核となった。
イクイアーノの自伝は黒人の「奴隷物語」の雛型となったが、その人生行路は半世紀以上前のデフォーの主人公のそれと、奇妙なまでに共通している。『モル・フランダーズ』の女性主人公と同じく、イクイアーノもアメリカのヴァージニア州とイングランドを移動する。さらに、故郷を離れて海賊の捕虜となり、やがて自分ひとりの島を手に入れて自立するロビンソン・クルーソーのように、イクイアーノも危機に満ちた航海のなかで船長となり、敬虔な信仰にめざめた勤勉な「経済人」として成功するのだ。自由を奪われて、恐怖と不安にさらされた俘虜が、経済的・宗教的地盤を手に入れて独立的な主体となる――デフォーとイクイアーノはこの主体形成の物語を共有していた。
しかも、イクイアーノの移動経路は、まさにクルーソーと同じく環大西洋的な広がりをもっていた。ヴァージニア、フィラデルフィア、マルティニク、イングランド等を横断するイクイアーノは、まさに黒人のグローバリストであり、その〈世界〉との遭遇こそが白人の優位性を解体することになる。彼はキリスト教の神の名のもとに、肌の色を理由とした偏見を除去せよと「上品で傲慢なヨーロッパ人」に命じた。
自分たちが優越しているという高慢を溶かして、異色の兄弟たちの困窮と悲惨な状況に対する共感に変えよ。そして、知力は顔つきや肌の色にしたがって限定されないことを認めよ。世界を見渡して、もし歓喜を感じるのなら、その歓喜を和らげて他者への慈悲心に、そして、神への感謝にせよ。神は「一人の人からすべての民族を造り出して、地上の至るところに住まわせ」、その知恵はわれわれの知恵とは異なり、そのやり方はわれわれのやり方とは異なるのだ。[30]
これは実に驚くべき命令である。イクイアーノはヨーロッパの白人以上に信心深いキリスト教徒となって、神の意志を正しく実行するように宣告するのだから。ここには、ラス・カサスにも通じる普遍主義がある。
私は二〇世紀半ばのオーウェルとエリスン、イギリスの白人文学とアメリカの黒人文学を対置したが、そもそも世界文学の源流には、イギリス人デフォーとアフリカ人イクイアーノという、交差することのなかった二人の一八世紀作家がいた。人間の悪に直面した彼らは、ともに交換の力によって、そこからの人間性のリハビリを企てた。しかし、新世界における「悪の発見」という傷はその後も完治することなく、世界文学の人間像に不気味な揺らぎを与え続けたのである。
[1]グスタボ・グティエレス『神か黄金か』(染田秀藤訳、岩波書店、一九九一年)四一頁。
[2]同上、六、一七六頁。むろん、スペイン人をたんに粗野で邪悪な集団と見なすのは誤りである。グティエレスが強調するように、彼らは植民地支配の是非を神学的・法的な問題として徹底的に検討したのだから。「インディアスにおけるヨーロッパの存在の合法性と正当性に関する大論争を行う勇気は、スペインにしかなかったという事実」(二頁)は重要である。しかも、この大論争は、主観的な反省や訂正では終わらず、法的な責任論にまで及んだ。ラス・カサスは、財産と生命を不当に奪われたペルーへの賠償責任について論じている。彼の『インディアスの破壊をめぐる賠償義務論』(染田秀藤訳、岩波文庫、二〇二四年)参照。
[3]ラス・カサス『インディオは人間か』(染田秀藤訳、岩波書店、一九九五年)訳者解説参照。
[4]ホセ・アコスタ『新大陸自然文化史』(上巻、増田義郎訳、岩波書店、一九六六年)訳者解説参照。
[5]J・H・エリオット『旧世界と新世界 1492-1650』(越智武臣+川北稔訳、岩波書店、一九七五年)三二、八三頁。
[6]清水憲男『ドン・キホーテの世紀』(岩波書店、二〇一〇年)二九‐三〇頁
[7]エリオット前掲書、一二〇頁。
[8]ガリヴァーは続けて、新世界に上陸した海賊がその貪欲ぶりを発揮して、先住民を虐殺する姿を想像している。これは、ラス・カサスの報告、さらには後のコンラッドの『闇の奥』とも共通する植民地での強奪の情景である。Claude Rawson, God, Gulliver, and Genocide, p.18.
[9]例えば、ロシアの共産主義(ボリシェヴィズム)は、人間そのものを新人類に生まれ変わらせようとする、誇大妄想的な構想をもっていた。共産主義と「新しい人間」への欲望の結合については、佐藤正則『ボリシェヴィズムと新しい人間』(水声社、二〇〇〇年)が詳しい。この「新しい人間」への志向は、ソ連の積極的な宇宙進出とも関わるだろう。いわばスターリン(共産主義)はガガーリン(宇宙)によって補完されるのだ。
[10]ジェニファー・A・ウィキー『広告する小説』(富島美子訳、国書刊行会、一九九六年)二〇六、二四五、二六八頁。
[11]アラン・バディウ『思考する芸術』(坂口周輔訳、水声社、二〇二一年)一八九頁。
[12]О・ベルナル『ベケットの小説』(安堂信也訳、紀伊國屋書店、一九七二年)一七、三六、七二、一一六頁。
[13]ジョナサン・クレーリー「J・G・バラード――散乱する形態」(浅田彰+市田良彦訳)『GS』(第四号、一九八六年)五一六頁
[14]ゾラ「実験小説論」(古賀照一訳)『新潮世界文学』(第二一巻、新潮社、一九七〇年)八〇三頁。なお、生理学者による生物改造を描いたH・G・ウエルズの『モロー博士の島』(一八九六年)では、ベルナール=ゾラ的な「実験」に内在する悪夢的要素が誇張されている。詳しくは、拙著『感染症としての文学と哲学』第四章参照。
[15]アラン・パジェス『フランス自然主義文学』(足立和彦訳、白水社、二〇一三年)一〇四頁。
[16]アントニイ・バージェス『1985年』(中村保男訳、サンリオ文庫、一九八四年)三一六頁。さらに、フェミニズム批評の視点からは、『一九八四年』が徹底して男性中心主義的であることも批判の対象となった。支配層も反逆者もともに「ブラザー」として描く一方、ジュリアのような女性をもっぱら性的存在に押し込めたオーウェルに、ミソジニーの要素があることは否定できない。
[17]リチャード・ローティ『偶然性・アイロニー・連帯』(齋藤純一他訳、岩波書店、二〇〇〇年)三八七‐八頁。
[18]レイモンド・ウィリアムズ『オーウェル』(秦邦生訳、月曜社、二〇二二年)四二頁。
[19]チャールズ・スクラッグズ『黒人文学と見えない都市』(松本昇他訳、彩流社、一九九七年)一六〇頁。
[20]ヒューストン・A・ベイカー・ジュニア『ブルースの文学』(松本昇他訳、法政大学出版局、二〇一五年)三一九‐二〇、三四八頁。
[21]ラルフ・エリスン『影と行為』(行方均他訳、南雲堂フェニックス、二〇〇九年)九七頁。
[22]スクラッグズ前掲書、二七頁。荒このみ『アフリカン・アメリカン文学論』(東京大学出版会、二〇〇四年)一六七頁。
[23]実際、ジャズの評論家でもあったエリスンは、アメリカの黒人たちが再創造したシュルレアリスムに隣接していた。第一次大戦後のパリに生まれたシュルレアリスムは、まさに言葉の可塑性を拡大したことによって、黒人の恐怖や怒りを、新しい社会関係や新しい生の様式に転換させる力となった。ロビン・ケリーによれば「シュルレアリスムは、美学の教義などではなくて思考の解放にかかわる国際的な革命運動なのである」。エメ・セゼールのようなマルティニク島の黒人詩人からセロニアス・モンクのようなアメリカの黒人ジャズピアニストに到るまで、シュルレアリスムは超現実的な生き方に向けた技法として、つまり現実的な生への「介入」として利用された。ロビン・D・G・ケリー『フリーダム・ドリームス』(高廣凡子他訳、人文書院、二〇一一年)二〇、二五七頁。
[24]グティエレス前掲書、一五五頁以下。
[25]エリスン前掲書、四七頁。
[26]ウォーラーステイン『史的システムとしての資本主義』一二六、一二八頁。なお、主人が奴隷に依存すること、つまり奴隷制こそが近代の前提であることを早くに見抜いたのは、哲学者のヘーゲルである。ポール・ギルロイ『ブラック・アトランティック』(上野俊哉他訳、月曜社、二〇〇六年)一一一頁。
[27]エリック・ウィリアムズ『資本主義と奴隷制』(中山毅訳、ちくま学芸文庫、二〇二〇年)二〇頁。
[28]ゲーテ『色彩論』(木村直司訳、ちくま学芸文庫、二〇〇一年)三四一-二頁。荒前掲書は、白人こそ美しいというゲーテの考えを、ヨーロッパの「カラー・フォビア(肌の色恐怖症)」の一つの原点を見なしている(六七頁)。
[29]ベイカー前掲書、五九-六〇頁。
[30]オラウダ・イクイアーノ『アフリカ人、イクイアーノの生涯の興味深い物語』(久野陽一訳、研究社、二〇一二年)二二‐二三頁。
この記事は、PLANETSのメルマガで2024年5月24日、5月28日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2024年6月13日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。