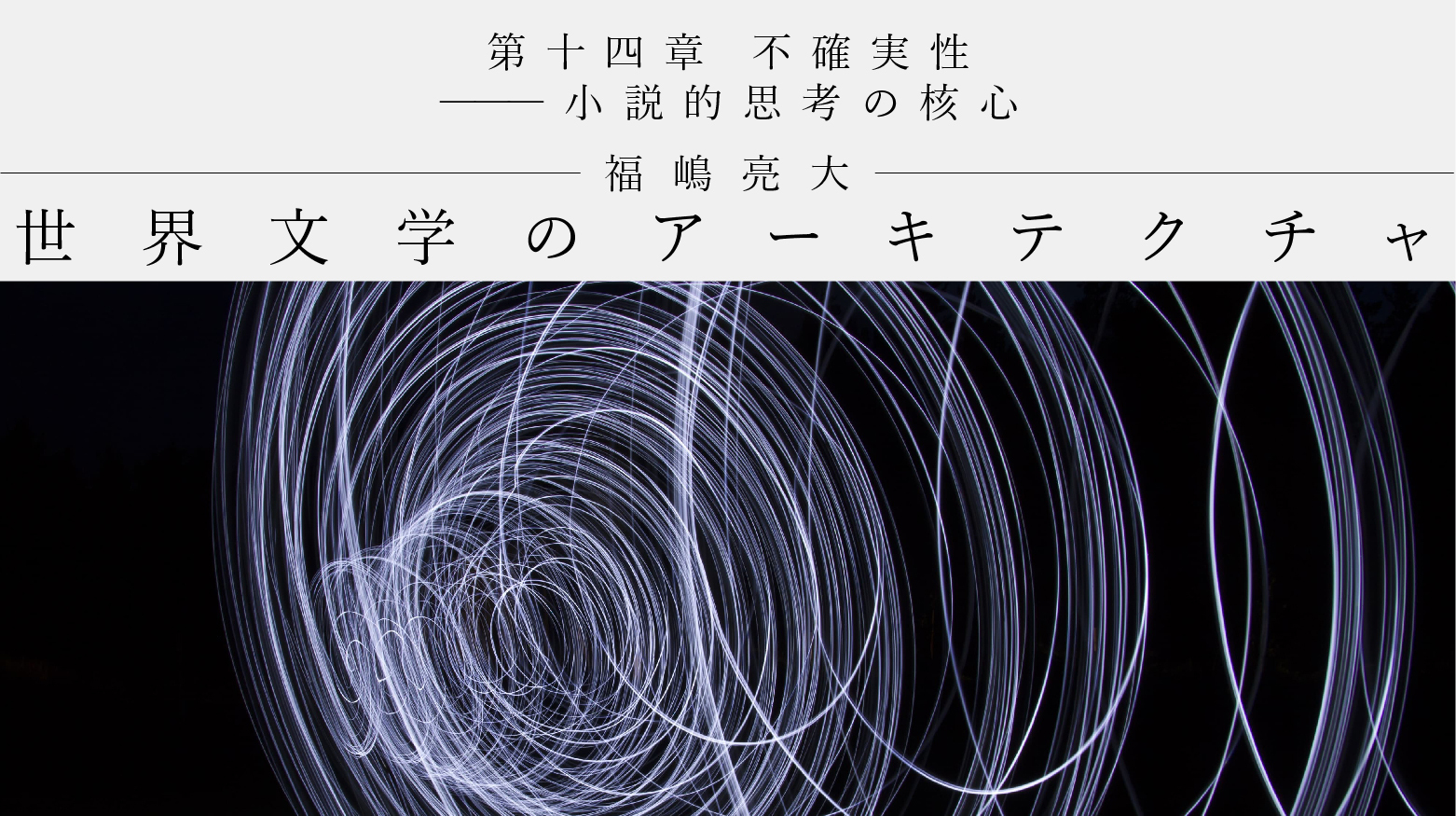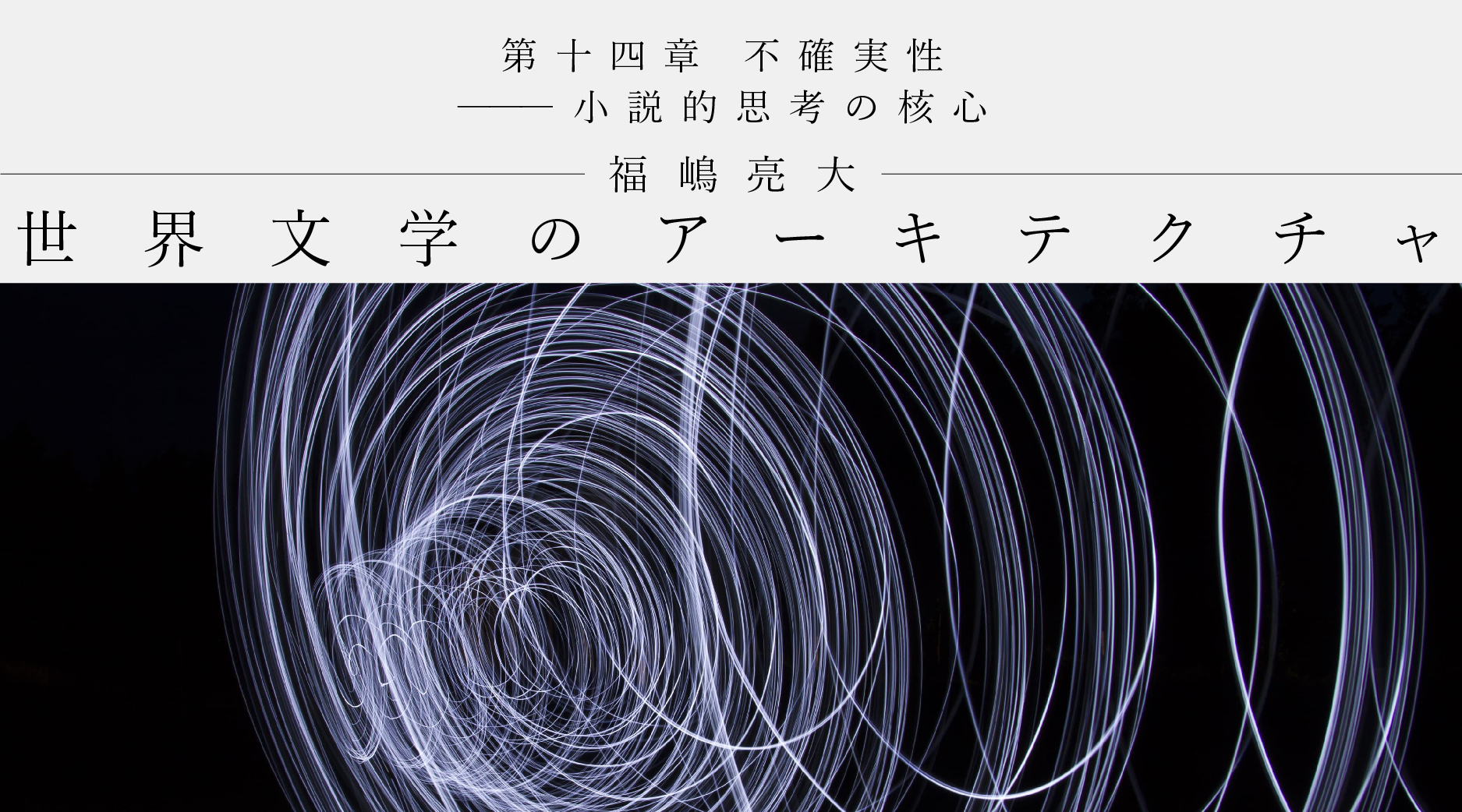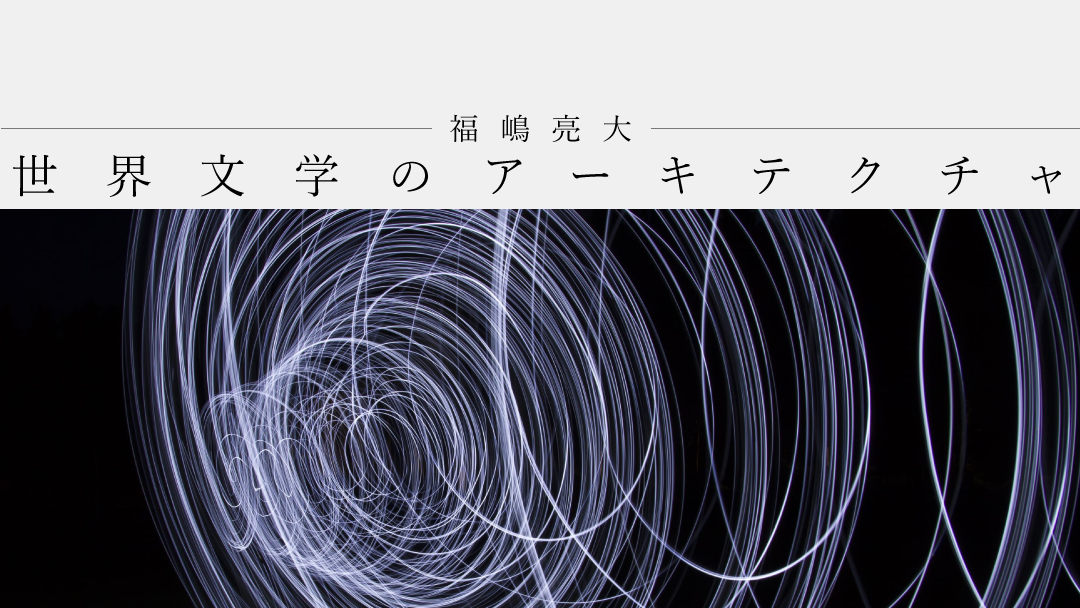
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、不確実性を思考する
本連載もそろそろ終わりに近づいている。私はここまで、世界文学の中心を占める小説を、広義の人類学的対象として捉えてきた。人類の諸文化がそれぞれ世界理解の型をもつように、小説もいわば特異な人工知能として、世界を思考し、解釈し、再構成する力をもつ。人類と小説はドン・キホーテとロシナンテのように、異質な隣人として共生関係を結んだ。人間は小説を利用して、世界を了解し直す。その一方、小説は人間の利用を利用して、その流通の版図をグローバルに拡大してきたのである。
小説とは、隣人である読者=人間の心を巻き込みながら、思考を引き延ばす装置である。それは人間の心そのものではないが、人間の心の諸機能(知覚、想像、情動、想起、予測……)を擬態する能力をもつ。私は小説を、人間の心の動きを言語的なレベルに翻訳した《心のシミュラークル》と考えたい。この心の似姿は、ときにかえって本物の心以上に複雑怪奇な多面体として現れるだろう。心と言語を結合させた小説が、ウイルスのように流行し、人間の思考の不可欠の隣人になったのは、それ自体が人類学的現象として注目に値する。
心のシミュラークルとしての小説の流行は、ヨーロッパ近代において、思考の意義が更新されたこととも関わる。その指標として、思考そのものを思考した一七世紀のパスカルの『パンセ』を挙げておこう。
パスカルは「人間の尊厳のすべては、考えのなかにある。だが、この考えとはいったい何だろう。それはなんと愚かなものだろう」と記した。彼によれば、思考は人間の尊厳の根拠になるほどには偉大であり、それでいて非常に愚かで卑しいものである。思考は確実なものや堅固なものは何一つ与えない。ゆえに、人間が多くの不確実なもの、具体的には「航海」や「戦争」に賭けるのは当然である。「人が明日のため、そして不確実なことのために働くとき、人は理にかなって行動しているのである」[1]。デカルトが懐疑の果てに、思考しつつある我(コギト)という根源にたどり着いたのに対して、パスカルは存在の根源にいわば「賭け続ける我」を発見した。
もとより、パスカル自身は小説家ではないが、彼の洞察はその後の小説の時代の予兆になっている――近代小説の歴史はまさに航海と戦争という「賭け」によって導かれたのだから。思考はもはや確実な地盤に到る技術ではなく、不確実性の海における賭けの連続に等しいのではないかというパスカル的な問いに、小説というジャンルは新たな活力を与えた。小説とは、さまざまな不確実性を織り込んで思考し続けるための装置なのである。
では、小説という特異な思考装置は、いかなる進化史をたどって構成されたのか。それが私の取り組んできた問いである。この問題にアプローチするにあたって、私は文学史をさまざまな角度からリプレイし、得られた結果を多層的に重ね書きするようにして記述してきた。この作業を世紀の区切りを基準として、もう一度実行しておきたい。
2、《場を超える場》としての海――ダンテからメルヴィルへ
一四世紀のダンテの『神曲』地獄篇第二六章で語られるオデュッセウス(ユリシーズ)の物語は、強い印象を与える。「この世界を知り尽くしたい」という知の欲望に駆り立てられたギリシアの英雄オデュッセウスは、家族を捨てて仲間たちと禁断の航海に出るが、地中海をめぐり、スペインやモロッコを横目にジブラルタル海峡を越えようとしたとき、神意によって船を転覆させられる。「やがて私たちの上には海がまたもと通り海面を閉ざした」[2]。不確実性への賭け=航海は、神の力によって封印されたのである。
西に向かう「狂気の疾走」を強制終了され、神の禁止を破った罪によって地獄の火で焼かれるダンテ版のオデュッセウス――その苛酷な姿は、不吉とされた西方にあえて旅立ったコロンブス以降のヨーロッパ人の存在様式を、見事に先取りしている。ダンテはここで、未来の探検の時代を明晰に「予言」しつつ、峻厳に「拒否」したのだ[3]。のみならず、『神曲』のオデュッセウスは後の文学上の冒険者たち、特に『白鯨』のエイハブ船長の先駆けにもなった。ボルヘスが指摘したように、両者はともに「刻苦と豪胆さによってわが身の破滅を招く」のであり、その最期の言葉まで似通っているのだから[4]。
ただ、『神曲』の場合、世界=海への欲望は、地獄・煉獄・天国から成る三位一体の神学的構造のなかに拘禁された。ダンテは〈世界〉への欲望を予告しつつ、それを厳しく断罪した。オデュッセウスの船が沈められ、海が閉ざされたとき、世界もまた閉ざされたのだ[5]。
逆に、およそ五〇〇年後の一九世紀の『白鯨』になると、海=世界はもはやこのようなリジッドな構造に収容されず、むしろ不確実性に満ちた不定形の時空として現れる(第六章参照)。海をワープするように移動する鯨の出現は、確率的に推測するしかない。鯨を追跡するエイハブは、オデュッセウスのように特定の場(地獄)に束縛されず、船員たちもろとも《場を超える場》、つまり脱領土化された海に没入してゆく。『白鯨』には土台を失った〈世界〉における、ほとんど愚かしいとも言える賭けの連続が記録されている。不確実性を思考するメルヴィルは、尊厳と愚かさが「賭け」において両立するというパスカル的問題を、小説の核心に据えたのである。
3、〈世界〉に響くダイモンの声――ラブレーと海
ここで、ダンテとメルヴィルのあいだに一六世紀のフランソワ・ラブレーを挿入してみよう。ラブレーの奇想天外な小説『ガルガンチュアとパンタグリュエル』の「第四の書」(一五五二年)では、巨人族のパンタグリュエル一行が神託を求めて航海に出る。彼らは後のガリヴァーのようにさまざまな部族の住む国を巡り、その奇妙で珍しい習慣や暮らしぶりを記しながら、当時の反動的な教会や医者に対して、強烈な批判を浴びせてゆく。
この文化人類学的な探検は断片的なエピソードの連続であり、『神曲』のような厳格な構造をもたない。大船団を組織したパンタグリュエルらは「出エジプト」の詩編の朗誦に見送られ、暴風雨にさらされながら未知の島に気安く上陸し続けては、ときに巨大な鯨を退治し、ときに派手な戦争も引き起こす。この聖書のパロディのような多産多死の航海は、陽気であり、しかも危険に満ちている。パンタグリュエルの考察によれば、航海者は「死にながら生きており、生きながらも死んでいる」[6]。ラブレーの海は生にも死にも属さない別の人間、オルタナティヴな人間を浮上させる。そして、この生と死のあいだを放浪する航海の終わりに、パンタグリュエルの心に突然謎めいた声が響く。
「ううん、なにやら」と、パンタグリュエルがいった。「急に、後ろから引っぱられるような気持ちがしてきたぞ。〈この場所に上陸するなかれ〉と命じる声が、遠くから聞こえてくるような気がするのだ。心のなかで、そのような気持ちの揺れを感じるたびに、わたしは、こうやって引き止められた方向に進むのをあきらめて、その場所を立ち去ったことを、それでよかったのだと思ったし、あるいは反対に、わが心が勧めた方向に従って進んでいった場合もあるけれど、それもまた、それでよかったと思っているのだ」
パンタグリュエルは祝祭的な船旅の終わりになって〈この場所に上陸するなかれ〉という禁止の声を耳打ちされる。興味深いことに、彼の部下は、この不思議な声を「ソクラテスのダイモン」として説明する[7]。プラトンの『ソクラテスの弁明』によれば、ダイモンはソクラテスが間違いを犯しそうになったとき、それに「反対」する神霊の声として現れた。この不可視の霊的な声は、ソクラテスに「何をすべきか」は一切教えず、その代わり「何をしてはならないか」を告げたのである。
『神曲』のオデュッセウスを束縛した神の厳格な禁止とは違って、「ソクラテスのダイモン」の唐突な声は、内的であり謎めいている。だが「その行為は間違っているから引き返せ」という内なる否定の力は、パンタグリュエルの旅の性質を劇的に変える。この宣告に従うようにして、世界を陽気に航海してきたパンタグリュエルの物語は、慌ただしく閉じられる。そのとき、快活な探検の旅は終わり、進むべきとも退くべきとも決められない根源的なあいまいさが立ち現れてくる。
世界進出に反対する「ソクラテスのダイモン」の声をきっかけとして、パンタグリュエルの心に未知の揺らぎや迷いが生じること――この奇妙な展開は、ラブレーとほぼ同年に生まれたラス・カサスが、新世界の悪を批判したことを思わせる。ラス・カサスはヨーロッパの言論空間に「その行為は間違っているから引き返せ」というダイモンの声を、キリストの霊とともに響かせたと言えるだろう。この見地から言えば、陽気なパンタグリュエルをあいまいな心境に導くダイモンの声は、新大陸でのジェノサイドを引き起こした黒い歴史への応答ではなかったか。
この内的な禁止の声を振り切るには、ときに常人離れした異常な意志が要求される。現に、ダンテ版のオデュッセウスの狂気を引き継いだ『白鯨』のエイハブは、慎重さを求めるスターバックの声を無視して、決然と海に乗り出した。裏返せば、狂気の力なしには、自己はただちにあいまいさや不確実性に呑み込まれてしまう。それが〈世界〉との接触の帰結である。
一四世紀のダンテは神学的な構造のなかで、不確実な〈世界〉への誘惑を断ち切った。しかし、ポスト神学時代になると、〈世界〉は「ソクラテスのダイモン」のような不可解な力、禁止を発する超自我の声を呼び覚ます。小説は確かに人間を中心にするが、その人間は自己とは別の力によってあらかじめ規定されてもいるのだ。私は先ほど、小説を「さまざまな不確実性を織り込んで思考し続けるための装置」と呼んだが、その思考は人間を超えた霊的な声に先行されている。
4、陰謀とゴシップにくり抜かれたシェイクスピア的主体
この「あらかじめ」の問題を考えるのに、私はラブレーやメルヴィルの巨人的な小説だけでなく、ラブレーの死のおよそ十年後に生まれたシェイクスピアを道標としたい。なぜなら、シェイクスピアの作品では、劇が始まる前に多くの重大な出来事があらかじめ起こっているからである。
例えば、一七世紀初頭の『マクベス』の観客は、幕が開いて早々に、怪しげな陰謀を企む三人の魔女に出会うことになる。この奇妙な発端は何を意味するのか。詩人マラルメの秀逸な批評によれば、それは仕組まれたアクシデントである。魔女たちは本来隠されるべき舞台裏の存在であるのに、うっかり観客の前に暴露されてしまった。「この傑作にあって、幕が単に、一瞬、早く開いてしまったのであり、ために宿命の企てる陰謀が露呈させられたのだ」[8]。軍人マクベスは国王を暗殺するが、このクーデターは魔女の予言と陰謀に踊らされただけである。マクベスの主体性はあらかじめ大幅にくり抜かれている。この点で『マクベス』はアンチ・ドラマとすら言えるだろう――なぜなら、劇の始点の魔女たちが、すでに事実上の終点を予告しているのだから。
『マクベス』に限らず、シェイクスピア劇は陰謀の先行性、あるいは人間の「遅れ」を構造化している。そして、この「遅れ」の作用を最も強く受けるのが、社会システム内部の他者である。批評家のレスリー・フィードラーによれば、シェイクスピアは四種類の他者の元型、すなわち女性(『ヘンリー六世・第一部』)、黒人(『オセロー』)、新世界の先住民(『テンペスト』)、ユダヤ人(『ヴェニスの商人』)を作中に書き入れた[9]。これらの他者は、ヨーロッパ社会のヒエラルキーのなかで、あらかじめその存在の意味を規定されている。魔女が登場しなかったとしても、これらの劇ではしばしば社会の側の悪意や陰謀が先行しており、他者はそこに遅れてやってくるのだ。
なかでも、ヴェニスを舞台とした『オセロー』は、レイシズムの前史を捉えた重要な作品である。一六世紀末の段階では、人種差別はまだ大規模な体制や教義にはなっていなかったが、それでもすでにアフリカ出身の黒人には奇形や怪物に近いイメージが与えられ、白人たちの嫌悪を向けられていた[10]。黒い肌をしたムーア人のオセローは、流浪の末に国際都市ヴェニスに受け入れられ、多大な功績をあげた軍人だが、その反面、彼は異常なよそものとして否定的な評価を下されてもいる。オセローは社会の中枢にいて名声を獲得しながら、その社会に帰属していない。
ここで重要なのは、ヴェニスにとっての潜在的な怪物オセローが、軍事力のみならず語りの力によって象徴的な力を獲得したことである。彼は自らの功績を言葉巧みに宣伝し、このプロパガンダによって自らの権力と地位を増進させる。ヴェニスの良家の娘デズデモーナがオセローと結婚するのは、彼の語りの力によって認識を操作されたためである。アラン・ブルームが指摘したように「デズデモーナは、彼[オセロー]の物語ゆえに彼を愛する」。デズデモーナはヴェニスの提供するあらゆる価値観、その最善のものにすら満足できないでいる。そこに彼女が、異邦人オセローとの不釣り合いな結婚を選ぶ要因があった[11]。
要するに、オセローの語りはリアリティの基準を攪乱し、ありそうもないことを引き起こす。デズデモーナはその境遇も肌の色も、何から何まで自分とは正反対のオセローをことさら結婚相手に選ぶが、この異例の結婚は、不可解なほどに強烈な悪意にさらされて破局を迎える。この悪意を具現化したのが、オセローの部下の軍人イアーゴーである。
オセローを執拗に陥れるイアーゴーは、ゴシップの化身のような人間である。イアーゴーの言葉は常に教訓的・格言的である。つまり、彼は自らに固有の言葉を話すのではなく、社会にあらかじめ流通している教えを戦略的にサンプリングし、それをオセロー夫妻への誹謗中傷の言葉として効果的に機能させるのだ。ゆえに、イアーゴーが「彼を取り巻くすべての人々の忠実な鏡」(アラン・ブルーム)と見なされるのも不思議ではない[12]。
シェイクスピアの描くヴェニスは、香辛料貿易で栄えた開放的な国際都市というだけでなく、ゴシップと自己宣伝の充満した不穏な都市でもある(この性格は、貿易商とユダヤ人金融業者を法廷で対決させる『ヴェニスの商人』にも当てはまる)。オセローは黒い肌の移民であり、性的に放埓という噂を立てられている。その一方、美貌のデズデモーナも若い男を漁っているのではないかという性的な好奇心にさらされている。つまり、事実はどうあれ、性的なゴシップがこの異例の有名人カップルをあらかじめ取り巻いている。
したがって、ゴシップと確執を増大させるイアーゴーは、悪意の創作者ではなく、共同体の欲望を反射した悪意のシミュラークルである。彼の陰謀によって、オセローは自身に向けられた不定形の悪意には関心をもたず、妻であるデズデモーナにこそ悪意を認める。この致命的な誤解が嫉妬、つまり「緑色の目をした怪物」を肥大化させ、オセローを自滅へと導く。
もとより、イアーゴーは伝統的な道化役の変形だが、シェイクスピアはそこに「人種差別的トリックスター」という特異な性格を付け加えた[13]。彼は、社会の通念やルールと戯れながら、その悪ふざけを強烈な悪意へと横滑りさせるジョーカーである。彼の特徴は、自ら事の真相を探ろうとせず、真偽不明の伝聞情報だけでオセローへの悪意を膨張させるところにある。
俺はムーアが憎い。世間じゃ、やつが俺の女房の布団にもぐりこみ、俺の代わりを務めたという。本当かどうか知らんが、こういうことにかけちゃ、俺は単なる疑いでも許しちゃおかない。ムーアは俺を信用している。だから、なおさら騙すのには好都合だ。(第一幕第三場)
オセローを失墜させるためには、イアーゴーは屈辱的な被害者(
こうして、イアーゴーは『マクベス』の魔女と同じく、
5、一六世紀――知の解放、ひび割れた世界
世界文学の進化を考えるとき、一六世紀に最初のブレイクスルーがあったことは明らかである。文学の主人公の中心はしばしば「壺」のようにくり抜かれ、その周囲に不定形なものや不確実なものが浮上した。一六世紀後半の哲学者ジョルダーノ・ブルーノが「無限」の概念によって、地球であれ太陽であれ、特定の中心をもつ宇宙像を破棄したように、一六世紀の世界文学にも、自我の中心性を解除する力が書き込まれたと言えるだろう。
このブレイクスルーは、当時の知の解放運動とも隣接する。世紀末から一七世紀初頭にかけて活動したシェイクスピアおよびセルバンテスに先立って、ラブレー、ラス・カサス、ホセ・デ・アコスタ、エラスムス、トマス・モア、ルターら革新的な人文学者や神学者が一六世紀の知の推進者となった。科学史家の山本義隆によれば、このような人文的な運動は、大学に独占された知を解放する「文化革命」の到来を告げるものである。ジョルダーノ・ブルーノのスコラ学批判の対話篇やガリレオの『天文対話』は、大勢に理解できるイタリア語で書かれたが、それらは既得権益層である教会の強い反発を買いながらも、続く一七世紀の「科学革命」を準備した[14]。
さらに、一六世紀から一七世紀にかけての革新は、ヨーロッパだけで起こったわけではない。出版革命の起こった一六世紀以降の中国でも、官僚予備軍である民間の知識層が、やはり俗語(白話)で書かれた小説を刊行した。これもまた知の解放運動として捉えられるだろう。シェイクスピア劇や『ドン・キホーテ』とも時代の近い『水滸伝』が、この文化革命のシンボルであったことは、すでに述べたとおりである(第四章参照)。イアン・ウォットは一八世紀イギリスでの小説の勃興を、経済力をもつ中間層の誕生と結びつけたが[15]、中国ではすでにそれ以前に、科挙をめざす教育の副産物のような形で、小説の読者層が広がっていた。
ここで重要なのは、シェイクスピア劇と同じく『水滸伝』の世界像にも、あらかじめ亀裂が入っていたことである。『水滸伝』は好漢の物語の「前史」として、横柄な政府高官がうっかり妖魔を解き放ってしまうエピソードから始まるが、これは『マクベス』の幕が一瞬早くあがり、魔女たちの陰謀が暴露されるアクシデントとよく似ている。『水滸伝』はテクストに先行するコンテクスト、つまり当の小説を創設した小説外の事故や陰謀をも、テクストにおいて露見させたのである。
もとより、テクストの起源を明らかにすることそのものは、中国小説ではなじみ深い手法である。現に、『三国志演義』の冒頭では「分」と「合」の反復という歴史哲学が示され、『西遊記』では山頂の石卵が猴(サル)に変化するという神話が語られ、『紅楼夢』(原題は『石頭記』)では物語の語り手である石の来歴が語られるのだから。ただ、『水滸伝』のプロローグは、これらの神話的起源とは異質の印象を与える。なぜなら、傲慢にして卑小な政治家のもたらしたアクシデントに始まる『水滸伝』では、もはや神話では救済できない政治の頽廃が、世界をあらかじめくり抜いているからだ。
不治の病にかかり、根底的にひび割れた世界――それが『水滸伝』の原風景である。『水滸伝』のエピソードを家庭化しながら、快楽と消費のゲームを延々と書き綴った『金瓶梅』は、このひび割れをいっそう深化させ、底なしのニヒリズムへと導いた。これらから言えるのは、中国の小説が哲学とは異なるやり方で、世界を了解する特異な精神状態を象ったことである。
二〇世紀中国を代表する哲学者の牟宗三によれば、中国哲学は古来より「憂患意識」において世界を了解してきた。牟の考えでは、中国的な主体性は、理知的・論理的なものではなく、世界を強く憂える感情から生じる「道徳性」にルーツをもつ。宗教の起源に宇宙に対する「恐怖意識」――キルケゴールの言う「おののき」――があり、それが人間の意識を神に向かって上昇させるとしたら、中国哲学の起源には強烈な「憂患意識」があり、そこをめがけて世界(天命)が下降してくる。中国の哲人政治家(聖人)は、この世界を受信するアンテナのような憂えの感情に根ざして、道徳的な世界の実現をめざした[16]。
超越的な神を求める代わりに、内在的な憂患意識のなかに世界をインストールすること――このような主体化のプログラムは、確かに中国のエリート知識人(士大夫)の精神史を特徴づけている。小説もその例外ではない。ただ、『水滸伝』、『金瓶梅』から一八世紀の『儒林外史』や『紅楼夢』に到るまでに、小説における憂患意識の所有者は政治家や士大夫だけにとどまらず、市民や女性にまで広がった[17]。白話という新たな出版語に根ざしながら、世界を了解する精神状態を市民レベルにまで拡大することが、小説という思想運動の推進力になったのである。
6、一八世紀――世界認識を刷新する小説
再び西洋の状況に戻ろう。一七世紀ヨーロッパの小説は、セルバンテスの『ドン・キホーテ』という巨星から始まったわりに、その進化はいささか低調であった。フランスではコルネイユ、ラシーヌ、モリエールという古典主義を代表する三人の劇作家が活躍する一方、シャルル・ソレルの『フランシヨン滑稽物語』――『デカメロン』やスペインのピカレスクロマンの遺産を継承したエロティックな諷刺小説――から、心理小説の先蹤となったラファイエット夫人の『クレーヴの奥方』に到る小説が書かれたものの、セルバンテス死後数十年の小説の歩みは、総じて「不規則で緩慢」であった[18]。
その反面、一七世紀には重大な知的変革が相次いだ。ニュートンやライプニッツらが科学を飛躍させる一方、デカルトやジョン・ロックを契機として哲学の「主観性への転回」が生じた。
あえて単純化すれば、一八世紀の小説は、一六世紀の〈世界〉と一七世紀の〈主観〉を合流させたと言えるだろう。例えば、スウィフトの『ガリヴァー旅行記』は、巨人が船で架空の諸外国をめぐるラブレーの『ガルガンチュア』と似ているだけではなく、ラス・カサスの記述したジェノサイドの問題も取り入れていた(前章参照)。さらに、ラブレーの愛読者であった一八世紀後半の牧師ローレンス・スターンは、ディドロによって「イギリスのラブレー」と呼ばれた[19]。ともにアイルランド生まれのスウィフトとスターンは、一六世紀的な〈世界〉への志向を、一八世紀の小説のテーマとして再創造したのである。
その一方、一八世紀の小説家たちはリチャードソンの書簡体小説を筆頭に、主観性を際限なく引き延ばす技法を作り出した。書簡とは「思考の延長」を可能にする瞑想的なアプリケーションである(第一一章参照)。小説の創作した主観性は、一七世紀の哲学的なモデルへの批判的な応答という一面をもちあわせていた。現に、スターンはジョン・ロックの自我同一性の哲学を支える観念連合説をパロディにするようにして、奇想天外な小説『トリストラム・シャンディ』(一七六七年完結)を書いた。このとき、スターンの思想は同世代のスコットランドの哲学者ヒュームと近接する。ヒュームはロックを批判しながら、自我の感覚を移ろいやすい知覚の束と見なしたが、それは脱線や不確実性を強調したスターンの小説と共鳴するものであった。
一八世紀の小説は一七世紀の哲学とは異なるやり方で、主観性の探究のための新たなルートを開削した。それは、欲望の機能の評価という新たなプロジェクトにも差し向けられる。ジャック・ラカンによれば、一八世紀フランスのディドロやサドらの企て――それは挫折するのだが――は「欲望の自然主義的解放」とでも呼べるもの、つまり「快楽人間」の思考を追求した。それは神に対する挑戦であるだけではなく、欲望が何をなしうるかのデモンストレーションになった[20]。このような欲望の検証も、一七世紀の哲学には欠けていたものである。
その際、神の重力を逃れようとする一八世紀の小説が、散文の時間性を利用したことも見逃せない。言語学者ロマン・ヤコブソンによれば、詩(verse)がラテン語の語源的に「規則的回帰という概念」を含むのに対して、散文(prose)は同じく語源的には「前進」を示す[21]。詩の言葉は、過去への回帰的視線と未来への期待を、現在のなかに包摂しており、時間を重層的に重ねあわせている。逆に、散文はこのような回帰性をいったん手放し、前進する時間にアクセントを置いた。それが、ガリヴァーやクルーソーのような一八世紀の冒険者たちに推進力を与えたのである。
7、グローバリズムをくり抜く地震
こうして、一八世紀の新興の小説家=散文家は、オープンで不確実な世界への冒険を活気づけた。ただ、ここには面白い逆説がある。それは、進歩的な冒険者に集中すればするほど、その主人公をあらかじめくり抜いている力が目立つことである。小説を読むとき、われわれは主体という「図」にフォーカスするだけでなく、主体の背後にあって主体をあらかじめ規定する「地」を考慮に入れなければならない。なぜなら、小説ではしばしばこの図と地の反転が生じるからである。
この問題を「地震」をモデルに考えてみよう。ヴォルテールが『カンディード』で一七五五年のリスボン地震の惨禍を取り上げる以前に、デフォーの『ロビンソン・クルーソー』はすでに島の地震で生き埋めになる恐怖を記していた。島のクルーソーは、自分一人のための衣食住の場所を建設しようとする。彼の労働は「もつこと」と「住むこと」の充実によって「あること」(存在)を根拠づける作業であった。しかし、この建設の途上で不意に地震が起こり、クルーソーを驚かせる。
地震というできごとそのものに、ぼくはひどく面食らった。こんな感覚は味わったことがなかったし、他人から話に聞いたことさえなかったものだから、死んだように全身が麻痺してしまった。大地が動くので、まるで波に揺られたように吐き気を覚えた。(一一八‐九頁)
堅固な大地が、未知の地震によっていきなり海に変わってしまう――このアクシデントが、クルーソーの存在を揺るがし「吐き気」を催させる(なお、前章で言及したアフリカ人オラウダ・イクイアーノの自伝でも、ヨーロッパで地震を初めて体験したときの恐怖が記されるのは興味深い)。自己の核をくり抜くものとして、シェイクスピアが舞台裏の魔女の陰謀を露見させたのに対して、デフォーは大地を海に変える地震によって、クルーソーの心身を麻痺させた。ここには、自己の中心化によって、かえって自己の脱中心化も加速するというパラドックスがある[22]。
大地での居住可能性の喪失という危機は、意外にも、後のカントの見解とも共振する。リスボン地震の直後に、若きカントが地震の自然学的な分析に取り組んだことはよく知られている。彼は地下の洞穴に蓄えられた「火」が地震を引き起こすと予想したが、それは今から見れば当然誤りにすぎない。ただ、より重要なのは、不可視の地下が複雑なネットワーク(多様な迷路)で一つに結びついているというカントの見解である。「自然は、われわれの眼やわれわれの直接の探求に対して隠しているものを、その作用によって打ち明ける」。地震が打ち明けるのは、地上ではなく地下こそが、真にグローバル(全球的)な世界だということである。地震の教えを真摯に受け入れるとき、人間は世界の住人ではなく、むしろ「異邦人」として理解される。
人間ははかないこの世の舞台上に永遠の庵を結ぶようには生まれつ
ヴォルテールにとって、地震が「すべては善である」
人間の目的を地上で完結させてはならない――
特に、一七二四年に刊行されたデフォー最後の長編小説『
しかし、
8、自己の中心化と脱中心化――スターンのモダニティ
このような脱中心化の運動を極限に導いたのは、
しかも、この常軌を逸する運動は、
彼[スターン]の賞賛さるべき点は、
ニーチェが言うように、あらゆる「まじめさ」や「厳粛さ」
繰り返せば、文学のモダニティの特徴は、
私がここまで言及した作品は、
9、一九世紀――旅行文学から翻訳文学へ
繰り返せば、ヨーロッパ小説は『神曲』
ただ、「新世界」にアクセスしようとする一六世紀以来の欲望は、
こうして、『パルムの僧院』
では、このような文学的内向の進んだ一九世紀のヨーロッパでは、
ゲーテの世界文学のシステムとは、
10、野生の翻訳者たち――メルヴィルとソロー
もっとも、翻訳というテーマを発展させたのは、
多言語ならぬ多物質を内包した鯨は、
このような過剰な翻訳にさらされた鯨という巨大な物質からは、
さらに、メルヴィルと並ぶ野生の翻訳者としては、ヘンリー・
しかも、このような物質どうしの「翻訳」は、
その一方、ソロー晩年の傑作『コッド岬』になると、
この非人間的な海の岸辺は「難破」と「死」
このアモラルで即物的な態度は、コッド岬が「
海岸はいわば中立地帯のような場所であり、
森が音楽を漂流させるように、海は物質やその匂いを漂流させる。
11、二〇世紀――小説という壺
私はここまで「世界から引き返せ」という声に始まる、
そして、二〇世紀に入ると、
そのような観察には事欠かない。「僕は僕の夜の思想を以て、
モダニズムの運動もまた、
ジョイスら二〇世紀の作家を経て、
アメリカでも一七九〇年以前には、
要するに、ジャンルを攪乱するトリックスター、
ただ、二〇世紀においては、
[1]パスカル『パンセ』(前田陽一他訳、中公文庫、二〇一八年)二五九、一八三頁。
[2]ダンテ『神曲 地獄篇』(平川祐弘訳、河出文庫、二〇〇八年)三五一頁。
[3]レスリー・A・フィードラー『消えゆくアメリカ人の帰還』(渥美昭夫他訳、新潮社、一九八九年)三四頁。なお、ダンテはホメロスの『オデュッセウス』を知らなかった。『神曲』のオデュッセウスの淵源となったのは、オウィディウスの『変身物語』である。Prue Shaw, Reading Dante, W.W. Norton & Company, 2014, p.122.
[4]J・L・ボルヘス『ボルヘスの「神曲」講義』(竹村文彦訳、国書刊行会、二〇〇一年)五九頁。
[5]オデュッセウスに限らず、『神曲』の登場人物はその終局的な場、つまり人生のファイナル・アンサーを固定されている。E・アウエルバッハ『世俗詩人ダンテ』(小竹澄栄訳、みすず書房、一九九三年)によれば「ダンテが『神曲』に見せてくれるのは、掛け値なしに登場人物たちの最終運命である。地上の束の間の時間は彼らから流れ去り、煉獄にいる例外もあるが、彼らはすでに定められた場所にいる。そしてその場所を離れることは永遠にないだろう」(一四三頁)。
[6]ラブレー『ガルガンチュアとパンタグリュエル 第四の書』(宮下志朗訳、ちくま文庫、二〇〇九年)二三八頁。
[7]同上、五四六頁。
[8]「『マクベス』における魔女たちの贋の登場」(渡邊守章訳)『マラルメ全集』(第二巻、筑摩書房、一九八九年)四九二頁。
[9]レスリー・フィードラー『シェイクスピアにおける異人』(川地美子訳、みすず書房、二〇〇二年)四頁。二〇世紀になると、シェイクスピアの登場させた他者の文学(女性文学、黒人文学、ラテンアメリカ文学、ユダヤ文学)が浮上した。それは、シェイクスピアの他者イメージの先駆性を物語っている。
[10]マイケル・D・ブリストル「『オセロー』におけるシャリヴァリと除け者の喜劇」アイヴォ・カンプス編『唯物論シェイクスピア』(川口喬一訳、法政大学出版局、一九九九年)一五九頁。
[11]アラン・ブルーム『シェイクスピアの政治学』九三頁。
[12]同上、七五頁。
[13]ジェイムズ・R・アンドレアス「オセローのアフリカ系アメリカ人たちの後輩たち」カンプス前掲書、二一六頁。
[14]山本義隆『一六世紀文化革命』(第二巻、みすず書房、二〇〇七年)五五六、五八二頁。山本によれば、外科医学、代数学、植物学、鉱物学、力学、天文学、地理学等の諸分野の勃興した一六世紀においては、グーテンベルク以降の印刷術を用いて、職人や科学者らが俗語の科学教科書を書き、自らの思考を表明し始めた。それによって、それまでは大学で独占されていた知が、その外へと急速に拡散したのである。
[15]イアン・ウォット『イギリス小説の勃興』第二章参照。
[16]牟宗三『中国哲学的特質』(台湾学生書局、一九六三年)一五頁以下。
[17]ただ、一七世紀中国の作家が出版に強い関心をもったのに対して、一八世紀の文人小説は商業出版に背を向けて、一部のエリート文化人のあいだでのみ流通したことも見逃せない。この点は、『儒林外史』を一八世紀の精神史的変動と結びつけた商偉『礼与十八世紀的文化転折』(生活・読書・新知三聯書店、二〇一二年)の序論を参照。
[18]Ioan Williams, Idea of the Novel in Europe 1600-1800, New York University Press, 1979, p.26.
[19]伊藤誓『スターン文学のコンテクスト』(法政大学出版局、一九九五年)一二頁以下、一一五頁。なお、同書付録の「小説研究の動向」は、英語圏の小説研究の一端を紹介した便利なガイドである。
[20]ジャック・ラカン『精神分析の倫理』(上巻、小出浩之他訳、岩波書店、二〇〇二年)四頁。
[21]ロマン・ヤコブソン『言語芸術・言語記号・言語の時間』(浅川順子訳、法政大学出版局、一九九五年)三〇頁。
[22]さらに、スコットランド生まれのトバイアス・
[23]「地震の歴史と博物誌」(松山壽一訳)『カント全集』(
[24]ダリオ・ガンボーニ『潜在的イメージ』(藤原貞朗訳、
[25]『ニーチェ全集』(第六巻、中島義生訳、
[26]スターン『トリストラム・シャンディ』(上巻、
[27]ヴォルフガング・シヴェルブシュ『楽園・味覚・理性』(
[28]スタンダール『パルムの僧院』(上巻、大岡昇平訳、
[29]アントワーヌ・ベルマン『他者という試練』一三五頁。
[30] 同上、二七七頁以下。
[31]今福龍太『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(みすず書房、二〇一六年)一六三頁以下。
[32]伊藤詔子『よみがえるソロー』(柏書房、一九九八年)
[33]ヘンリー・デイヴィッド・ソロー『コッド岬』(
[34]同上、二六三、二七八頁。
[35]Jacques Derrida, Acts of Literature, ed. Derek Attridge, Routledge, 1992, p.36.
[36]このジョイス的翻訳と呼応するのが、
[37]Day, op.cit., p.7.
[38]Cathy N. Davidson, Revolution and the Word: The Rise of the Novel in America, Oxford University Press, 1986, pp.40, 152, 170.
[39]ラカン前掲書、一八一頁。
この記事は、PLANETSのメルマガで2024年7月9日、7月17日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2024年9月5日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。