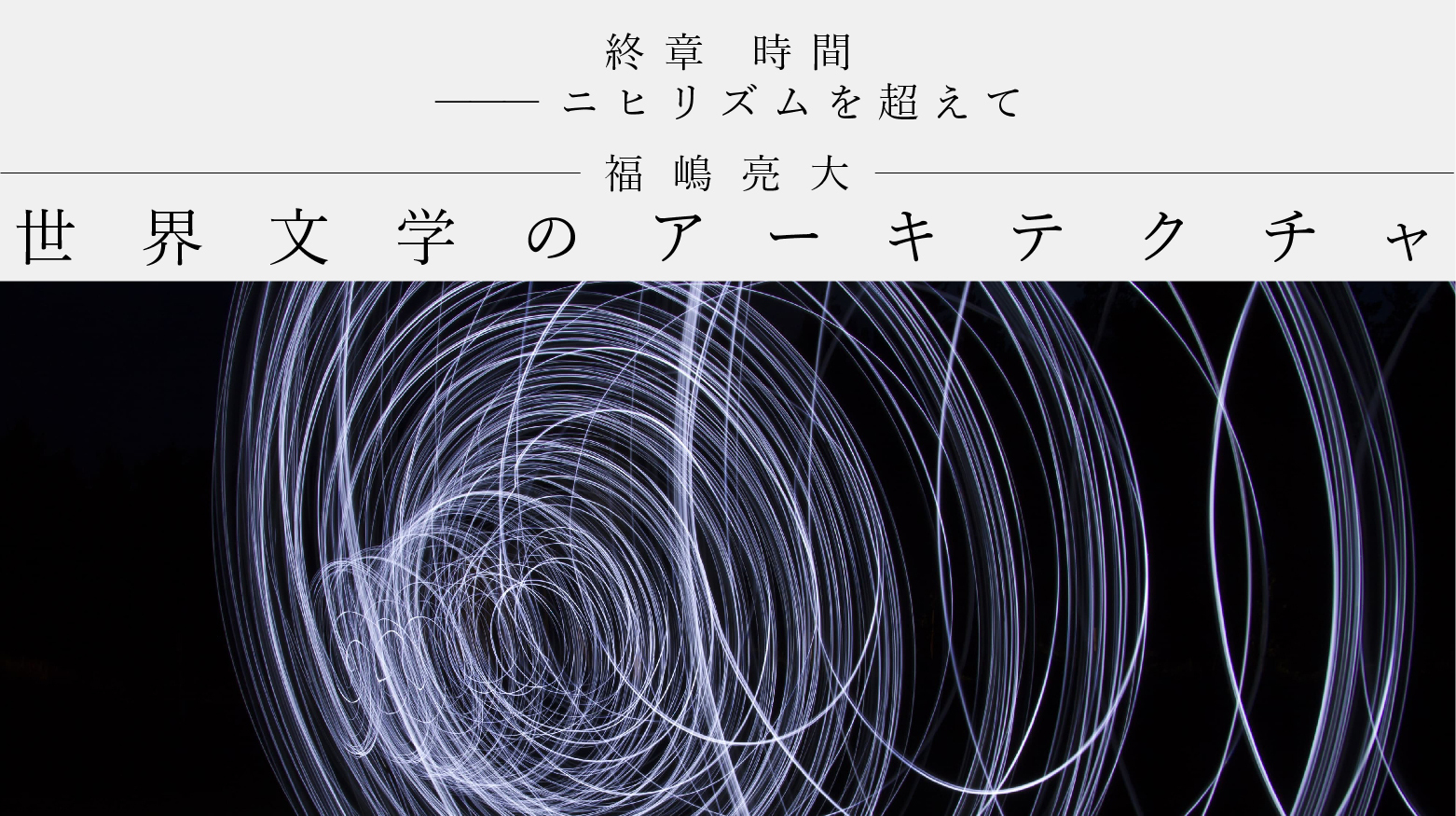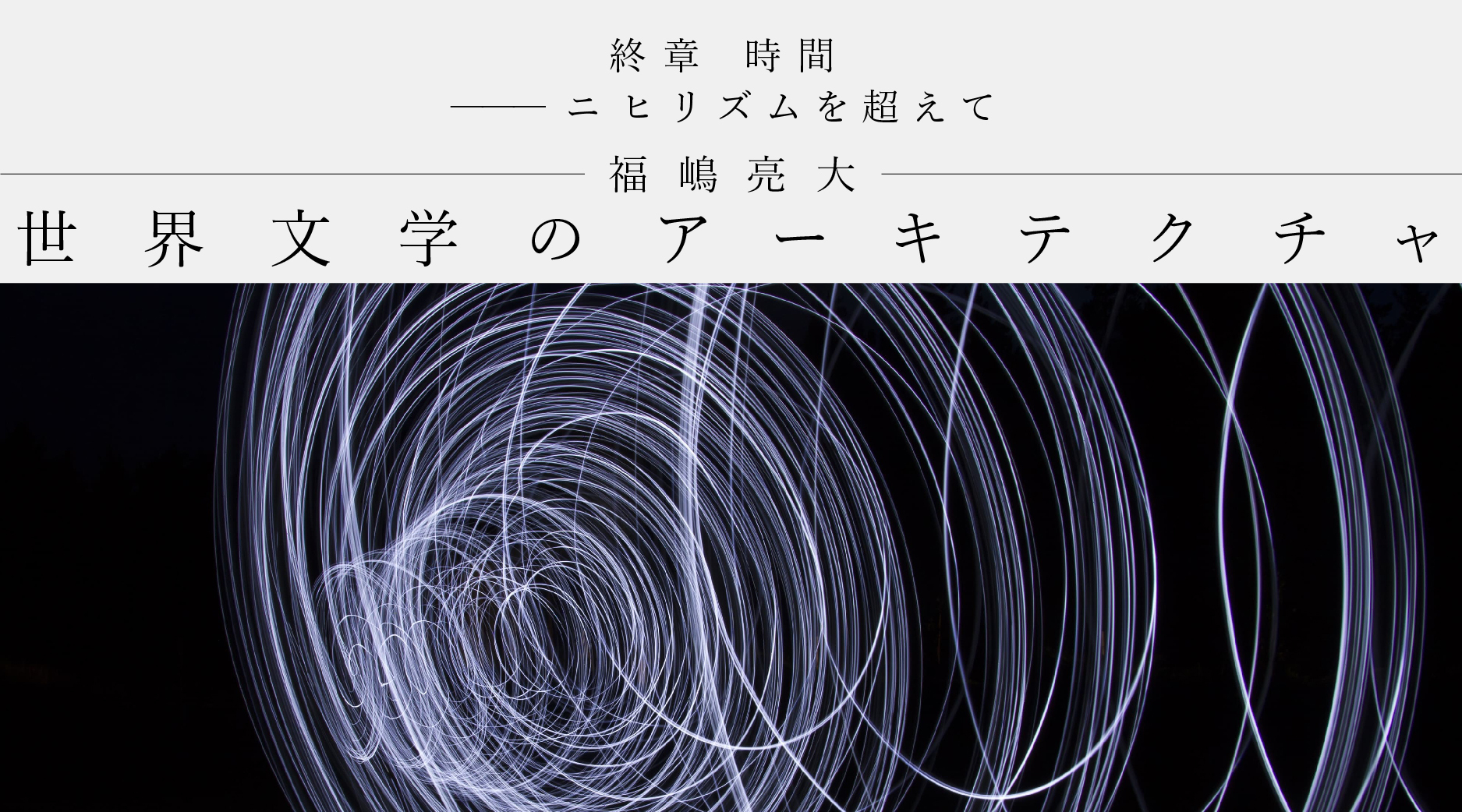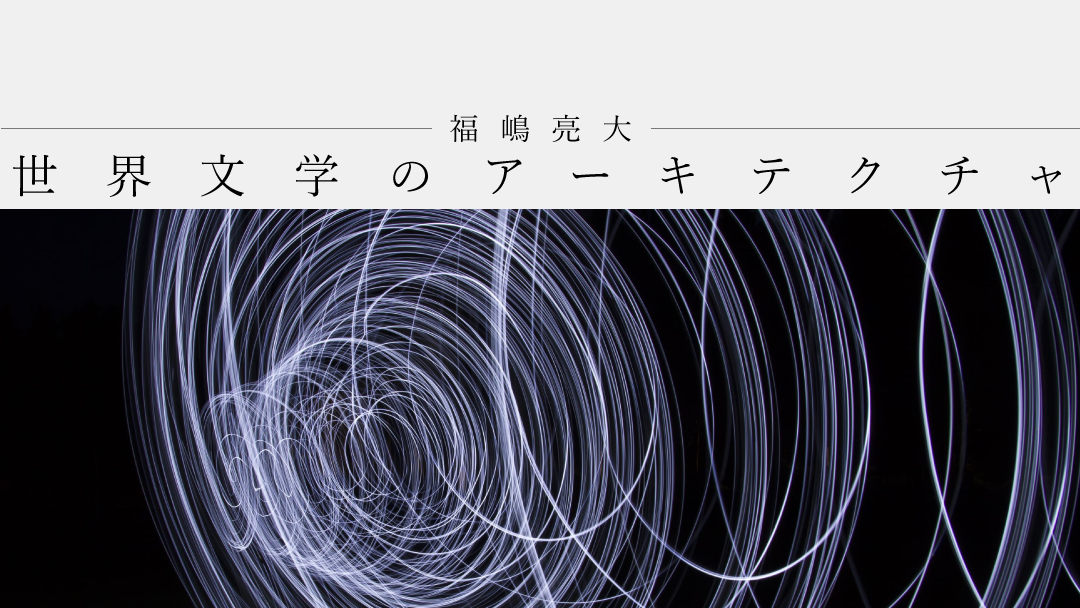
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、近代小説に随伴するニヒリズム
一八八〇年代に書かれた遺稿のなかで、ニーチェは「ニヒリズムが戸口に立っている。このすべての訪客のうちでもっとも不気味な客は、どこからわれわれのところへ来たのであろうか」と書き記した。ニーチェによれば「神が死んだ」後、人間の基準になるのはもはや人間だけである。しかし、神の死によって生じたのは、神のみならずあらゆる価値を崩落させ、意味の探究をことごとく幻滅に導く「不気味」な傾向であった。ニヒリズムとはこの「無意味さの支配」を指している。
ハイデッガーの解釈によれば、ニーチェの哲学において「意味」は「価値」や「目的」とほぼ等しい。つまり、意味は「何のために」とか「何ゆえに」という問いと不可分である。意味を抹消するニヒリズムが支配的になるとき、世界の「目的」や「存在」や「真理」のような諸価値もすべて抜き取られる。ニーチェが示すのは「諸価値を容れる《位置》そのものが消滅」したということである。われわれは世界に価値や意味を嵌め込んできたが、今やそれを進んで抜き取っている――このようなニヒリズムの浸透は、世界に「無価値の相」を与える[1]。目的をもたなくなった世界で、人間は確かに価値の重荷から解放されるが、それは幸福を約束しない。
ここで文学史を回顧すれば、すでにニーチェ以前に「ニヒリズムという不気味な客」の来訪する予兆があったことが分かる。宗教が世界に意味や価値を嵌め込んだのに対して、デフォーの『ペスト』やスウィフトの『ガリヴァー旅行記』を筆頭とする一八世紀の近代小説は、意味の探究を超えた不確実性に傾いてきた。小説は安定した意味のシステムを自らくり抜き、一種の「壺」として自らを造形したが(前章参照)、特に絶滅やジェノサイドへのオブセッションは、小説という壺に底なしの空虚をうがち続けてきた。小説にとって、ニヒリズムは不意の来客というよりも、むしろ長期にわたって共生してきた伴侶なのである。
そう考えると、ニヒリズムがニーチェに先立って、まずロシア文学において結晶化したことも不思議ではない。ツルゲーネフは一八六二年の『父と子』で若き医師で唯物論者のバザーロフをニヒリストとして描き、この概念を広く普及させた(第十章参照)。宗教的な救済のヴィジョンを内包したロシア文学は、人生の意味の飽くなき希求によって、かえって世界の無意味さの深淵に足を踏み入れた。その後もロシア文学は、哲学とは異なるやり方で、ニヒリズムに応対したように思える。その興味深い例として、一八六〇年生まれのアントン・チェーホフを取り上げよう。
2、二〇世紀最初の文学――チェーホフの『三人姉妹』
生粋の一九世紀思想家ニーチェは一九〇〇年に亡くなるが、その翌年の二〇世紀最初の月すなわち一九〇一年一月に、チェーホフの戯曲『三人姉妹』がモスクワ芸術座で初演された(以下、チェーホフの作品の引用は松下裕訳[ちくま文庫版全集]に拠り、巻数と頁数を記す)。その第二幕に、雪の降る日に父をなくした三人姉妹の一人マーシャが、正教徒の軍人トゥーゼンバッハとやりとりをする場面がある。もう一人の軍人ヴェルシーニンが、未来の新しい幸福な生活のために働くべきだと言うのに対して、トゥーゼンバッハは百万年後にも生活の法則は変わらないと断言する。マーシャは、世界を無意味と見なす彼の態度に懸念を示す。
マーシャ それでも意味は?
トゥーゼンバッハ 意味ねえ……。こうして雪が降っていますがね。どんな意味があります?
(間)
マーシャ わたしはこういう気がするの。人間は信仰を持たなくてはいけない、すくなくとも信仰を求めなくてはいけない、でなければ生活はむなしくなる、むなしくなる、って……。生きていながら知らないなんて、なんのために鶴が飛ぶのか、子どもたちが生まれるのか、空に星があるのか……。なんのために生きているのか知らねばならないし、さもないと何もかもがつまらない、取るにたらないものになってしまうわ。
(間)
ヴェルシーニン それにしても残念でたまらない。青春の過ぎ去ったのが……。(第二巻、二四七‐八頁)
トゥーゼンバッハはここで、生の意味を否定するニヒリストのように振る舞う。雪が降るように、人間が生まれ死ぬだけなのだとしたら、人生に意味や目的を求めるのは無益だろう。ここで思い出されるのは「雨の降るごとく死が降る」と記した哲学者のドゥルーズである。ドゥルーズはたんに雨が降るという「非人称的」な出来事を人間的な意味づけに優先させたが[2]、トゥーゼンバッハの考え方はそれに近い。
逆に、マーシャは世界に意味や目的がなければ、人間の生が取るにたらないものになることを恐れている。ただし、このマーシャの発言は誰かに賛同されたり反論されたりするわけではない。ひとしきりの「間」があってから、話題は別の方面に移り変わる。トゥーゼンバッハもマーシャも、この件で口角泡を飛ばして議論しないし、自説に固執もしない。彼らの思想は、ティータイムの前の退屈しのぎとして語られるにすぎない。
ツルゲーネフの『父と子』における若い男性知識人たちの熱っぽい会話とは対照的に、およそ四〇年後の『三人姉妹』では、意味と無意味に関する問いは、空白やためらい、退屈や倦怠の気分のなかに控えめに浮かんでいる。すでに青春を過ぎた彼らの口調は、決然とした強さをもたない。彼らは他者を声高に説得しようとする意志を欠いたまま、会話の「間」に滑り込んで、つぶやくようにして自らの考えを語る。
この慎ましさにおいて、チェーホフは明らかに反ドストエフスキーないしポスト・ドストエフスキーの作家である。ドストエフスキーの登場人物は、経験的にはふつうの人間と何ら変わらないが、その存在には「形而上学的な次元」が随伴している。ドストエフスキーを特徴づけるのは、経験的なレベルと形而上学的なレベルの「神秘的な一体化」である[3]。逆に、チェーホフは生と思想をむしろ乖離させる。自己の思想を論文や文学を動員してまで述べようとするラスコーリニコフやイワン・カラマーゾフのような熱意を、チェーホフ的人間は初めからもちあわせていない[4]。
二〇世紀最初の文学である『三人姉妹』が「意味」の問題を提示したこと、これは非常に示唆的である。ただ、チェーホフの独自性は、人生の意味ないし無意味というテーマを、ニーチェやドゥルーズのような「哲学」としてではなく、人間の頭上を鳥のように通過するあいまいな思念や気がかりとして示したことにあった。トゥーゼンバッハに言わせれば「渡り鳥、たとえば鶴などは、ただひたすら飛んで行くだけで、高遠な思想やちっぽけな思いが頭のなかに浮かんだとしても、飛んで行きながら、やっぱりなぜ、どこへ飛んで行くかを知りはしない」(第二巻、二四七頁)。彼にとっては、いかなる思想も人間の頭脳には根づかない。チェーホフ的人間は、思想の所有者ではなく、思想の一時的な止まり木なのだ。
アメリカの哲学者コーネル・ウェストは、チェーホフの文学の根幹に「世界との不一致」があり、それが彼の喜劇性の源泉になっていると指摘した。「彼は最も洗練された知性的なやり方で、知性の失敗と不十分さについて語る」[5]。『三人姉妹』の人間たちは、彼らにとって価値あるものが過ぎ去った時点にたたずんでいる。このuntimelyな――反時代的で時機を失した――チェーホフ的人間たちは、世界に対して遅れてやってくる。思想と生とが乖離してしまう、このチェーホフ的な「不一致」の情景においては、世界は有意味とも無意味とも断定されない。ニヒリズムは文字通り「客」であり、人間の生に定住はできない。
3、ニヒリズムの梗塞
このような「世界との不一致」の情景は、チェーホフの一八九二年の小説「六号室」ですでに模範的に示されていた。主人公の医師アンドレイ・エフィームイチは、自らの勤務する辺境の精神病院がいかに劣悪であり、患者を苦しめているかを重々承知しながらも、死ねば誰もが「空」になるという皮肉な諦念のもと、高尚な哲学的議論で暇つぶしをしている。屈辱や不快を味わったときも、「百万年後」の宇宙的な視点が彼を慰める。
もしも百万年後に地球のそばの空間を何かの霊が飛びすぎて行ったとしたら、その目には粘土と裸の岩山しか映らないだろう。すべては――文化も、道徳律も消え去って、きれいさっぱり忘れられているだろう。酒屋のおかみに対する恥ずかしい思いや、くだらないホーボトフや、ミハイール・アヴェリヤーヌイチの重苦しい友情がいったい何だろう。すべては愚にもつかぬたわごとではないか。(第六巻、四四九‐四五〇頁)
しかし、このようなシニカルな認識も、心の平安にはつながらない。エフィームイチは「愚にもつかぬたわごと」に一喜一憂するうち、やがて自分自身が罠にはまって精神病棟に収容される。この予想外の出来事にうろたえながらも、彼は「この世のことのいっさいはたわごと、空の空」(四五八頁)といういつもの論理で自らを納得させようとするが、それは監禁のむごい現実を前にして潰え、やがて脳梗塞による急死へと到る。
この巧妙な構成をもつ小説において、医者でもあったチェーホフは、マイルドなニヒリズムを精神安定剤的に用いる医者=患者の姿を浮かび上がらせた。人間の絶滅した「百万年後」の視点から言えば、精神病患者の非人道的な扱いはもとより、戦争やジェノサイドもすべては無意味な「たわごと」にすぎない。しかし、ひとたび現実的な苦境に陥れば、このようなニヒリズムはただちに行き詰まり、文字通り「梗塞」するだろう。チェーホフが示したのは、たとえニヒリズムをインストールしても、人間の心身はそれに耐えきるだけの強度をもたないということである。エフィームイチの思考は、人間的な弱さが露見したとたんに硬直する。ニヒリズムを口に出せても、それを生き抜くことはできない。
人間では最後まで背負いきれない思考や観念――これと同種のテーマは、一八八九年に発表された中編小説「退屈な話」にも現れていた。大学教授ニコライ・ステパーノヴィチは学問的名声を博しているが、老いはますます募り、大学の講義でも家庭でも気づまりが増すばかりだ。彼は有名人であるにもかかわらず、気づけば旅先のハリコフのベッドで一人膝を抱えている。高い地位とは不釣りあいの侘しいホテルの一室で、彼の思想はまとまりを失って、あいまいに四散してゆく。ステパーノヴィチは「それぞれの感情、それぞれの思想が、わたしの心のなかでてんでんばらばらに生きて」いることに気づくが、それらを統合する力はもう残っていない。
わたしは考えてみる、長いこと考えてみる、だがいくら考えても何ひとつ思いつかない。どれほど考えてみても、どう思いめぐらしてみても、わたしの願望のなかには肝腎なことは何ひとつ、大事なことは何ひとつないことがよくわかる。〔中略〕
こんなに貧弱だとすれば、重病にかかったり、死の恐れを感じたり、環境や他人の影響を受けさえすればたちまち、以前わたしがこれこそ自分の世界観だと考えたもの、そこにこそ自分の人生の意義があり喜びがあると思ったものが、ことごとく引っくりかえり四散してしまったにちがいない。(第五巻、五〇七‐八頁)
人間は「ちょっとした鼻かぜ」で精神の平衡を失う。そして、ひとたび人生のバランスが崩れれば、ペシミズムだろうとオプティミズムだろうと、あらゆる思想は人生から剥離してしまうだろう……。このような考えはそのまま老教授ステパーノヴィチ自身の孤独な現況を説明する。知的な「世界観」を失って、中身のない空虚な考えにふけるステパーノヴィチは、侘しいホテルの一室でいわば非存在に近づく。要するに、彼は存在していたのではなく、存在していると思い込んでいただけなのだ。
思想と生、そうであると思うことと現にそうであること、言っていることとやっていることは、必ず食い違う。ゆえに「生きられた思想」とはそれ自体がまやかしを含む。チェーホフはこの生と思想の乖離、およびそこから来る悲喜劇性を、冷徹な医師のように克明に記録した。彼自身、自らの文学観を次のように説明している。
作家の役目はただ、人物、環境、及びそれらの人物が神やペシミズムについて語る形態を表現することにあるのです。芸術家は自分の生み出した人物の裁き手であってはならず、また、それらの人物が語ることの裁き手であってもなりません。ただ公平な証人であるべきです。[6]
「聡明な人間は学ぶことを好み、愚かな人間は教えることを好む」と言ったチェーホフにとって[7]、文学とは教師でも裁判官でもなく「公平な証人」である。問題の解決に向けて展望を示したり、登場人物の生き方に白黒つけたりする代わりに、問題を正しく公平なやり方で提示すること――この証言者の慎ましさが、チェーホフ文学特有の洗練を生み出したのである。
4、ロシアの宇宙的な時間
ここでチェーホフを文学史的なコンテクストに置き直してみよう。ロブ゠グリエやクロード・シモンを筆頭とする戦後フランスのヌーヴォー・ロマンになると、人間を取り巻く非人称的なもの(非人間的なもの)の力が拡大された(第十三章参照)。ある研究者に言わせれば、彼らは「退屈している作中人物を私たちに見せようと努めたのでなく、作中人物を退屈させている世界を見せようとしたのだ」[8]。
それに対して、世紀転換期のチェーホフの文学は、あくまで「退屈している人間」の像を手放さなかった。人間の自己中心性を解体するのに、人間をなお暫定的な中心に据えるというチェーホフの手法は、ヴァージニア・ウルフ(『ダロウェイ夫人』や『オーランドー』)やベケット(『モロイ』や『マーフィー』)らモダニストにおける伝記スタイルの再創造とも共通性をもつ。特に、世界と人間がいかに関係し損なうかというチェーホフ的な「不一致」のテーマは、ベケットにおいて極限に達したように思える。
ベケットの小説とは、世界といつまでも一致しない言葉でうだうだおしゃべりしながら、人間の廃墟をうろつき回る非人間的人間のドキュメントである。例えば、モロイにとっては「めざめていること、それは眠っているのと同じ」であり、肯定(真夜中だ、雨が降っている)と否定(真夜中ではなかった。雨は降っていなかった)が共存する。あるいは、マロウンは「わたしは一種の昏睡状態のまま生きてきた」と認める[9]。一九五三年の『名づけえぬもの』になると、人格性はすっかり蒸発し、自己増殖的なおしゃべりだけが残るだろう。このどんづまりの貧しさのなかでは、もはやいかなる意味ももちこたえられない――しかし、この絶体絶命の状況がなぜか絶望する理由にもならないところに、ベケット特有のユーモアの至芸があった[10]。
ただ、私としてはベケットという極限に向かう一歩手前、つまり人間的なものをなお残存させているチェーホフの地点に立ち止まりたい。ここで注目に値するのは、チェーホフの失敗の「証言」において、時間が大きな位置を占めたことである。繰り返せば、チェーホフ的人間はアンタイムリーな存在、進行する時間に置き去りにされた寄る辺ない存在である。「各瞬間が失敗であるように見える。〔…〕チェーホフ劇は他のどんな演劇にもまして、過ぎ行く時の印象をあたえる」(ロジェ・グルニエ)[11]。この「過ぎ行く時」が未来に投射されると、「六号室」のように、人間の絶滅した百万年後の時間が現れる。
もともと、一九世紀のロシア思想では、宇宙的なスケールの時間はロシア正教の伝統に通じる神秘主義に組み込まれた。いわゆるロシア宇宙主義(コスミズム)の先導者となった哲学者ニコライ・フョードロフは、はるか未来の人類の宇宙進出がすべての被造物の復活と再生、つまり「不死性」のめざめを促すと考えた(生物圏から精神圏への移行)。宇宙主義者たちの考えによれば、人間にあらかじめ含まれた「神の声」を呼び覚ますことによって、人類は「地球上の幽囚」という身分から脱出し、本来の精神的存在に復帰できる。チェーホフと同世代のツィオルコフスキーは、このフョードロフの神秘的な進化論の延長線上で、人類を宇宙に導くロケット工学の研究に尽力した[12]。
人類に破格の意味=目的を与えるコスミズムは、人間の生の意味=目的を抹消するニヒリズムと、ちょうどコインの裏表の関係にある。チェーホフの主人公が唐突に語り出す「百万年後」の世界は、コスミズムとニヒリズム、そのいずれにも通じているように思える。しかし、実際にはチェーホフ的人間は不死性への道を端から信じていないし、かといってニヒリズムを貫くだけの強度ももたない。彼の思想は、知性の失敗や会話の「間」にふと浮かび上がるだけだ。思想を生き損なうこと、頼りなさや寄る辺なさに包まれながら言葉を発すること、それがチェーホフ的な情景なのである。
5、世界性の根拠――空間から時間へ
ともあれ、チェーホフを含めてロシアの文学者や思想家が、宇宙的なスケールの時間を喚起したことの意義は再確認されてよい。というのも、一九世紀後半以降、文学の世界性の根拠は空間から時間にスライドしたように思えるからである。ここからはロシアの外に視点を移そう。
私は本連載で一貫して、ルカーチや柄谷行人の注目した「内面の発見」だけではなく、一六世紀以降の〈世界〉の発見こそが近代性の主要な条件であると主張してきた。主体(私)はむしろ、世界の探索のために事後的に構成されたプログラムである。内面の描写は、この遅れてやってきた主体を実体化する技術として導入された。ルカーチや柄谷はそこに近代性の核心を認めたが、それだけでは、近代小説の「原史」を解明するのには不十分である。
二〇世紀文学で特筆すべきなのは、この世界性のドメイン(領域)が、空間から時間へと推移したことである。一六世紀に一人称で『インディアスの破壊についての簡潔な報告』を著したスペインのラス・カサスを嚆矢として、一八世紀イギリスのデフォーやスウィフトは、主体という世界探索のプログラムを異質な「新世界」に送り込んだ。これらの文書では主に空間的な差異に基づいて、世界性が象られた。しかし、資本主義がグローバル化すると、空間的な差異は平準化されざるを得ない。ゲーテやマルクスの世界文学論はそのことを早くから見抜いていた。
空間のポテンシャルが減衰した後、一九世紀末のコンラッドから、プルースト、トーマス・マン、ジョイスらに到る二〇世紀前半のモダニストは、時間の探査を試みた[13]。彼らが示したのは、「大人」に向かって成長するビルドゥングス・ロマンのリニアな時間ではなく、狭小な空間における円環的・迷宮的な時間である。特に、ジョイスは声変わりする前の「未成熟」な子どもの声を駆使するようにして、人類の諸言語を途方もない規模のダジャレに変換し続けた[14]。直線的な成長よりも円環的な無限を象るジョイスのモダニズムは、アルゼンチンのボルヘスやフリオ・コルタサル、さらにはキューバの「ネオバロック」の旗手ホセ・レサマ゠リマの『パラディーソ』等のラテンアメリカ文学に受け継がれる[15]。
世界性の根拠を空間から時間に移行させたことは、モダニズムの重要な功績である。もっとも、時間が豊饒な迷宮として再創造されるにあたっては、たんに文学的な実験だけではなく、自然科学の新しい認識も不可欠であった。一九世紀半ばのダーウィンの進化論やライエルの地質学は、数億年というスケールを備えた《深い時間》を発見した。このダーウィン革命のインパクトを受けて、チェーホフと同時代人のイギリス人H・G・ウエルズの『タイム・マシン』(一八九五年)は、空間ではなく時間のなかに諸世界――現実の世界に隣りあったさまざまなパラレルワールド――を畳み込んだ。諸世界を収容し得る深い時間は、ウエルズの後に盛期を迎えた二〇世紀SFにとって最大の切り札となったのである。
6、南北戦争の解釈――マルクスとフォークナー
二〇世紀文学が世界性の根拠を時間性に認めたこと――この現象を考察しようとするとき、一八九七年生まれのアメリカ文学の巨匠ウィリアム・フォークナーの名を欠かせない。思うに、一九世紀アメリカの最大の思想家は、他のいかなる哲学者でも学者でもなく、小説家のメルヴィルである。それはメルヴィルが、資本主義の空間性=世界性を誰よりも多面的に捉えていたからである。同様に、フォークナーは時間性=世界性の迷宮に誰よりも深く踏み込んだ点で、二〇世紀アメリカ最大の思想家と言えるのではないか。
もとより、アメリカ文学の世界性は、明るい未来に向かって前進するというリニアな時間には一元化されない。なぜなら、アメリカは北部と南部という二つの世界をもつからである。南部とは、アメリカという新世界のなかの旧世界、しかも旧世界(ヨーロッパ)よりも古い旧世界である(第十三章参照)。ここには時間的な転倒がある――古い世界が新しい世界の後に現れたのだから。フォークナーの文学は、まさにこの二つの世界の狭間で生起した時間的錯綜体として読み解くことができる。
北部と南部、この二つの世界の相反性は、一八六一年から六五年まで続いた南北戦争によって強固に輪郭づけられた。当時、南北戦争に思想的な意味を与えたのがマルクスである。一八六二年のドイツの新聞論説で、マルクスはリアルタイムで進行中の南北戦争について、その戦線の広大さといい、兵力や軍費の多さといい、「どのような観点から考察するにしても、アメリカの内戦はこれまでの戦史の記録のうちに類似のものをもたないようなひとつの光景を示している」と評した[16]。マルクスはエンゲルスとともに、この前代未聞の内戦の成り行きを注視していた。それは彼にとって、南北戦争が「第二次アメリカ革命」と呼び得るような画期的な解放運動であったためである。
急進的な奴隷解放の立場に立ったマルクスは、世界史的な革命戦争として南北戦争を位置づけた。戦争終結後まもなく刊行された『資本論』の一八六七年の序文では、一八世紀のアメリカ独立戦争がヨーロッパのブルジョワを刺激したのに対して、一九世紀の南北戦争はヨーロッパのプロレタリアートを鼓舞したと評価される。さらに、『資本論』第一巻の「労働日」の章でも、マルクスは南北戦争に言及しながら「黒人の労働が焼き印をおされているところでは、白人の労働も解放されない」と断言した。レイシズムが存在する限り、労働者の真の解放もあり得ない――それが南北戦争によって明確化されたマルクスの認識なのである[17]。
もとより、マルクスにとってアメリカは、たんなる西方の一国家ではなく、ヨーロッパをも巻き込むトランスアトランティックな政治思想的運動の震源地であった。『資本論』という理論的書物のなかで、南北戦争という直近の事件が評価されていることの意義は大きい。『共産党宣言』の段階ではレイシズムや奴隷制に言及していなかったマルクスは、アメリカの内戦を転換点として、人種と階級の交差に重要な意味を認めるようになる。マルクスが断固としてアメリカでの奴隷解放を支持したのは、人種問題と階級問題は切り離せないという洞察のためである。
ただ、マルクスの触れていないもう一つの重要なポイントがある。それは、内戦はしばしば対外戦争以上に熾烈になり、後世に多くの禍根を残すということである。現に、南北戦争終結のおよそ三〇年後に南部のミシシッピ州で生まれたフォークナーは、北部の側に立つマルクスとは根本的に異なった態度を示していた。フォークナーによれば、勝者の成功はロケットの閃光のように一時的なものにすぎない。真の勝者はむしろ敗者なのである。彼は『西部戦線異状なし』で知られるドイツ人作家レマルクを論じた評論で、次のように記していた。
敗北の彼方には、勝者には知り得ない勝利がある。〔…〕人間は、成功にあまり耐えられるものではないようだ。とりわけ一国の国民、民族はそうである。敗北は国民にとって、民族にとって、良いことなのである。[18]
勝利は何の説明も要らないが、敗北は説明と熟考を要する。ゆえに、敗北こそが国家に「ある領域、ある安全な土地」を与えるのだ。真に耐久性をもつ歴史は、敗北を抱きしめ、敗北の意味を考え抜くところに生じる――この発見こそがフォークナーの文学を貫く強固な認識となった。そして、この敗者の抱く特異な思想の深部にアクセスできるのは、彼にとって小説だけである。フォークナーにおいて思想家であることと小説家であることが交わるのは、そのためである。
7、高密度で持続する《黒い時間》
チェーホフの文学ではさまざまな思想が議論されるが、それらは人間的な現実に地盤をもたない。ニヒリズムのような思想も、人間では背負いきれず、会話の「間」に一瞬浮かび上がるだけである。フォークナーの登場人物もまた、世界に遅れてやってきたアンタイムリーな存在、限りなく亡霊に近い何ものかである。ただし、チェーホフ的人間が常に思想を生き損なうのと違って、フォークナー的亡霊はむしろ思想に憑かれている。彼らの奇怪なオブセッションは「敗北の彼方には、勝者には知り得ない勝利がある」という逆説と切り離せない。
フォークナーはこの敗者の歴史を、手に負えないほど複雑で迷宮的な問題に仕上げた。フォークナー的な歴史は死者や敗者を中心に置くが、彼らは生の根拠をもたない非存在であり、そのことがかえって語り=評価を限りなく誘発する。例えば、一九三〇年の実験的小説『死の床に横たわりて』では、息子たちが棺桶に入る寸前の母の身体を運ぶなか、複数のパースペクティヴから問いと解釈が語られる。世界から消失しつつある亡霊的存在を核として、持続的な語りが結晶化したのだ。
この謎めいた力は、ラテンアメリカの作家たちを強く触発した。ガルシア゠マルケスはフォークナーを「カリブ海の作家」と呼び、ラテンアメリカ文学の淵源と見なした。この発言はたんに、南部(ミシシッピ)と南米の地理的な近接性を指すだけではないだろう――植民地主義の圧力にさらされたカリブ海やラテンアメリカ諸国も、勝者と敗者が交錯するコンタクト・ゾーンであったのだから。フォークナーもガルシア゠マルケスも、ヨーロッパのモダニズムの財産を継承して辺境のミクロコスモスのなかで時間を重層化したが、それは勝者の樹立した単線的な歴史からは決して生まれない。「あの敗北や失敗はいったい何を意味していたのか」と執拗に問い続ける能力をもつ敗者だけが、歴史を重層化し得るからである。
このような敗者の物語を一つのピークに導いたのが、南北戦争からおよそ七〇年後の一九三六年に刊行された『アブサロム、アブサロム!』(引用は藤平育子訳[岩波文庫]に拠り、頁数を記す)である。二〇世紀初頭のシーンから始まるこの恐ろしく異様な小説では、南部の敗北という屈辱の記憶がすべての語りに染み込んでいる。
敗戦から一九〇九年までの四三年間、ブラインドをあげることのない暗い部屋で、黒い喪服をまとい続ける老女ローザ・コールドフィールドは、クエンティン・コンプソンに向かって、トマス・サトペンに対する怒りと憎しみの物語を語り伝えようとする。クエンティンはボストンのハーヴァード大学入学のために、南部を離れる支度をしている若者だが「いずれは亡霊となる宿命を免れ得ない」(上・二一頁)と予告されている。「彼〔クエンティン〕の身体そのものが、敗北者たちの名前が朗々と響きわたる、がらんとした広間〔ホール〕であり、彼は一つの存在ではなく、一つの実体でもなく、一つの共和国だった」(上・二六頁)。無数の敗者=亡霊の語りを強烈な響きに変える「ホール」のような若者を聞き手として、ローザは部屋に棲みついた地縛霊のように「古い侮辱」と「古い決意」を反復する。
今はただ、古い侮辱の中で、サトペンの死という最後の完全な辱しめによって踏みにじられて裏切られ、絶対に許すまいと思った古い決意の中で、四十三年も戦陣を張り続けてきた、孤独でねじまげられた年老いた女の肉体の発する叫びに過ぎなかった。(上・三一頁)
小説の中心にいるトマス・サトペンは、黒人たちを連れてどこからともなく街に現れ、巨大な農園を「創設」して南北戦争時には大佐となるが、最後は自らの農園で殺される。彼の「計画」(デザイン)は、白人と黒人の血の混淆を断ち切ることに向けられるが、それは失敗に終わる。歴史を暴力的に創始しながらも、歴史を統治することはできなかったサトペンの人生は、南部が敗北によって自らの正統性を奪われたことと呼応している。
もともとプアホワイトの家に生まれ、ハイチを経由して黒人たちを動員したサトペンの異常な創設行為は、さまざまな評価にさらされている。例えば、ローザは自らにかかった「呪い」の原因となったサトペンを「悪魔」と呼ぶ一方、クエンティンの父親はその暴力的なサトペンが「孤立無援」の状態にあったと回顧する(上・一〇二頁)。そして、若いクエンティンもまた北部の大学で、サトペンとは何であったかという謎を友人相手に語らずにはいられない。語り手たちにはそれぞれのバイアスがかかっており、その主張は歪曲され非中立的である。ただ、どの立場が事実として正しいかは、さほど問題ではないだろう。南北戦争を「両親も安全もすべて奪い去ったホロコーストの戦争」(上・四〇頁)と呼ぶローザが、四三年間ひたすら敗北=絶滅の意味を問い続ける、その途方もない持続性こそが問題なのだ。
ホロコーストに瀕した敗者こそが真に持続的な歴史を生み出す――このフォークナー的な逆説は、南部人のみならず、南部で奴隷とされた黒人によっても導かれている。カリブ海の仏領マルティニーク島の作家エドゥアール・グリッサンはその優れたフォークナー論で「黒人が持続のなかへすべり込むことができるのは〔…〕彼らが歴史を統べることができないからである」と鋭く指摘した。フォークナーの描く黒人たちは、歴史の支配者ではなく、歴史の重荷を耐え忍ぶ存在である。グリッサンが言うように、フォークナーは「持続のなかにいる」ことと「耐え忍ぶ」ことを結合したのだ[19]。
異常に高密度な持続、それがフォークナー的な時間である。この持続する時間は、敗北を耐え忍ぶうちに、際限なく深まり、錯綜し、ねじれてゆく。ロシア宇宙主義やモダニズム、さらにSFが《深い時間》のなかに諸世界を畳み込んだとすれば、一九三〇年代のフォークナーは時間そのものを質的に変容させ、目もくらむような持続性をもつ《黒い時間》を創出した。ガルシア゠マルケスやグリッサンを含めて、ラテンアメリカの作家たちを強く触発したのは、まさにこの黒く持続する時間ではなかったか。
8、『八月の光』における亡霊の現像
文学はいかなる語調で語り、どのような言葉を選び、誰に言葉を向けるかという「語り」の操作によって、環境の価値を評価する(第二章参照)。フォークナーの画期性は、南部という敗者のトポスにおいて、語ることと考えることに前例のない持続性を与えたことにある。フォークナーにおいて、物語ることと思考することは切り離せない。
繰り返せば、チェーホフにおいて、思想は生に定住しなかった。逆に、フォークナーにおいて、思想は人間に――というより人間の語る物語に――執拗に絡みつく。フォークナー的人間とは自ら統べることのできない歴史にさらされた敗者=亡霊であり、それゆえに解決不可能な問題(アポリア)を抱え込んでいる。グリッサンが言うように、フォークナーは南部という霊廟を「解決策のない矛盾の場所」として象った[20]。敗北の後にやってきた南部人たちは、この「矛盾の場所」でガンガンと共鳴する「響きと怒り」のなか、悪戦苦闘せざるを得ない。敗者である彼らの探索は、世界は有意味か無意味かという問いの彼方で続けられる。フォークナーの小説はニヒリズムを超えたところで、黒い時間の深淵をさらに黒く掘り抜こうとするのである。
フォークナーはこの試みを、すでに『アブサロム、アブサロム!』に先立つ一九三二年の『八月の光』(引用は諏訪部浩一訳[岩波文庫]に拠り、頁数を記す)で推し進めていた。その主人公ジョー・クリスマス――ジーザス・クライストと同じイニシャルをもつ――は黒人の血を引く混血児と噂されているが、それは見た目からは判断できない(それは、イエスが外見上は神聖な「神の子」ではなく、ふつうの男性であったことを思わせる)。黒人でも白人でもない身元不明の宙吊りの状態、それが彼を特徴づけている。ジョーは「徹底した根無し草」であり、南部であれ北部であれ、いかなる帰属先ももたない。「まるでどんな町も都会も彼の場所ではなく、どんな通りも壁も、一片の土地でさえも、彼の住処ではないようだった」(上・四六頁)。
ゆえに、ジョーの存在は徹底して不確定性に浸潤されている。フォークナーは彼を表現するのに多様なメタファーを導入するが、それは、ジョーの存在が常に他の何かとの記号的な類比によって語られるしかないこと、つまり確定したアイデンティティをもたないことの裏返しである。フランケンシュタインの怪物を思わせる、生まれながらの流浪者ジョーの心は、神経過敏であり、死への強烈な予感にたびたび襲われる。例えば、彼は性的に高揚するとき、かえって自らの身体を「濃くて黒い、澱んだ溜まりの中にある溺死体」のように感じる(上・一五六頁)。彼はある意味で生きながらに死んでいる。「広く、人気がなく、影の落ちた道にいる彼は亡霊のようであり、おのれの世界の外に出てしまった霊魂がさまよっているという感じだった」(上・一六六頁)。
しかし、その一方で、亡霊的なジョーは自ら進んで黒人として演技し、共同体のゴシップも彼を黒人として同定する。ジョーの不確定性は一つの場所、一つの記号、つまり「黒人性」に割り当てられる。そのせいで、彼は凶悪な殺人犯として追跡される身となり、ついに貧困白人(プアホワイト)の男によって去勢され惨殺される。もとより、ジャック・デリダが言うように「言語なしのレイシズムはない」[21]。人種は実体ではなく、言語的な構築物である。共同体の言語的習慣は、隠喩を現実と取り違えさせ、それが苛烈な人種的暴力を引き起こす。根無し草のジョーもまた、黒人として確定されることによって、致死的な暴力を向けられるのである。
ジョン・キーツの名詩「ギリシアの壺に寄す」を愛したフォークナーは自らを「壺」にたとえたが[22]、ジョーもまた中身をあらかじめくり抜かれた「壺」を思わせる。『アブサロム、アブサロム!』のクエンティン・コンプソンの身体が、敗者の声を増幅させるアンプのようなホール=共和国であったように、『八月の光』のジョー・クリスマスの身体にも、厳密には彼自身のものとも言えないような無数の声が響いている。そして、この不確定的で亡霊的な彼の存在は、そのつど写真のように現像される。
腰に両手をあて、裸のまま、腿の高さまである埃まみれの雑草の中に立っていると、車が丘をこえて近づいてきて、ライトがまともに彼を照らした。彼は自分の身体が現像液の中から出てくる写真のように暗闇から白く浮き出るのを見た。(上・一五七頁)
亡霊の現像。これが『八月の光』の発明した驚くべき技法である。そして、この現像された亡霊の侵入こそが、南部=敗者の共同体に黒々とした怒りを呼び起こす。黒人が白人になりすまして社会に入り込み、白人の血の純潔性を脅かすこと――南部にとってこれは不名誉のきわみである。この「響きと怒り」の充満する時空を、死の予感に満たされたジョーがさまようとき、ジョーと南部共同体はともにヴァージニア・ウルフ的な感覚の雪崩に襲われることになる。
ここでシェイクスピアの『オセロー』を思い起こそう。すでに『タイタス・アンドロニカス』で黒人(ムーア人)の奴隷を登場させていたシェイクスピアは、『オセロー』では黒人を政治的人間として、つまり都市の統治の最前線に位置する人間として描いた。オセローは移住者でありながら権力者でもあり、ゴシップに取り巻かれている。独裁者マクベスと同じく、オセローも異常な栄達を遂げるものの、その主体性は陰謀やゴシップによってあらかじめ芯をくり抜かれていた(前章参照)。
ジョー・クリスマスは権力者で軍人のオセローとは似ていない。とはいえ、世界と世界の狭間の移民ゆえに語りを誘発するという点では、両者には共通性がある(もとより、代表作『響きと怒り』のタイトルを『マクベス』から借りたフォークナーは、シェイクスピアを強く意識していた)。ジョーは北部と南部、白人と黒人という二つの世界のコンタクト・ゾーンに息づく亡霊であり、帰属先もなければ所有物もないが、それゆえに読む者をむせ返らせるほどの強烈な語りを自らのうちに濃縮する。ジョーという亡霊を現像することは、まさに世界と世界の「あいだ」を現像することと等しい。それはシェイクスピアが『オセロー』で試みたことを、より徹底するような作業であった。こうして、『八月の光』はその息苦しい閉鎖性にもかかわらず、正統的な《世界文学》として現れてくるだろう。
9、三つの円環の交差
加えて『八月の光』の世界性は、ジョー・クリスマスとは対照的な二人の人物によって補強されている。一人は牧師のゲイル・ハイタワーであり、もう一人は妊婦のリーナ・グローヴである。
ハイタワーは南北戦争時に祖父の死の原因となった事件に、いまだに心を奪われている。過去の幻影に囚われた彼の精神は、黒く閉じている。ハイタワーが社会に復帰する見込みはない。ろくに服を洗わない彼には「もはや現実の生を生きていない人間の臭い」が立ちこめている(下・一〇〇頁)。彼の人生は、事実でも真実でもない共同体の「習慣」(上・一〇八頁)に包囲され、すっかり呪われたものとなっている。習慣の力は人間を作り変え、ある地点に固定する。ジョーが居場所をもたない放浪者だとしたら、ハイタワーは場所に縛られた地縛霊である。
とはいえ、この硬直化したハイタワーの人生にも、フォークナーは特異な時間を与えている。小説の最終盤になって、ハイタワーは自らの人生を回想する。その「思考の車輪」は極度に遅くなり、彼の意志的なコントロールを離れて重々しく回り続ける。
これは考えたくない。これを考えてはいけない。これはとても考えられない。窓辺に座り、じっど動かぬ両手の上に身を乗り出している彼から、汗が流れ始める。血のように吹き出しては流れていく。その瞬間から、砂につかまれた思考の車輪は、さながら中世の拷問器具のごとく、彼の魂と人生のねじられ砕かれた関節窩の下で、ゆっくりと容赦なくまわっていく。(下・三五八頁)
著名なフォークナー研究者アンドレ・ブレイカステンが指摘するように、円環(circle)は『八月の光』の数ある比喩の一つという以上に、小説の構造や意味そのものを統括する最重要の比喩である[23]。ジョーにとって、円環は彼を閉じ込める象徴である。殺人の後に七日間の逃避行を続けたジョーは「それまでの三十年をあわせたよりも遠くまで旅をした。しかしそれでもなお、彼はその円の内側にいるのだ」(下・一三二頁)。かたや、ハイタワーを巻き込む「思考の車輪」は、本来は目を背けたいことへと彼を強制的に運んでゆく。ブレイカステンはこの異様なヴィジョンが、もはやハイタワーのものでもフォークナーのものでもなく「テクストの思考」であると説明している[24]。
こうして、思考の車輪はハイタワー本人を追い越してゆっくりと静かに回転し、非情な拷問のように彼の人生に黒い虚無をうがち続けるが、これはそのままフォークナーの「作品」の寓意として読めるだろう。あらゆる書物は自己自身に向かって閉じようとする力をもつ。特にフォークナーの小説は、渦巻を描くようにして敗者の心の深淵に入り込んでゆく。フォークナーの語りは、まるで自らの内部にめり込むように思える。強い求心力を備えた小説群は、ミシシッピ州を舞台とするサーガの一部でありつつも、それぞれに特異なやり方で閉じようとする――ちょうどハイタワーが特異なやり方で自己に引きこもっているように。
その一方、ジョーともハイタワーとも異なる「円環」をもつのがリーナ・グローヴである。リーナはお腹の子の父親を探して旅をしている。その純朴さや穏やかさを強調された人柄は、ジョーの放浪やハイタワーの自己閉鎖とは対照的に、のどかでリラックスした調子を作品に与えている。ジョーにまつわる不確定性が、彼自身のアイデンティティに由来するとしたら、リーナにまつわる不確定性は、彼女自身というよりむしろ伴侶となる他者と関わる。リーナは出産した後、本来探していたルーカス・バーチではなく、バイロン・バンチという似た名前の別の男性を旅の連れに選ぶが、この「聖家族」を思わせる三人組は、ジョーやハイタワーとは根本的に異なる偶発的な人生の軌跡を描いていた。
そして、このリーナの時間感覚の記述にも「円環」のヴィジョンが現れる。「八月の午後の暑く静止した静寂」のなか、丘の上のリーナに向かって、極度にゆっくりと進む馬車が、がたぴしという硬質な響きとともに近づいてくる場面を引用しよう。
あまりにも遅いので、見つめる目は馬車の姿を見失い、視覚と感覚は、道自体がそうであるように、あの夜と昼の平和で単調な繰り返しにまどろむように混じりあい溶けこんでしまう。まるで、長さを測り終えた糸が糸巻きに巻かれていくかのようだ。(上・一三‐一四頁)
ここには、物事の輪郭を溶かすほどにゆっくりと持続=回転する時間が書き込まれている。ジョーやハイタワーの悲劇的な円環とは異なり、リーナの円環はまどろみをもたらす。もっとも、この時間はたんにのどかで楽天的なものではない。どちらかと言えば、リーナの円環から連想されるのは、サンチョ・パンサに「良いことも悪いこともそうそう長続きするはずはないのであってみれば、われらにずいぶんと悪いことが続いた今、良いことがすぐ近くに来ておるに決まっているからじゃ」(前篇・第一八章)と教え諭すドン・キホーテの妙に醒めた認識ではないか。良いことには悪いことが、悪いことには良いことが続く――リーナはこのような循環のなかにいるように思える。
一見してそれぞれに孤立した三つの時間の環は「夜と昼の平和で単調な繰り返し」のなかで溶けあい、交差する。その交点にいるのがリーナの赤ん坊である。リーナは赤ん坊の父親がジョー・クリスマスではないかと錯覚し、ハイタワーはリーナの出産を助けるのだ。この胎児はリーナ、ジョー、ハイタワーの形作るボロメオの環の結び目のように機能する。リーナは出産によって、南部のなかにもう一つの世界、もう一つの時間を受胎させる。ここから分かるのは、フォークナーが世界に遅れてやってくる存在、つまり「後から来るもの」に対して、チェーホフとは異なりポジティヴな意味を与えていたことである。
10、最後にして最初の世界文学
私は『八月の光』を「最後にして最初の世界文学」と呼びたい。「最後」というのは、フォークナーの小説群においては、デフォーからメルヴィルに到る小説家が描いたグローバルな空間性が爆縮を起こし、郵便切手のように狭く小さい「旧世界」へと反転させられたからである。この圧縮によって、それまで世界性を保証してきた海はいったん押しつぶされ、過去の亡霊のうごめく場に取って代わられる。
逆に「最初」というのは、この爆縮されたミクロコスモスから、複数の「持続する時間」が生じてくるからである。『アブサロム、アブサロム!』の持続性が「耐え忍ぶこと」と不可分であったとしたら、『八月の光』の持続性は「回転すること」と結びつく。このような持続性は、世界に意味があるかないかという問いそのものの彼方へと読者を導く。なぜなら、回転する時間においては、空虚な壺のようなジョー・クリスマスも、社会的関係から切断されたゲイル・ハイタワーも、ニヒリズムという地点に定住することはできないのだから。この点で、『八月の光』にはニヒリズムを超える時間の力が書き込まれていた。フォークナーが「人が耐えることの手伝いをすることが、作家に与えられた特権なのです」とノーベル文学賞受賞講演で語ったことを、ここで改めて思い起こしてよいだろう[25]。
われわれはこのような文学をどう評価すればよいだろうか。思えば、二一世紀の世界観は、単一のグローバルな世界市場(世界文学)という地盤に、多文化(各国文学)が分立するというモデルに支配されている。このような多文化主義は、人類の時間が一つのプラットフォームに統合された状態を前提としている。マルクスとエンゲルスは『共産党宣言』で、世界市場は民族的偏狭さを超えた「一つの世界文学」を形成すると予告しながら「ブルジョア階級は、かれら自身の姿に型どって世界を創造するのである」と記したが、まさに二一世紀のブルジョアの姿にあわせて描き出されたのが、統一されたグローバルな世界時間における多文化の共存というイメージである。
それに対して、二〇世紀のフォークナーが示したのは、多文化性ならぬ《多時間性》に根ざした世界であった。フォークナーの世界は、複数の円環的な時間の交差によって特徴づけられる。人類の時間やテンポは決して一つにはならない。いわば野生のでこぼこした庭のように、その内部にさまざまな時差を孕んだ世界時間――フォークナーはその発見者であった。多文化主義の時代に生きるわれわれは恐らく、その《多時間性》の文学の富をまだ十分に汲み尽くせていない。つまり『八月の光』は――最後にして最初の世界文学は――本質的に未完なのである。
[1]マルティン・ハイデッガー『ニーチェ』(第二巻、細谷貞雄監訳、平凡社ライブラリー、一九九七年)二六九、二七四、二九一、三〇三‐四、三一一、三二三頁。
[2]ジル・ドゥルーズ『意味の論理学』(上巻、小泉義之訳、河出文庫、二〇〇七年)二六五頁。
[3]イーゴリ・エヴラームピエフ『ロシア哲学史』(下里俊行他訳、水声社、二〇二二年)一二三頁。エヴラームピエフによれば、ロシアの哲学は、絶対的・精神的な「神」と有限的・物質的な「人格の生」をいかに接合するかという問いをめぐっており、ドストエフスキーはその問いに卓抜な哲学的見解を示した思想家として理解される。
[4]さらに、チェーホフとトルストイの差異も見逃せない。チェーホフは一八九〇年に苛酷な流刑地であったサハリン島に命がけで旅行した後、かつて心酔していたトルストイを批判するようになる。トルストイが農民的なモラルに傾斜したとすれば、チェーホフは「電気や蒸気」に、つまり科学の時代に人間探究の鍵を探し出そうとした。トーマス・マン「チェーホフ論」(木村彰一訳)原卓也編『チェーホフ研究』(中央公論社、一九六九年)三九三頁。
[5]Cornel West, “Chekhov, Coltrane, and Democracy”, The Cornel West Reader, Basic Civitas Books, 1999, p.556.ここでウェストがジャズを参照して、チェーホフの悲喜劇性をジョン・コルトレーンに、その喜劇性をチャールズ・ミンガスに対応させているのは興味深い。
[6]ソフィ・ラフィット『チェーホフ自身によるチェーホフ』(吉岡正敏訳、未知谷、二〇一〇年)九九‐一〇〇頁。
[7]ロジェ・グルニエ『チェーホフの感じ』(山田稔訳、みすず書房、一九九三年)九五頁。なお、チェーホフと並んで、救いのない世界を「証言」した作家としてはカフカ、とりわけその日記が重要である。不眠と疲労に包まれた独身者カフカは、自己省察的な日記を残した。彼が人生のトラブルや心理的な混乱をまるで機械の動作のように報告し、苦痛に満ちた生を規則正しくレイアウトするとき、日記はいわばカフカ的日記に「変身」する。彼の「空っぽ」の実存には、救済の余地がない。しかし、カフカの透明で瞑想的な記述は「無力なものの力」(ヴァーツラフ・ハヴェル)を読者に伝えるだろう。
[8]J・ブロック゠ミシェル『ヌヴォー・ロマン論』(島利雄他訳、紀伊國屋書店、一九六六年)五九頁。
[9]リチャード・エルマン『ダブリンの四人』(大澤正佳訳、岩波書店、一九九三年)一五三、一六五頁。
[10]イノック・ブレイター『なぜベケットか』(安達まみ訳、白水社、一九九〇年)八七、九七頁。
[11]グルニエ前掲書、一八三頁。
[12]S・G・セミョーノヴァ他編『ロシアの宇宙精神』(西中村浩訳、せりか書房、一九九七年)。近年、美術批評家のボリス・グロイスはフョードロフに始まるロシア宇宙主義の不死性への欲望の根幹に「無条件の生政治の要求」を見出し、それを「ニヒリズムの克服」のロシア的形態と位置づけている。グロイス編『ロシア宇宙主義』(乗松亨平監訳、河出書房新社、二〇二四年)一二、一七頁。
[13]特に、チェーホフと同世代のコンラッドは、消尽した空間的ポテンシャルを、異常に長大な語りの時間のなかで再生させた点で特異である。コンラッドの小説では、一八世紀小説のようにさまざまな空間が踏破されるが、『ロード・ジム』や『闇の奥』をはじめ、その海外の諸世界は語りのなかに梱包される。つまり、異質な空間は虚構化・間接化されて、聞き手に伝えられる。アンドレ・ジッドは『秋の断想』(辰野隆他訳、新潮文庫、一九五二年)に収めた印象的なエッセイで、親交のあったコンラッドについて「書物でも会話でも、個人的なことをすべて、虚構によって転位し、非個性化し、自己から遠ざけることを余儀なくされた。それゆえ、直接の話は奇妙に不器用だった。彼は虚構の中でしか、気楽でいられなかった」と回想している(七九頁)。デフォーやスウィフトのリアリズム的な旅行記とは違って、コンラッドは空間を「虚構に転位」させるという手続きを必要とした。世界を虚構に封じ込めること――それはコンラッドのみならずジッドの文学の特性でもある。
[14]エルマン前掲書、一三〇頁。
[15]César Augusto Salgado, From Modernism to Neobaroque: Joyce and Lezama Lima, Bucknell University Press, 2001.
[16]「アメリカの内戦」『マルクス・コレクション』(第七巻、村岡晋一他訳、筑摩書房、二〇〇七年)一一四頁。
[17]ケヴィン・B・アンダーソン『周縁のマルクス』(平子友長監訳、社会評論社、二〇一五年)二八八、二九一頁。北部は大資本によって支配されていたので、マルクスが断固として北部の側に立ったことは、後の一部のマルクス主義者を当惑させることにもなった(一三五頁)。しかし、レイシズムが奴隷労働の正当化のために要求されるというウォーラーステインやエリック・ウィリアムズの考えに先駆けて、人種と階級の交差に着眼したマルクスはやはり慧眼と言うべきだろう。
[18]「書評エーリヒ・マレーア・レマルク『還りゆく道』」『フォークナー全集』(第二七巻、大橋健三郎他訳、冨山房、一九九五年)二〇三頁。
[19]エドゥアール・グリッサン『フォークナー、ミシシッピ』(中村隆之訳、インスクリプト、二〇一二年)九四頁。
[20]同上、三九頁。
[21]Jacques Derrida, “Racism’s Last Word”, in Henry Louis Gates Jr. ed., Race, Writing, and Difference, University of Chicago Press, 1985, p.331.
[22]「『響きと怒り』序文」フォークナー前掲書、二七五頁。
[23]André Bleikasten, The Ink of Melancholy: Faulkner’s Novels from The Sound and The Fury to Light in August, Indiana University Press, 1990, p.350.
[24]ibid., p.347.
[25]「ノーベル文学賞受賞演説」フォークナー前掲書、一三八頁。
[26]マルクス+エンゲルス『共産党宣言』(大内兵衛他訳、岩波文庫、一九五一年)四五頁。
この記事は、PLANETSのメルマガで2024年8月27日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2024年10月10日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。