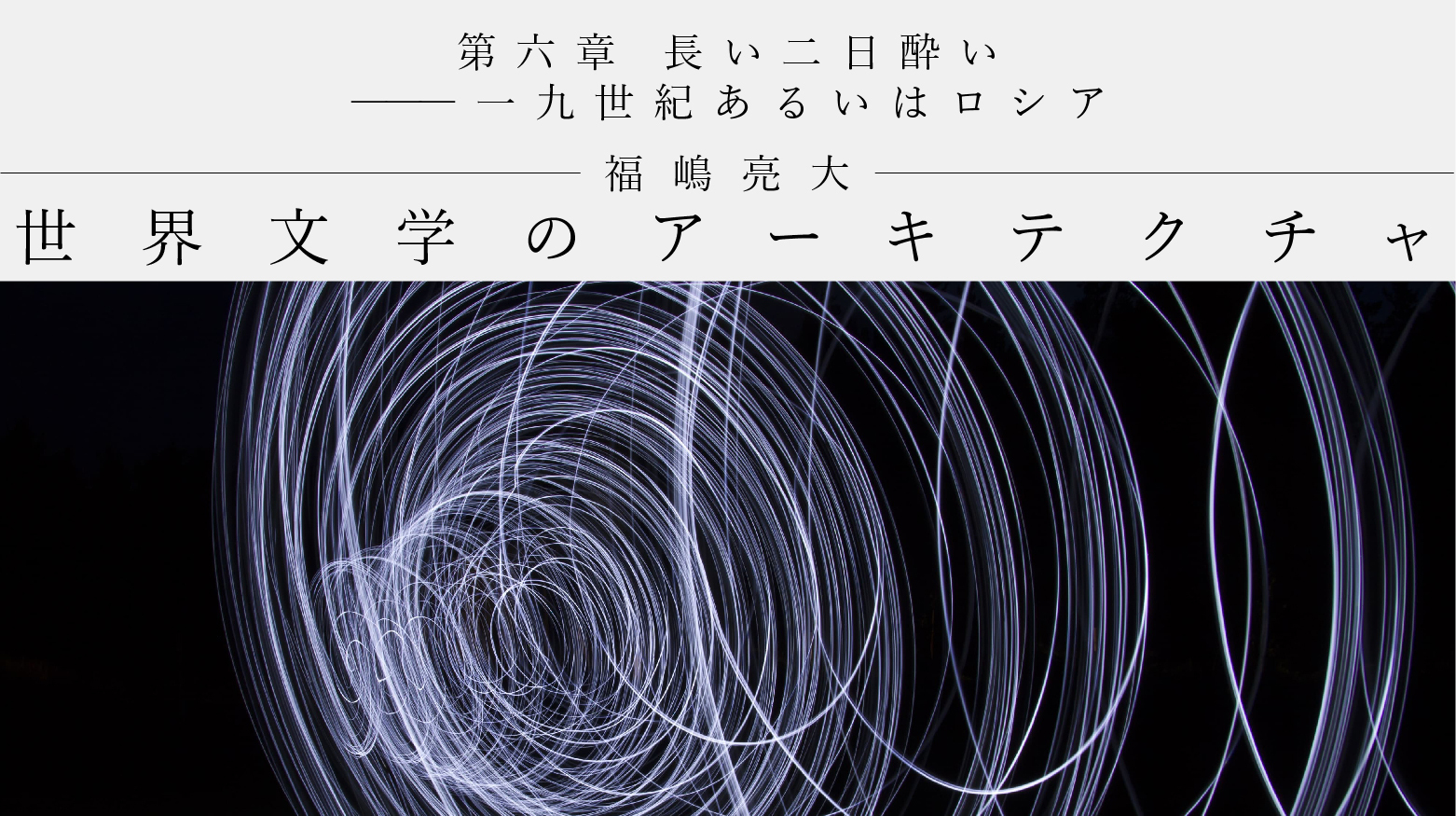批評家・福嶋亮大さんが「世界文学」としての小説とそれを取り巻くコミュニケーション環境を分析していく連載「世界文学のアーキテクチャ」。
今回は19世紀ヨーロッパにおける社会思想について分析します。アメリカ独立戦争やフランス革命の反省から個人の人権尊重への意識が高まった前半期、自然科学が優勢となった後半期にかけてどのような思想の変遷があったのでしょうか。
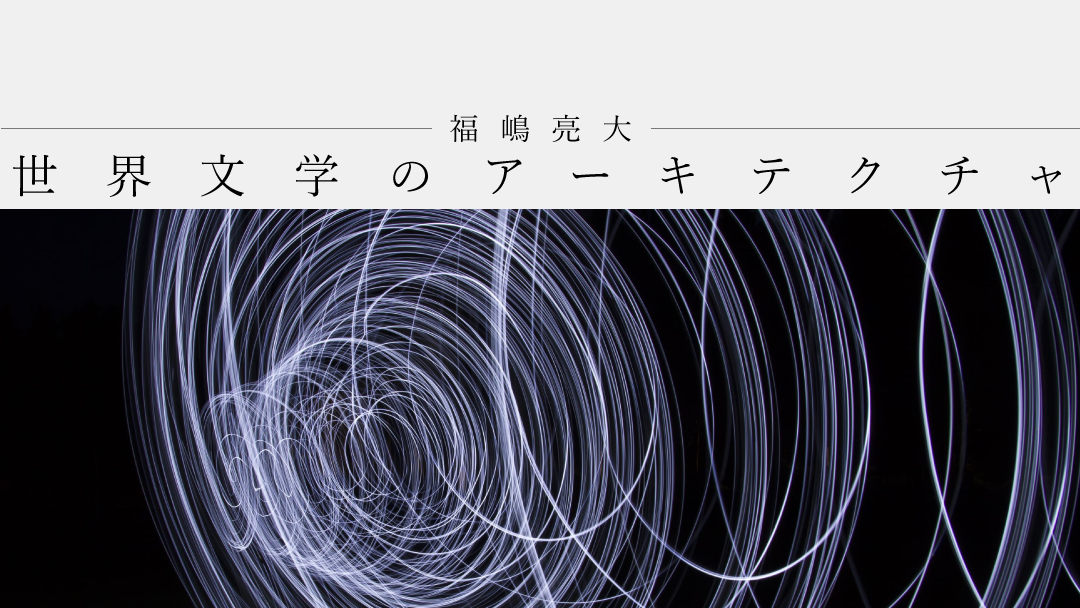
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、消費社会と管理社会の序曲
一九世紀ヨーロッパの社会思想史は、大きく前半と後半で分けることができるだろう。アメリカ独立やフランス革命を経た一九世紀前半には、誰もが自由や幸福を追求する権利をもつという理念が、多くの思想家たちに抱かれていた。彼らは、恐怖政治に陥ったフランス革命の限界を見据えつつ、貧困をはじめとする産業社会の問題に立ち向かう新しい社会体制を構想した。
特に、一八二〇年代から四〇年代のフランスでは、サン゠シモンおよびその後継者たち(生産の優位を掲げ、人間による地球の開発を正当化し、社会を束ねる世俗宗教を支持した)からルイ・ブラン、ブランキ、さらにはプルードン(中間集団を一掃して個人を国家に依存させるサン゠シモンとは異なり、自立した個人がその労働を通じて自由と尊厳を得るアソシエーションを構想した)に到る社会主義者が、さまざまな国家像や労働観を示した。彼らはイギリスの産業革命のインパクトを強く受けつつ、しかしイギリスを「反面教師」として、労働者を中心とする社会革命のシナリオを描いた[1]。
しかし、このような変革の機運は、一九世紀後半のヨーロッパでは萎んでしまう。革命運動が下火になる一方、自然科学や医学の重要な発見に伴って、形而上学よりも実証主義が優勢となり、経済的には繁栄期を迎えた。むろん、デンマーク戦争、普墺戦争、普仏戦争といった争いはあったが、それらはいずれも短期間に終わり、その戦域も限られていた。このおおむね安定した社会では、変革のエネルギーはビジネスや科学に向けられた。芸術家もそれと無関係ではいられない。例えば、一九世紀後半のドイツの教養市民層に根ざしたブラームスは、社会問題には無関心を貫く一方、ナショナリズムには熱烈に反応した。彼の音楽も、人類全体に呼びかけるベートーヴェン的な交響曲よりも、小規模で親密な室内楽に傾いた[2]。
現代の政治学者ジョン・ミアシャイマーは、ナポレオン戦争後の一九世紀の大半が「多極的な安定構造」の時代であり「ヨーロッパ史の中で最も紛争の少ない時代になった」と評している[3]。フランス革命やナポレオン戦争のような血なまぐさい沸騰を目の当たりにすれば、その後にすさまじい変革の時代がやってくると考えるのが自然である。しかし、一九世紀ヨーロッパはかえって、大国どうしがバランスをとる相対的な安定期に入った。このような政治的不発の感覚が、当時のヨーロッパ的精神風土の根底にある。
騒乱と変革の時代から、安定と均衡の時代へ――その折り返し点を示す象徴的な出来事が、フランスの二月革命のたどった奇妙な顛末である。一八四八年二月、経済政策に不満を抱いたブルジョワたちが、フランス国王ルイ゠フィリップの体制(七月王政)を倒して新政権を樹立した。このほとんど誰にも予見できない不意打ちとして起こった革命は、ただちにヨーロッパ各地に飛び火する。フランス革命以前のヨーロッパへの回帰を企てた「ウィーン体制」の旗振り役であった保守派のメッテルニヒも、オーストリアからロンドンへの亡命を余儀なくされた。フランスの革命はヨーロッパの「諸革命」(いわゆる諸国民の春)へと発展したのである。
しかし、この不意に始まった諸革命は、あっという間に沈静化してしまった。革命運動が行き詰まるなか、ナポレオンの甥ルイ゠ナポレオン・ボナパルトが、一八五一年にクーデタを起こし、市民の絶大な支持を集め、翌年にはナポレオン三世として帝政を樹立した。彼がよく弁えていたのは、たとえ独裁者であってももはや民衆の「世論」を無視できず、禁止や抑圧という強権的なやり方では政権を保てないという、政治の新しいルールである。彼の体制はあくまで普通選挙の結果であり、民意の支持なしには成り立たなかった。
こうして、いったん勝利したはずの市民革命が、皮肉なことにかえって反動的な帝政を呼び込んでしまう――しかも、このドタバタ劇の後、社会は表面的には安定と繁栄に向かった。オリジナルのナポレオンが軍事的な拡大をめざしたのに対して、そのシミュラークルとしてのナポレオン三世はむしろ商業的・平和的な社会を望んだ。彼の政権下で開催された一八五五年および六七年のパリ万博では、産業社会そのものが神聖化され、不衛生であったパリの街もジョルジュ・オスマンの指揮のもとで「改造」された。さらに、「貧困の根絶」を目標とするナポレオン三世は、金融と産業の発達によって貧困を除去しようとするサン゠シモン主義の継承者であり、労働者用の共同住宅やリハビリ施設を建設しつつ、新しいベンチャー・キャピタルの創設にも手を貸した[4]。
この「第二帝政期」のフランスを覆ったのは、ナショナリズムとポピュリズムを背景としながら、産業そのものを宗教として、労働者の福祉や社会保障にも配慮するマイルドな権威主義であった。この新たな統治システムは、上からの一方的な禁止ではなく、ミシェル・フーコーの言う「管理」の技術を駆使しながら、世論を味方につけようとする[5]。そう考えると、一九世紀後半のフランスが、今日のポストモダンな消費社会・管理社会の序曲になっていることが分かるだろう。この時代を批評することは、ポストモダンの前駆的環境でいかなる芸術や社会思想があり得たのかという問いを惹起せずにはいない[6]。
2、「長い二日酔い」の世紀
ところで、市民革命の反転という奇妙な現象に、早くからシャープな考察を施したのはマルクスである。マルクスは二月革命の顛末を分析した一八五二年の著作『ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日』において、歴史の反復に関して「一度は偉大な悲劇として、もう一度はみじめな笑劇として」という有名な認識を記した。つまり、当時のフランス市民は「ナポレオン」という偉大な悲劇を「ルイ・ボナパルト」という退屈なコメディに取り換え、しかもこのコピーの政治を支持したのである。
マルクスによれば「彼らは昔のナポレオンのマンガ版を手に入れただけではなく、一九世紀半ばにはそう見えるにちがいないのだが、昔のナポレオン自身をマンガにしてしまった」[7]。この民衆の支持を受けた漫画的専制において、革命の理念はその反対物に転じてしまった。マルクスはこの成り行きを「二日酔い」にたとえている。
一八世紀の革命である市民革命は、成功につぐ成功へと迅速に突進して、その劇的効果を競いあい、人間も物もダイヤモンドに囲まれたように輝き、恍惚が日々の精神となる。しかし、それは長くもたず、すぐにその絶頂に達し、社会は、その疾風怒濤時代の成果をしらふで習得するより前に、長い二日酔いに襲われる。
一九世紀の革命であるプロレタリア革命は、たえず自分自身を批判し、自分で進みながら絶え間なく中断し、成就されたと見えるものに立ち戻って改めてやり直し、最初の試みの中途半端さ、弱さ、みすぼらしさを情け容赦なく徹底的に嘲笑する〔…〕。[8]
一八世紀の革命は市民階級をうっとりさせたものの結局スカであり、フランス人はナポレオン三世の快適な専制政治に順応していった。だからこそ、マルクスはいわば革命の革命としてのプロレタリア革命――虚偽の完成を拒み、何度でもやり直し続ける永続革命――の必要性を強く訴えたのである。
マルクスの分析は一九世紀そのものの二面性を鋭く言い当てている。当時の市民は、前世紀から市民革命の理念を受け継いだが、それは第二帝政の誕生という「中途半端」な結果をもたらした。しかも、この帝政は表面的にはうまくいっていたので、ラディカルな変革の機運はますます後退した。こうして、高揚した希望を抱きながら、退屈な現実にからめとられた一九世紀的人間は、麻痺的な「長い二日酔い」を味わうことになったのである。
3、量子状態のパリ――『レ・ミゼラブル』
一九世紀の折り返し点で、マルクスは市民革命以後のhangover(二日酔い/興奮の後の気抜け)を、時代の症状として捉えた。ここで重要なのは、ロマン主義的な高揚と、それに続くアンチ・ロマン的なみすぼらしい気抜けという二面性が、当時の文学や芸術にもたびたび再現されたことである。いささか図式的になるが、ここでも一九世紀の前半と後半を分けてみるのがよいだろう。
日本の曲亭馬琴がロマンティックな『八犬伝』を書き継いでいた一八一〇年代から四〇年代にかけて、ドイツではゲーテが『イタリア紀行』や『西東詩集』に続いて、『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』および『ファウスト』第二部を刊行するとともに、世界文学論の構想を語った。一八三〇年代になると、フランスではバルザックが長大な「人間喜劇」シリーズを旺盛に書き進め、詩人にして政治家のヴィクトール・ユゴーが健筆をふるった。さらに、同時期のイギリスでは、二〇代のディケンズの出世作(『オリバー・ツイスト』や『クリスマス・キャロル』)が刊行された。ブロンテ姉妹の『嵐が丘』と『ジェーン・エア』の発表はともに一八四七年である。その翌年、パリの二月革命の直前に、ロンドンの出版社からマルクス&エンゲルスの『共産党宣言』が出る。
これらには総じて、社会の底部にうごめく不穏な「エス」への注目がある。かつて哲学者のディルタイが評したように、一八三〇年代以来、社会の与える「重圧」に抵抗しようとした作家や思想家は、現実の醜さを解剖しながら「下から上」へと社会を突き上げる力、つまり不可視の欲動のエネルギーに注目した[9]。例えば、ヨークシャーの荒野を舞台としたエミリ・ブロンテの『嵐が丘』では、孤児のヒースクリフが荒々しい「エス」の化身として現れる。あるいはバルザックの一連の小説では、商品経済の渦に巻き込まれた人間たちの欲動を――『あら皮』に見られるフェティシズムのテーマも含めて――生理学的に把握しようとする態度がある。いずれも、人間を衝動的に突き動かす「下」からの力が主要なテーマとなった。
さらに、一八二〇年代から三〇年代を舞台としたユゴーの『レ・ミゼラブル』(一八六二年)の最終盤には、主人公のジャン・ヴァルジャンが、負傷したマリユスをかついで、革命のバリケードからパリの下水道へと降りる有名な場面がある。一八〇二年生まれのユゴーは、一九世紀前半の市民戦争(内戦)の時代を回顧しながら、革命家たちの足元に広がる不気味な地下水脈に潜り込んだ。下水道の歴史に関する作者の詳しい解説があった後、ジャン・ヴァルジャンはパリの不可視のアンダーグラウンドに、突然ワープする。
パリが海と似ている点がもうひとつある。大海と同じで、そこにもぐりこんだ人間は姿を消すことができる。
場面の転換は空前のものであった。ジャン・ヴァルジャンは町のまん中にいながら、その町の外に出てしまっていたのである。彼は蓋を開けて閉める間もなく、真っ昼間から真っ暗闇に、正午から真夜中に、喧騒から沈黙に、雷鳴の渦巻から墓場の沈滞に、さらにあのポロンソー通りでの大波瀾をもしのぐ不可思議な急展開によって、これ以上はないくらい極端な危難から究極の安全へと移行したのである。[10]
ナポレオン三世の帝政に抵抗してベルギーに逃れた亡命作家ユゴーは、ここで一九世紀の「二日酔い」的な時代精神を見事に浮き彫りにした。沸騰する地上から、死の静寂に包まれた地下への移動は、まさに「不可思議な急展開」として生じる。極端な危険と究極の安全は、このシーンにおいて背中あわせにされた。長大な『レ・ミゼラブル』を終局に向かわせるにあたって、ユゴーはいわば0と1が重ねあわせになった量子状態の世界として、革命下のパリを再創造したのである。
地上の革命が熱狂に達したとき、人間的なものを絶滅させた下水道が、その分身=影として不意に現れる――この地下の≪新世界≫は、バリケードを築いて革命に邁進する気高いシトワイヤン(市民)の世界でもなければ、ポスト革命の快適な消費社会にすっかりなじんでしまった俗物的なブルジョワの世界でもない、死せるモノたちの世界である。そこには地上とは別の次元が開かれる。哲学者のジャック・ランシエールが言うように、『レ・ミゼラブル』の「下水道では、栄華と貧窮の遺品が混じりあい、社会的な壮麗と演劇的なまがい物の遺品とが混淆し、別の平等性が別の言語で表されている」[11]。
ゲーテのファウストが、自滅もいとわない上昇型の加速主義者として、悪魔やホムンクルスと接触したとすれば(第一章参照)、ユゴーのジャン・ヴァルジャンは自己犠牲もいとわない下降型の英雄として、あらゆるものを「平等」に並列する下水道=墓にワープする。あるいは一八世紀ヨーロッパの思想家たちが初期グローバリゼーションを背景として、文化・習慣の異なる他者を海外に求めたとしたら(第三章参照)、一九世紀半ばのユゴーはパリの地下こそを内なる他者として出現させた。『レ・ミゼラブル』の二年後に出たドストエフスキーの特異な小説『地下室の手記』もそうだが、一九世紀小説の画期性は、オルタナティヴな世界としての「地下」を発明し、世界そのものを二重化したことにある。
4、不発弾を抱えた作家――ボードレールとフローベール
このように、『レ・ミゼラブル』はロマン的な革命の沸騰とアンチ・ロマン的な墓の静けさを二重写しにしたが、ユゴー以下の世代の文学者はこの量子状態を引き継ぎつつも、二日酔い特有の麻痺の感覚をいっそう強調した。この一九世紀後半の精神風土を象徴するのが、ともに一八二一年生まれの詩人シャルル・ボードレールと小説家ギュスターヴ・フローベールである。
後に、ヴァルター・ベンヤミンは消費文化の爛熟したパリを「一九世紀の首都」と呼び、ボードレールをその化身と見なした。ベンヤミンによれば、ボードレールの詩を特徴づける「憂鬱」は「恒常的な破局に対応する感情である」。近代社会は表面的にうまくいっているが、まさにそのことによって、実はたえず壊れ続けている――それこそがボードレール的憂鬱に映じたショッキングなイメージである。「ボードレールは、砕け散る波に向かって話しかける人のように、パリの街の喧騒に向かって話しかける」[12]。ボードレールは繁栄する≪近代≫を、そのまま無数のカタストロフの集積として読み替えた。
そもそも、ベンヤミンが言うように、第二帝政期は「真の詩人をもはや必要としなく」なった商品経済の時代である。「人間を取り巻く事物の世界は、ますます仮借なく商品の姿をとってゆく。それと同時に広告が、事物の商品としての性格を被い隠しはじめる」。ボードレールにとって、万物が商品としてパッケージされる資本主義世界は近代の帰結であり、そこから逃れる術はない。ゆえに、彼は「心地よさ」を徹底的に拒絶しつつ「新しいものの永劫回帰」としての流行(モード)を生き抜こうとした。ボードレールの詩の冒頭は、しばしば「深淵からの浮上」という運動性を示すが、それはぐるぐると渦を巻く商品世界の迷宮から、逆説的な≪救済≫の可能性を引き出そうとする彼の文学のアレゴリーになっている[13]。
こうして、ボードレールが詩人を不要とする第二帝政期のパリの廃墟で、商品=モードの永劫回帰を生き抜く内的亡命者になり、後にベルギーのブリュッセルへと逃走したのに対して、フローベールはパリから離れたクロワッセに早くから隠遁し、自らの散文の彫琢に取り組んだ。『サランボー』で成功を収めた後、ナポレオン三世に招待されたこともあったとはいえ、彼がもっぱら田舎の仕事場に釘づけにされていたのは確かである[14]。パリを舞台とした『感情教育』は別として、フローベールはもっぱら、俗物と因習に支配された田舎のブルジョワの社会を解剖し、そのすべてを語るという使命を自らに課した。
この前代未聞の苦行の果てに、『ボヴァリー夫人』(一八五七年)や晩年の『ブヴァールとペキュシェ』(一八八一年)のようなフローベールの小説は、民主主義(=平等の理念)の文学的表現という様相を呈する。ジャック・ランシエールが論じるように「[フローベールの]小説で実現されている平等性は、民主主義的な主体のモル的な平等性ではなく、ミクロな出来事、個体性の分子状の平等性である」[15]。政治上の民主主義は哲学者ドゥルーズの言う≪モル的なもの≫、つまり統合された主体を単位とする。しかし、フローベールはそれをさらに分割して、主体未満の≪分子的なもの≫の働きまで緻密に描写しようとした。この単位の変更は、人間たちの民主主義ではなく、いわばミクロなモノたちの民主主義への道を開くものである。
文学の仕事を戦略的な「数え間違い」に求めるランシエールにとって、世界をいわば分子的なレベルで数え直したフローベールの小説は、文学の新しいパラダイムを予告していた[16]。亡命中のユゴーを支援したこともあったフローベールは、万物を平等化するユゴー的な下水道を、むしろ地上の俗物的なブルジョア社会にまで引き上げた。フローベール自身は「平等とは隷属です。だからこそ、ぼくは芸術が好きなんです」と述べ、一人一票の普通選挙を「人間精神の恥」として忌み嫌っていたが[17]、その小説では、人間未満のこまごまとしたモノたちの民主主義が象られていた。
しかも、フローベールはこの分子状の戯れに、高度な自律性を与えようとした。彼が自らを「精神の僻地」に置きながら「外部へのつながりが何もなくて、ちょうど地球がなんの支えもなしに宙に浮いているように、文体の内的な力によってみずからを支えている書物」を夢想したことは、よく知られている[18]。医者の父をもつフローベールには、もともと「腐敗」や「解剖」へのオブセッションがあった。表向きはうまくいっているが、実際にはすでにすっかり腐敗してしまったブルジョワ社会を分子レベルで解剖することによって、彼は人間とモノのあいだのヒエラルキーを壊し、取るに足らない主題から「地球」のように自転する芸術を作り出そうと企てた。
生粋の一九世紀人であるボードレールとフローベールは、いわば大量の不発弾を抱えた作家であった。彼らの捉えた≪近代≫とは、起こるはずの変革が起こらないまま、ミクロな破局の予兆ばかりがたえず累積してゆく社会である。彼らはこのエクスタシーもカタルシスもない状態から、分子状のモノたちの螺旋状の運動を引き出した。そこには、何も始まらないうちに、何もかもがすでに終わってしまったという二日酔いの世紀特有のパラドックスが濃縮されている。
5、異常なアゴーギク
ボードレール的憂鬱やフローベール的分子は、彼らの抱えた不発弾の対応物である。われわれは彼らの苦境に、一八世紀と一九世紀のあいだの差異を読み取ることができる。家出の衝動に駆られ、ついに大西洋の孤島へと到るロビンソン・クルーソーのような一八世紀型のグローバリスト――放蕩息子としての実業家――は、一九世紀にはもはや存在の根拠をもたない。サルトルの恐ろしく長大なフローベール論が『家の馬鹿息子』と題されたのは、きわめて象徴的である。
細切れにされた分子状のモノたちが、入口も出口もない螺旋のなかを戯れ続けること――それは文学のみならず音楽とも深く関わるテーマだろう。興味深いことに、晩年の坂本龍一は一九世紀後半生まれの異形の巨匠指揮者たち(フルトヴェングラー、クナッパーツブッシュ、メンゲルベルク等)を引きあいに出しながら、彼らの演奏におけるテンポの揺らぎ、さらには一九世紀のロマン主義的な音楽の存在形態の謎にたびたび言及していた[19]。彼らの異常なアゴーギク(テンポの伸縮)は主観的・恣意的にも思えるが、そうではない。というのも、ときに音楽の流れそのものが崩壊しかねないほどに揺れ動くそのロマンティックなテンポは、むしろ主観を超えた分子レベルでの音の運動を出現させ、ほとんど超常的な時間感覚を聴き手にもたらすからである。
文学であれ、音楽であれ、不発弾の蓄積した一九世紀の精神風土では、一定のペースで規則正しく進むという「しらふ」の明晰さは維持しがたい。この精神的な二日酔いの帰結は、およそ以下のようなものである。
・平常な言葉では表現できず、想像も及ばない何ものかへのあこがれに取り憑かれる。
・眠り込んだはずの狂気じみたエネルギーが、夢のなかで次第に肥大化し、やがてその微細な振動が現実を覆い尽くす。
・干からびた現実から逃れようとするものの、かえって足をずぶずぶととられ、間延びした退屈のなかに埋没する。
・心地よい酩酊状態はすでに去ったのに、足元のおぼつかなさや深刻な頭痛はいつまでも残り続ける。
・表向きはうまくいっている現実が、憂鬱と疲労のなかでたえず破局のヴィジョンへと横滑りする。
このような一九世紀特有の極端なアゴーギクを最も鮮烈に表現したのは、ヨーロッパ以上にロシアの文学だと思われる。この問題に進む前に、まずは一九世紀ヨーロッパの思想家が、アメリカやロシアのような≪新世界≫をどう捉えたのかを手短に確認しておこう。
6、ヘーゲル、トクヴィル、マルクス
一七七〇年生まれの哲学者ヘーゲルは、世界史をアジアからヨーロッパへと進歩するプロセスとして捉えた。ただ、その場合アメリカはどうなるのか。一口に言えば、ヘーゲルの狙いは、世界史と≪新世界≫のデカップリング(分離)にあった。
ヘーゲルの独断的な見解によれば、アメリカ大陸は社会を結集させる力を欠いている。そこでは動物も人間も弱々しく、衰亡の瀬戸際にある。「新世界は旧世界よりずっと脆弱であることが示されており、また鉄と馬という二つの手段が不足している。アメリカは新しく、脆弱で力を欠いた世界である。ライオン、トラ、ワニはアフリカのものよりも弱く、そのことは人間に関しても同様である」「この国〔アメリカ〕は生成途上の未来の国であり、それゆえこの国はわれわれにはまだ関わりのないものである」[20]。ただ、ヘーゲルの口調が自信たっぷりであるように見えて、最終的な判断を保留するような含みをもつことも見逃せない。彼はこの脆弱な≪新世界≫が、いつか世界史に関係してくる未来を否定しきれていないのだから。
一八〇五年生まれのフランスの政治家にして思想家のトクヴィル――二月革命の折に外務大臣を務めた経験を、後に『フランス二月革命の日々』で回想している――になると、≪新世界≫の勃興は世界史の転換点として捉えられた。彼の『アメリカのデモクラシー』第一巻(一八三五年)の末尾には、アメリカおよびロシアという新興国が「いつの日か世界の半分の運命を手中に収めることになる」という、きわめて正確な予想が記された。後年カール・シュミットは、頑固なヨーロッパ中心主義者ヘーゲルと違って、若きトクヴィルが「ヨーロッパ精神の刻印を受けつつなおヨーロッパ的でないこの新興二大国」を明確に名指ししたことを「驚きの極みである」と評している。シュミットがトクヴィルを「一九世紀最大の歴史家」と呼ぶのは、いわばヨーロッパの私生児であるロシアとアメリカにこそ人類の未来を認めた、その並外れてシャープな時代認識のゆえであった[21]。
しかも、慧眼なトクヴィルは、この両国の尋常ではない発展速度に注目していた。「[ロシアとアメリカは]どちらも人の知らぬ間に大きくなった。人々の目が注がれているうちに、突如として第一級の国家の列に加わり、世界はほぼ同じ時期に両者の誕生と大きさを認識した」[22]。私は先ほどから、フランスの二月革命や『レ・ミゼラブル』を例にして、事態の「不意打ち」や「急転」が一九世紀の特徴だと述べてきた。二日酔いでふらつく一九世紀的人間は、社会の安定構造のなかでまどろみながら、ときにそれを出し抜く急転に巻き込まれる。変化を加速させ、ヨーロッパ人のしらふの意識を追い抜いてしまったロシアとアメリカは、まさに異常なアゴーギクを国家形成のプロセスにおいて実現した。トクヴィルは一種の速度論(kinetics)の立場から、この両国の地滑り的な変化の速度そのものに注目したのだ。
さらに、ヘーゲルともトクヴィルとも異なるやり方で≪新世界≫の世界史的位置を考えたのが、一八一八年生まれのマルクスである。一八五二年に『ブリュメール一八日』を刊行したマルクスは、それに続いてロシアの分析に取り組んだ。クリミア戦争(一八五三~六年)の時期に構想された彼のロシア論は、ヨーロッパとは異なる政治経済のシステムを「タタールのくびき」(モンゴル帝国による支配)以降のロシアの専制政治に認め、その形成プロセスを批判的に検討したものである。
後にマルクスは一八六七年刊行の『資本論』で、亡命先の経済先進国イギリスを拠点として、資本主義を分析した。そこでは、資本主義のグローバルな拡大が前提とされている。ただ、一八五〇年代のマルクスによれば、ロシアの政治経済システムはむしろ資本化の作用をせきとめる専制主義を内包していた。この悪しき障害物がある限り、たんに資本主義の揚棄をめざすだけでは、人類の真の解放には到らない。マルクスはこの「東洋的専制」のシステムが、一八世紀初頭のピョートル大帝によって強化されたと見なした。ピョートルは西欧文明を効果的に利用しながら、国境に近いバルト海沿いに「中心から外れた中心」しての新都ペテルブルクを急ピッチで建設した。マルクスはこの驚くべき「速成的創造」に、ロシアが海の帝国に変わった瞬間を認めたのである[23]。
このマルクスのロシア論が、クリミア戦争の渦中から出てきたことは見逃せない。一九世紀ヨーロッパは相対的な安定期であったが、クリミア戦争は例外的に、膨大な死者を出した史上初の「全面戦争」であった。ロシア帝国とオスマン帝国の軍事衝突で始まったこの戦争は、やがてカフカス(コーカサス)から黒海沿岸にまで戦域を広げ、ヨーロッパ諸国の参戦も招いた。そこでは、新型兵器や電報のような通信テクノロジー、最新の軍事医学までもが動員され、まさに総力戦の様相を呈した[24](クリミア戦争に従軍し、軍の衛生環境と看護婦の地位を改善したイギリスのフローレンス・ナイチンゲールはその象徴である)。このヨーロッパとアジアのコンタクト・ゾーンにおける熾烈な世界戦争を背景としながら、マルクスはロシア特有の政治経済システムを考察した。
ヘーゲルにとって、いわば世界史の時計は一つであった。その途上でいかなる困難があろうとも、ヨーロッパの理念が次第に自己完成に向かうという原則は疑われていなかった。しかし、一八五〇年代のマルクスはむしろ人類が複数の時計をもつこと(ピョートルのロシア)、さらに時計が逆戻りし得ること(ナポレオン三世のフランス)を認めていた。この認識は二一世紀のわれわれにとっても示唆に富む。現に、いったん全面的に勝利したはずのポスト冷戦期の自由主義的なグローバリズムが、かえってその反動としてのプーチン(いわばピョートルの劣化コピー)や習近平(いわば毛沢東の劣化コピー)を生み出している現状は、マルクスの先見性を示すものだろう。
7、アンチ・ファウスト――プーシキン
このように、ヨーロッパ中心主義者のヘーゲルは世界史と≪新世界≫のデカップリングを試み、トクヴィルはむしろ≪新世界≫にこそ人類の未来を認め、マルクスはロシアの政治経済システムのもつ特殊性を強調した。この三者三様の言説から分かるように、ヨーロッパの第一級の知識人にとっても、ロシアやアメリカは知的に解決しがたい謎であった。
ここで興味深いのは、当のロシア人自身が自らを奥深い「謎」として了解したことである。ロシア近代文学の祖となった一七九九年生まれの作家アレクサンドル・プーシキンは、一八二二年に「ロシアはいまだ未完成である」と端的に述べた[25]。これはロシアが今後何にでも変わり得ること、そこには無限の可塑性があることを意味する。ロシアの知識人は総じて、自らが創出したロシアという謎に酩酊した。過去と未来にアクセスしながら、ロシアをたえず発見・発明し続けようとする未完の思想運動の中心にいたのが、まさにプーシキンのような詩人であった。
ロシア史家のオーランドー・ファイジズが強調するように、ロシアへの回帰を促したのは、一八一二年のナポレオン侵攻である。もともと、ロシアの上流貴族はフランスにすっかり夢中であり、家庭での教育もフランス語でなされていた。ナポレオン戦争を描いたトルストイの『戦争と平和』が、フランス語の会話で始まるのは、それを諷刺したものである。しかし、ロシアがナポレオンを撃退した後、農民とともに戦った兵士たちは、むしろロシア人のネーションとしての一体性を強く自覚するようになり、それが一八二五年のデカブリスト(農奴解放を訴える自由主義的な将校)の蜂起へとつながってゆく[26]。この国民統合をめざす新しいナショナリズムが、プーシキン以降のロシア近代文学の枢軸になったと言えるだろう。
もとより、ロシアが未完であることは、バラ色の未来を約束するものではない。現に、プーシキンはロシアを晴れやかな進歩にではなく、むしろ底なしの混沌に接続した。その文学上の拠点となったのが、ピョートルの築いた新都ペテルブルクであった。バルト海沿岸の湿地に工学的に築かれたペテルブルクは、その狂気じみた都市計画の代償として、たびたびネヴァ川の凶暴な洪水に襲われてきた。プーシキンの『青銅の騎士』は、若く貧しい下級官吏エヴゲーニーの視点から、この自然からの復讐を描いた長編叙事詩である。
ピョートルの騎馬像が傲然とそびえたつペテルブルクに、あるとき獣じみた洪水が襲来する――この粗暴な侵略者の創造した黙示録的光景を前にして、エヴゲーニーをはじめ民衆はただ茫然とするしかない。見慣れた街角は戦場のような廃墟に変わり、都市の繁栄はリセットされる。しかし、洪水が収まった後、ペテルブルクの生活は再び元通りになり、お互いに対して冷たく無関心な態度がよみがえる。エヴゲーニーにとっては、洪水という非日常よりも、洪水の後の退屈な日常こそが耐えがたい。世間からすっかり疎遠になった彼は、やがて荒々しいピョートルの騎馬像に取り憑かれ、狂気のなかで孤独な死を迎える。
ピョートルの悪魔じみたエネルギーの所産であるペテルブルクでは、破局と退屈が背中あわせになっており、人間的な生には何ら意味が与えられない。ボードレールはパリの商品世界を破局の集積として捉えたが、プーシキンは悪魔の創造したペテルブルクが、いわば誕生時にすでに破滅しており、その住民たちはたかだか人間の影絵でしかないことを示していた。ネヴァ川の荒々しい暴力は、このあらかじめ終わった都市を、何一つ変えなかったのである。
してみると、ロシア文学者のミハイル・エプスタインが『青銅の騎士』を「アンチ・ファウスト」の文学として位置づけたのも、不思議ではない。「プーシキンの作品は『ファウスト』が事実上終結したところに始まる」[27]。究極の人工都市ペテルブルクは、まさに自然を克服しようとするファウスト的な労働の一大成果である。しかし、それは人間の完成という達成感どころか、敗北感ばかりを募らせる。エヴゲーニーはペテルブルクの洪水を経て、精神的な二日酔いにいっそう深く沈み込んでゆく。ショッキングな洪水=革命の酔いは、退屈な日常がよみがえった後も、彼にだけはいつまでも残り続けた。ペテルブルクの化身であるピョートルは、この覚醒と酩酊の狭間にいるエヴゲーニーを罰するように、みじめな死に到らしめる。
かつて井筒俊彦は、意識の殻を吹き飛ばす「ディオニュソス的暴風圏」――ペストや洪水のような負の祝祭も含めて――を、プーシキン文学の核心と見なした[28]。それに付け加えれば、『青銅の騎士』の仕掛けは黒い祝祭を歌い上げるディオニュソス的な声が、かえってアンチ・ロマン的な日常に吸収されたことにある。この二重写しには、ロシア文学を深く規定する「パラドックス」(エプスタイン)を認めることができるだろう。
8、グローバルあるいはナショナル――ゴンチャロフ
ところで「ロシアは未完成である」というプーシキンの認識は、ロシアが自己拡張してゆく状況とも深く関わっていた。プーシキン自身、南方のカフカス(コーカサス)に居住した経験がある。多民族の群居するカフカスは長くオスマン・トルコの支配下にあったが、一九世紀にはロシアの植民地となり、プーシキンはそこで半自伝的な『コーカサスの捕虜』を書いた。この作品そのものはプーシキンの代表作とは言いがたいが、その後のカフカス表象の雛形となった。プーシキンはペテルブルクの詩人であっただけではなく「カフカスの発明者」でもあった[29]。
ロシアはヨーロッパに知的に植民地化される一方、その周辺地域を軍事的に植民地化した帝国でもあった。プーシキン以来の近代文学には、軍事的な支配者にして文化的な被支配者でもあるというロシア帝国の二重性が刻印されている。この点で、最も興味深い作家の一人は、前章でも言及した一八一二年生まれのイワン・ゴンチャロフである。というのも、ゴンチャロフという作家には、まさにロシアの内に向かうヴェクトルとロシアの外に向かうヴェクトルが共存していたからである。
一八四九年から十年がかりで刊行されたゴンチャロフの主著『オブローモフ』は、もっぱらロシアの知識人の苦境を描いた文学として読み解かれた。本来は「火山にも似た熱しやすい頭脳」をもつ主人公のイリヤー・イリッチ・オブローモフは、農奴にかしずかれながら「孤独と隠棲」に沈み込んでいる。彼の日中の脳裏には、自分が世の悪をなくす功業を立て、ナポレオンも凌ぐ百戦百勝の指揮官として、諸国民を従えるイメージが浮かんでいる。しかし、彼の興奮は日が沈むとともに静まり返る。唯一の理解者であるドイツ人のシュトルツがしきりに海外で活動するのに対して、オブローモフは退嬰的な生活に甘んじている。
イリヤー・イリッチのこうした内面生活を知るものは、誰ひとりとしていなかった。誰も彼もが、オブローモフは別にどうということもなく、ただごろごろ寝て、うまいものを食っているばかりで、それ以外なに一つあの男から期待するわけにゆかない、あの男の頭のなかには纏まった考えなんかほとんど宿ることはないのだ、とそう思っていた。[30]
オブローモフの知的情熱が行き場をもたず、むなしくくすぶり続けることに対応して、小説前半のテンポはずいぶんのろく感じられる。この文学上のアゴーギクは、大量の不発弾を抱え込んだオブローモフの二日酔い的な重苦しさを表現している。フランスの『レ・ミゼラブル』が革命と墓場を重ねあわせた賑やかな小説であったのに対して、同じく「惨めな人間」を主役としたロシアの『オブローモフ』は、終わりのない退屈と停滞に支配されていた。
ただ、オブローモフの苦境は、実は必ずしもロシア人とのみ関連するものではない。そもそも、作者のゴンチャロフは当時指折りの外国通であった。『オブローモフ』の執筆と並行して、ゴンチャロフは一八五〇年代にプチャーチン提督率いるパルラダ号に乗り込んで、アフリカから日本、シベリアまで訪問している(前章参照)。当時『オブローモフ』以上のベストセラーとなった彼の旅行記『フリゲート艦パルラダ号』(一九五八年)には、グローバルな帝国になろうとするロシアの欲望が色濃く投影されていた。途中クリミア戦争の勃発によって、パルラダ号が英仏の敵になるというアクシデントを経ながらも、そこには主に分類学的な「人種」の概念を尺度としながら、グローバル世界の人間の多様性を知的に把握しようとする態度が貫かれている[31]。
ゴンチャロフは諸外国のなかで日本を比較的高く評価していたが、それでもこの「鍵をなくしたまま閉ざされた玉手箱」のような国については辛口のコメントも目立つ。特に、彼が苛立ったのは、日本人との交渉がのろのろとしか進まないことであった。「私にとって、もはやこの極東はさしあたり極端な退屈以外何の得るところもない!」とまで酷評するゴンチャロフは、眠そうにあくびをしては、外交にも無関心を決め込む一部の日本人についてこう述べる。
活発なまなざし、勇敢な表情、生き生きとした好奇心、すばしこさ――こうしたヨーロッパ人が自覚して身につけているものすべてのものが、何一つないのである。[32]
これはオブローモフの無気力そっくりである。ゴンチャロフにとって、豊富な知識をもちながら精神的に麻痺してしまったオブローモフ的人間、いわゆる≪余計者≫は、ロシア人に限らず日本人を含めた人類の一つの可能的未来を暗示する存在であった。ゴンチャロフの文学がグローバルなものとナショナルなもの(ロシア的なもの)の交差点で、人間の決定的な退化を捉えていたことには、ポストヒューマンの想像力の先駆という一面がある。
さらに面白いのは、ロシア作家(ツルゲーネフやゴーゴリ)の翻訳者であった日本人作家の二葉亭四迷が、後に「平凡」や「退屈」というゴンチャロフふうのテーマを日本の知識人に見出したことである。四迷は日本近代文学の創始者となったが、近代化を一種の袋小路としても捉えていた。そのことが、彼の主人公をロシア的な≪余計者≫に近づけたのである。ゴンチャロフが日本にオブローモフ的人間を認めたそのおよそ半世紀後に、今度は当の日本人作家がオブローモフ的人間を造形する――この興味深いリレーは、ヨーロッパの外部において、ポストヒューマンな世界文学の生態系が生まれつつあったことを示すものだろう。
9、ウクライナあるいはロシア――ゴーゴリ
ゴンチャロフが世界旅行と並行してロシアの袋小路と人間の退化を描いたとすれば、一八〇九年生まれのニコライ・ゴーゴリはウクライナの作家からロシアの作家へと変身した。後に作家のウラジーミル・ナボコフが「彼[ゴーゴリ]が場所から場所へとあっという間に移り行くさまには、いつでも蝙蝠か影を思わせるなにものかがあった」と評したのは興味深い[33]。この稲妻のようなすばやい転換こそが、生粋の一九世紀作家ゴーゴリを特徴づけている。
以下では、エディタ・ボジャノウスカの近年の見晴らしのよいゴーゴリ論に沿って、議論を進めていこう。一八三一年の『ディカーニカ近郷夜話』で人気作家となったゴーゴリは、当初は批評家から、ウクライナのナショナリズムを背負ったウクライナ的作家と見なされていた。それが次第に、そのウクライナ性が強調されなくなり、むしろスラヴ的背景をもつロシアの主要な作家として読み替えられていったのである。ただ、ここで重要なのは、ゴーゴリ自身にこの二つの立場のいずれにも還元されない量子的な性格があったことである。
東ウクライナのポルタヴァ州に生まれたゴーゴリは、もともとロシア語とウクライナ語のバイリンガルであり、ポーランド語を読む能力もあった。一八二八年にはペテルブルクに出るが、その魂を欠いた人工都市はゴーゴリを深く失望させた。そのことがゴーゴリを故郷ウクライナの再発見・再創造に向かわせたのである。彼はロシア人の読者に宛てて、土着のウクライナ性をロシア語の文学へと「翻訳」したが、その際にドイツの哲学者ヘルダー流のナショナリズム――文化・歴史・言語とリンクされた有機的共同体としてネーションを理解するもの――を生地として、そこに一種のエスノグラフィー(民俗誌)としての性格を与えた。
短編集の『ディカーニカ近郷夜話』やコサックを主人公とした戦争文学『タラス・ブーリバ』をはじめ、ゴーゴリの再創造したウクライナには、平和的・定住的な農民のイメージと好戦的・遊牧民的なコサック(草原の民)のイメージが共存している。この「戦争と平和」の振幅のなかで、ゴーゴリは文化や言語が緊密に一体化した有機的全体性としてのウクライナ・ネーションを象った(ゆえにそこではジプシーやユダヤ人は排除されている)。もとより、ボジャノウスカが指摘するように、コサックの栄光は当時すでに過去のものであり、ヘルダー的共同体としてのウクライナはロシア帝国の圧力のもとで危機に瀕していた。だからこそ、『ディカーニカ近郷夜話』はその回顧的な構えのなかで、ウクライナ固有の文化を保存したのである[34]。
しかし、ゴーゴリがペテルブルクを描くとき、このロマンティックな有機的全体性は解体される。ゴーゴリのウクライナものが「モル的」だとしたら、『外套』や『鼻』のようなペテルブルクものは「分子的」である。そこには、フローベールにも通じるモノたちの戯れがある。ナボコフが鋭く指摘したように「この不条理な世界にうごめいているのは人間ばかりではない。あまたの物体にも、人間に劣らぬ役割がふられている」[35]。
例えば、下級官吏コヴァリョフの鼻がさまよい歩く『鼻』では、ひとびとのかわす無責任なゴシップに寄生しながら、身体の一器官が人間になりかわって活動する。鼻は語りの海のなかでときどき顔を出しながら、持ち主のコヴァリョフを翻弄し続ける。ゴーゴリ版のペテルブルクの人間たちは、旺盛な語りの力によって、いわば人間未満の奇妙な「モノ」たちを作り出しては、それを都市の亡霊としてさまよわせるのだ。面白いことに、ナボコフはゴーゴリの登場人物の語る逸話(アネクドート)に一瞬現れるだけの人間たちに注目し、彼らを「ホムンクルス」と呼んでいる[36]。都市の通りすがりの語り手たちが、そのゴシップのなかにホムンクルス的な小人を創造する――コヴァリョフの「鼻」はまさにそのような語りを母胎とする、滑稽な生命体なのである。
そもそも、コヴァリョフ自身にロシア帝国の生み出したホムンクルスとしての一面がある。彼は植民地のカフカスで、かろうじて八等官の職を得た役人であった。ロシアの植民地主義的な自己拡張の生み出した矮小な人物が、工学的に建築された都市ペテルブルクにおいて、身体を分子化・断片化される――そこに『鼻』の特筆すべき批評性がある。『タラス・ブーリバ』のウクライナ・コサックの身体はポーランドとの戦争によって殲滅されたが、『鼻』ではむしろペテルブルクの内在的な作用として、モル的な人間は分子的なホムンクルスへと変容させられる。
さらに、ゴーゴリの傑作『外套』になると、このポストヒューマンな想像力が人間的なものの絶滅に向かって進む。市役所で筆耕を務める主人公のアカーキー・アカーキエヴィッチは、新しい外套を手に入れて「陽気な気分」で歩を進めるうちに、やがて人影のすっかり絶えた不気味な広場に行きつく。
街並の方は、木造の家と塀になり、人っ子一人見かけない。通りに積もる雪だけが光り、鎧戸を閉めて眠りに落ちた低いあばら家がもの悲しげに黒ずんでいた。彼は通りの切れ目に来たが、そこはかろうじて反対側の家々が見えるはてなき広場で、まるで恐ろしい荒野であった。[37]
この人間の消え失せた広場で、アカーキー・アカーキエヴィッチは大切な外套を奪われために憤死し、都市を夜な夜なさまよう亡霊と化す。ここには、明るく酔った気分から暗い墓場へのユゴー的な急転直下がある。躁鬱的な気分に支配されたゴーゴリのペテルブルクものの主役たちは、二日酔いの揺らぎのなかでホムンクルスへ、さらには都市=荒野の亡霊へと姿を変えてゆく。
10、≪歴史の終わり≫の後で――ドストエフスキー
一般にロシア文学と言えば、一八一八年生まれのツルゲーネフ、一八二一年生まれのドストエフスキー、一八二八年生まれのトルストイらに代表されるが、その想像力の土台そのものはすでに先行世代によって形成されていた。黒人奴隷の血を引くプーシキンも含めて、ロシア文学の建築家と言うべきゴンチャロフやゴーゴリらは、純血のロシア性からのズレを含む。帝国の周縁――ウクライナやカフカス、シベリアも含めて――を経由した作家こそが、文学のナショナリズムを推進したことは見逃されるべきではない。
それに加えて、ロシア文学の重要性は、ヨーロッパ的な「人間」のモデルからの逸脱がたえず生じていたことにある。このポストヒューマンな想像力の頂点に位置するのは、やはりドストエフスキーである。
ここではまず、ドストエフスキーのヨーロッパ観に注目したい。私は先ほどトクヴィルやマルクスのロシア論を紹介したが、ドストエフスキーは逆にロシア人の立場から第二帝政期のフランス社会を鋭く観察していた。シベリアでの服役から帰還し、一八五九年に出た『オブローモフ』を絶賛した後、ドストエフスキーは一八六二年夏に最初のヨーロッパ旅行に出て、翌年その旅行記を『冬に記す夏の印象』と題して発表した。そこには、ヨーロッパ文明に対する諧謔と幻滅の入り混じったシニカルな見解が充満している。
バルザックの『ウジェニー・グランデ』の翻訳者でもあったドストエフスキーは、一八四〇年代のロシア文壇がフランスに拝跪していたことを回想する。当時の教養のあるロシア人で、フランスひいてはヨーロッパの圧力に屈しなかった者はいなかった。ヨーロッパは「あたかも押しかけ客のごとく」ロシアに入り込み、ロシアの近代化を図るピョートルの大望と融合して「地球上のあらゆる都市のなかで最も幻想的な歴史を持った、最も幻想的な都市」ペテルブルクを生み出したのである。
ドストエフスキーの考えでは、このロシアのヨーロッパ化はついに最終的な段階に入りつつある。しかし、それはロシア人がヨーロッパ人と同じく、欺瞞的なブルジョワになることと等しい。ロシア人は「フランスのブルジョアになりつつあるのだ。もうしばらく経てば、南部諸州のアメリカ人のように、聖書の言葉を引用して、黒人売買の必要を弁護するようになるだろう」。ドストエフスキーはこの辛辣な認識を、彼自身の見たヨーロッパの大都市――万国博覧会や水晶宮でひとびとを驚かせたロンドン、自己満足した市民たちで満ち溢れたパリ――の空疎な繁栄と結びつけた。
ちょうどボードレールがパリを「憂鬱」の色で染めあげていたとき、同い年のドストエフスキーはパリやロンドンを空疎な「書割」として認識していた。この書割のなかで最高のブルジョワ支配――「ブルジョワは王様だ、ブルジョワはすべてだ!」――が実現されたにもかかわらず、なぜかパリでは皇帝ナポレオン三世の影で「何もかもが縮こまっている」。第二帝政期のフランス社会の空洞化を描いたフローベールと同じく、ドストエフスキーにとっても、ブルジョワの勝利と繁栄はそのまま黙示録的な「終末」の到来を意味していた。
「これこそまさしく達成された理想なのではあるまいか?」と諸君は考える。「これこそ終末ではあるまいか?これこそまさしく『一つの群』ではあるまいか?これこそ全き真実であると考え、もはや何も言うことができなくなってしまうようなことになるのではあるまいか?」これらすべてがあまりにも堂々と、あまりにも傲然と勝ち誇っているので、諸君は息苦しささえ感じはじめる。[38]
ロシア文学者のマイケル・ホルクイストが指摘するように、ドストエフスキーはここで、第二帝政期フランスの中産階級を≪歴史の終わり≫に生きる人間(ニーチェの言う「末人」)として描いたが、それはそのまま一八六四年の『地下室の手記』における近代人の不安というテーマの予告編になっている。ドストエフスキーの描く「地下室人」は、「1足す1は2」という類の法則に支配された社会――彼はその象徴として、先端テクノロジーの結晶であるロンドンの水晶宮に言及する――にあえて逆らって、偶然性を擁護する[39]。それ以降の『罪と罰』(一八六六年)から『カラマーゾフの兄弟』(一八八〇年)に到るまでの驚異的な大作群は、ヨーロッパのブルジョワの入り込んだ袋小路、つまり≪歴史の終わり≫からの脱出という一面をもっていた。
11、量子状態としてのポリフォニー
大まかに言えば、ロシアの革新的な知識人として、一八四〇年代世代(フォーティーズ)と一八六〇年代世代(シックスティーズ)を想定できるだろう。ヨーロッパの市民革命の影響を受けたフォーティーズは、農奴制を残した後進国ロシアに不満を抱き、急進的な自由主義者・進歩主義者として活動したが、一八四八年以降に厳しく弾圧された(社会主義サークルに加わっていたドストエフスキーも逮捕され、処刑寸前にシベリア流刑を言い渡された)。ゴンチャロフの描いたオブローモフには、ロシアの知識人の入り込んだトンネルが表現されている。
しかし、二月革命後のヨーロッパとは違って、ロシアの革命の機運がそれで途絶えたわけではなかった。政治哲学者のアイザイア・バーリンが指摘したように、ロシアの革新派は一八四八年の後に「進歩という理念そのものへの不信」を抱くようになった。つまり、ヨーロッパからの輸入思想だけでは対処できない「ロシアだけが提示している特殊な諸問題」の解決が、最重要の課題として浮上したのである。クリミア戦争の敗戦後に、農奴制の解体をめざしたアレクサンドル二世の改革のもとで、シックスティーズたちはロシアの特殊問題は何かというテーマを深化させた。ツルゲーネフの『父と子』(一八六二年)には、そのテーマが刻印されている。一八四〇年代以降、ロシアの進歩的運動はますます「内向的」かつ「非妥協的」なものになったが、バーリンによれば、この非妥協性こそがレーニンのロシア革命の呼び水になった[40]。
一八四〇年代に新進気鋭の作家として華々しくデビューし、その後シベリアに送られ、一八六〇年代以降に巨大な長編小説を書き続けたドストエフスキーの人生は、ロシアの社会と知識人のたどったジグザグの――いわば『罪と罰』に出てくる酔漢マルメラードフ的な――足取りと並行している。ヨーロッパのブルジョワ社会を≪歴史の終わり≫と見なした彼にとって、一八四〇年代的な「進歩という理念」は懐疑の対象となった。
例えば、一八六一年の『虐げられた人々』――ペテルブルクで長編小説を書こうとするものの、うまく進まず憂鬱に囚われた作家「私」の視点から語られる――には、一八四〇年代ロシアの進歩主義サークルへのアイロニーが書き込まれていた。その中心人物である若いアリョーシャは背が高く「優雅な容貌」をもち、誰にでも子どものように甘える「永久の未成年」として描かれる。彼の完璧な均整を保った美しいスタイルは、しかし一切の社会的現実と関わりをもたない[41]。アリョーシャの語りは、きわめて明朗で正直であるがゆえに、無垢な思いを熱っぽく語っては自己弁明へとたえず戻ってゆく。あまりにも素直で軽薄なアリョーシャは、まさにテンポの揺らぎ続ける二日酔いの状態にある。
この語りのアゴーギクには、ヨーロッパ化したロシア人の陥った袋小路が見事に表現されている。優雅さだけが取り柄のアリョーシャには、ドストエフスキーなりの進歩主義へのシニカルな見方が凝縮されているが、それはアリョーシャを小馬鹿にすることとは異なる。なぜなら、この永久の未成年者の熱っぽい語りこそが、ドストエフスキーの長編小説において不可欠な推進力になっているからである。アリョーシャの浮ついた語りの断片は、他の登場人物にも(さらには読者にも)分子状にからみあって、不思議な化合物を生み出すだろう。ドストエフスキーはこのような語りの化学変化によって、フォーティーズの理想を生き残らせたのである。
ドストエフスキーの語りが一種の分裂を孕んでいることは、文芸批評の大きなテーマとなってきた。ミハイル・バフチンがドストエフスキーの小説を「ポリフォニー」のメタファーで呼んだことは有名である。彼の小説においては「それぞれに独立して互いに融け合うことのないあまたの声と意識」が、事件の竜巻的展開のなかであらわにされる。この複数の声=意識を、作者ドストエフスキーの単一の声=意識に解消することはできない[42]。バフチンによれば、ドストエフスキーは一人の声がすでにして複数の声であるという独特の文体を編み出した。私なりに言い換えれば、それはいわば0と1が重ねあわせになった量子状態の文体である。
繰り返せば、このような「重ねあわせ」はドストエフスキーに限ったものではない。ロマンティックな酩酊を引きずったまま、麻痺的な退屈に呑まれた一九世紀の二日酔いの風土は、それ自体がポリフォニックであった。ただ、並外れて宗教性の強かったロシアでは、この酩酊がいっそう強められたと言えるだろう。「ロシア帝国は、国境問題であれ、外交関係であれ、ほぼすべての問題を宗教のフィルターを通じて解釈する宗教国家だった」(オーランドー・ファイジズ)[43]。この「フィルター」が、ドストエフスキーのポリフォニックな語りをいっそう極端にしたのは確かである。
宗教的情熱を抱え込んだドストエフスキーの小説では、一九世紀特有のアゴーギクがその極致に達している。そこにはユゴー的な反転もあれば、ゴンチャロフ的な麻痺もある――つまり、事態が何の前触れもなく急展開するかと思えば、現実を置き去りにした語りが延々と続くこともある。≪歴史の終わり≫に直面したドストエフスキーは、この揺らぎ続ける極端な語りから、一筋の救済の可能性を探り出そうとした。『虐げられた人々』のアリョーシャはその一つの原型となったと言えるだろう。
12、ソヴィエトあるいはロシア
私はここで、一八四〇年代のドストエフスキーの初期作品(『貧しき人々』と『白夜』)に遡ってみたい誘惑に駆られる。しかし、それは後の章に回し、本章の締めくくりとして、一点だけ別のテーマを付け加えておきたい。それは、ドストエフスキー的な量子状態が二〇世紀になって政治体制のレベル、つまりソヴィエトあるいはロシアという二重体制に転移したことである。
カレール゠ダンコースが述べるように、二〇世紀のソヴィエト連邦は、いかなる具体的な地名にもよらずに、政治計画をその名に冠した異例の国家であった(ソヴィエトとは「評議会」の意)。ホモ・ソヴィエティクス(ソヴィエト的人間)という新しいタイプの人間を創設し、その導きによって全世界を永続的に変革すること――この前代未聞のプロジェクトがソ連の核心にある[44]。その推進のために、ロシアの伝統は社会主義にいったんその座を譲ったが、ロシア的人間がソヴィエト的人間にすっかり上書きされたわけでもない。ここにもやはり「重ねあわせ」の問題がある。
現に、ソヴィエトという人工的な「重ねあわせ」のシステムが崩壊したとき、ただちに厄介な政治問題が現れた。この問題が集約されているのがクリミア半島である。クリミア戦争の敗戦国であったにもかかわらず、ロシアでは長らくその敗北の悲劇が国民意識の核になった。ロシアが敗北を喫したセヴァストポリは「耐え難い恥辱」の象徴である一方、西欧諸国とトルコを相手に兵士たちが勇敢に闘った、気高い祖国防衛の場でもあった(逆に戦勝国トルコでは、この戦争の記憶は意図的に抹殺された)。クリミア戦争に従軍したトルストイの『セヴァストポリ物語』は、この英雄的な敗北をロシア・ナショナリズムの神話に変えるのに大いに役立った[45]。
しかし、その後、ソ連のフルシチョフ書記長時代に、クリミア半島は同連邦内のウクライナに移管された。そのため、ロシア人のナショナル・アイデンティティの「聖地」であったセヴァストポリは、ソ連崩壊後にはウクライナ領に編入された。ここにはまさにゴーゴリ的状況がある――ソヴィエトという酔いから覚め、ロシア人が固有のロシアを再発見しようとしたとき、いわば大切な「外套」のようなクリミア半島はすでにその手元には残っていなかったのだから。作家のアレクサンドル・ソルジェニーツィンが、ウクライナがクリミア半島を受け取ったことを「国家による盗み」だとまで批判したことをはじめ[46]、この一連の出来事はロシアの民族主義者に強烈なショックを与えた。彼らはクリミア半島のロシア復帰キャンペーンを展開し、それが二〇一四年のプーチンによるクリミア併合へとつながってゆく。
二〇二二年に始まるウクライナ戦争の序曲となったのは、まさにこのクリミア半島をめぐる感情の政治であった。ロシアにとって、ウクライナは自己の分身と言うべき他者であり、ゆえにそれに対する感情的な屈折が消えることもない。古都キエフあるいはキーウがロシア諸都市の「母」だとしたら、セヴァストポリはヨーロッパに立ち向かう気高いロシア・ナショナリズムの「父」であり、それらのウクライナ化はロシアの精神的危機に直結する。この込み入った状況を生み出した要因は、ソヴィエトあるいはロシア、帝国あるいは国民国家という二重体制にあるだろう。
してみれば、ロシアとウクライナの戦争はふつうの対外戦争とは違っている。ソ連時代を基準とすれば、それはむしろ「内戦」に近く、それゆえに危険である。カール・シュミットが的確に述べたように「内戦には独特の陰惨さがある。それは骨肉間の闘争である。〔…〕内戦は他のいかなる戦争より危険である。なぜなら各陣営が仮借なく自己の正義を前提し、同様に仮借なく相手の不正義を前提せざるをえないからである」[47]。内戦はお互いの敵意をとめどなく亢進させる。
ゆえに、バフチンの言うポリフォニーとは、文学と政治を横断する概念である。単一の声がすでにして複数の声であるという状況は、一九世紀のロシア文学において先取りされ、やがて政治的なアイデンティティにも根深い作用を及ぼした。一八五〇年代のクリミア戦争の余震は、一五〇年以上経っても収まる兆しを見せない。同じように、一九世紀の二日酔いという亡霊も、二一世紀になってもしつこく出没し続けているのである。
(続く)
[1]阪上孝『プルードンの社会革命論』(平凡社ライブラリー、二〇二三年)三三、一〇四、二〇八頁。その一方、サン゠シモンと決別したオーギュスト・コントは、反革命の立場から、実証主義的な社会学の創始者となった。
[2]クリスティアン・マルティン・シュミット『ブラームスとその時代』(江口直光訳、西村書店、二〇一七年)五六頁以下、一〇三頁以下。なお、ブラームスとは対照的に、ヴァーグナーは「財産は盗みである」と言ったプルードンの信徒であり、彼のオペラ『ニュルンベルグのマイスタージンガー』にはビスマルクのドイツとは異なり、芸術家たちの協同組合が(アイロニーも交えつつ)理想化されている。三光長治『新編 ワーグナー』(平凡社ライブラリー、二〇一三年)六一、八九頁。
[3]ジョン・ミアシャイマー『大国政治の悲劇』(奥山真司訳、五月書房新社、二〇一七年)一四頁。
[4]鹿島茂『怪帝ナポレオン三世』(講談社学術文庫、二〇一〇年)第四章参照。
[5]阪上孝「一八四八年をどうとらえるか」阪上編『1848 国家装置と民衆』(ミネルヴァ書房、一九八五年)参照。
[6]日本では蓮實重彦の一連の批評(特にフローベールの友人マクシム・デュ・カンを主役とする『凡庸な芸術家の肖像』)が、この問題を多角的に論じている。
[7]カール・マルクス『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』(植村邦彦訳、平凡社ライブラリー、二〇〇八年)二〇頁。
[8]同上、二二頁。
[9]ディルタイ『近代美学史』(澤柳大五郎訳、岩波文庫、一九六〇年)八頁以下。
[10]ヴィクトール・ユゴー『レ・ミゼラブル』(第五巻、西永良成訳、平凡社ライブラリー、二〇二〇年)一七七頁。
[11]ジャック・ランシエール『文学の政治』(森本淳生訳、水声社、二〇二三年)四〇頁。
[12]「セントラルパーク」『ベンヤミン・コレクション1』三六四、三八九頁。
[13]同上、三六九、三八二、三五九頁。
[14]ジャック・デュボア『現実を語る小説家たち』(鈴木智之訳、法政大学出版局、二〇〇五年)二六九頁以下。
[15]ランシエール前掲書、四七‐八頁。
[16]同上、六八頁。なお、世界の「数え方」に関してフローベールと好一対なのが、一八二八年生まれのジュール・ヴェルヌである。フローベールとは異なり、ヴェルヌはユゴー的な深層を再創造した。ただし、ヴェルヌの舞台はもはや都市の地下ではなく、むしろ崇高な自然環境――火山、地底、深海等――であり、そこは新奇な事物で満ちている。特に、『海底二万里』(一八七〇年)の貴族的なネモ船長は、清潔な潜水艦ノーチラス号のなかに世界の縮図と言うべきコレクションを築いているが、ここには世界の事物を科学の力で数えあげようとするポーズがある。この点で、『海底二万里』は科学的調査のパロディでもあるフローベールの『ブヴァールとペキュシェ』と比較されるべきだろう。
[17]『ボヴァリー夫人の手紙』(工藤庸子編訳、筑摩書房、一九八六年)一三〇頁。菅谷憲興「民主主義のなかの小説家」松澤和宏+小倉孝誠編『フローベール 文学と〈現代性〉の行方』(水声社、二〇二一年)一五八頁。
[18]『ボヴァリー夫人の手紙』一〇一頁。
[19]例えば、坂本龍一のキュレーションによるCD『耳の記憶』(commmons)所収のブックレット参照。
[20]G・W・F・ヘーゲル『世界史の哲学講義』(上巻、伊坂青司訳、講談社学術文庫、二〇一八年)一三七‐八、一四〇頁。ただ、ヘーゲルが植民地生まれの混血のクレオールにだけは、独立の気概を認めたことは注意されてよい。
[21]「獄中記」(長尾龍一訳)『カール・シュミット著作集』(第二巻、慈学社出版、二〇〇七年)一四三頁。
[22]トクヴィル『アメリカのデモクラシー』(第一巻下、松本礼二訳、岩波文庫、二〇〇五年)四一八頁。
[23]カール・マルクス『一八世紀の秘密外交史』一九五頁。
[24]オーランドー・ファイジズ『クリミア戦争』(上巻、染谷徹訳、白水社、二〇一五年)二一頁以下。
[25]エレーヌ・カレール゠ダンコース『未完のロシア』(谷口侑訳、藤原書店、二〇〇八年)二六七頁。
[26]オーランドー・ファイジズ『ナターシャの踊り』(上巻、鳥山祐介他訳、白水社、二〇二一年)九五頁以下。
[27]Mikhail Epstein, The Irony of the Ideal: Paradoxes of Russian Literature, Academic Studies Press, 2018, p.11. エプスタインが指摘するように、ゲーテのほうも一八二四年のペテルブルクの洪水のニュースを、『ファウスト』第二部に生かした可能性がある。
[28]井筒俊彦『ロシア的人間』(中公文庫、一九八八年)一〇〇頁。
[29]Susan Layton, Russian Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, Cambridge University Press, 1994, chap.2.さらに、乗松享平『リアリズムの条件』(水声社、二〇〇九年)はカフカスの植民地化とロシア近代文学の誕生を結びつけている。
[30]ゴンチャロフ『オブローモフ』(上巻、米川正夫訳、岩波文庫、一九七六年)一四〇頁。
[31]Edyta M. Bojanowska, A World of Empires: The Russian Voyage of the Frigate Pallada, Belknap Press, 2018, chap.5.
[32]イワン・A・ゴンチャローフ『ゴンチャローフ日本渡航記』(高野明+島田陽訳、講談社学術文庫、二〇〇八年)五九、九七、一〇八頁。
[33]ウラジーミル・ナボコフ『ニコライ・ゴーゴリ』(青山太郎訳、平凡社ライブラリー、一九九六年)四八頁。
[34]Edyta M. Bojanowska, Nikolai Gogol: Between Ukrainian and Russian Nationalism, Harvard University Press, 2007, chap.2.
[35]ナボコフ前掲書、八七頁。
[36]同、七五頁以下。ゴーゴリは尊敬するプーシキンらにアネクドートをねだって、それをもとに小説を構成した。その書き方の特異性については、ボリス・エイヘンバウム「ゴーゴリの『外套』はいかに作られたか」(小平武訳)『ロシア・フォルマリズム文学論集1』(せりか書房、一九八四年)参照。
[37]ゴーゴリ『外套 鼻』(吉川宏人訳、講談社文芸文庫、一九九九年)三八頁。
[38]以上、「冬に記す夏の印象」(小泉猛訳)『ドストエフスキー全集』(第六巻、新潮社、一九七八年)一三、二〇、二四、四二、四九頁より引用。
[39]Michael Holquist, Dostoevsky and the Novel, Princeton University Press, 1977, p.48, 54.
[40]バーリン『ロシア・インテリゲンツィヤの誕生』(桑野隆編、岩波文庫、二〇二二年)一八、一九、四六頁。
[41]ドストエフスキー『虐げられた人々』(小笠原豊樹訳、新潮文庫、一九七三年)六九頁。
[42]ミハイル・バフチン『ドストエフスキーの詩学』(望月哲男+鈴木淳一訳、ちくま学芸文庫、一九九五年)一五頁。
[43] ファイジズ『クリミア戦争』(上巻)四一頁。
[44]カレール゠ダンコース前掲書、一〇頁。
[45]ファイジズ『クリミア戦争』(下巻)二九八頁以下。なお、トルストイは『戦争と平和』の構想段階では、クリミア戦争直後のロシアを舞台に、デカブリストを主役にした小説を予定していた。それがやがてナポレオン戦争というテーマに移行したのである。トルストイにとって、この二つの戦争はロシア国民の自己犠牲的な愛国精神を顕現させた、国民統合のシンボルと言うべき出来事であった(同、三〇四頁)。
逆に、ペテルブルクという「書割」めいた幻影都市を背景にしたドストエフスキーは、国家間の戦争よりも、むしろ三面記事的な逸話をポリフォニー小説の地盤とした。ここには、この二人の巨匠の大きな違いがある。だとしても、一見して「モル的」なトルストイの国民文学の底に、その統一性をひび割れさせる「分子的」な戯れを見出すことも十分可能だろう。
[46]アレクサンドル・ソルジェニーツィン『廃墟のなかのロシア』(井桁貞義他訳、草思社、二〇〇〇年)一〇四頁。
[47]シュミット前掲書、一五九頁。シュミットはここで、ホッブズの『リヴァイアサン』がイングランド内戦への応答であることを念頭に置いている。
(続く)
この記事は、PLANETSのメルマガで2023年9月19日、9月26日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2023年11月9日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。