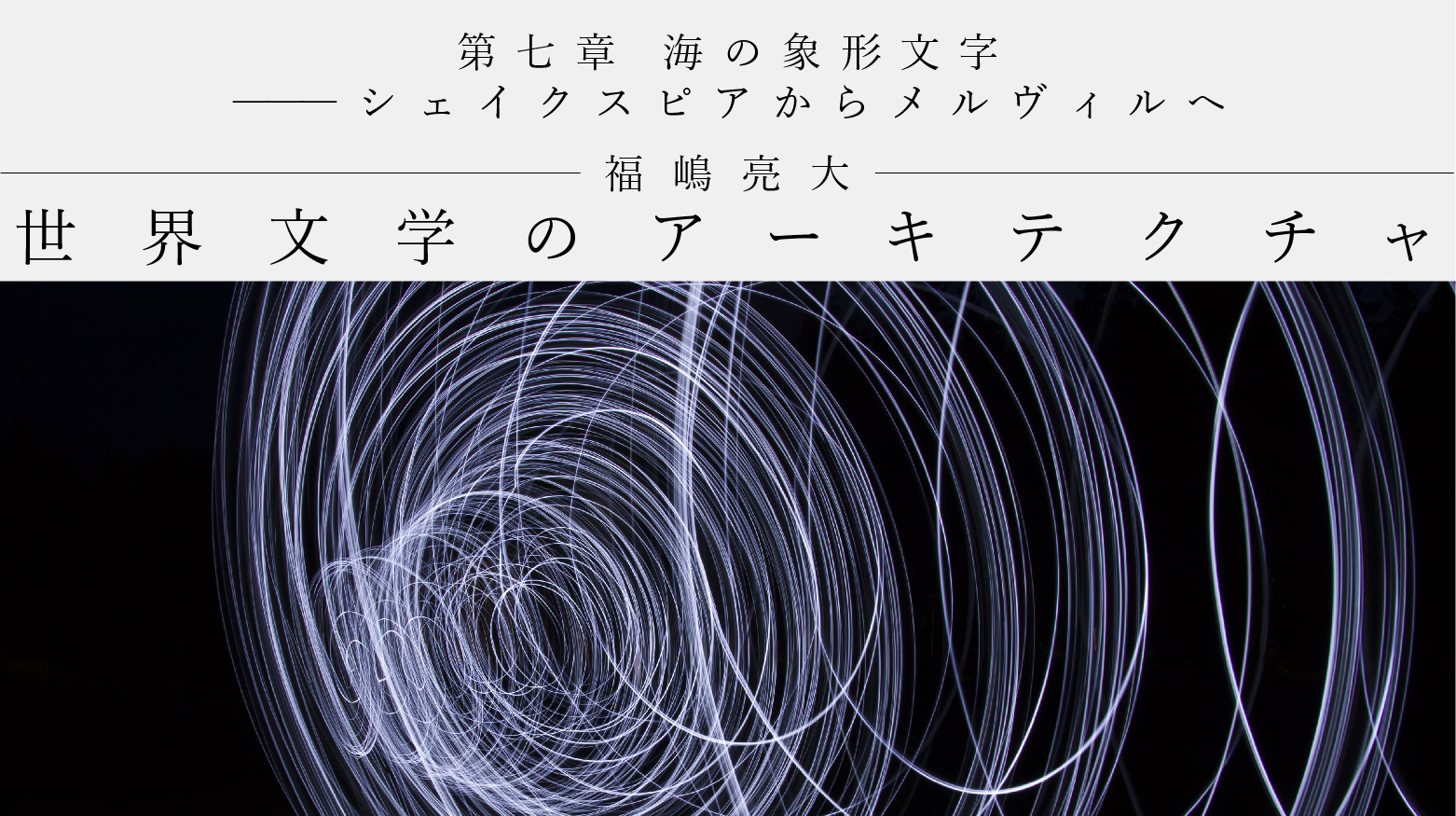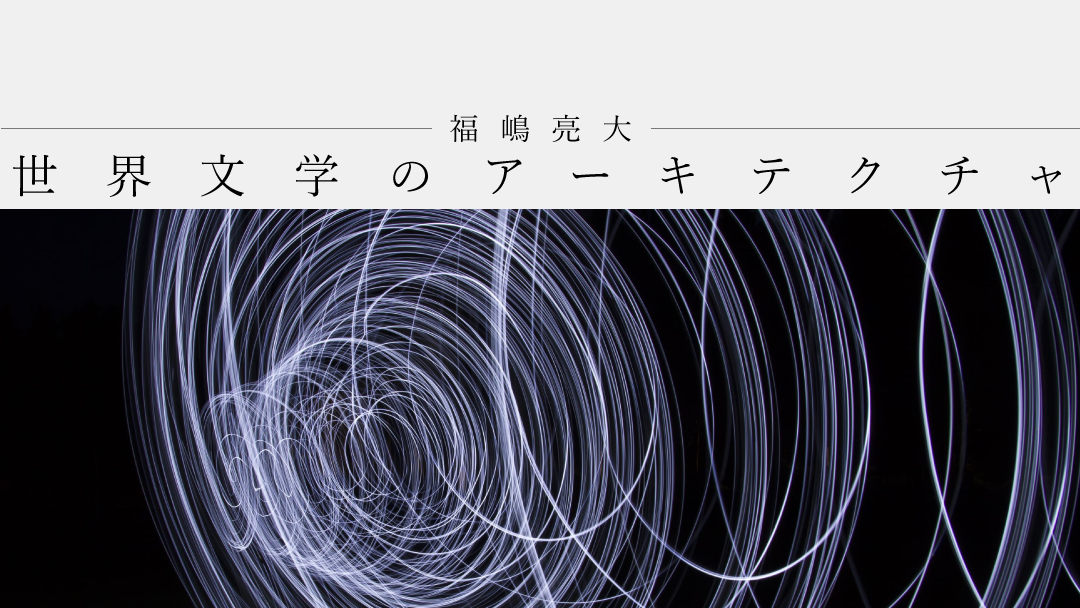
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、世界文学としてのアメリカ独立宣言
アメリカの生み出した最初の、そして最も強い衝撃力を備えた≪世界文学≫は、一七七六年に発せられたアメリカ独立宣言(United States Declaration of Independence)である。政治学者のデイヴィッド・アーミテイジが指摘するように、この宣言は「現在まで存続し続けている政治的著述の一ジャンル」の誕生を告げた[1]。そのユニークさは、主権国家としての対外的な独立のみならず、諸個人の「生命、自由、そして幸福の追求」の権利も強く主張したことにある。国家の権利と人間の権利の価値を、世界という法廷で高らかに「宣言」し、現実のものに変える創設的な言説――それこそがアメリカ建国の始祖たちの発明したものである。独立宣言というジャンルは、ちょうど一八世紀のヨーロッパ人が「小説」を飛躍させたことに匹敵するような、言説の歴史における驚くべき発明であったと言えるだろう。
しかも、この新しい政治的著述のジャンルは、強力な感染力を備えていた。アーミテイジによれば「アメリカ革命は、主権という名の伝染病の最初の大発生であり、この伝染病は一七七六年以降の数世紀の間、世界に大流行した」。この主権のパンデミックは「諸帝国が織りなす世界」から「諸国家が織りなす世界」への移行を決定づけた。この政治的疫病によって、世界じゅうに諸国家がひしめきあう新時代の扉が開かれた。一九世紀のヨーロッパが多極的な安定構造の時代であったのに対して(前章参照)、同時期の南北アメリカ大陸はむしろ国家の繁殖地となり、ハイチ、ベネズエラ、ブラジル等が相次いで独立を宣言し、二〇世紀になるとアジア、アフリカ、中東、バルカン半島、旧ソ連、東欧等で「主権という名の伝染病」が再燃した[2]。独立宣言という文書ジャンルは、この感染症の媒体になったのである。
私がアメリカ独立宣言という「ノンフィクション」の文書を≪世界文学≫に数え入れるのは、そこにヨーロッパ文学の財産が受け継がれているからである。そもそも、一八世紀後半まで、文学(literature)は現代ならばノンフィクションに分類される著述――歴史、旅行記、哲学、科学等――を含む多義的な言葉であった[3]。当時のイギリスの『ロビンソン・クルーソー』や『ガリヴァー旅行記』は、いずれもノンフィクションの体裁を利用した作品である。逆に、それ以降のロマン主義者たちは、「オリジナリティ」や「天才性」や「想像力」という概念を駆使し、literatureをむしろ現実から独立したフィクションに近づけた。一八世紀のクルーソーやガリヴァーが後に本格的な文学というより、しばしば児童文学のキャラクターとして扱われたのは、この大きな変化と関係している。一九世紀のliteratureの観念からすれば、一八世紀のliteratureは不純なテクストに映るだろう。
しかし、われわれはむしろここで、今で言うノンフィクションからフィクションまでを横断する一八世紀的な「文学」の概念を呼び戻そう。なぜなら、アメリカ独立宣言という第一級の政治的文書のなかにも、大西洋を横断する(transatlantic)文学の痕跡があるからだ。
現に、独立宣言の起草者の一人であるトマス・ジェファーソンは、ジョン・ロックの啓蒙思想に加えて、同時代のイギリスの小説家ローレンス・スターン、特にその最も実験的な『トリストラム・シャンディ』の愛読者でもあった。transatlanticな文学の研究者ポール・ジャイルズによれば、ジェファーソンがスターンの多面性――センティメンタルなモラリストにしてコスモポリタンな旅行者、下品な道化師にしてメタフィクション的なソフィスト――に魅了されていたのは、大いにありそうなことである。加えて、ジャイルズは独立宣言の掲げる有名な「幸福の追求」の権利も、スターンの思想と関連性があると推測した。
ふつう「幸福」の意味は、共和主義的な公共的参加か、あるいはジョン・ロック的な私的財産の獲得と結びつけられることが多い。しかし、ジェファーソンの好んだ文学を鑑みれば、彼の幸福概念には恐らく、身体と心が複雑に織り交ざったスターン的な「感覚の衝動」のテーマが入り込んでいた。たえず揺れ動きながら、人間を本来的な「自然」と結びつける感覚(sensibility)は、一八世紀の知的パラダイムにおいて高く評価されたものであり、ジェファーソンの主著『ヴァージニア覚え書』を読んでも、彼が民主政治の諸制度の根底に、アメリカの風土や気候を感じ取る能力を置いていたことが分かる。公共的な生と個人的な生をともに包み込む「感覚」の哲学者・文学者としてジェファーソンを理解しようとするジャイルズの見解は、十分な注目に値するだろう[4]。
その一方、アメリカがヨーロッパに及ぼした思想的影響も甚大であった。一八世紀の初期グローバリゼーションを背景として、当時のヨーロッパの思想家たちの観念は、環大西洋世界から強い作用を受けた。『カンディード』や『ロビンソン・クルーソー』の心象地理には、さも当然のように大西洋が組み込まれていたし、イギリスのデイヴィッド・ヒュームの哲学的著述も、環大西洋世界から得られる多くの情報によって支えられていた[5]。ジェファーソンもまた、アメリカの最も知的な政治家であり、かつ政治の前線に立つ一八世紀の大西洋人でもあるという二重性を備えていたと言えるだろう。
2、すべてを変えてしまった革命
では、独立宣言の切り開いたアメリカではいかなる《世界文学》が産出されたのだろうか。この本題に入る前に、ヨーロッパ人がアメリカへの進出をどう理解していたかというテーマを、もう少し掘り下げておこう。
独立宣言と同じ一七七六年に、イギリスでは経済学者アダム・スミスの『国富論』が刊行された。スミスはそこでヨーロッパ人の植民史を大きく取り上げている。彼によれば、古代のギリシア人やローマ人にとって植民地建設には居住空間の拡大という明快な目的があったのに対して、アメリカ大陸の植民地ははっきりしたニーズがないままに創設された。
アメリカと西インド諸島における植民地の設立は、必要性から生じたものではなく、その結果生じた効用がきわめて大きなものであったとはいえ、それは、まったく明白かつ明瞭なものではなかった。それは最初に設立された時に理解されておらず、しかも、その設立の動機や、それを発生させることになった発見の動機でもなかったから、その効用の性質、程度や限界は、おそらく今日でも十分に理解されていないのである。[6]
ヨーロッパ人は自らがなぜ植民地を欲するのか、植民地がいかなる効用をもつのか十分に理解しないうちに、アメリカと西インド諸島に植民地を創設した。しかも、このニーズを超えた過剰な集団行動こそが、世界を劇的に変化させたのである。ミクロな個人の利益追求がマクロな「意図せざる目的」を達成するという≪見えざる手≫に注目したアダム・スミスは、ヨーロッパの植民史にも人間の意図を超えた力を認めた。
さらに、フランスのディドロも同時代のスミスとよく似た認識を記していた。フランス革命前夜の一七七〇年に初版刊行されたギヨーム゠トマ・レーナルの大著『両インド史』に寄せた序文で、ディドロは新世界の発見を「革命」だと明言した。「新しい関係と新しい欲望によって、もっとも離れた国の人間同士が相互に近づいた」。経済圏が広がり、人間どうしの距離が縮まった結果として「いたるところで、人びとは意見や法律や慣習や病気や薬や美徳や悪徳をお互いに交換してきた」。ディドロはここで、あらゆるものが交換可能な商品になった、グローバルな商業ネットワークの到来を率直に認めていた。
そもそも、スミスやディドロが生きたのは、ヨーロッパの資本主義経済が急速に拡大した時代である。ウォーラーステインによれば、一七五〇年前後を境にして、インド亜大陸、オスマン帝国、ロシア、西アフリカといった諸地域が、世界経済に組み込まれた[7]。ディドロが気づいていたのは、それまで資本主義の外部にあった地域を内部化してゆく巨大な経済圏の出現が、前例のない「革命」であったということである。
しかも、ディドロの考えでは、自ら植民地を築いたにもかかわらず、ヨーロッパ人はこの全人類の接近の帰結を十全に理解していない。「ヨーロッパはいたるところに植民地を作ってきた。しかし、ヨーロッパは、植民地がどのような原理にもとづいて作られなければならないかを知っているだろうか」。このスミスにも似た問いかけは、人類の未来に対するディドロの懸念をいっそう深くした。
すべてが変わってしまったし、今後も変わっていくに違いない。しかし、過去に生じた革命は、人間本性にとって有益なものであっただろうか。また、今後、まちがいなく起こると思われる革命は、人間本性にとって有益なものになるだろうか。いつの日か人間は、これらの革命のおかげで、よりいっそうの平安と幸福と快楽を得ることになるだろうか。人間の状態は、よりいっそうよくなるだろうか。それともただ変化していくだけなのだろうか。[8]
ディドロは植民地の獲得が、ヨーロッパのすべてを根本的に変えてしまったことに驚いている。ヨーロッパ人はこの思いがけない革命が「人間本性」にとって、幸福な変化であったかを検証する術をもたなかった。
ヨーロッパ人が植民地事業によって、自らの根源的な自然=本性(nature)をも知らないうちに変えてしまったというディドロの考え方には、深い内省の跡が感じられる。それは、一八世紀文学の主人公像とも無関係ではない。例えば、ロビンソン・クルーソーは南米植民地の経営者、海賊の捕虜、さらに孤島の漂流者へと生まれ変わる。このめまぐるしい変身は、植民地の支配者であることによって、かえって不慮のアクシデントにさらされ、孤独な漂流者になったヨーロッパ人の姿を寓意している。『両インド史』に関わったディドロは、このクルーソー的な逆説を見事に捉えていたように思える。
3、有限の地中海から無限の大西洋へ
その『両インド史』の編纂者であり、腕利きのジャーナリストであったギヨーム゠トマ・レーナルは、すべてを変えてしまったヨーロッパ人に改めて自他の認識の基盤を提供した。ディドロらフィロゾーフ(哲学者)の援助も受けた『両インド史』は、信じがたいほど情報豊富な大著であり、ヨーロッパ各国のベストセラーとなった。そこには、ヨーロッパ人の進出した東インド(その範囲はあいまいだが、おおむねアジアの「旧世界」を指す)と西インド(南北アメリカ大陸という「新世界」を指す)についての大量の数値的なデータが集積されていた。
もとより、アメリカ大陸の住民にとって、入植者であるヨーロッパ人のジェノサイドは最悪の蛮行以外の何ものでもなかった。スペイン人によるインディオの虐殺を記した修道士ラス・カサスの告発文書は、すぐさまヨーロッパの各国語に翻訳されたが、アメリカ大陸で残虐行為を働いたのはスペイン人のみならず、イギリス人やオランダ人も同じであった。つまり、ヨーロッパの文明人が野蛮人を征服したのではなく、むしろ彼らの征服行為こそが恐るべき野蛮を生み出した。それは相手の人間性を破壊し「モノ」に変えるような殺戮において、最も顕著に発揮された[9]。
レーナルもディドロも、スペイン人の暴虐さおよびイエズス会の宗教的狂信への嫌悪や怒りを隠していない。特にディドロにとって、ヨーロッパの三百年の植民史は「人間の背徳の年代史」そのものであった。スペイン人は新世界を搾取し、その富をむさぼってきた。しかも、この大規模な犯罪がキリスト教の名のもとに遂行されたことを、啓蒙思想家ディドロは問い詰めてゆく。それによって、フランスの植民地政策の失敗も含め、従来の植民地化がいかに非人道的で誤ったプロジェクトであったかが立証されるのだ。
アメリカ独立宣言が主権国家を創設する言説のコンパクトな雛形になったとしたら、同時期の『両インド史』はヨーロッパの植民史への反省を促す巨大なアーカイヴとなった。植民地とは何かを知らないまま、新世界ひいては人間の本性をも思いがけずに変化させてきたヨーロッパを、膨大なデータを根拠にして批評し、人道と正義への道を作り直すこと――このような企図をもった『両インド史』は、すでに卓越したポストコロニアル研究であり、初期グローバリゼーションへの批判でもあったとすら言えるだろう。そして、ディドロたちはこの血塗られた植民地化事業へのアンチテーゼとして、より文明的・平和的な貿易を推奨したのである[10]。
スミス、ディドロ、レーナルらが象徴する一七七〇年代の知の驚異的な多産性は、旧来の地中海中心のヨーロッパ的世界像が、重大な転換点にさしかかっていたことを示唆している。『国富論』や『両インド史』のような画期的な書物は、ヨーロッパ経済が大西洋世界と深く結びつき、地中海周辺で自己完結できなくなった状況と対応している。フランス革命に先立って、この世界像の変更が生じていたことは、ここで見逃すわけにはいかない。
そもそも、カール・シュミットに言わせれば、地中海やアドリア海はたかだか「海の盆地」にすぎず、「世界の海洋の無限の広がり」と比べれば、その小ささは明白であった。地中海の「内海文化」や「海岸文化」を象徴するヴェニスは、一五七一年のレパントの海戦を経て海の主役の座から降り、それ以降はイギリスを中心として、遠隔地どうしを結ぶ「海洋文化」の時代に入った。SF的な飛躍を恐れないシュミットは、このイギリスの導く新しい海洋の時代になって、大地に直立する人間とは異なる存在、つまり「海のエレメント」を基盤とする「別の人間存在」が誕生したと述べている[11]。
有限の地中海から無限の大西洋へ――シュミットの言うこの≪空間革命≫の重要性は、確かにどれだけ強調しても足りない。では、この空間の質的変容に対して、文学はいかに応答したのだろうか。その重要な記録は、『ロビンソン・クルーソー』のおよそ一世紀前のシェイクスピア晩年の傑作『テンペスト』に見出すことができる。
4、存在を人間に変える力――シェイクスピア的共和国
もとより、誰も世界そのものを知り尽くすことはできない。われわれはただ「何をもって世界と見なすか」という問いを改訂し続けるしかない存在である。空間革命の先頭に立ったイギリスの劇作家にふさわしく、シェイクスピアはこの世界性への問いを、特異な空間とカップリングして提示した。その歩みには、地中海から大西洋へというヴェクトルを認めることができる。
政治思想家のアラン・ブルームによれば、一六〇〇年前後に書かれたシェイクスピアの『ヴェニスの商人』や『オセロー』の舞台であるヴェニスは、当時数少ない「共和国」の成功例であった。ヴェニスが世界有数の貿易都市として発展したのは、そこが「様々な種類の人間が自由に交わることができる」寛容な場所であったからである。ユダヤ人貿易商のシャイロックやムーア人のオセローのような異質なマイノリティも、この地中海に面した共和国では存在が許される。シェイクスピアはこの最も先端的な都市を、文学の酵母としたのである。
特に、シャイロックのようなユダヤ商人は、ヴェニスに資本投下するベンチャーキャピタルの担い手であった。ヴェニスの商業的繁栄の基礎を築いたのは、ユダヤ人という「よそもの」の商人にも人間的な権利を与える法の力である。ゆえに、シャイロックは法を善の基準として尊重する。にもかかわらず、シャイロックを法廷で破滅に追いやるのは、まさに彼を保護してきた法の機械的な作動である。シャイロックは自らを人間にしてくれた法のえじきになり、その厳格な判決によって社会的地位を剥奪されてしまう[12]。
ブルームが指摘するように、シェイクスピアは「人間が人間に、ただひたすらに人間になろうとする試みに関心を抱いていた」[13]。そして、この人間になろうとする意志が強く発揮されるのは、どこにでもある一般的な環境においてではなく、ヴェニスのような高度な政治的秩序をもつ都市国家においてである。シェイクスピア劇の政治性は、ある存在を人間に仕立てたり、逆に人間の座から追い落としたりするさまざまな権力――法、恋愛、人種、貨幣等――と密接に関わっていた。シェイクスピア的人間とは多数の権力の創造物であり、いわば地中海の首都=資本(capital)と呼ぶべきヴェニスは、これらの力を全部まとめて上演できる特異な劇場なのである。
シェイクスピアにおいて、ある空間が特別な≪世界≫としての資格をもつためには、存在を人間化する「力」が必要であった。彼はその力を、地中海のシンボルである共和国から引き出した。ただ、繰り返せば、地中海はあくまで「海の盆地」にすぎない。ヴェニスは確かに当時有数の世界都市ではあったが、その力の及ぶ範囲は内海に限られており、しかもその勢威はレパントの海戦を経て曲がり角にさしかかっていた。
この点で、シェイクスピアは、同時代人であるスペインのセルバンテスと符合するところがある。セルバンテスの『ドン・キホーテ』もまた、あくまで地中海世界を背景としながら、自分自身を限りなく重層化してゆくメタフィクションであった。レパントの海戦に参加した兵士セルバンテスは「ガリレイ的言語意識」(第二章参照)を縦横に駆使して、多様な対象を小説に畳み込んだが、その出来事はもっぱら荒涼とした陸地で起こる――むろん、『ドン・キホーテ』というスペイン語の小説そのものはやがて大西洋を渡り、ラテンアメリカ文学の始祖として再創造されるが、ドン・キホーテその人はやはり内海文化の所産なのである。
そう考えると、一六一一年に初演されたシェイクスピア最後の劇『テンペスト』の画期性は、いっそう際立つだろう。なぜなら、そこでは世界性の位置が、ついに地中海から大西洋へと移し替えられたからである。シェイクスピアは晩年に到って、力を上演する空間=世界そのものを転位しようと試みていた。それはまさに《文学上の空間革命》と呼ぶにふさわしい。
5、世界性の転位――『テンペスト』
地中海から追われた祖国喪失者プロスペローの支配する無名の島――それが『テンペスト』の舞台である。彼はもともとイタリアのミラノ公であったが、弟アントーニオーのクーデターによって放逐された後、一人娘のミランダとともに島に渡り、魔術を駆使して怪物キャリバンを奴隷化し使役する。キャリバンは島に響く不思議な音楽にうっとりし、反抗心をもちつつも骨抜きにされてしまっている。つまり、プロスペローはキャリバンを武力で屈服させるのではなく、むしろ彼に未知の感覚的快楽を植えつけることによって、権力を掌握したのである。
その一方、プロスペローはミラノを追われた屈辱を忘れていなかった。彼が大気の妖精エーリアルに命じ、宿敵アントーニオーやナポリ王アロンゾーの乗った船を嵐で沈没させる恐ろしい場面から、この劇は開幕する。島に流れ着いたアントーニオーたちはキャリバンをけしかけて、プロスペローに攻撃を仕掛けようとするが、今回のクーデターはあっけなく鎮圧される。そして、アロンゾーの息子ファーディナンドがミランダと結婚することによって、プロスペローは再び返り咲きの機会を得る。
クーデターで力を失った人間が、新世界において権力を奪回する。あるいは逆にクーデターで不正に権力を握った簒奪者が、魔術的な力によって失墜する――ここには『ハムレット』や『マクベス』でもおなじみの、いかにもシェイクスピア的な力の配置転換がある。しかも、『テンペスト』の場合、この力の転換のドラマは、血や暴力以上に「夢」や「眠り」にやさしく包み込まれていた。「吾らは夢と同じ糸で織られているのだ、ささやかな一生は眠りによってその輪を閉じる」(第四幕第一場/以下、シェイクスピア劇からの引用は福田恆存訳[新潮文庫版]に基づく)というプロスペローの言葉は、『テンペスト』の存在論を見事に要約している。未知の感覚に呑み込まれ、その自由を奪われたキャリバンをはじめ、島の人間たちは半ば夢見心地で動いているのだ。
ここで再びディドロやアダム・スミスの見解を繰り返せば、ヨーロッパの植民地建設は理性的なコントロールを逸脱した企てであった。つまり、ヨーロッパ人の入植行為そのものが「夢と同じ糸で織られている」のであり、しかも彼らはこの夢の布地のなかで、最悪のジェノサイドを引き起こしたのである。シェイクスピア劇の核心には常に「夢」があるが、『テンペスト』ではそれが地中海と大西洋のギャップ(間隙)で発生している。ゆえに、この劇にはヨーロッパの植民史への注釈として読める一面がある。
もとより、『テンペスト』の島の地図上の位置は明示されないが、それが地中海のような「海の盆地」の外にあるのは間違いない(劇中では、海難事故の多かった北大西洋のバミューダが「あらしの絶え間無い魔の島」として言及されている)。その一方、『テンペスト』の作劇法そのものは、従来のシェイクスピア劇の延長線上にあった。それゆえ、ピーター・ヒュームが指摘するように、『テンペスト』では「もともとの地中海テクストに重なるようにして、大西洋的テクストが地中海的言語のあいだに書き込まれている。唯一の例外はキャリバンで、彼はどちらにも属する一種の言説の怪物であり、彼を作り出した闘争の名残をとどめる妥協の産物ともいえる」[14]。
ミラノの権力者プロスペロー、そしてアルジェリア生まれの魔女を母とするキャリバンは、ともに地中海世界の住人でありながら、大西洋世界に――いわば『スタートレック』の登場人物のように――転送された。時空をワープさせる転送装置としてのシェイクスピア劇では、古代の英雄が近代的な心理の持ち主として再創造され、地中海の人間が新世界の環境でエミュレートされる。その結果、しかるべき人間がしかるべき場所でしかるべき役割を演じるというわけにはいかず、むしろしばしば場違い(out of place)の感覚が上昇してくるのだ。
シェイクスピアの作品とは、それ自体が時空を転位させる超‐劇場である。そして、『テンペスト』は地中海から大西洋への転位によって、その後のアメリカ文学の想像力を先取りしたところがある。シェイクスピアは恐らく、エリザベス女王時代に書かれたアメリカ旅行記を読んでいた。そのアメリカ像は、歴史にさらされていない楽園(処女地)であり、恐るべき荒野でもあるという二重性において、『テンペスト』の島とよく似ている。ゆえに、文学研究者のレオ・マークスが『テンペスト』を「アメリカ文学への序論[プロローグ]として読まれるべき作品」と評したことにも、十分な根拠があるだろう[15]。
しかも、ラス・カサスの死の二年後に生まれたシェイクスピアは、新世界との接触から血の要素を取り除いた。『マクベス』や『ハムレット』等で血なまぐさいクーデターや内戦をテーマとしてきたシェイクスピアにとって、『テンペスト』を暴力的な劇に仕立てることは、お手の物であっただろう。しかし、プロスペローは一滴の血も流さずに島のトラブルを解決した。大西洋の娘ミランダと地中海の息子ファーディナンドの結婚が象徴するように、この島では対立は相互浸透や和解へと導かれる。マークスが指摘するように、ミラノにいたとき現実にうとい学者であったプロスペローは、島では「社会開発立案者」へと華麗に変身した。そして、そのソーシャル・プランナーとしての手腕によって、新世界は戦争のない平和な楽園へと仕立てられた[16]。
デフォーは後にやはりスペイン人の暴虐さを批判しながら、ロビンソン・クルーソーとフライデーを擬似的な親子として描いた(第三章参照)。シェイクスピアとデフォーという近代文学の二人の巨匠は、ともに新世界との暴力的接触を回避し、むしろ新旧二つの世界のあいだに家族的な親密さを成立させた。しかも、この穏便なやり方によって、プロスペローとクルーソーは島の領有を首尾よく実現したのだ。
6、人間ならざるものたちの資源化
このように、ヨーロッパの近代文学の起源には、植民地化の素朴な肯定ではなく、むしろ従来の横暴なコロニアリズムを反省的に修正し、無害化するプログラムが含まれていた。新世界の未知の他者に出くわしても、そこから正面衝突の因子を取り除く免疫システムが、シェイクスピアやデフォーの文学には作動していた。先述した『両インド史』と同様に、彼らのコロニアルな文学はすでにポストコロニアルな操作を含んでいたと言えるだろう。
プロスペローもクルーソーも、この免疫を強化する腕利きのソーシャル・プランナーとして描かれる。彼らの魔術やテクノロジーは、野蛮状態への感染を抑止しながら「人間がひたすらに人間になろうとする」実験を進める。私は先ほど、一七七六年の独立宣言を契機に「主権というパンデミック」が発生したことを述べたが、イギリス文学はそれに先んじ、プロスペローやクルーソーを独立国家の主権者に仕立て上げた。それを可能にしたのが、彼らのもつ武力以外の力である。
特に『テンペスト』が示すのは、その人間化のプログラムが、人間ならざるものの資源化によって支えられていることである。プロスペローの制作したアンドロイドのようなミランダおよび魔女の息子キャリバン――この片親しか知らない二人には、主体としての地位を与えないからこそ、プロスペローの権力は保証される。ミランダは父権的な支配のもとで知識を極端に制限され、結婚に向けたシナリオに従わされる。そして、この父娘の物質的な生活を、奴隷化されたキャリバンが支えるのだ。
ただし、ミランダとキャリバンを人間ならざる資源として用いるプロスペローの権力ゲームには、亀裂が入ってもいる。ミランダは当初プロスペローの言葉を聞き流し、キャリバンも最終的にプロスペローに対して叛乱を起こす[17]。プロスペローの言葉は絶対的な指令(command)として発せられるが、その伝達経路は不具合や不協和音を含んでいるため、彼の支配のプログラムはいつでも故障する危険性がある。力は言葉によって伝わるが、その言葉は同時に力を歪めるものでもある――シェイクスピアはこのような両価性を『テンペスト』の各所に忍び込ませていた。
プレヒューマンとポストヒューマンのあいだを行き来するゲーテの『ファウスト』は、『テンペスト』の問題を引き継いでいる(第一章参照)。シェイクスピアとゲーテが発見したのは、人間になろうとする試みが、いかに人間ならざるものの力に依存しているかということであり、この人間ならざるもの、つまり超人間的なものの領域を露出させたものこそが、大西洋というインフラなのである。われわれはすぐ後で、ハーマン・メルヴィルの『白鯨』に即してそのことを再確認するだろう。
7、愚かさを拡大する新世界――デフォーの『モル・フランダーズ』
シェイクスピア劇においては、しばしば二つの異質の世界が交差する。それを象徴するのが、地中海世界の中心であるヴェニスにアウトサイダーとしてやってくるアフリカの黒人オセローであり、ミラノから退出して新世界の支配者となったプロスペローである。そのなかで、ハムレットは旧世界の飽和を感じさせる人間である。
T・S・エリオットが、ハムレットの悩みは「客観的相関物」を欠くと批判したことはよく知られている[18]。ハムレットは自らの悩みに対応する客観的な現実をもたないため、その心は場違いの感覚にさいなまれ、とめどない内部分裂に向かわざるを得ない。この分裂はメタフィクション的な劇中劇――王の犯罪を告発する罠――において、きわめつけに複雑なものとなる[19]。ハムレットは芝居の脚本家となり、父の暗殺を再現し、自らの苦悩の原因を虚構として演じ直す。しかし、彼がどれだけ演技を積み重ねても、らせん状に迷宮化した自らの心から脱け出すことはできない。
ただ、「デンマークは牢獄だ」(第二幕第二場)と言い放つ閉塞的なハムレットの前には、本来は無限の海が広がっていた。この海との遭遇こそが、煮え切らなかったハムレットに政治的な決断を促す。彼が叔父である国王クローディアスに復讐するきっかけになったのは、デンマークからイギリスに出港したとき、海賊に襲撃されて(ちょうどロビンソン・クルーソーのように)捕虜になり、その際に自らを殺させようとする国王の陰謀に気づいたときである。海上のハムレットは再び陸地に戻って、復讐を決行する。しかし、もし海賊の捕虜となった彼がそのままデンマークを離れ、大西洋につながる「海的実存」に生まれ変わっていたとしたら、内部に向かってとぐろを巻くような彼の心には、別の解放の道筋が開けたに違いない[20]。
興味深いことに、シェイクスピアの活躍からおよそ一世紀後の一六八九年に、アメリカのカロライナ憲法の制定にも関わった哲学者のジョン・ロックは「最初の頃は、全世界がアメリカのような状態であった」(『統治二論』後篇・四九節)と述べながら、貨幣ももたずに「生存の必要」(同・四六節)だけで動いている初期状態の人間のモデルとしてアメリカ人を描いた。ロックがアメリカを自己流に理想化しているのは否めないとはいえ、飽和したヨーロッパ社会をまとめて初期化できるジョーカー的存在としてアメリカが現れたことは重要である。実際、シェイクスピア以降の近代小説の主人公は、ハムレットのように悩みを内的に自乗する代わりに、むしろその累積したエネルギーを外に振り向け、人生を新たに始め直すようにして大西洋を横断した。
例えば、ダニエル・デフォーはロビンソン・クルーソーを環大西洋的存在として造形した後、一七二二年のピカレスク・ロマン『有名なモル・フランダーズの運不運』で、新世界アメリカへの旅立ちを物語の核心に据えた。ロンドンのニューゲートの牢獄で生まれた女性主人公――本名を隠してモル・フランダーズという変名を名乗る――は、虚栄心にとりつかれ、自ら破滅への道を歩まずにはいられない。その美貌を駆使して結ばれた二人目の夫は、彼女をアメリカのヴァージニア州のプランテーションに連れてゆく。しかし、この夫が実の弟であったというショッキングな事実が判明し、彼女は一人で帰国するのである。
当時のヴァージニアは「ニューゲートやその他の牢獄」から流刑になった人間たちで溢れていた。イギリスでは罪人であった彼らは、うまくやればアメリカの植民地で出世することもできた。夫=弟の母(つまりモル・フランダーズの実母)が「ニューゲートにいた連中でえらぶつになっている人がたくさんいるよ。ここには治安判事や民兵団の将校や自分の住んでいる町の判事でも、腕に焼印のある人が何人もいるんですよ」と語るように[21]、ヴァージニア植民地はシェイクスピアのヴェニスにも似たアウトサイダーたちの「共和国」であり、モル・フランダーズも含めた悪人も、統治側の人間に生まれ変わる可能性をもった土地であった。
この小説のテーマは、犯罪者たちがお互いに秘密を隠しながら、騙し騙される関係を生き延びてゆくことにあった。西洋文学史を振り返っても、モル・フランダーズほど戦略的な女性はほとんどいない。ロビンソン・クルーソーが島を計算づくで経営するのに対して、彼女はむしろ人間関係を巧妙に計算して操作する。しかも、デフォーが画期的なのは、社会の下層のアウトサイダーが人間になろうとするシェイクスピア的なゲームの底面に「愚かさ」を据えたことである。
実際、モル・フランダーズは愚かしい虚栄心に導かれるままに、新世界の社会に滑り込もうとするが、結局は弟との近親相姦というこれまた愚かしい予想外のエラーによって、その企ては失敗に終わる[22]。新世界アメリカへの渡航は、理性のコントロールの及ばない領域を浮かび上がらせた。『テンペスト』が「眠り」や「夢」として描いた問題は、『モル・フランダーズ』では「愚行」に変換される。後のディドロと同じく、デフォーにとっても植民地の創設は、人間性のひび割れを拡大するものであった。
8、世界文学は新世界文学である
デフォーはショッキングな例外状態によって、読者を外部に連れ出す作家であった。彼の近代性の核は、ヨーロッパ社会を動かす法(プログラム)を強制停止し、別の法則を備えた世界へと人間を連行したことにある。『ロビンソン・クルーソー』の漂流、『疫病の年の日誌』のペスト、『モル・フランダーズ』のヴァージニア渡航と近親相姦――これらはいずれも、人間を人間たらしめる理性ではなく、人間をその安全な進路から突き落とすショッキングな不意打ちとして描かれた。
このデフォーの手法は、演劇から小説へという近代の枢軸のジャンルの変化とも関連する。ヴェニス、デンマーク、大西洋等を舞台としたシェイクスピアは、演劇的空間の弾力性の高さを存分に活用した。プロスペローが放逐された経緯は、彼の一つのセリフのなかに圧縮されるため、地中海から大西洋への移動もSF的なワープのように軽快に処理される。それに対して、ジャーナリストでもあった小説家デフォーは、このような気ままな省略を許さなかった。クルーソーやモル・フランダーズがヨーロッパから離れるプロセスは、動機や行動経路を含めて詳細に記録されるが、その移動の根幹には人間性そのものの揺らぎがある。シェイクスピアが世界を可変的なシアターに仕立てたとしたら、デフォーは世界を激変させるショックの力を利用したのだ。
では、デフォー以降のヨーロッパの作家は、アメリカにどのような意味を与えたのか。世界文学論の観点から言えば、デフォーからおよそ一世紀後の晩年のゲーテがやはり重要である。
ゲーテはアメリカを組織的・集団的な起業の場として描いた。彼の『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』(一八二九年)では、主役の一人であるレナルドがアメリカ移住を志す。レナルドは紡績工を募集し、「真に活動的な人間」たちとともに新天地アメリカに工場を設立しようと試みた。彼の長い演説によれば、その企ては土地所有を最善とするヨーロッパ的な価値観を乗り越えて、むしろ最高の理念を「動産」および「行動に富む生」を認めるものである[23]。新世界アメリカに適した人格は、デフォー的な犯罪者からゲーテ的な企業家へと移り変わったが、そのいずれも私的所有よりもオープンな「生」を求めるタイプであったことは注目に値する。
ゲーテはアメリカに、私的所有制を超克するアソシエーショニズムの理想を投影した(すでに前作の『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』でも、フリーメイソン的な「塔の結社」を主宰するロターリオにアメリカ経験があった)。この理想の背景には、全人類を結びつけるフリーメイソン的な「世界同盟」(Weltbund)のアイディアがあった。世界同盟とは遍歴=さすらい(Wandern)の人間たちの集うアナーキズム的な結社だが、レナルドがその樹立を試みるとき、ヨーロッパの土地所有制度から脱出することが必要であった[24]。
レナルドの壮大なプロジェクト(人類補完計画?)は、明らかにゲーテの世界文学論――各国が文学を所有するのではなく、活発な翻訳と相互浸透を通じて世界規模の文化的コモンズを創設しようとする企て――と通底している。ゲーテの世界文学論は、私的所有制を批判する一種のアソシエーショニズムとつながっていた。しかも、このアソシエーションが機能するには、ヨーロッパとは異なる人間的結合を実現する《新世界》が欠かせなかった。レナルドとその生みの親ゲーテは、ともに同じ問題を抱えていたと言えるだろう。
こうして、『ファウスト』でポストヒューマンの領域へと踏み込んだゲーテは、『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』および世界文学論では、ポストヨーロッパの時代の到来を予告した。すでに『テンペスト』というアメリカ文学の序論に先取りされていた問題が、ゲーテによってくっきりと輪郭づけられた。一七世紀のシェイクスピア、一八世紀のデフォー、一九世紀のゲーテの三人を並列するとき、そこには世界文学とは新世界文学であるというテーゼが浮かび上がってくるだろう。
9、問いを発するべくして生まれたアメリカ
ただ、実際にアメリカ大陸に渡ったアレクサンダー・フォン・フンボルトやトクヴィルのような後続世代と違って、アメリカに足を踏み入れなかったゲーテが現地の認識において後れをとったことは否めない。ゲーテに限らず、一九世紀のヨーロッパ文学は、アメリカあるいは海という巨大な怪物を扱いきれなかったように思える。
例えば、アメリカの作家エドガー・アラン・ポーの真価を誰よりも鋭く見抜いたパリのボードレールも、無限にうねり続ける海と人間の「格闘」を詩的に認識した一方(「人と海」『悪の華』所収)、海にその全存在を賭けることはなかった。シュミットの言う「海のエレメント」を基盤とする「別の人間存在」は、ボードレールの想像力では十分に消化しきれなかった。ゲーテはエッカーマンとの対話で、パリを「大国の最高の頭脳」の集積地と評したが(一八二七年五月三日)、この一九世紀最先端の知的中枢神経を擁したフランスの文学者ですら、『海底二万里』のジュール・ヴェルヌを例外として、海的実存に生まれ変わるための手法を発明できなかったのではないか。
逆に、ポーの『ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語』(一八三八年)やハーマン・メルヴィルの『白鯨』(一八五一年)を筆頭に、一九世紀のアメリカ文学はむしろ海を抜きにしては考えられない。彼らの先輩の超越主義者R・W・エマソンは、アメリカは歴史のない国であり、だからこそ「人間が問いを発するべくして生まれた土地」であるとの印象的な言葉を残したが[25]、その問いの文学上の拠点となったのが海である。海と接触したアメリカの作家たちは、世界への問いかけをヨーロッパ人とは異なるやり方で組織してきた。
一九世紀のヨーロッパはナショナリズムの隆盛によって特徴づけられるが、ポーやメルヴィルはアメリカの文化・出版状況を背景としながら、ナショナルな領土支配の及ばない海洋にアクセスした。政治学者アイザイア・バーリンは「一九世紀ロシアは、一八世紀のヨーロッパの方に類似している」と述べたが[26]、これと似たような時差は一九世紀アメリカにも認められるだろう。私の考えでは、一八世紀ヨーロッパの初期グローバリゼーションの文学を隔世遺伝的に引き継いだのが、一九世紀のいわゆる「アメリカン・ルネッサンス」の作家、とりわけハーマン・メルヴィルである。
フローベールやドストエフスキーとほぼ同世代である一八一九年生まれのメルヴィルの文学的成長において、海の経験は不可欠であった。好評を博した彼のデビュー作『タイピー』(一八四六年)からして、自身が船乗りとして長期滞在した南太平洋が舞台となっている。一七一三年生まれのディドロの『ブーガンヴィル航海記補遺』のタヒチ島は、あくまで伝聞に基づく想像物であった。それに対して、百年後のメルヴィルは自らの実体験をスリリングな冒険物語に仕立てることによって、新奇でセンセーショナルな情報を求める読者の期待に応えたのだ。
だとしても、メルヴィルの文学は単声的な私小説とは明らかに異質である。彼の海洋文学の最高峰は、一九世紀の折り返し点に登場した規格外の小説『白鯨』であり、そこでは「私」は多様な語りのなかで限りなく乱反射し続け、一つの像を結ぶことがない。一九世紀のあらゆる小説のなかで、『白鯨』くらい一八世紀的な知の風土――百科全書や初期グローバリゼーション――に深く関連する作品はない。と同時に、メルヴィルの小説は一八世紀までの「世界性」の描き方に大胆に干渉し、それを異常化してゆく。この点で、『白鯨』には二重のアナクロニズム(時代錯誤)がある。それは一九世紀にありながら一八世紀的であり、しかも一八世紀をも飛び越して、未来へと延びてゆくような小説なのである。
10、異常な思考――メルヴィルの『白鯨』
鯨というリヴァイアサン(海の巨獣)にその中心を占拠された『白鯨』は、メルヴィルの従来の小説からの質的な飛躍を含んでいる。メルヴィルによれば「鯨は巨体を誇るがゆえに、こちらが拡大し、増幅し、ひろく敷衍するにふさわしい豊富な主題を提供してくれる。それを縮小したり凝縮したりするのは、したくともできる相談ではない」(104/以下『白鯨』の引用は千石英世訳[講談社文芸文庫版]に拠り、章数を記す)。人間ではその全貌を把握しきれないからこそ、思考のテーマをとめどなく産出する怪物――それは読者にめまいをもたらさずにはいない。『白鯨』とは何よりまず、怪物に呼び覚まされた異常な思考をめぐる小説である。
メルヴィルが試みたのは怪物の探求であり、その探究の手法(マニエラ)の発明である。ゆえに『白鯨』をマニエリスム文学の最高峰と呼んでも、言い過ぎにはならないだろう。そこには「鯨学」という学問的な語りがあるかと思えば、鯨の生々しい解体も含む船員体験のレポートがあり、鯨と闘うセンセーショナルな光景もある。モービィ・ディックと呼ばれる伝説の鯨は巨大な迷宮であり続ける一方、鯨についての語りはとめどなく増殖し、この怪物をミステリアスな多面体として再創造する。
もともと、捕鯨は初期グローバリゼーションにおける中核的な産業であった。それは莫大な富を生むだけでなく、振幅の激しい感情をも生産する。すでにデフォーはジャーナリストとしての立場から、イギリスを「貿易によって国威を高めた国」と讃えながら、貿易がいかに富を増大させ、いかに人間の心を劇的に変えたかを雄弁に語っていた。彼によれば「商いのない国民は元気がなく悲しげに見える」が、商業国の国民は「生気と活気」にみなぎっている。そして、ぞっとするような恐怖をふりきって、寒冷地で捕鯨に従事する勇敢な商人こそが、まさに快活な商業人の最上位にいたのだ[27]。
逆に、『白鯨』ではグローバリゼーションの最先端を進む捕鯨者こそが、ひどく陰鬱な気分に包み込まれている。語り手のイシュメールは「財布の中身は底をついて、加えて我が心をひきつけるものはもうこの地上には何もないということになった」(1)という無一文の状態にあり、自らの剣に身を投げた古代ローマのカトーを引きあいに出しながら、海に行くことは「拳銃と銃弾」の代わりだとうそぶく。“Call me Ishmael.”という冒頭の有名な宣言によって、彼は旧約聖書の登場人物イシュメールになりすますが、この変容のすばやさは、彼が死の一歩手前の絶体絶命の境遇にあり、社会から脱落しかかっていることとコインの裏表なのである。
金銭も情熱もすべて枯渇し、陸地ではすっかりout of place(場違い)の状態になった経歴不詳のイシュメール。この自らをがけっぷちに追い込んだ語り手が、拳銃自殺する代わりに「しずかに無言で海に行く」ことを決断するところから、小説は音もなく始まる。彼はニューヨークのマンハッタン島を出て、マサチューセッツ州の捕鯨の街ニューベドフォードに移動し、ナンタケット島でピークオッド号――この名前は絶滅したアメリカ先住民の部族にちなんでつけられた――に乗り込んで、大西洋から喜望峰を経由してインド洋、さらには日本列島の近海にまで向かう。ピークオッド号はまるで地球儀の完成をめざすように、グローバルな世界を遍歴する。メルヴィルは捕鯨にかこつけて、地球史そのものを象ったと言えるだろう。
しかも、この地球をなぞる「海的実存」たちには、徹底して男性的かつ独身者的なイメージが与えられた。ピークオッド号の乗組員は「すべてが島生まれ、島育ち」であり、各自が「孤島」として独立している(27)。『白鯨』では発展的なダイアローグは希薄であり、鯨や海について証言する個々の孤島のような船員たちのモノローグが際立たせられる。加えて、彼らは家庭的な安らぎともほとんど関わらない。そのため『白鯨』には、常軌を逸した怪物を求めるというそれ自体怪物的な事業に引き寄せられた、独身者たちの証言集という趣がある。
あまりにも大きなショックを受けた瞬間、ひとは有機的な対話や安らいだ感情を断ち切られ、ただ絶句するか、ぶつ切りの独白を続けるしかなくなる――二〇世紀のアウシュヴィッツや広島・長崎の生存者がそうであるように。同じように、モービィ・ディックとはトラウマ的対象であり、そこからは相互に孤立した断片的な「証言」が得られるだけである。デフォーにとって、ショックの引金は安定的な社会からの漂流にあった。メルヴィルはそれだけでは飽き足らず、怪物との遭遇によって、人間がその言葉ごと捻じ曲げられるところに、最大のショックを認めたのである。
『白鯨』のもう一つの仕掛けは、生存の条件をもぎとられた絶体絶命の人間こそが、怪物にアクセスできるという逆説を示したことにある。現に、精神的にも物質的にもゼロになった陰鬱な独身者イシュメールこそが、グローバリズムの欲望を結晶化させた最大最強の怪物にアクセスするのだから。
この種の逆転(inversion)は『白鯨』を特徴づけるものである[28]。例えば、イシュメールは「闇の奥」へと進むピークオッド号を操舵するうちに一瞬居眠りして、目覚めたときに一八〇度身体を回転させている。そのとき、何処かへ向かうことと何処かから遠ざかることが識別できなくなり、彼はひどい混乱に陥る(96)。これは『白鯨』そのものを象徴するシーンだと言って差し支えない。また、ピークオッド号は「古さびて珍奇な」老いた船であり、骨のような外観をさらしているが(16)、この骸骨のような船がことさら世界そのものでもあるかのように語られる。「世界は航行のさなかにある船そのものなのだ」(8)。船乗りが孤島になり、ぼろぼろの老いた船が世界になる――これはまさに異常な変身である。
そして、この異常さは常に語り手の思考のうちで生じる。『白鯨』の最大の価値は、自らの片足を奪ったモービィ・ディックへの復讐心に駆り立てられた船長エイハブを筆頭として、まさに思考の異常化を留保なく進めたことにある。そもそも、メルヴィルによれば、どれほど飲みにくく、ごつごつしたものであったとしても、人間は「やたら強靭な胃袋をした駝鳥」のようにその奇怪なものを呑み込んでしまう(49)。『白鯨』の思考は駝鳥のように、崇高なものからコミカルなものまで見境なく呑み込んでゆく。その結果、読者は「全宇宙を巨大な冗談と考える奇怪な瞬間、奇異な場面」の訪れを体験することになるだろう。
11、ベンチャーとしての捕鯨、量子化する鯨
ところで、未知の世界に乗り出すピークオッド号の航海には、明らかにアメリカの西部開拓との類似性がある。一八三〇年頃まで、西部開拓民にはろくでなしの半野蛮人という悪いイメージが与えられてきた。開拓民はアメリカの創設者であったにもかかわらず、人間性を放棄し、野蛮状態に逆戻りしかねない危険な無法者として理解されていた[29]。『白鯨』の執筆時期にはこのイメージはようやく好転していたが、ピークオッド号のならず者の船員たちには、かえって野蛮に近い開拓民のイメージが与えられている。
メルヴィルはこの多人種的な船員たちの世界に「民主主義的威厳」(26)を認める一方、そこに「狂乱のデモクラシー」(34)を重ねあわせた。ピークオッド号とは文字通り超‐民主主義的な空間である――なぜなら、そこではデモクラシーがどこよりも徹底され、そのことによってデモクラシーが異常で狂乱的な冗談へと転化するからである[30]。われわれはここにも《メルヴィル的逆転》を認めることができるだろう。
そもそも、一九世紀の捕鯨業は現代のベンチャーキャピタルと同じく、ロングテール型の利益分布を形成していた。ほんの一握りの航海(投資)だけが莫大な利益をあげ、その他の航海はほとんどリターンを得られずに終わる――しかも、その航海は死と隣り合わせの過酷なものであり、どれだけの成果を得られるかも予測不可能であった。この損益の幅の大きさにもかかわらず、成功すれば途方もない報酬を得られるという期待は、乗組員たちの強烈なインセンティヴになった。
面白いことに、現代の歴史家によれば、捕鯨船は「エージェントと船長が一等航海士からキャビンボーイまで、平均するとおよそ三〇名に及ぶ乗組員」を雇用したが、その規模は「スタートアップ企業とよく似ている」[31]。つまり、捕鯨業者の集まった一九世紀のニューベドフォードやナンタケット島は、二一世紀のシリコンバレーのように、一獲千金を狙うベンチャー企業の集積地でもあった。良質の鯨油のとれる抹香鯨からは、特に多くの利益があがった。狂気じみた船長エイハブと市民的理性の持ち主の一等航海士スターバックが、ともにこのギャンブルに関与するのは、今のシリコンバレーを考えればよく納得できるだろう。ベンチャー(冒険)とは狂気と理性を共存させる特異な場なのである。
私は先ほど、シェイクスピアの『テンペスト』に、人間ならざるものの資源化が書き込まれていると述べた。人間が人間になろうとする企ては、資源として利用できる非人間的なものに支えられている。『白鯨』では文字通り、鯨という動物的な資源の追求が語りの中心に置かれた。ただし、鯨は人間に確実な利益を与える従順な自然ではなく、むしろ人間を滅ぼしかねない超‐自然物であり、フィジカルなものとメタフィジカルなものが交差している。つまり、鯨とは確実に存在するモノではなく、存在そのものの不確定性を含んだ怪物的資源である。ベンチャーとしての捕鯨は、まさにこの超‐自然物としての資源にアクセスしようとする無謀な企てなのだ。
メルヴィルは鯨から不確定性のテーマを見事に引き出した。そこにはいくつかの水準がある。第一に「捕鯨船は不慮の事故に見舞われる確率が他のどんな船にもまして高い」(20)。捕鯨は多大なリスクを背負っているが、それでもエイハブやイシュメールたちは危険を冒して「海を耕す」(14)のをやめない。それは、彼らが命を賭けてギャンブルするという「危険の威光」(45)に魅惑されているからだ。
第二に、神出鬼没に動き回る鯨そのものが確率論的存在である。その出現を前もって予測することはできない。だからこそ、エイハブはその限界を超えて、ありもしない確実性を求める。「可能性がやがて確率となり、エイハブの期待するごとく、確率がやがて確実性となり、ついにはこの日この時この場所でということにはならぬものなのか」(44)。可能性を確実性に変えようとするエイハブの異常な思考こそが、骸骨のようなピークオッド号を地球遍歴へと駆り立てるのだ。
第三に、海の事件を伝えるコミュニケーションの不確実性がある。例えば、捕鯨者が鯨もろとも海底に沈んでしまったとしても、そのニュースは陸地にうまく伝達されない。「なぜなら、こことニューギニアの間を結ぶ郵便はかなり不規則なのだ。事実、ニューギニアからのいわゆる定期便によるニュースなるものを、直接にしろ間接にしろ聞いたことなど一度もないはずだ」(45)。海の恐ろしい出来事を伝達しようとしても、郵便網に不備がある限り、それは常に失敗のリスクにさらされている。『テンペスト』のように魔術的なワープを用いることはできない。
このように、鯨は恐ろしく巨大であるにもかかわらず、その行動は予測できず、観測次第で存在したりしなかったりする。しかも、その情報を遺漏なく陸地に届けようにも、その伝達の回路が故障してしまっている。メルヴィルは鯨という超‐自然的な資源のなかに、存在の偶然性と伝達の偶然性を畳み込んだ。そのことが、鯨のイメージをひどく分裂的なものに変えることになる。
現に、柴田元幸をはじめ多くの研究者が注目するように、『白鯨』にはナルシスやドッペルゲンガーに象徴される「分身」のテーマがある[32]。鯨にリヴァイアサンという聖書的なイメージが重ねられるのは、たんに巨大で恐ろしいからというよりも、それが観測するたびに様態を変える量子論的対象だからである。「鯨学なる学問の不安定、かつ不透明な現状」(32)を誇張とユーモア交じりに示す『白鯨』は、鯨を一つの「像」に定着させない。鯨はときに聖書的な怪物であり、ときに資本主義経済を駆動させる豊富な素材であり、ときに虐殺され食い尽くされる哀れな肉であり、しかもそのいずれにも還元されない。
その一方、世界の観測者たるイシュメールにしても、その語りが彼自身のものなのか、それともメルヴィルのものなのかは必ずしも判別できない。つまり、一人の語り手にも常にナルシス的な分身が重なっている。『白鯨』の語りはモノローグ的でありながら、それは量子状態にある。不確定な怪物を探究するという怪物的な企てが、このような分裂を強いるのである。
前章で述べたように、一九世紀のユゴーやドストエフスキーの小説には、生と死が量子状態で重なっているところがある。彼らはパリやペテルブルクという人工的な都市を、この重ねあわせの実験場とした。逆に、『白鯨』はむしろ新興の都市ニューヨークを離脱し、誰も所有者のいない確率論的な海で活動する。メルヴィルの小説はその脱‐都市性において、同時期のヨーロッパ・ロシア文学とは質的に違っていた。メルヴィルは一八世紀的なグローバリゼーションの文学を、他の誰とも異なる独創的かつ迷宮的なやり方で引き継いだと言えるだろう。
12、敵の誤認、ホモセクシュアルな友愛
メルヴィルは編集者への手紙で、シェイクスピアさえときに率直さに欠けると批判しながら「独立宣言だけは他との違いを際立たせています」と述べている[33]。このような言い方は、メルヴィルがアメリカを創設した言説=文学の力に魅せられていたことを示唆する。繰り返せば、アメリカ独立宣言という≪世界文学≫は、大地に「主権というパンデミック」を引き起こした。『白鯨』もまさに「独立」した独身者たちの乗り込む孤独な捕鯨船を描いている。しかし、海は大地とは違って、主権の確立を拒む。つまり、決して独立があり得ない世界での独立というパラドックスが、『白鯨』には仕組まれている。
このパラドックスゆえに、『白鯨』は宿命的な不確定性に取り憑かれる。メルヴィルは不確定性そのものを本格的に主題とした最初の小説家である。彼の描いた海的実存は一切の安らぎを失っており、それが読者に強烈なショックを与え続ける。サイードが巧みに形容したように、『白鯨』は「やりすぎること、追求しすぎること、限界を超えることについての小説」である。文学史上稀に見る過剰さを演じながら、メルヴィルは「不安や不確実性の両方を生み出す物語行為」に読者が参加するよう、強く要請した[34]。
このブレーキの利かない逸脱は、エイハブ船長の思考においてピークに達する。自らを省みず鯨を追い求めるエイハブは、海と誰よりも深く同化しつつ、海と敵対する。その結果、心身をさいなみ抜かれた「海の王者」(30)は、シェイクスピアの描いたリア王のように、甲板上をよろめきながらさまよい歩くばかりだ。この満身創痍の船長に対して、語り手はおごそかな口調で宣告を下す。
悲しきかなエイハブ、老いたる人よ、あなたの心の思いはあなたのうちに、ついに一つの生き物を作ってしまったのだ。その熾烈なる思いによって自らをプロメテウスと化してしまった人間、それがあなたなのだ。(44)
自然を支配しようとするプロメテウスの化身エイハブにとって、白鯨の追跡は悪=自然との闘いを意味している。片足を奪われた彼の怨念は、桁外れのエネルギーを生み出すが、その向かう先はぴたりと照準があうわけではない。なぜなら、存在を誇示しながら、同時に存在を隠すというパラドックスを備えた巨鯨は、面と向かった「闘争」という概念そのものを解体する量子的存在だからである。ボルヘスが鋭く指摘したように、『白鯨』は「悪との闘いの物語」だが、その闘争は「誤った方法で企てられる」[35]。エイハブは本来闘うべきではない相手に、間違ったやり方で闘いを挑む――それこそが彼の狂気の源泉なのである。
この点で、エイハブには錯乱したテロリストという一面がある。彼の思考は鯨を恐怖(テロル)の対象に仕立て、船員にも恐怖を与えながら、この鯨に電撃戦を挑む。テロリストとは他者に恐怖を与える存在であるとともに、恐怖を最も強く感じ取る人間である。エイハブは鯨そのものというよりも、鯨についての自らの思考に基づいて行動する。彼の思考はまさに近代のプロメテウスとして、超‐自然的な怪物を熱烈に創造し、それを支配しようとせずにはいられない。
こうして、エイハブとモービィ・ディックが常軌を逸したカップルになったとしたら、それと対照をなすのがイシュメールとクイークェグのカップルである。モービィ・ディックがエイハブの異常な思考において不倶戴天の「敵」として捏造されるのに対して、クイークェグは当初恐るべき「敵」として認識されながら、それが最も親密な「友」へと反転するのだから。このメルヴィル的逆転は実に強烈な印象を与える。
クイークェグは食人種の酋長の息子である。イシュメールは彼に恐れを抱くが、やがてその貴族的な野蛮人というたたずまいに触発されて、たちどころに親密な関係となる。イシュメールとクイークェグはホモセクシュアルな肉体的接触を経て、仲睦まじいカップルへと変身する。「翌朝、陽光さわやかなるなかに目覚めてみると、クイークェグの腕は慈しむかのごとく、愛するかのごとくおれの体に巻きついていた。まるでおれがかれの妻であるかのようだった」(4)。「おれとクイークェグのふたりは、心地好く愛しあう夫婦となって、新婚の新床にもぐりこんだのであった」(10)。イシュメールは女へと反転し、食人種クイークェグの妻となる――これに似た場面を他の文学から探そうとしても難しいだろう。
メルヴィルのクイークェグは、シェイクスピアのキャリバン、デフォーのフライデーの系譜に属する野生人である。もとよりロビンソン・クルーソーとフライデーのあいだに潜在的なホモセクシュアリティを認めることはたやすいが、デフォーはそれを父子関係に置き換えた。放蕩息子のクルーソーは、島で旧約聖書の詩篇や新約聖書の使徒言行録に強く触発されて「悔い改め」(メタノイア)を経た後、威厳ある父としての立場から、食人種のフライデーを手なずける。しかし、メルヴィルはより大胆に、食人(カニバリズム)のモチーフをホモセクシュアルのモチーフへと横滑りさせた[36]。しかも、キャリバンやフライデーが島に隔離されていたのに対して、クイークェグは港町のニューベドフォードという市民的空間を堂々と闊歩している。
クイークェグのごとき風体異様の人物が、文明社会の上品なる社交の場ともいうべきこの宿に闊歩するのを見て、おれとしては、最初はやはり驚愕の念に打たれた。だが、いまはじめて明るい午前の光のなかで、ニューベドフォードの街を散策してみると、そうした驚きもすぐに立ち消えに消えて行く思いに見舞われるのだ。(6)
ただし、『白鯨』の常として、この民主主義的な世界には狂乱の要素が含まれている。クイークェグは自らの「傷」だらけの身体を隠さない。「顔に一面切り傷の跡が刻み込まれている」彼は「まるで三十年戦争に従軍していた負傷兵、体中に手当の膏薬を張り巡らせて帰ってきた帰還兵」(3)のように見える。つまり、クイークェグはたんに異人種であるだけではなく、近代の戦争の痕跡へと横滑りするような暗号をその身に帯びているのだ。
しかも、骨相学にも詳しい語り手は、この「野蛮人」の頭の形状から、あろうことか建国の英雄ワシントンの胸像の頭部を連想する。「ジョージ・ワシントンが食人種として成長して行くとクイークェグになる」(10)。メルヴィルはここで、野蛮から文明へというお決まりの図式を反転させている――ワシントンという文明人が進化して食人種になるというのだから。クイークェグとは過去の未開人であるばかりか、未来のアメリカの予兆でもある。つまり、彼もまた「分身」に近づくのだ。
13、商品モデルから象形文字モデルへ
モービィ・ディックという謎、あるいはクイークェグという謎。『白鯨』の語り手はこれらの謎に立ち向かう解読者として現れる。「捕鯨船こそは、おれのイェール大学であり、おれのハーヴァード大学であったのだ」(24)というイシュメールの言葉はよく知られている。彼ら船乗りは捕鯨船という大学で、前例のない思考を繰り広げるが、それはしばしば暗号解読のような様相を呈していた。
その背景には、当時のアメリカ文壇におけるエジプトへの関心がある。エマソン以降のアメリカの作家たちはまさにエジプト象形文字に魅せられており、ポーやホーソーンも暗号解読を小説に組み入れていた[37]。『白鯨』もその例外ではない。「この抹香鯨という巨鯨[レヴァイサン]の顔の皺をたどり、頭の隆起に触れるということは、いかなる人相学者も、また骨相学者もいまだ手をつけたことのない仕事だ」と述べながら、エジプト象形文字の解読者シャンポリオンに言及する。つまり、鯨とは海の象形文字なのであり、その「ピラミッドのごとき沈黙のなかにこそ、かれ〔鯨〕の天才は表れている」(79)とメルヴィルは断定してみせる。
先述したように、一八世紀のディドロは、万物が商品として交換されるグローバルな交易世界を見据えていた。それに対して、一九世紀のメルヴィルはもう一歩進んで、世界をむしろ株式市場のように捉えている。「世界はどこへ行こうと、相身互い、相互に株式を持ち合う世界のようなもの。我々人食い人種がこのキリスト教徒たちの力になってやらなくてはならぬ」(13)。この価値の気まぐれな変動は、『白鯨』にまさに多くの暗号的な象形文字がばらまかれていることと対応する。メルヴィルは商品モデルの底部に象形文字モデルを据えた。
しかも、メルヴィルにとって、このような象形文字は死をも包摂するもの、死の彼方にアクセスする行為でもあった。『白鯨』には何度でも読み直されるべき素晴らしい文章がある。
死ぬということは、まだ見ぬ未踏の世界へ一歩踏込んだということを意味するのみ。死ぬということは、無限に遠いものが持つ可能性に宛てて、手紙の第一行目を記したにすぎない。野蛮、水、無、これらへ向けて手紙の一行目を記したにすぎない。だから、自殺への内なる良心の呵責を持ちながら、しかしなおも死を望む人の前には、海が、手紙のつづきに何を書こうとも、すべてを受け取り、すべてを読み解いてくれる海が、隅々まで白紙の胸を広げ、誘惑的に手招きして待っているのだ。(112)
この無限の太平洋から、人魚はこのように呼びかける。「ここは死ぬことなしに、世界を越え、驚異に出会うことができる。ここへお出なさい!ここに来て、自分を新しい生に埋めなさい。憎悪し、憎悪されて過ぎ来る陸の生を忘れさせること、死よりはるかにまされるこの新たな生に埋まりなさい」。
繰り返せば、イシュメールは自己に「拳銃と実弾」を用いる手前にいた。断崖絶壁にいる彼にとっては、生きた時間そのものが沈没し、もはやそれを取り戻すことはできない。「わたしという時計全体が下へ下へと沈んで行く。心が錘になってしまっているのだ。引き上げる鍵がどこにも見当たらない」(38)。『白鯨』は恐ろしく多弁な小説だが、その背後には音のない空間が広がっていたことを忘れてはならない。冒頭でイシュメールは一人黙って海に向かい、鯨は「ピラミッド」のように沈黙を守る。『白鯨』の語りはこの巨大な空洞のなかでエコーし、凝集と拡散を繰り返すのだ。
しかし、イシュメールは心の暗い底へと無限に沈み込みながら、無限の海を横に進み、鯨という象形文字の解読を推し進める――それは「死よりはるかにまされるこの新たな生」を生き直すことに等しかった。ハムレットは「あるかあらぬか」(to be or not to be)という二者択一の問いに直面したが、『白鯨』はこのハムレットの問いを超え出る。メルヴィルの海は死を終着点ではなく「新たな生」へのファースト・ステップに変えるからである。
いささか唐突に言えば、親にとって子は象形文字である――子には読めない文字で何かが書いてあり、それを完全に解読することはできないが、親はそこに未来を読み込まずにはいられない。『白鯨』の独身者たちは、子の代わりに鯨という象形文字、海という象形文字を自らの思考にたえず割り込ませる。海は「手紙のつづきに何を書こうとも、すべてを受け取り、すべてを読み解いてくれる」巨大なアーカイヴであり、それが「無限に遠いものが持つ可能性」へのアクセスを誘惑し続けるのである。
(続く)
[1]デイヴィッド・アーミテイジ『独立宣言の世界史』(平田雅博他訳、ミネルヴァ書房、二〇一二年)一二頁。
[2]同上、一二三頁。
[3]Jonathan Arc, American Literary Narrative 1820-1860, Cambridge University Press, 1995, p.2.
[4]Paul Giles, Transatlantic Insurrections: British Culture and the Formation of American Literature, 1730-1860, University of Pennsylvania Press, 2001, p.101, 116.
[5]バーナード・ベイリン『アトランティック・ヒストリー』(和田光弘+森丈夫訳、名古屋大学出版会、二〇〇七年)七五頁。
[6]アダム・スミス『国富論』(下巻、高哲男訳、講談社学術文庫、二〇二〇年)一〇四頁。
[7]I・ウォーラーステイン『近代世界システム』(第三巻、川北稔訳、名古屋大学出版会、二〇一三年)一六三頁。
[8]ギヨーム゠トマ・レーナル『両インド史 東インド篇』(上巻、大津真作訳、法政大学出版局、二〇〇九年)七頁。以下の『両インド史』に関する私の記述は、『両インド史』の続刊も含めた大津の訳者解説に多くを負っている。
[9]ベイリン前掲書、一〇頁以下。
[10]Anthony Pagden, Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain, and France c.1500-c.1800, Yale University Press, p.165.
[11]カール・シュミット『陸と海』(中山元訳、日経BP、二〇一八年)一九、四九、六一、一二九頁。
[12]アラン・ブルーム『シェイクスピアの政治学』(松岡啓子訳、信山社、二〇〇五年)二八頁以下。なお、ヴェニスのもつ共和国的な寛容性は、ずっと後に、トーマス・マンの『ヴェニスに死す』でアイロニカルに再現された。ヨーロッパ人の集うヴェニスのホテルは、ポーランド人の悪魔的な美少年タッジオからインド由来のコレラまでを「寛容」に受け入れる。その結果、生粋のヨーロッパ的教養人である主人公のアッシェンバッハは、海を夢見ながら浜辺で滅び去るのである。
[13]同上、五九頁。
[14]ピーター・ヒューム『征服の修辞学』一四八頁。
[15]L・マークス『楽園と機械文明』(榊原胖夫+明石紀雄訳、研究社、一九七二年)八四頁。
[16]同上、六三頁。
[17]なお、奴隷化されたキャリバンを雑種的な主体として組織し直したのが、エメ・セゼールの改作版『テンペスト』(本橋哲也他訳、インスクリプト、二〇〇七年)である。そこでも言葉が重要な意味をもっている。他方、ミランダをフェミニズムから読み解く系譜については、E・ショウォールター『姉妹の戦略』(佐藤宏子訳、みすず書房、一九九六年)第二章参照。
[18]「ハムレット」(中村保男訳)『エリオット全集3』二九八‐九頁。
[19]リュシアン・デーレンバック『鏡の物語――紋中紋手法とヌーヴォー・ロマン』(野村英夫・松澤和宏訳、ありな書房、一九九六年)二五頁。
[20]カール・シュミットの『ハムレットもしくはヘカベ』(初見基訳、みすず書房、一九九八年)は、ハムレットにヨーロッパの岬を超え出る「海的実存」の先駆けを認めた。
[21]デフォー『モル・フランダーズ』(上巻、伊澤龍雄訳、岩波文庫、一九六八年)一三七頁。
[22]Dennis Todd, Defoe’s America, Cambridge University Press, 2010, p.123.
[23]『ゲーテ全集』(第八巻、登張正實訳、潮出版社、一九八一年)三二九頁以下。
[24]登張正實『ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』』(郁文堂、一九八六年)一九七、二二一頁。なお、ゲーテ自身、エマソンからメルヴィルに及ぶアメリカの作家たちに絶大な影響を及ぼしたが、そこにはジェンダー論に関わる問題がある。
例えば、アメリカ屈指のベストセラー小説『若草物語』(一八六八年)の著者ルイーザ・メイ・オルコットは、父親の影響から超越主義者のエマソンに傾倒し、そのエマソンから贈られた『ヴィルヘルム・マイスター』を読んでゲーテを信仰するようになった。ただ、彼女は父権的な環境のなかで育ちながらも、『若草物語』ではその男性文化を女性版のビルドゥングス・ロマンへと変奏した。オルコット自身が色濃く投影された二女のジョーらはセルバンテス、シェイクスピア、ディケンズ、ウォルター・スコット、ファニー・バーニー、バニヤン等の文学をモデルに、女性の自立に向けた自己教育の場を形成する。父の超越主義を娘の教養主義に転用するオルコットの戦略については、ショウォールター前掲書、第三章参照。
[25]マークス前掲書、八〇頁。
[26]バーリン『ロシア・インテリゲンツィヤの誕生』一一頁。
[27]ダニエル・デフォー『イギリス通商案』(泉谷治訳、法政大学出版局、二〇一〇年)一、三五頁。
[28]カレブ・クレイン「友の肉の求者たち」(田村恵里訳)『ユリイカ』(二〇〇二年四月号)二四二頁。
[29]ジェイムズ・ベリッチ「アメリカ西部はなぜ移民が増えたのか」ジャレド・ダイアモンド+ジェイムズ・A・ロビンソン編『歴史は実験できるのか』(小坂恵理訳、慶應義塾大学出版会、二〇一八年)九〇頁。
[30]なお、メルヴィルはデビュー作から、大衆好みのセンセーショナリズムを巧みに操作してきた。この操作によって、彼の小説は民主的な広がりをもつばかりか「転覆的な想像力」をも引き寄せたのである。David S. Reynolds, Beneath the American Renaissance: The Subversive Imagination in the Age of Emerson and Melville, Alfred A. Knopf, 1988, p.279.
[31]トム・ニコラス『ベンチャーキャピタル全史』(鈴木立哉訳、新潮社、二〇二二年)三二頁以下。
[32]柴田元幸『アメリカン・ナルシス』(東京大学出版会、二〇〇五年)第一章。Kevin J. Hayes, The Cambridge Introduction to Herman Melville, Cambridge University Press, 2007, p.57.
[33]牧野有通『世界を覆う白い幻影』(南雲堂、一九九六年)一二頁。
[34]エドワード・W・サイード「『白鯨』を読むために」『故国喪失についての省察』(第二巻、大橋洋一他訳、みすず書房、二〇〇九年)六五、七四‐五頁。
[35]ホルヘ・ルイス・ボルヘス+オスバルド・フェラーリ『記憶の図書館』(垂野創一郎訳、国書刊行会、二〇二一年)四六頁。
[36]クレイン前掲論文、二四七頁。
[37]リチャード・ジェルダード『エマソン 魂の探求』(澤西康史訳、日本教文社、一九九六年)九三頁。サイード「エジプトの儀礼」『故国喪失についての省察』(第一巻)一五三頁。John T. Irwin, American Hieroglyphics: The Symbol of Egyptian Hieroglyphics in the American Renaissance, Yale University Press, 1980.
(続く)
この記事は、PLANETSのメルマガで2023年11月7日、11月28日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2024年1月4日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。