コロナ禍によって在宅ワークが広がった結果、「家」を中心としたローカルなライフスタイルのあり方が、いま改めて問い直されています。東京の高円寺にある銭湯・小杉湯が今年3月に新たにオープンした「小杉湯となり」は、「銭湯」という場を活かして、あたらしい「くらし」の模索を始めています。プロジェクトを率いる平松佑介さん、建築家の加藤優一さんに、そのねらいと課題を伺いました。
端的に言うとね。
「街で暮らす」というライフスタイルをつくる
──平松さんは、東京・高円寺で80年以上の歴史をもつ銭湯「小杉湯」を三代目として受け継ぎながら、そのセミパブリックスペースとしての性格を現代的に再定義して、これまで様々な活動をされてきています。アーティストや企業とのコラボなど、従来の銭湯のイメージを打ち破る意欲的な取り組みについては、いろいろメディア取材も受けられていると思いますが、昨年には都市型コミュニティの再設計という観点から、PLANETSチャンネルの番組にもご出演いただきました。
そのときに、銭湯事業を中心に置きつつ、さらに住環境全体にパブリック性を拡張する試みとして、隣接物件を利用した「小杉湯となり」の構想を伺っていました。今日は、その後どのような経緯でオープンしたのか、そして、現在のコロナ禍の状況下でどのように活動されているのか、お伺いしたいと思っています。

▲東京・高円寺で80年以上の歴史をもつ銭湯「小杉湯」
(Photo by 株式会社小杉湯)
平松 はい。まず、僕個人としては、あの番組に出させていただいたのはすごく大きかったんです。あの番組をきっかけに、僕の中で小杉湯が環境なんだという再定義ができました。小杉湯では、いろんなイベントやコミュニティが生まれているんですが、何か「コト」を起こして人を集めているのではなくて、人がすごく集まった結果、「コト」が起きている。それは環境や建築的な要素によるものが強いと思っていて。
その上で、3月16日に、小杉湯の隣に小杉湯となりをオープンしました。その背景となっているプロセスについては、加藤からお話しさせてもらえればと思います。
加藤 3年前、小杉湯の隣には解体予定の風呂なしアパートがあったんです。僕が設計事務所で働きながら小杉湯に通っていたときに平松さんと出会って、アパートを活用してほしいと相談されました。ちょうど『CREATIVE LOCAL:エリアリノベーション海外編』という本を書くために海外でリサーチした後で、世界中の人が自分の暮らしづくりを楽しんでいる様子を見て、自分もやってみたいなと思っていたときでしたね。
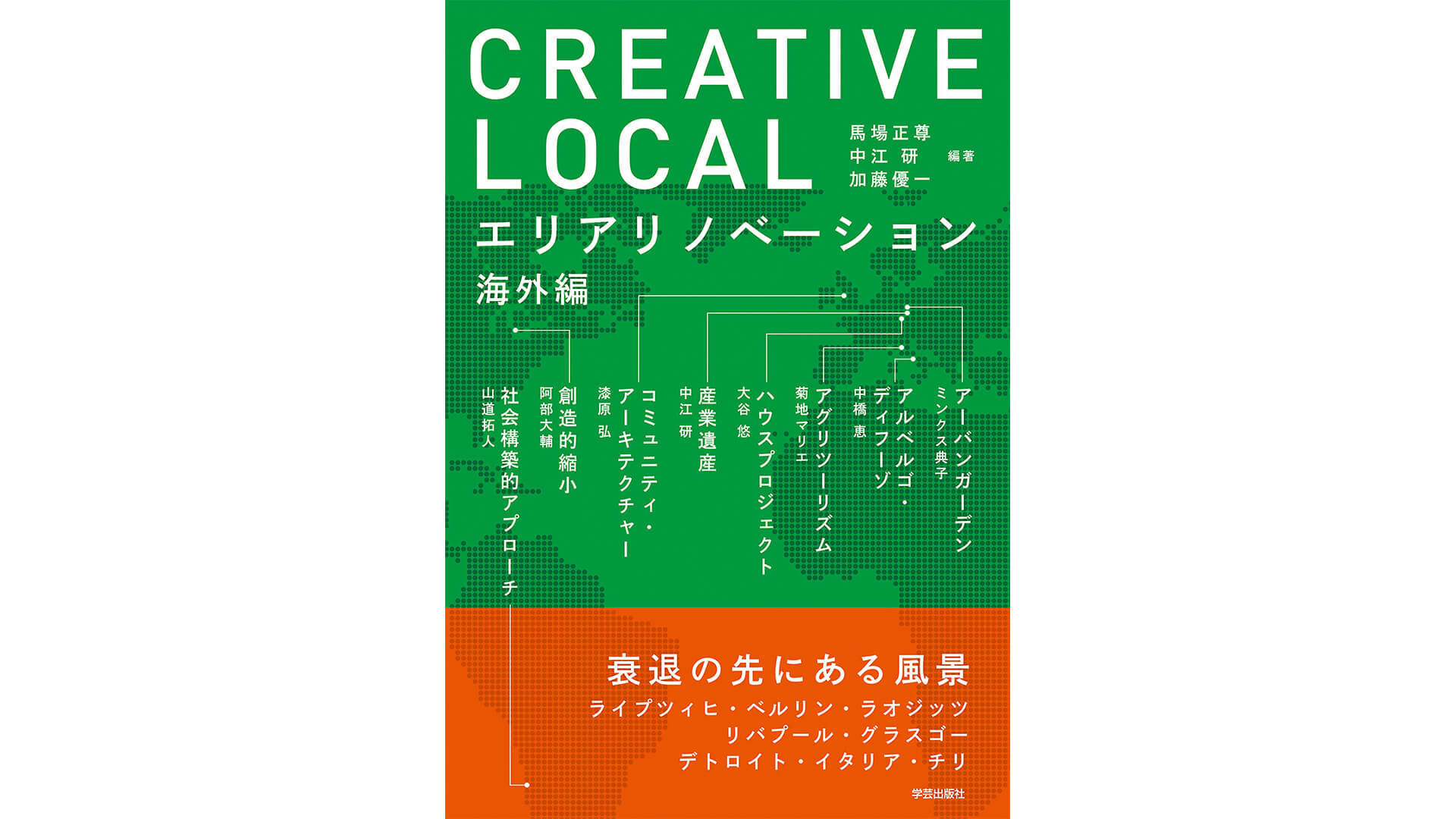
▲『CREATIVE LOCAL: エリアリノベーション海外編』
そこではじめたのが「銭湯ぐらし」というプロジェクトで、銭湯の常連客から多様な職種のメンバーを集めて、1年間風呂なしアパートに住みながら、銭湯と暮らしの可能性を探りました。風呂なしアパートを、銭湯つきアパートとしてリブランディングしながら色々な活動を展開しましたが、何より銭湯の隣に暮らすという体験が最高だったんですね。アパートを再建して住民だけがこの生活を体験するのではなく、より多くの人に伝えたいと思い、小杉湯となりを企画しました。それで、建主が小杉湯、企画と運営が銭湯ぐらしという役割で事業を進めることになりました。
銭湯のある暮らしが良かったのは、選択肢が増えたことです。ひとつは日常の選択肢です。日常の延長に、心と体の力を抜いてゆっくりできる時間とか、人の気配を感じられる場所がある大切さに気づいたんです。銭湯が街のお風呂であるように、銭湯の隣にもう1つの家のような場所があれば、自宅に大きい風呂や書斎がなくても、暮らしが充実すると思いました。家を拡張して「街に暮らす」というライフスタイルです。
もうひとつは、関係性の選択肢ですね。銭湯って「みんな」のパブリックスペースというより、名前は知らないけど見たことはある「あの人」の集積によって、程よい距離感が保たれていると思うんです。その安心感があるから、自分と向き合うことも、常連さんと言葉をかわすことも選択できる。ですが、意外にそういう場所は最近の都市空間にない。いわゆる近代のパブリックスペースは、拠り所が少ないんですよね。銭湯に毎日入る生活を通して、人との距離感や過ごし方を選べる場所をつくりたいと思ったのが着想です。
その後、週一回の定例会をベースに、銭湯でのアンケートや事例調査を取り入れながら、事業計画から運営体制、空間づくりまで進め、ようやく2020年3月16日に小杉湯となりがオープンしました。3階建てなんですが、1階は湯上りの一杯や食事が楽しめる食堂のような場所、2階は畳の上で仕事をしたりくつろいだりできる書斎のような場所、3階は六畳一間を自分の部屋のように使える場所になっています。

▲「銭湯のある暮らし」を体験できる小杉湯となり

▲小杉湯となり1階

▲小杉湯となり2階

▲小杉湯となり3階
(Photo by 株式会社銭湯ぐらし)
──ありがとうございます。しかしこのコロナ禍は、銭湯という業態にとっては大きな打撃だったんじゃないでしょうか?
平松 はい、このコロナの影響を受けて、小杉湯はお客さんが4割減っている状況なんです。
──7割減とかになってるんじゃないかって勝手に心配してました。逆に4割で済んでるってすごくないですか?
平松 そうなんですよ。今回のコロナ禍にあたって、「家にお風呂がある人は来店を控えてください」というメッセージを出して、要は高円寺周辺に住んでいて銭湯が生活の基盤となっている人に向けて営業を続けることにしたんです。営業時間とかも変えないようにして。宇野さんとのお話でも学んだように、小杉湯は環境であるという位置づけを考えると、やっぱりいつも通りにやっていくことはすごく大事なことなので、そこは覚悟を決めました。その上で、感染リスクをいかに抑えられるかを考えて4月から営業しています。結果的に6割来てくださっていて、その判断はすごく良かったと思っているんです。来てくださっている6割のお客さんのほとんどが、高円寺周辺に住んでいる小杉湯の常連の方で、大体の顔がわかるんです。つまり、普段のお客さんのうち、小杉湯の常連は6割だったということがよくわかりました。
小杉湯のスタッフは、元からうちのお客さんだった人が働きたいと言ってスタッフになっているケースが多くて、みんな高円寺に住んでるんですよ。電車に乗らずに通勤できるので、運営はできています。
小杉湯となりに関しても、このコロナ禍になって、小杉湯となりで飲食のテイクアウトをやってみたんですが、小杉湯のお客さんが買ってくれて、作ったものは売り切れた。
つまり今、小杉湯って、高円寺周辺の本当に小さい共同体の中で経済を回しているような状態なんですが、これでも生き延びられるんだっていうことが、今回のコロナ禍で肌感覚としてわかったんです。
メンバーシップではなくパーミッションによる中距離のコミュニティの強み
──非常に面白いですね。そこでお伺いしたいんですけど、そのコミュニティってどのぐらいの規模で、所属している人たちはどれぐらいの距離感でいるんですか?
平松 小杉湯のお客さんと小杉湯の運営スタッフ、小杉湯となりを運営してるメンバーでも、それぞれ距離感と規模が違っていますね。
──何階層にも分かれている感じなんですね。
平松 はい。小杉湯のお客さんはやっぱり、セミパブリックに近いというか、距離感が中距離的なんですよ。だからお客さん同士って名前や年齢とかも知らないけど、お互いの存在は知っていて、挨拶や他愛もない話くらいはするような関係性が多いです。一人ひとりはどちらかと言えば自分と向き合って内省してる人が多いんです。だけど、銭湯の中ではプライベートとセミパブリックぐらいの感じの行き来があるから、そこで人のつながりを感じられている。
加藤 サイレントコミュニケーションと呼んでいるんですが、会話をしなくても人の存在を感じられる距離感がいいですよね。銭湯って、時間によって小さなコミュニティのようなものがあるんです。早い時間はお年寄りや常連さんが多くて、遅い時間になってくると若者やワーカーが増えてくるんですが、たまにそのレイヤーが重なる瞬間があって、そのぐらいの関係性が心地良いんだと思います。
平松 小杉湯となりに関わっているメンバーについては、どうだろうね?
加藤 小杉湯となりだと、規模は大体30人ぐらいです。風呂なしアパートに住んでいた人が10人、銭湯ぐらしの法人化や小杉湯となりの立ち上げで、徐々に増えてきました。距離感としては、銭湯のような関係に近いかもしれません。アパート時代から、シェアハウスとは違って各々の部屋がある上で、必要に応じて集まったり銭湯で会ったりする関係でした。法人としても、メンバーのほとんどが兼業で関わっているので、それぞれの仕事と暮らしを持ち寄って活動しています。今では20歳〜80歳にまでメンバーが広がりましたが、その人の状況やライフステージに応じて関わり方を変えながら参加し続けてくれています。小杉湯となりの利用者もその広がりの延長にあるイメージです。
──プライベートとセミパブリックの中間ぐらいの、メンバーシップに縛られない距離感はすごく良いですよね。ローカルな公共性を考えるときに、「ご近所」的なコミュニティを再生してそこを足場にしよう、という考え方に僕は反対なんです。それは要するに、家族とそうではないものの間に線を引くということで、例えて言うなら常連の人間関係に認めてもらえないと楽しめない場所になってしまう。
友人が渋谷のシェアハウスで大企業の支援のもとに「拡張家族」的なコミュニティをつくる社会実験をしているのだけど、僕はこのコンセプトに懐疑的なところが多いんです。都心のクリエイティブクラスが疑似家族を作って、この輪をもっと広げていくんだと宣言して地方の農家とかと交流しているのだけれど、道路を挟んで隣の公園で寝泊まりしていたホームレスが再開発で追い出されることにはノータッチなわけです。
だから僕は、やはりコミュニティではなく「場」がまずあるべきだと思う。そこに行けばメンバーであろうとなかろうと承認されて、排除されることはない。こうしたメンバーシップに規定されない、ゆるやかなつながりを維持していける「場」であることのほうが、実空間を持っていることの意味があるはずです。なぜならば、メンバーシップを確認するならSNSで十分だからです。あえて嫌な言い方をするなら、敵を罵って味方同士傷をなめあって安心するようなコミュニケーションはいま、SNSで大安売りされている。
だから実空間を足場にするのならメンバーシップを与えるための「コミュニティ」ではなく、どんな人に出くわしても積極的に関わる必要もない代わりに、決して排除されない「場」を追求するほうが、その良さを引き出せるはずです。この実空間をあくまで「場」として使うことで風通しの良さと多様性が担保され続けていって、文化的な生成力を上げていくと思うんです。
平松 やっぱり、それが小杉湯という場所に紐付いているのが強いんだなと改めて思いました。
加藤 確かに、メンバーシップというよりは、環境とか生態系に近いのかなと思います。銭湯って、時代を越えて残ってきた場所と、時代によって変わる利用者との相互作用で使い方が最適化されてきたと思うんです。銭湯ぐらしも「銭湯のある暮らし」という都市での暮らし方が価値観の土台にあって、色々な人が集まっている。テーマ型コミュニティともちょっと違って、場所や生活の価値観を共有していることが特徴ですね。
──人に対してのコミュニケーションじゃなくて、土地や場所に対してのコミュニケーション、都市や空間に対してのコミュニケーションになっているからその関係性が成立しているんですよね。その共同体に入るにあたって、ボスからメンバーシップを確認されるのではなくて、土地や空間と人間のコミュニケーションがあって、そのコミュニケーションをどう豊かなものにしていくかを、他の客たちの背中を見て学んでいく。非常にうまい具合の中距離の関係性が、メンバーシップではなくてパーミッション(許容)によって成立している点が、僕はすごく重要だと思うんですよ。
パンデミック下で問われる「第二の家」のあり方
──小杉湯については、平松さんの私有物でありながら街のセミパブリックなインフラとして定着していたために、コロナ禍でも強みを発揮できたということだと思います。要するに、変な話だけど浴場という物理空間そのものの価値で生き延びているところがある。その一方で、オープンしたての小杉湯となりについては、相対的にその空間よりも、その空間で行われる社交の方に価値の中心があったことは間違いない。今回のコロナ禍によって、ダメージを負うのは空間そのものの価値よりも空間で行われる社交の方なので、これはかなり厳しい状況だと思います。
加藤 はい、まさに試行錯誤の日々です。
平松 小杉湯となりは、3月16日に席数や時間を減らしてオープンしたんですが、それから3週間後くらいに都知事の自粛要請(編集部註:4月10日発表)が出て、お客さんが7割減ぐらいに減ってしまうような状況になってしまった。それで、ゴールデンウィークくらいまでは、テイクアウトやデリバリー、EC事業を立ち上げていたんですが、やっぱり現場も疲労が蓄積してきてしまったのもあって、本当にやりたかったことを改めて考えたんです。
そこで、しばらくは店内の利用を会員限定にしようという話が出てきた。オープン時から、小杉湯と小杉湯となりを一体的に使える月額の会員プランはあったんですが、6月1日からいったんそこに集中しようと、日々話しているところです。
加藤 これがすごく悩ましくて、むしろ相談にのってほしいところなんですが(笑)、このコロナ禍の状況では、やっぱり「場」として外部に開き続けることが難しいじゃないですか。小杉湯となりは窓がたくさんあるので屋根のある公園のような環境を作ることはできるんですが、やっぱり環境の安全面だけでなく、家のような安心感みたいなものを作らないと、不安で来れない人にとっては、逆に閉じた空間になりかねません。
なので、今はあえて会員限定にして、いったん顔の見える関係性を作ろうとしています。銭湯でいう常連さんのように、この場所を最も使ってくれるであろう会員さんと一緒に、運営方法や外への開き方を考えていきたいなと。まずは、小さいつながりをつくり、少しずつ広げていくことで、長期的には開かれた場所にしていきたいと考えています。
ただ、メンバーシップではなくパーミッションに可能性があるという先ほどの話にもあったように、不特定多数の人と偶発的に出会うということが銭湯の魅力でもあるので、閉じた中からどう開いていくかをすごく悩んでいるところですね。今は軒下での販売などで模索している状況です。
──これは難しいですよね。もし、僕がお二人の立場だったらどうするか考えながら聞いてたんですけど、やはり「まずは一緒にリスクを背負ってくれる人とやっていく」というかたちで一度線を引くしかないんじゃないかな、と思いました。実際にどの程度リスクがあるのかは横に置いておいたとしても、リスクがあることをしているように世の中から見られてしまう。それを引き受けた上で、「これだけ面白いことができるなら参加しよう」と思ってもらえるようにすることが暫定解なのかなと思うんですよね。
ただ、これはポジティブシンキングが過ぎるのかもしれないけれど、「自分はこの小杉湯となりのような文化的なコミュニティの常連会員になっている」ことをドヤ顔でSNSに投稿しづらくなるのは、逆に良いことだと思っているんです。そういったスノビッシュな動機でくる人に対する緩いフィルターに勝手になっていく。だから、今集まってくれている人って、本当に小杉湯となりの可能性に少しでも賭けてみようと思って来てくれているはずで、そこを活かして、集まってきた人たちとどういう距離感で付き合って、何を仕掛けていくかを考えていくと良いのかもしれないですね。
都市の食文化の変化とローカル経済圏をめぐって
──ちなみにコロナ禍を受けての変化として、テイクアウトが小杉湯で伸びているというお話がありましたが、調理は小杉湯となりの方でやっているんですか?
加藤 そうです。1階の飲食スペースでつくっていました。
──テイクアウト、つまり外食でも内食でもない「中食」文化に関しては、コロナ禍の前から、たとえばゴーストレストランが人気になっているように、相対的に大きくなってきていてはいたはずなんです。「インスタ映え」するところに外食に出かけるのではなくて、テイクアウトした食事を食卓にかっこよく盛ってシェアするかたちにゆっくりとシフトしていたところに、コロナ禍での外出自粛の影響で一気に加速した。だから、このタイミングで、特に東京は食文化自体が大きく変わってしまうと思うんです。これは避けられなくて、飲食にコミットするなら、この変化を受け入れた上でどう逆手に取るかということを、まずは考えるべきだと思っています。
PLANETSでアルバイトしている若い子の実家が笹塚の鰻屋さんで、僕も応援したくて出前をとろうかなと思ったら、笹塚から出前してくれるのって新宿から方南町の間くらいまでなんですよ。やはり、笹塚から高田馬場はちょっと距離があるので、鰻を10食くらい頼まないとかえって迷惑をかけてしまう。つまりローカルな小規模の飲食店は採算が取れなくなってしまうので、5キロとか離れているとテイクアウトしてもらえないお店が多くなる。だから、今まで以上に中食のウェイトが上がることで、いい飲食店の近くに住んでいることの価値が上がってくる可能性があると思うんです。その部分をシェアリングエコノミーなどの応用で解消していくのかもしれないですけど、どういうシナリオになるかがまだ見えない。見えないけれど、お風呂に入ることと同じように、食べることも、街単位、街のインフラの一部に食い込んでいけると思っているんです。
加藤 もともとやりたかったことは変わっていなくて、家の機能を街に拡張して、高円寺の街全体を家と捉える「街に暮らすようなライフスタイル」を広げていこう、というコンセプトがあります。実際に、風呂なしアパートでの生活でも、風呂が銭湯で、食卓が定食屋だった暮らしが豊かだった。小杉湯となりがテイクアウトや会員プランを始めたのも、高円寺を家と捉えた暮らし方の選択肢を増やしていくことにつながっています。
平松 宇野さんも別の記事で書かれていますが、これからのライフスタイルに都会の家の機能が合っていないことは自分たちの実感値としても正しいと感じています。小杉湯となりをオープンする上でも、暮らしというものをサブスクリプション化して、家賃だけでなく、食や風呂などの暮らしに豊かなものを定額で生活に取り込めるような暮らし方を高円寺の中で作っていこうよ、というのがビジョンだったんです。
──その中で株式会社銭湯ぐらしが、とりあえずやってみようと思ったことが飲食とコワーキングだったけれど、2つともこのコロナ禍で大きく後退してしまった。でも、この状況下で、リモートワークを強いられてるからこそ、家で仕事ができなくてイライラしているような人がたくさん出てきたはず。だから、コロナ禍に対応したコワーキングや飲食店をやることで暮らしの中の選択肢をアップデートすることは、かなり可能性があると思うんです。
平松 まさにそこが、僕たちが今行き着いているところです。都市において、ステイホームの「ホーム」がもう1つ増えるような感覚で、自分の住んでいる街に第二の家を持つことを求めている人が結構いるように思うんです。
──このコロナ禍によって、グローバリゼーション下では、パンデミックのリスクが非常に高いことを人類は思い知った。昔だったら5年かかるものが、たった数ヶ月で地球規模に広がってしまう。だから、この状況がどこまで長く続くかはわかりませんが、完全に元には戻らないと思うんです。
たとえばいま、Amazonが生活用品のほうを優先して仕入れていて、本などの不要不急の物品の在庫をすごく減らしているんです。さらに、流通そのものが若干過負荷で混乱しがちになっている。僕はさっき加藤さんの本をAmazonで買いましたが、入荷未定で、僕の手元に届くのはいつになるのか分からない。この状態が長引いたら、僕個人としても、小さな出版社の経営者としてもすごく困ってしまう。僕が買うのは基本的に全部マニアックな本で、Amazonで買うのが一番確実で早かったんだけど、その前提が今、この状況下だけかもしれないけど崩れてしまっている。
こんなときにあったらいいなと思うのが、注文したら明日届けてくれるローカルな書店なんですね。たとえば、ジャンルに特化したゴーストキッチンならぬ、ゴースト書店のような仕組みです。ビジネス書、サブカルチャー、哲学書とそれぞれのジャンルの専門書店がローカルに存在していて、即日配送してくれる。もっと言ってしまえば、版元に注文したら翌日発送してくれる仕組みが備わればもっといい。僕は出版の人間だからこういう例が出てきたんだけど、同じようなことが他にもあるはずなんです。
平松 今までの取り組みを通じて、小さい共同体の中で経済が回ることの強さを実感してきているので、この状況下では高円寺という街の中で手を取り合って生き延びていくしかないなと。高円寺は飲食店が多くて、この状況下で厳しいお店がいっぱいあるんです。だから、何とか自分たちも生存戦略を立てながら、自分たちの共同体の中にいる人たちをつなぎ止められないかと考えて、ゴールデンウィークに自分たちの仲の良いお店の弁当や惣菜などのテイクアウト商品を代行で買って、配達するというデリバリーサービスをやりました。
小杉湯となりでも、もともと地域でお惣菜屋を営んでいた方を中心に飲食事業をやっていたので、自前のお弁当もあったんですが、実験的に他の店のデリバリーサービスもやってみたら、けっこう注文が入ったんです。やはり、高円寺の中で、本とお弁当を届けるとかローカルの中でぐるぐる回していくような仕組みは、利益が出ないかもしれないけれど、必要なことかなと思っています。
──さっきお話した笹塚の鰻屋さんは「隣のファミマだったらお使いもします」とチラシに書いているんです。ヤマトや佐川などの物流業者が過負荷になっていたり、Uber Eatsも混み合っていて、注文してから1時間以内にご飯が食べられるかどうかもわからなくなってしまっているような今の状況では、こういったローカルの配達サービスはけっこう需要があると思うんです。確かに、負荷がかかったり、利益がどの程度出るかはわからないですが、ローカルのサービスだからこそ時間もかからないし、Uber Eatsに比べると相対的に割安になるような仕組みも、たとえば、サービスを受けるために別途月額3000円取るとか、そういった工夫をすればできるかもしれない。
平松 そもそも、Uber Eatsって飲食店から35%も取っていて、しかも今始めても入金が5〜6ヶ月後とかになってしまう。だから、困っている飲食店には今お金が入ってこないんです。だから、僕らが試しにやったのは、飲食店からは手数料は取らずに、お客さんから配達料をもらうという仕組みです。ローカルなので、昼と夜で注文を受けると、1時間で10件以上回れちゃうんですよ。
加藤 宇野さんがおっしゃったローカルなデリバリーサービスとコワーキングスペースの2つは、両方やっていく予定です。中食のような家の中を充実させようという軸と、家だけじゃつらいから、家の外にある安心した場所に行こう、という2つの軸があると思っていて。両方ともサブスクリプションが適用できると思うんです。最初の軸が、地域の生協みたいなものなんですが、暮らしに関する地域の魅力を集めて再編集することで、お店にとっても利用者にとっても豊かなセーフティーネットができないかと考えています。2つ目の軸が、小杉湯となりの会員モデルですね。実は、僕はいまだに風呂なし3万円の物件に住んでいるんですけど、「となり」に対して家賃のように会費を払うことで、暮らしが充実しています。今後も、医療や教育、宿泊など色々な分野と連携することで、定額プランを広げていきたいと思っています。
──今までコワーキングスペースに課金することで買っていたものっていくつかあって、たとえば、アカデミーヒルズであれば権威やブランドだった。一方で、多くのコワーキングスペースにおいては、「家ではない場所」をみんなが買っていたわけですよね。このコロナ禍によって前者は崩壊していくのかもしれないけれど、後者の需要はより強くなっている。在宅ワークになって、オフィスチェアや腰に優しい椅子を作業用に買いましたという人が増えたけれど、すべてがオフィス用品で固めてるようなリビングとかはデザイン的にちょっとしんどいわけですよ。いま、人々はそういう現実に直面していて、この状態に対応した安心して外でひとりになれる空間としてのコワーキングスペースが、隠れた需要として掘り起こされつつあると思うんですよね。
加藤 環境として安心できる空間にするか、信頼関係があって安心できる空間にするかという差があって、小杉湯となりではオフィス化せず、信用をつくっていこうと思います。
平松 関わっている銭湯ぐらしのメンバーも、家族的というわけでもなくて、程よい距離なんですよ。一人ひとりが自立していて、お互いのプライベートに干渉し合わずに、セミパブリックっぽい空間を作っている、銭湯っぽい感じだと思うんですよ。小杉湯となりを第二の家として、会員40〜50名を住民としたときに、家族とも拡張家族とも呼びたくない。その中でのコミュニケーションをどう設計するかがすごい重要だなと思っていて、非常に悩んでいるところです。
加藤 これから会員を増やすにあたって、距離感が遠い人と近い人とが混ざり合ってくるような状態になってくるので、コミュニティが苦手な人が居やすい環境をどうやって設計していくかが課題ですね。普通は、お客さんから顔見知りになり、常連さんになっていくというステップがありますが、今回は先に常連さんをつくって広げていくかたちになるので。
──何かをシェアすることにリスクがある状況になった今、シェアということは別の意味でキーワードになっていると思っています。たとえば、同じシェアリングエコノミーでも、Uber Eatsは伸びた一方で、カーシェアリングはうまくいっていない。都市の個人主義を加速していくサービスは伸びていて、おじいさん、おばあさんを車に一緒に乗せて買い物に行くような共同体主義に親和性の高いものは感染リスクのために、非常につらい状況になっている。
今までは、とりあえず「所有からシェアへ」向かっていたんだけれども、シェアすることにリスクが伴う状況になって、シェアできるものと、できないものとが分かれてきた。住空間でいうと、シェアハウスからコワーキングスペース、アパートへの変化も十分ありえると思っているんです。
平松 今回のデリバリーをやった配達員は、Uber Eatsの配達員も同時にやっていたんです。一番の大きな違いは、コミュニケーションが発生するかどうか。同じ配達員でも、Uber Eatsは届けたときにその住民とのコミュニケーションが絶対に生じないんだそうです。だけど、小杉湯となりの人として配達するときは、コミュニケーションが発生する。
──それは一長一短で、喜ぶ人と喜ばない人といるんだろうな、と思います。たとえば一応、僕は世の中に対して多少顔が割れている人間なので、こういう場面で配達員の人とコミュニケーションが発生するのはちょっと嫌だな、と思うんです。そうでなくとも、今はSNSとかで誰もが顔割れしている時代で、みんながプライバシーに敏感にならざるを得ない状況になっていて、特に若い女性などは抵抗がある人もいるんじゃないかなと思います。だから、多少値段は高いけど、Uber Eatsのほうがドライで使いやすいなと思う瞬間はありますね。
加藤 そこにも選択可能性があるとよさそうですね。
──とはいえ、生活インフラを、もっとローカルなものにできるチャンスが来ているとは思うんです。つまり、ローカルな仕組みに、自分の生活をある程度預けるということの便利さや気持ちよさや面白さに、もっと多くの人が気づいていく可能性は高いと思う。これは決してコミュニティが強固にあって人の顔が見えるとか、ぬくもりを感じられるとか、そういったムラ社会の陰湿さとコインの裏表の「いい話」の価値ではなくて、もっと即物的な次元の話だと思うんです。コロナ禍で拡大した近所のメシ屋が、ランチをもっと簡単に出前してくれるところがあればいいな、ついでにお使いしてくれたらいいな、といったニーズを満たすためには、むしろグローバルなプラットフォームに依存しすぎないほうがいい場合もあるはずです。
こうして浮き彫りにされた欲望にいかにコミットしていけるかが問われているわけですが、そこにはいくつか越えなきゃいけないハードルがあるということだと思うんですよ。
加藤 小杉湯となりという「場所」を軸にするということは意識していきたいです。コミュニティに頼ってしまうと無理がきてしまうので、あくまで日常の延長にある「場所」として事業を考えると、自然なサービスや関係性が維持できる気がします。
平松 「となり」の建築はすごくいい建物で、雑誌「新建築」にも出させていただきました。そういう場所としての強みはあるので、そこにいること自体が気持ちいい、くらいがいいんだよね。

▲小杉湯となり 建築模型
加藤 それから、場所でも事業でも、人の気配を感じるということが大事だと思うんですよね。今、公園に人が集まっていますが、自粛期間を経たことで、自宅以外に暮らしの選択肢や、気配を感じられる場所の必要性が再認識されていると思います。銭湯での実感を「となり」にも活かしていきたいと思っています。
半径500メートルの「駅前」単位で街を捉え直す
──僕はランニングが趣味で、自粛ムードの中でもランニングを続けているんですが、新宿とか、東京の繁華街って、まばらだけど人が歩いていて、寂しくない程度に人がいる、これくらいの人出が一番気持ちいいなと思うんですよ。
寂しい一人暮らしの人が用もないのにコンビニに行くって話をたまに聞くじゃないですか。そういう、別に交流しなくてもいいし、賑やかじゃなくてもいいんだけれど、寂しくない程度に他人の気配が存在していて、同時に自分がその場にいることも許されるような快感に、コロナ禍によって気づかされた人って多いはずなんですよね。
平松 それが僕らの場合でいくと、たまたまコロナの前からそれを考えていたというのは、強みというか。
加藤 向き合ってきたことを続けられるという気がしますね。
──小杉湯の取り組みは高円寺という街でのお話でしたが、そこだけに限らず、他にも応用がきくのではないかと思います。コロナ禍によって、半径500mくらいの駅前単位で街を考えることの価値が再浮上していて、今後、そこをどう設計的に提供していくのかが問われていくと思うんです。
平松 このコロナ禍のタイミングでは、できるかどうかわからないんですけれども、自分たちで不動産仲介業をやって、小杉湯起点で不動産案内をするようなことをやってみたいなと思っています。実際に、小杉湯があるから高円寺に引っ越してくるという人たちが結構いるんです。小杉湯となりができたことで、さらにその選択肢が増してきて、需要があると感じています。
──それってOpen Aがやってきた「東京R不動産」などの発展版にあたる取り組みでもありますね。
平松 世に出ているサービスを高円寺エリアに特化してやっていくことに活路があるんじゃないかと思っています。飲食店さんも、デリバリーの話をすごく喜んでくれていて、ミールキットや冷凍した状態で届けられないかとか、いろいろな要望をいただいています。
──昔は町内や生活圏の拠点における象徴が、小学校の学区や特定郵便局だったのが、スーパーマーケットや小売店に変わり、供給が過剰な部分もあるけれど、今はコンビニエンスストアなどに置き換わっている。ところがそれが個人主義を加速させて、人々はコミュニティの呪縛から解放されたんだけれども、コミュニティ未満のつながりも一緒に失ってしまった。そこをどう回復するかということが、今問われているんだろうなと思います。
加藤 銭湯も一回閉じた家を開くという行為でもありますしね。
──これを機会にどんどん仕掛けていきましょう。この状況を逆手にとって。
[了]
この記事は、宇野常寛と山口未来彦が聞き手を、柚木葵と中川大地が構成をつとめ、2020年6月22日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。






