

「栗原一貴」さんについて取り上げた
これまでの記事の一覧をここに表示しています。






























リモート環境が常態化したいま、いつの間にか失われていた「周辺体験」とは何なのでしょうか。「効率化」がそぎ落とした、冗長だけれどもたしかに豊かさを感じ取ってもいた時間を再発見するための消極性デザインについて、メンバーの栗原一貴さんが語ります。
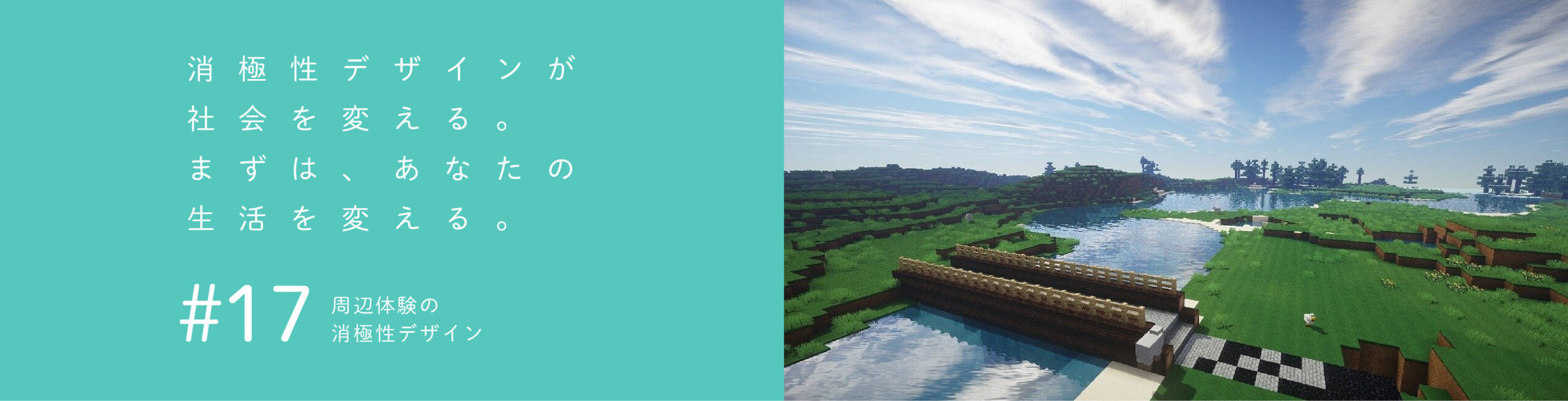
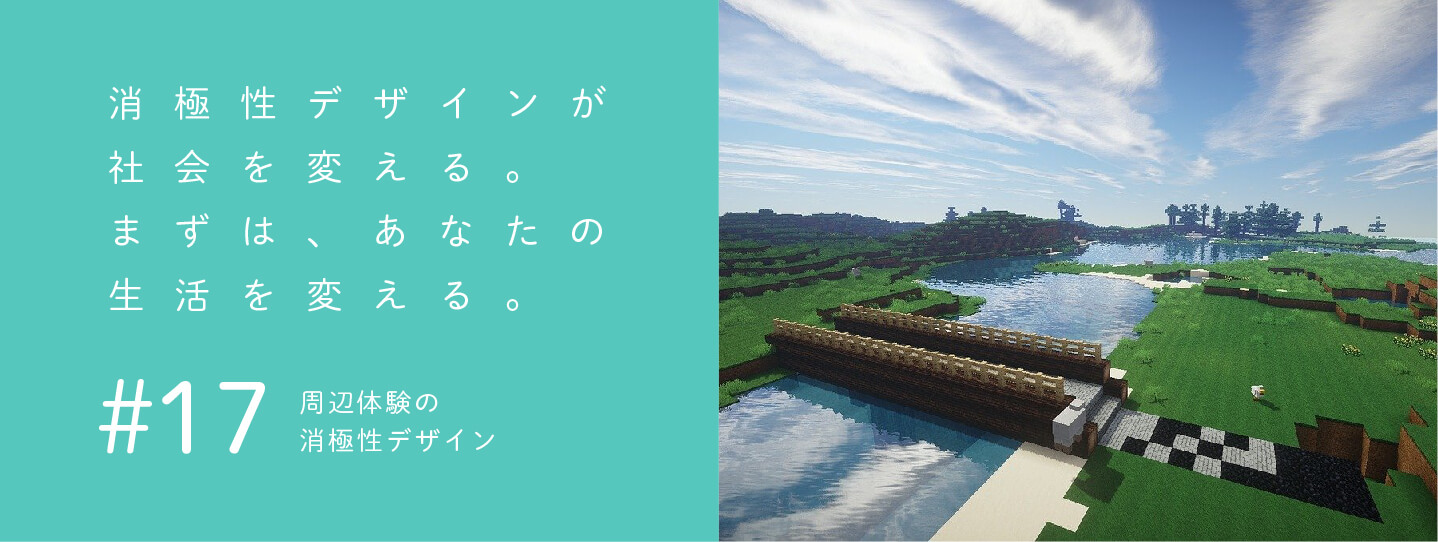 記事を読む
記事を読む消極性研究会(SIGSHY)による連載『消極性デザインが社会を変える。まずは、あなたの生活を変える。』。今回は栗原一貴さんの寄稿です。
栗原さんが客員講師としてシアトルを訪れたときに体験した、アメリカの「自主性・多様性」を重んじるコミュニケーション様式。日本にもそのエッセンスを持ち込むためには、「デザイン」の力が不可欠だと改めて実感したようです。

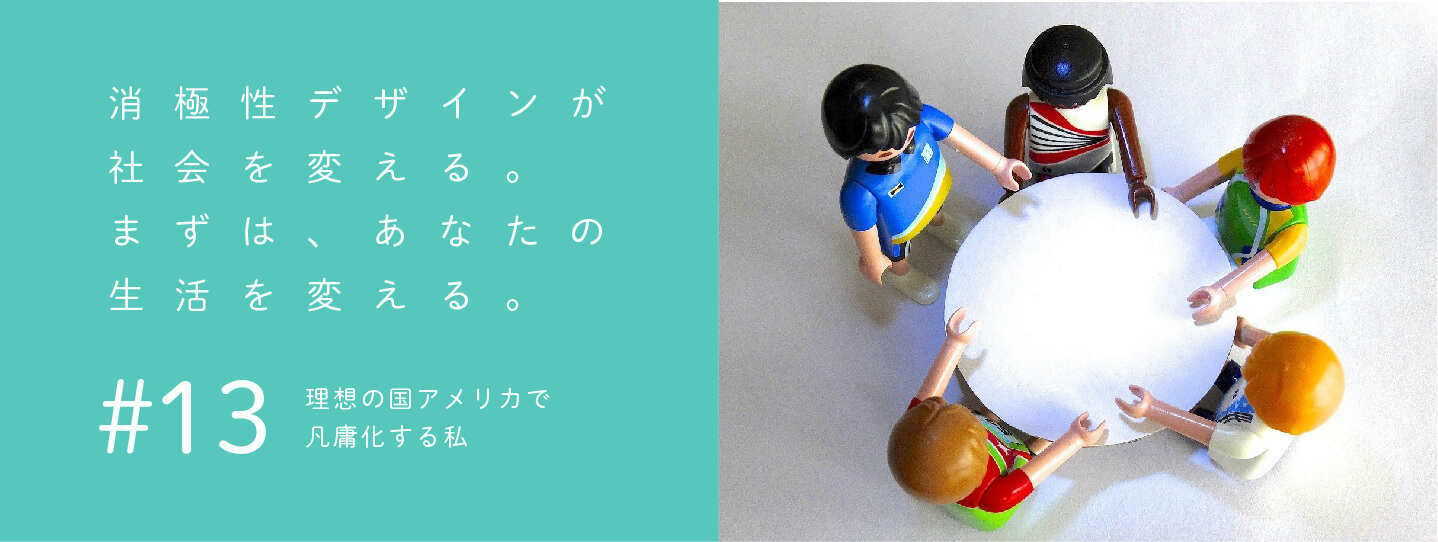 記事を読む
記事を読むみんなが同じようにアイコンをデコレーションしていると、なんとなく躊躇してしまったり、流行に乗るのが正しいのだろうかとつい考えてしまう。安易に流行には飛びつけない消極的な人だからこそできる、モノづくりの思考法があるのです。
「PeepDetectorFake」「スピーチジャマー」など、数々のモノづくりを経て、2012年には「イグノーベル賞」を受賞し、自らも消極的だという情報科学者の栗原さんが、身近な社会問題に「物議を醸すモノづくり」で挑みます。

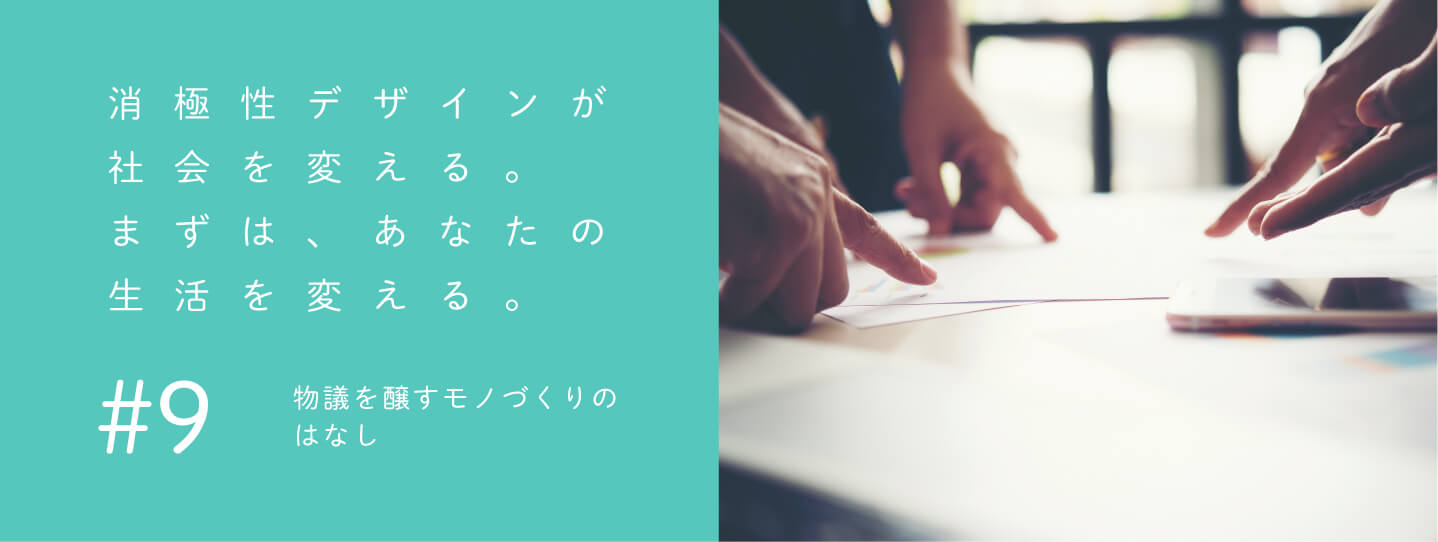 記事を読む
記事を読む情報技術とデザインによるハックで、シャイな人たちが直面するさまざまな生きづらさに向き合ってきた消極性研究会。そして、あらゆる人々が強制的に「消極的」に暮らすしかない状況が訪れた今、そのユニークな視点と知見は、どんなふうに活かしていけるのでしょうか。今回は番外編として、研究会フルメンバーが(もちろんリモートで)集結し、With/Afterコロナ時代の暮らしと社会を搦め手から考える座談会を行いました。

 記事を読む
記事を読む新型コロナウイルスの感染拡大により、オンラインでのコミュニケーションが拡大しました。慣れてしまえば昔には戻れないほど便利な反面、雑談が生まれにくくなったり、相手の反応が見えなかったりと、やりにくさを感じることもあるのではないでしょうか?
今回は、情報科学者の栗原一貴さんが、自身による大学でのオンライン講義の実践から、やりにくさの原因と、オンラインでのコミュニケーションを促進する方法を考えます。
オンラインならではのやりにくさは、テクノロジーの力で解決できるかもしれません。
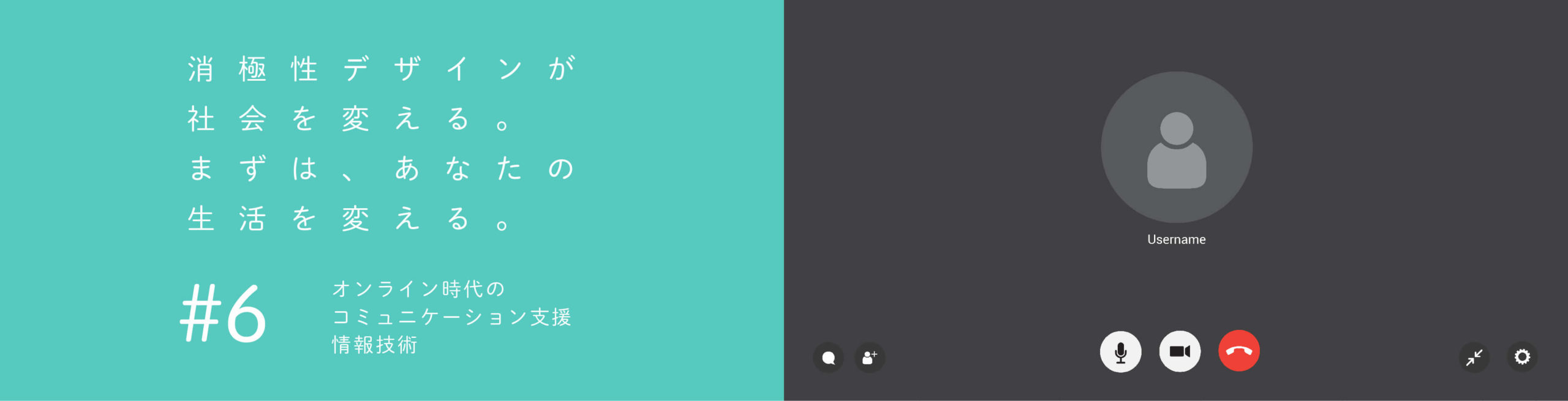
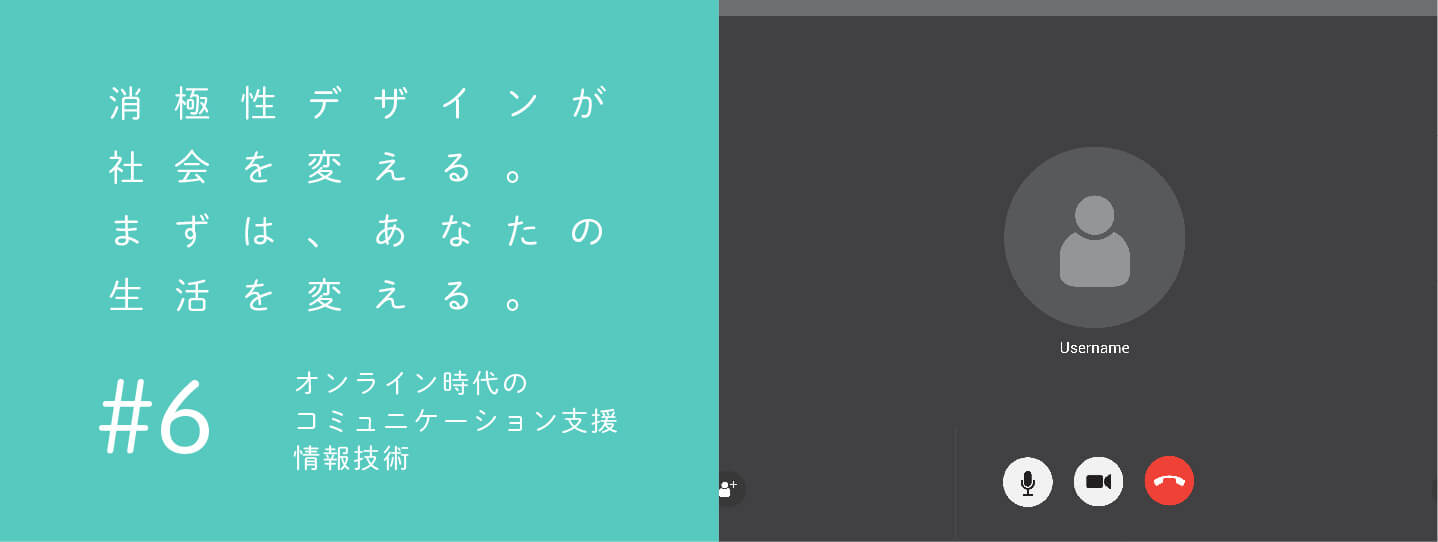 記事を読む
記事を読む人に指摘したり、注意するとき、指摘された側だけでなく、指摘する側もしんどくなってしまいませんか?今回は情報科学者の栗原一貴さんが、スマートスピーカーを利用して、言いにくいことを人に伝えやすくする仕組みを考えます。ちょっと言いにくいな、誰か代わりに言ってくれないかな……と遠慮しがちなみなさん、こんな工夫はいかがでしょうか。

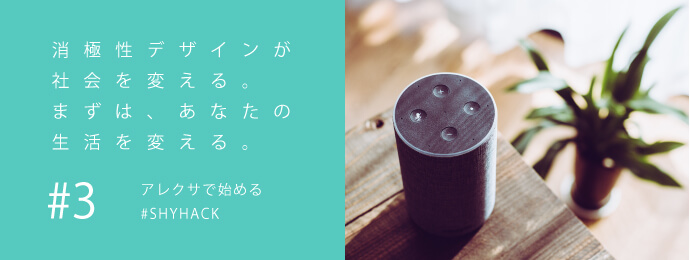 記事を読む
記事を読む