

「2023年7月」に公開された
選りすぐりの記事一覧です。






























SNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまったのがこの「庭プロジェクト」です。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、これから毎月レポートしていきます。
第1回の研究会では発案者の宇野常寛が、このプロジェクトで、何のために、何をやるのかについて何をやるのかについて話しました。会の後半では、そこでなされた問題提起に対して、「庭プロジェクト」のボードメンバーをはじめとする参加者たちが応答。「コミュニティ」でも「共創」空間でも「コモンズ」でもなく、なぜいま「庭」というキーワードを掲げるのでしょうか? 編集部メンバーの視点からそこでの議論をダイジェストし、いま都市空間に求められているプラットフォームの「外部」について考えます。
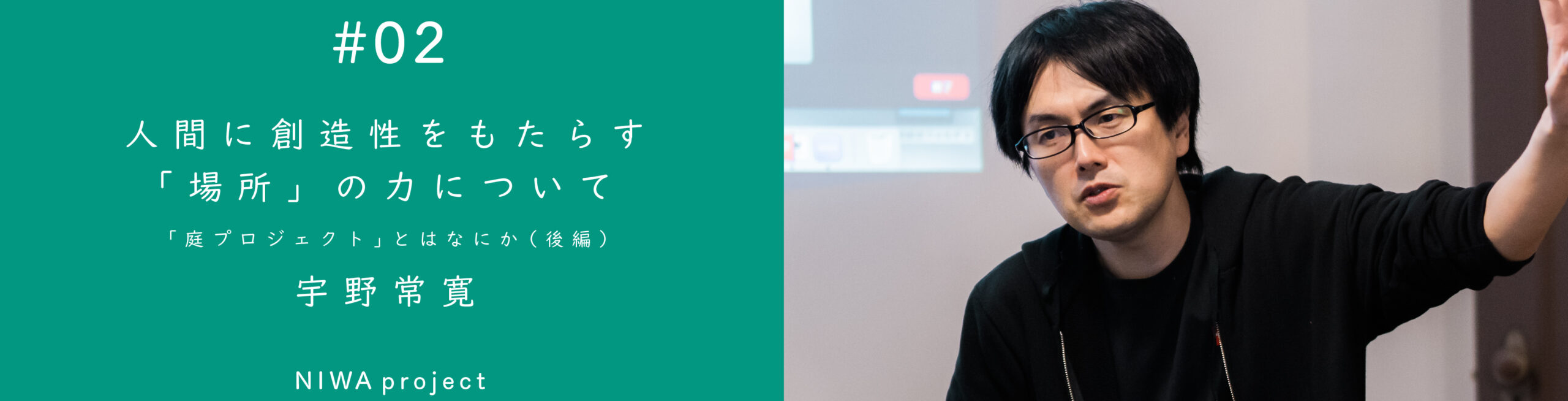
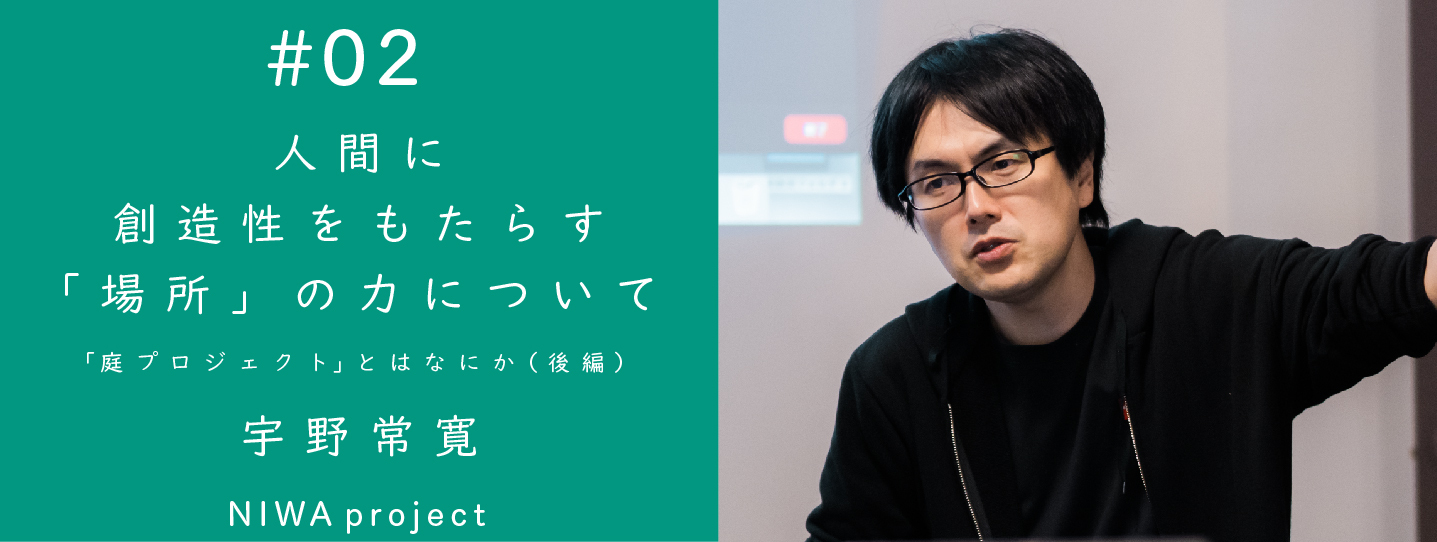 記事を読む
記事を読むSNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまったのがこの「庭プロジェクト」です。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、これから毎月レポートしていきます。
第2回の研究会ではボードメンバーである建築家・門脇耕三さんのプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。主にディスカッションされたのは、これからの公共空間のあり方を考えるうえで避けては通れない、「シェア」と「コモンズ」の問題です。この記事では編集部メンバーの視点からそこでの議論をダイジェストし、「イーロン・マスク/里山資本主義」の二択のどちらでもない、「せざるを得ない」からシェアする公共空間のあり方について考えます。
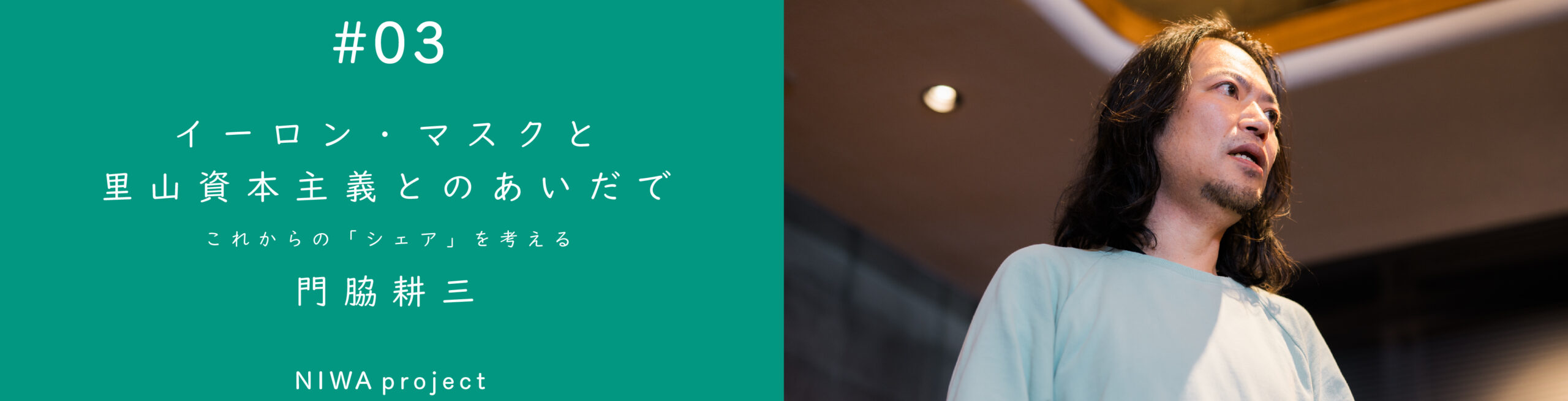
 記事を読む
記事を読む