

「渡邊恵太」さんについて取り上げた
これまでの記事の一覧をここに表示しています。






























Netflixの画面に大量に並んだコンテンツ、スマホにインストールされるたびにどんどん画面を占有していくアプリケーション……。それらの中から必要なものを能動的に選び取るのは案外煩雑なものです。
今回は消極性研究会メンバーの渡邊恵太さんが、選択肢の過多に有効なIoTの消極性デザインについて考察します。

 記事を読む
記事を読む発表の順番を決めるとき、あまったおやつの取り分を決めたいとき……そんなときの解決法といえば「じゃんけん」。このような、じゃんけんを使うときの意思決定は、どちらかといえば「どうでもいい意思決定」ではないでしょうか。
一見、簡単で合理的な方法ですが、参加人数が増えると「アイコ」が続いて時間がかかってしまうこともあります。今回は、インタラクションデザインの観点から、じゃんけんで決めてしまいがちな「どうでもいい意思決定」を効率化する方法を考えます。

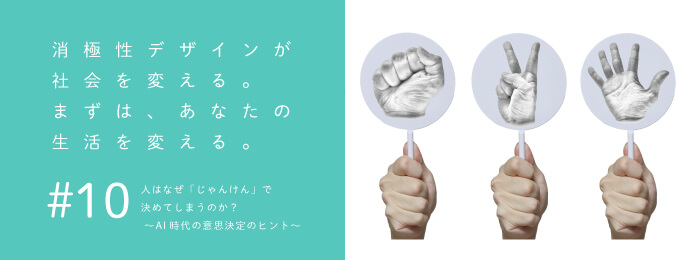 記事を読む
記事を読むコンビニに入っても、店員と会話せずにセルフレジを使用し、宅急便は宅配ボックス、置き配で受け取り、可能な限り人との接触を避けられるように行動する。今までは無機質に思えていた生活が、新型コロナウイルスの感染拡大により、「当たり前」の生活に変わってきていませんか?
今回は、インタラクションデザイン研究者の渡邊恵太さんが、一見消極的で冷たく思える、人と接触・対面せずにサービスを利用する仕組みがもたらした、快適でよりリッチな体験の可能性を考察します。

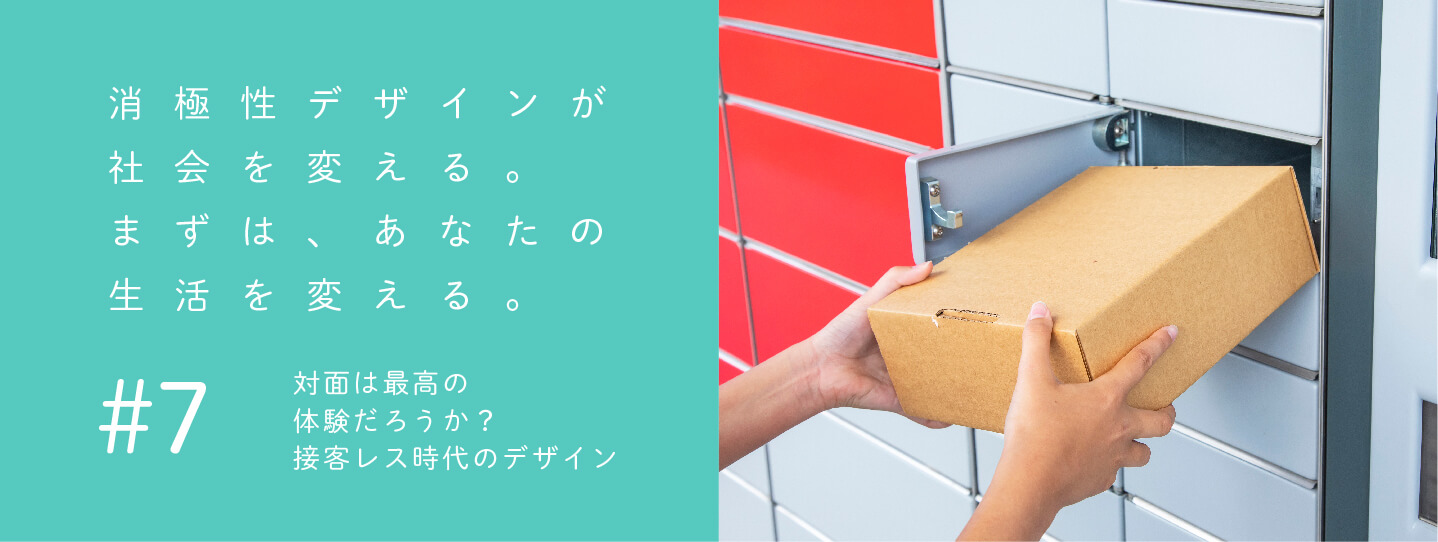 記事を読む
記事を読む情報技術とデザインによるハックで、シャイな人たちが直面するさまざまな生きづらさに向き合ってきた消極性研究会。そして、あらゆる人々が強制的に「消極的」に暮らすしかない状況が訪れた今、そのユニークな視点と知見は、どんなふうに活かしていけるのでしょうか。今回は番外編として、研究会フルメンバーが(もちろんリモートで)集結し、With/Afterコロナ時代の暮らしと社会を搦め手から考える座談会を行いました。

 記事を読む
記事を読むNetflixを開いて、「今日は何を見ようかな」と悩んでいるうちに時間が経ってしまっていたこと、ありませんか? 居酒屋で、「じゃあ、とりあえずコレで」と注文する串カツ盛り合わせのように、スムーズに決められないのはどうしてなのでしょうか。
工学者の渡邊恵太さんが、串カツ盛り合わせにあって、Netflixにはない、決めやすさの理由を考えます。

 記事を読む
記事を読む