

「橘宏樹」さんについて取り上げた
これまでの記事の一覧をここに表示しています。






























現役官僚である橘宏樹さんが、「中の人」ならではの視点で日米の行政・社会構造を比較分析していく連載「現役官僚のニューヨーク駐在日記」。
ロシアのウクライナ侵攻に対するリアクションが街のそこかしこに現れ、有事の空気感が漂う中で、先端的なニューヨーカーたちが日常の足として使う電動キックボードが象徴する、イノベーションに対するメンタリティについて考察します。

 記事を読む
記事を読む現役官僚である橘宏樹さんが、「中の人」ならではの視点で日米の行政・社会構造を比較分析していく連載「現役官僚のニューヨーク駐在日記」。
今回は、ニューヨークひいてはアメリカ社会で大きな存在感をもつユダヤ系の人々について。市内人口の9%を占め、金融・経済・政治・メディアの重要局面で絶大な影響力を発揮するユダヤ人社会が、現在どのような状況にあるのかをタイプ別に解説します。

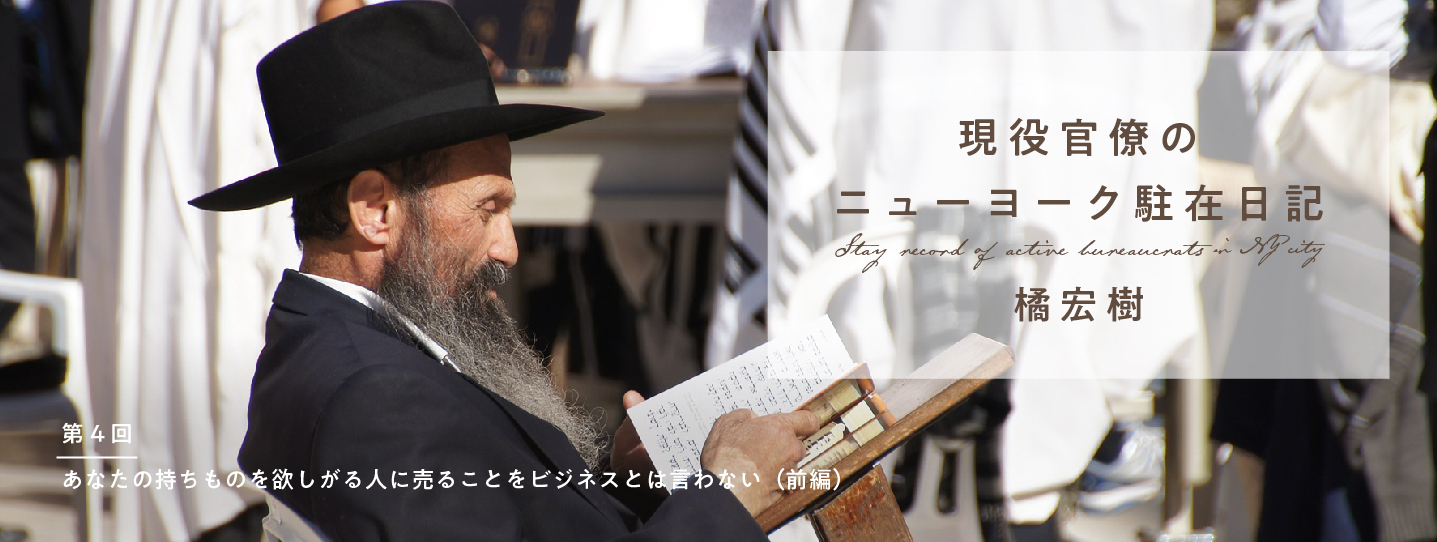 記事を読む
記事を読む現役官僚である橘宏樹さんが、「中の人」ならではの視点で日米の行政・社会構造を比較分析していく連載「現役官僚のニューヨーク駐在日記」。
今回は、コロナ禍での政府の意思決定のあり方について。アメリカの行政の説明責任への考え方、そして社会の分断に選挙制度の工夫で対抗しようとする試みについて考えます。

 記事を読む
記事を読む今日から、現役官僚である橘宏樹さんによる新連載「現役官僚のニューヨーク駐在日記」が始まります。これまでPLANETSでは「現役官僚の滞英日記」や「GQ(Governement Curation)」の連載を通して、「中の人」ならではの視点から政界の裏側や政治と生活との結びつきを紹介してくれた橘さん。
本連載では、ニューヨークへの赴任から1年を経たタイミングで、橘さんが改めて感じたアメリカの政治風土を日本の読者向けに紹介していきます。第1回は連載全体の見通しと、外国人参政権が可決されたことに対する橘さんならではの見解について。

 記事を読む
記事を読む菅政権の発足で、総理交代という久々の一大イベントに見舞われている霞が関。そんな中で、かつて「最大最強のシンクタンク」であったはずの日本の官僚機構が構造的に「情弱」化し、深刻な危機に陥りつつあると、現役官僚の橘宏樹さんは憂慮します。官僚が本来のパフォーマンスを発揮するためには何が必要か、「中の人」ならではのリアリティから検証します。
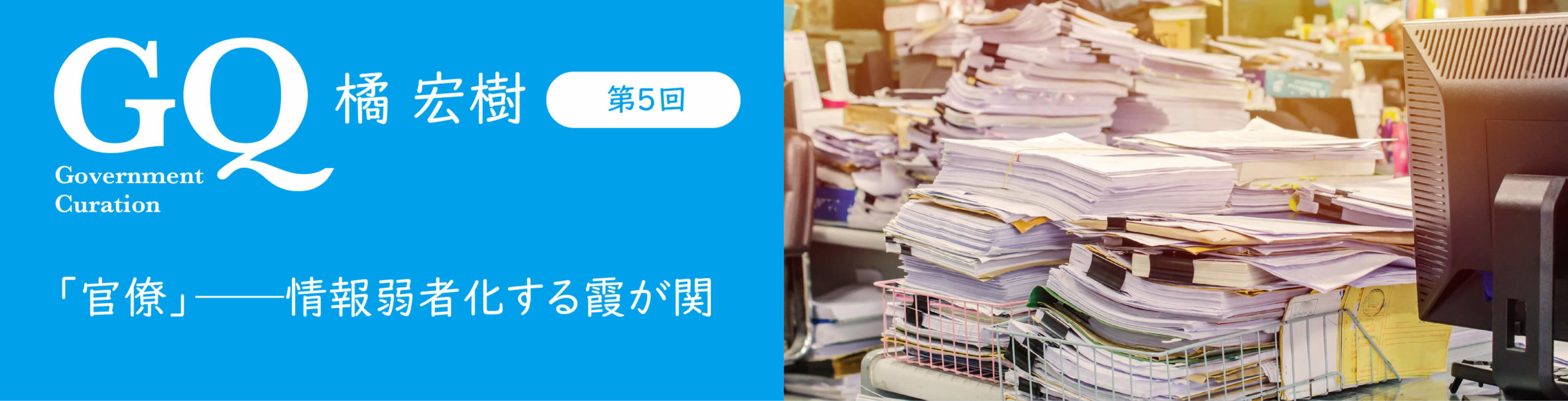
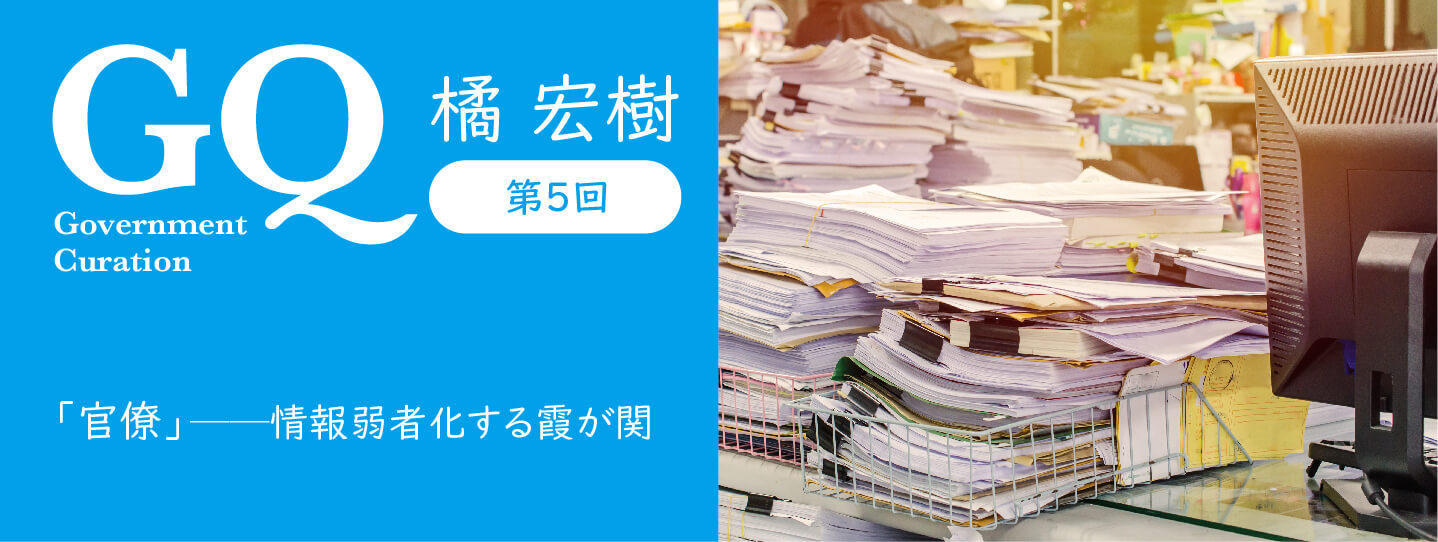 記事を読む
記事を読むこの夏、内閣の経済・財政の最も根本的な運営の軸を定める「骨太の方針2020」が閣議決定されました。「新しい日常」のための徹底した行政のデジタル化を目玉に掲げつつ、決定直前に駆け込むように盛り込まれたのが、「中央銀行デジタル通貨」をめぐる2行の文言でした。これからの日本の行く末に関わるかもしれないその意味を、現役官僚・橘宏樹さんが読み解きます。

 記事を読む
記事を読む国が国である以上、外すことのできない最も基幹的な公機能のひとつ「教育」。しかし社会に適合する標準的な「国民」を再生産すればよかった時代はとうに去り、いまの教育に求められているのは、「いかに個々の資質や状況に応じた多様性を尊重しつつ、社会を変えうる個人を育むか」の標準化です。この矛盾に満ちたミッションを、現役官僚・橘宏樹さんがチェックします。

 記事を読む
記事を読む出口の見えないコロナ禍の下で、生活者があらためて目を向けておかなければならない国家的な課題とは何か。今回、現役官僚の橘宏樹さんの目に留まったのは、近年、深刻な危機を迎えている「流通」です。物流を支えるトラック運転手の人手不足への対応やブラックな業界慣行の改革など、効率化と労働者保護に向けた各省庁の取り組みを吟味します。

 記事を読む
記事を読むこの国の未来のために「ほんとうに大事なこと」は、どのように決められているのでしょうか。Government Curation略して「GQ」では、現役官僚の橘宏樹さんが、メディアが報じない重要政策の動向を、折々の「官報」などから読み解きます。今回のテーマは「スーパーシティ」。人工知能やビッグデータの活用で世界最先端の未来都市の実現を目指すというこの特区構想のなりたちを検証しつつ、どんな勝算や課題があるのかを考えます。

 記事を読む
記事を読む