

これまでに更新した記事の一覧です。






























メガシティへの人口集中や気候変動により高まる災害リスク、そしてコロナ禍による生活様式の変化など、人類がずっと使い続けてきた「都市」という環境が、いま大きな曲がり角を迎えています。新雑誌『モノノメ 創刊号』では、生環境構築史というビジョンのもと都市や建築の歴史と現在を研究する松田法子さんが、台地と低地のキワにあらわれる「湧水」を入口に、東京という土地を改めてどんなふうに再発見できるのかを実際に歩きながら探り、これからの都市のあり方を洞察した長編論考を掲載しています。
その貴重なフィールド調査の記録を、ほんのさわりですが、誌面に掲載しきれなかった地形図・ルート図をまじえつつ抜粋掲載します。

 記事を読む
記事を読む国際コンサルタントの佐藤翔さんによる連載「インフォーマルマーケットから見る世界──七つの海をこえる非正規市場たち」。
今回は、ナイジェリアで発展するインフォーマルビジネスの背景と実像に迫ります。石油産業を中核にアフリカ屈指の経済大国へと成長しつつある一方で、政治的・軍事的には非常に不安定なナイジェリア。そんな環境のもとで生まれてきた新たなコンテンツ産業のクリエイティビティとは?

 記事を読む
記事を読む「インフルエンサー」台頭の影で、TVや出版・レコード会社などの老舗産業で特定のスキルを発揮しながら活躍する「プロ」の影響力は相対的に弱まっているようにも思えます。この流れに楔を打つ可能性があるのが、昨今注目を浴びはじめている「クリエイターエコノミー」です。果たして、インターネットをインフルエンサーの寡占から解放することは可能なのでしょうか? ジャーナリスト・専門家・作家などの個人向けニュースレター配信サービス「theLetter」を運営する濱本至さんに、事業者としての視点から、試論を展開してもらいました。

 記事を読む
記事を読むリサーチャー・白土晴一さんが、心のおもむくまま東京の街を歩き回る連載「東京そぞろ歩き」。今回歩いたのは、JR総武線の浅草橋駅から蔵前にかけてのエリア。多くの人が“浅草”と間違えて彷徨う「浅草橋トラップ」にあえて嵌まりながら、歴史ある日本有数の雑貨問屋街の周辺に垣間見える、昔ながらの街並みと現代的なセンスの再活用のおもしろさを堪能してきました。

 記事を読む
記事を読むNetflixの画面に大量に並んだコンテンツ、スマホにインストールされるたびにどんどん画面を占有していくアプリケーション……。それらの中から必要なものを能動的に選び取るのは案外煩雑なものです。
今回は消極性研究会メンバーの渡邊恵太さんが、選択肢の過多に有効なIoTの消極性デザインについて考察します。

 記事を読む
記事を読む「中東で一番有名な日本人」こと鷹鳥屋明さんが等身大の中東の姿を描き出す本連載。今回は2017年11月にクウェートで行われた「WAWAN CLASSIC 2017」というボディビル選手権に招待され、筋骨隆々の選手たちを間近で見てきたという鷹鳥屋さんに、珍しいイベントの様子を写真入りでレポートしていただきました。

 記事を読む
記事を読む滋賀県のとある街で、推定築130年を超える町家に住む菊池昌枝さん。この連載ではひょんなことから町家に住むことになった菊池さんが、「古いもの」とともに生きる、一風変わった日々のくらしを綴ります。今回は、前の住民から引き継がれた古道具たちが主人公です。古民家とともに歴史を刻んできたさまざまな「もの」たち。それらを使い続け、時には人に譲り、引き継いでいくことの意味について考えます。

 記事を読む
記事を読む国際コンサルタントの佐藤翔さんによる連載「インフォーマルマーケットから見る世界──七つの海をこえる非正規市場たち」。
今回は地中海東西のイスラエルとモロッコのインフォーマルマーケットを紹介します。片やハイテク中のハイテクでグローバルビジネスを展開、片やローテクの掘っ立て小屋で北アフリカのIT産業の裾野を広げている二つの「バレー」の実態に迫り、それぞれが果たしている起業文化への影響を考察します。

 記事を読む
記事を読む「好きを仕事に」だけが正解なのでしょうか? あえて仕事にせず、「趣味」として真剣に取り組む道だってあるはずです。休息や気晴らしではなく、自分のやりたいことを実現するために行われる趣味である「シリアスレジャー」について、余暇研究と学習科学の学際的な立場から趣味を研究している杉山昂平さんに寄稿してもらいました。趣味としてやっていく選択肢の意味から、楽しみ方の学習や学習環境デザインの必要性まで、シリアスレジャーの現在地と可能性に迫ります。

 記事を読む
記事を読むリサーチャー・白土晴一さんが、心のおもむくまま東京の街を歩き回る連載「東京そぞろ歩き」。今回は眠らない街・新宿歌舞伎町を歩きます。関東大震災後と戦後の2度の復興計画を契機に生まれ変わり、日本を代表する歓楽街として発展を遂げてきた歌舞伎町は、コロナ禍を経て現在どんな素顔を見せているのか。白土さんがそのカオスな魅力に迫ります。
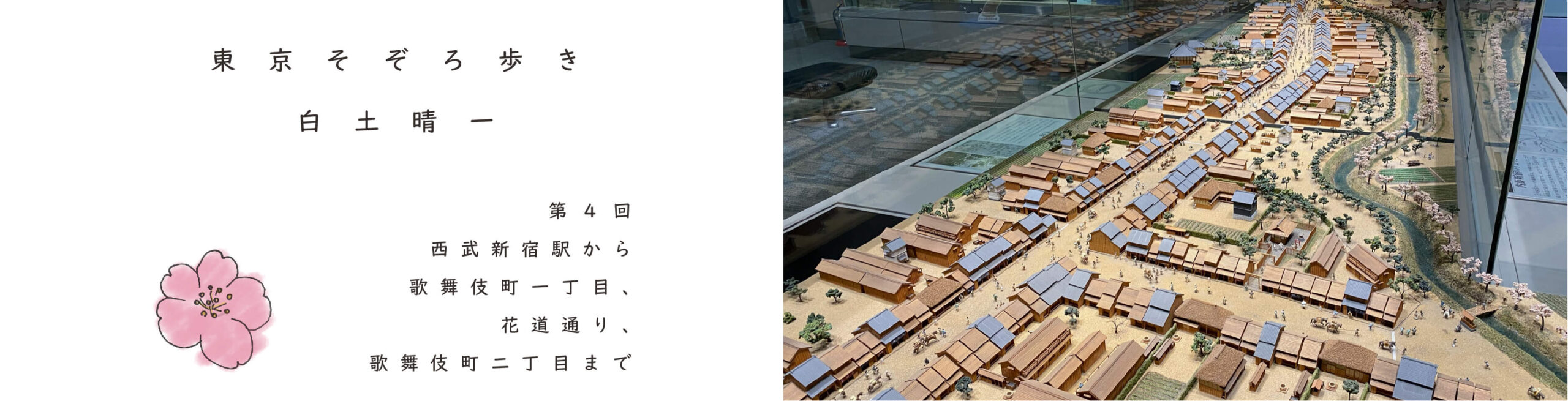
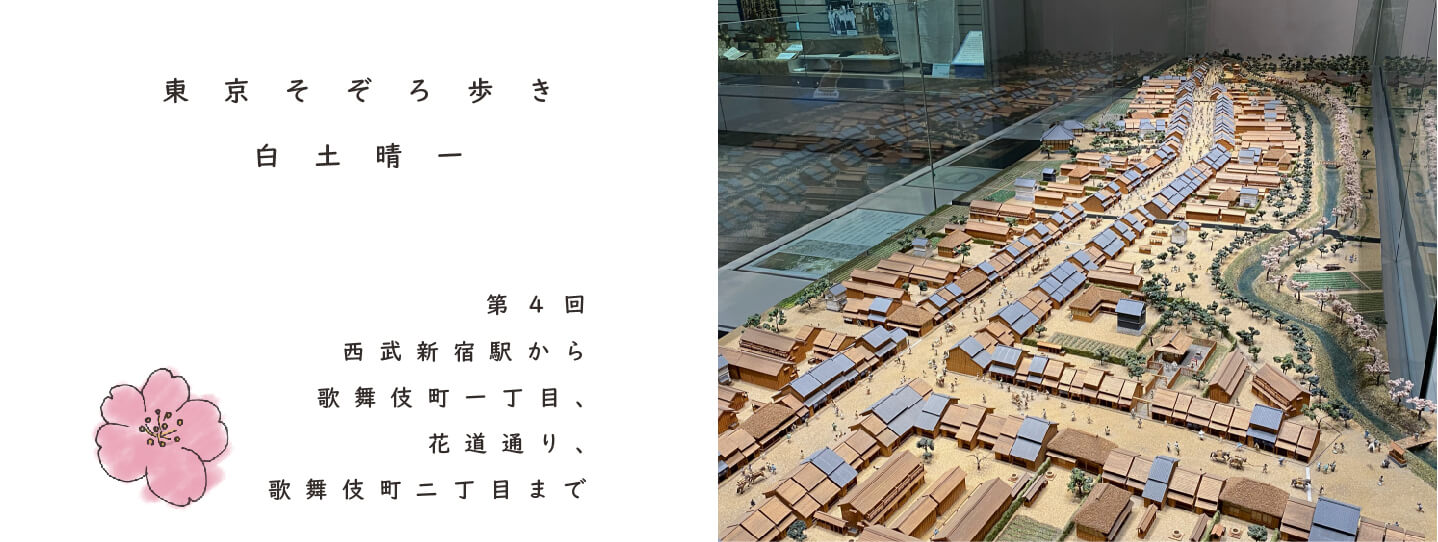 記事を読む
記事を読むデザイナー/小説家の池田明季哉さんが20世紀末のボーイズトイデザインを振り返る連載「“kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝」。今回から、90年代半ばにブームとなったビーダマンシリーズを取り上げます。銃器を想起するデザインに潜んだ暴力性に対し、競技ルールに忠実に則る少年たちの「倫理」はどのように立ち向かったのか。
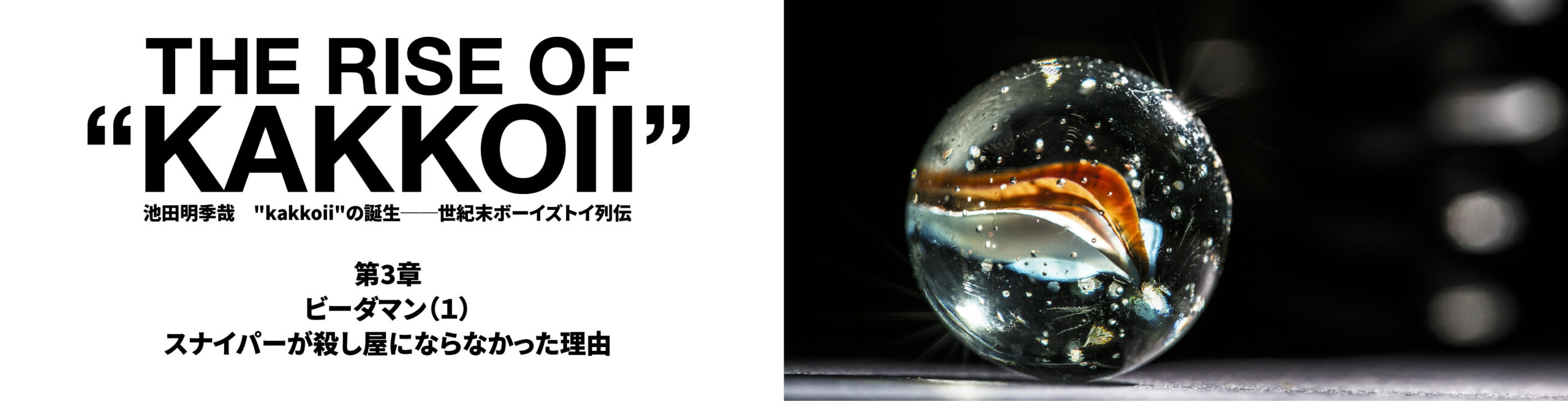
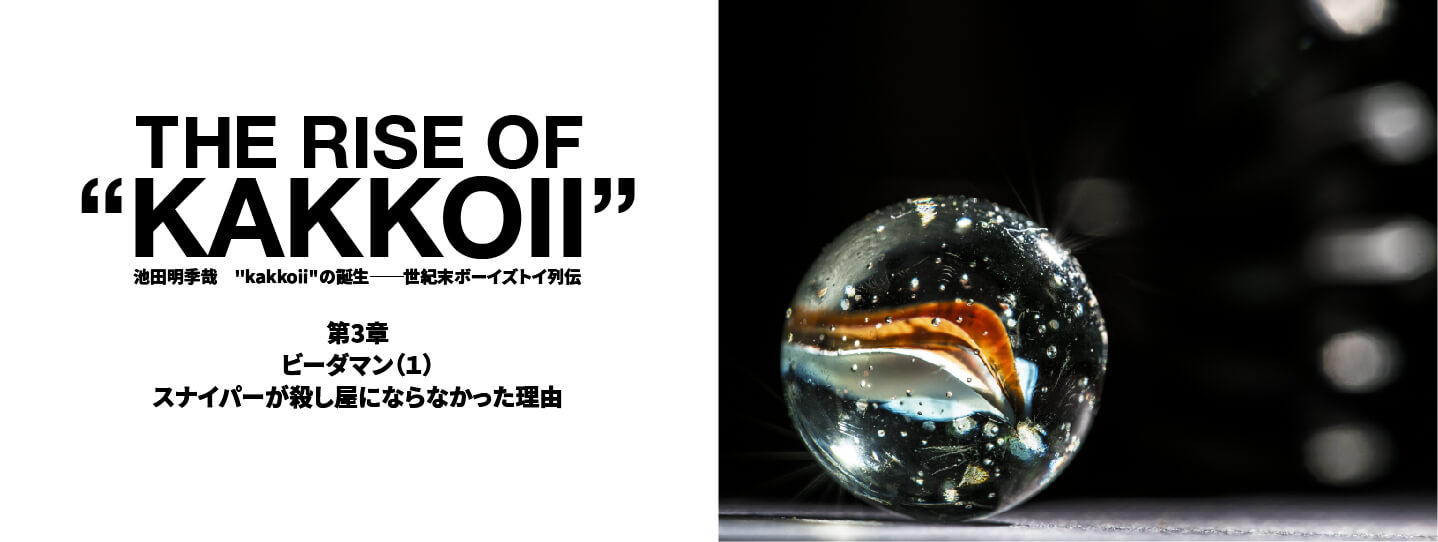 記事を読む
記事を読むチャットツールを使ったリモートワークもいまや当たり前のものとなりつつありますが、オフラインであれば感じ取れるはずの組織の雰囲気がつかみにくかったりすると、コミュニケーションに問題が生まれてしまいます。
今回は、実際に会社員としてチャットツールを使いながら働く簗瀬さんに、リモートコミュニケーションを円滑に進めるためのコツを紹介していただきました。

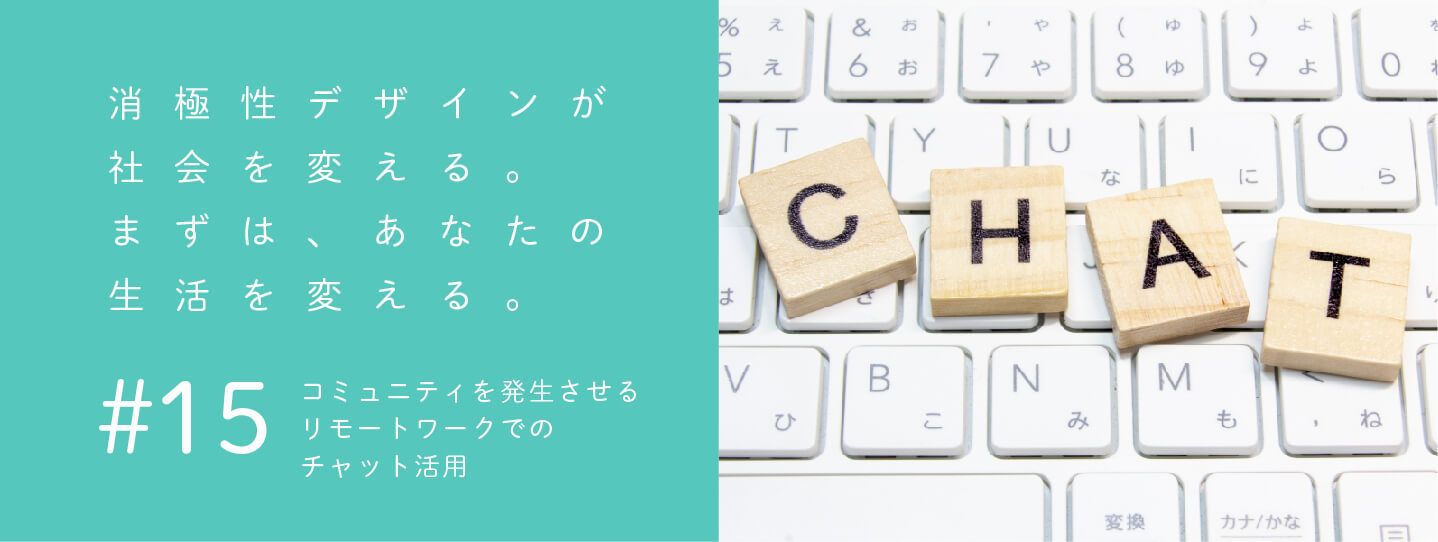 記事を読む
記事を読む