

これまでに更新した記事の一覧です。






























「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。
今回の研究会では、ゲストに招いた都市デザイン研究者の中島直人さんによるプレゼンテーション、そして参加者によるディスカッションが行われました。テーマは庭プロジェクトによる「神奈川県藤沢市及び鎌倉市への提案書:村岡・深沢地区の再開発について」を踏まえた、これからの都市デザインのあり方です。前編では、中島さんによるプレゼンテーションの内容をお届けします。
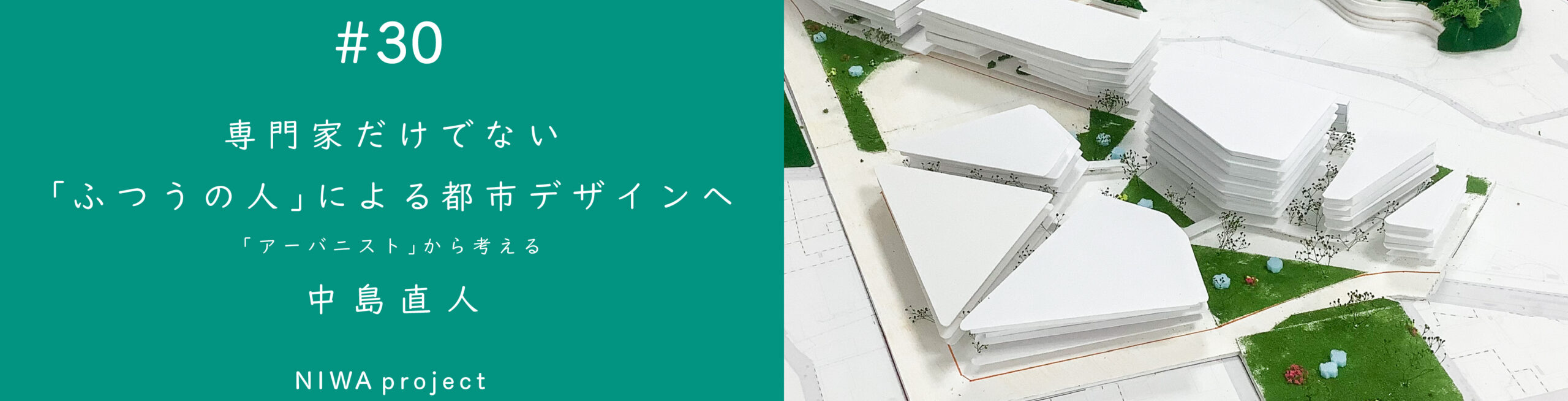
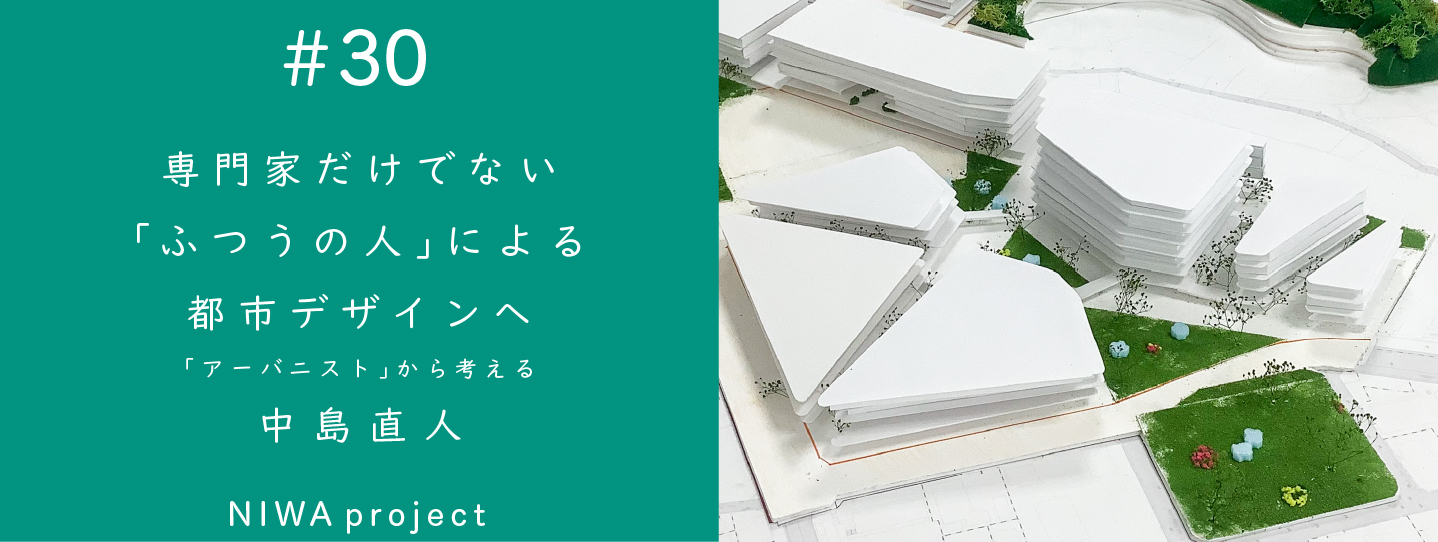 記事を読む
記事を読むデザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回は「変身サイボーグ」の後継シリーズ『ミクロマン』を分析します。サイズが12インチから3.75インチへと小型化したことで、〈少年=遊び手〉と〈玩具〉の関係がどう変わったのかを考えます。

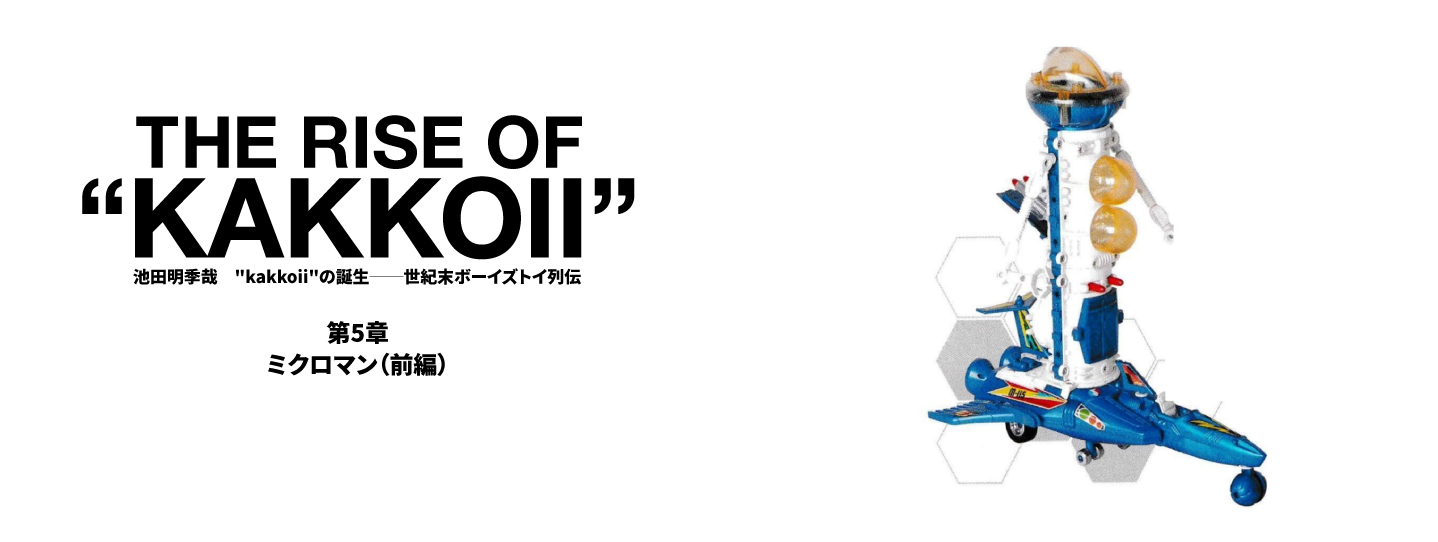 記事を読む
記事を読むゲーム研究者の井上明人さんによる連載「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。「ゲームや遊びとは何か?」。この問いに答えるべく、ゲームや遊びに関わる多様な現象——ルール、コミュニケーション、非日常など——が興味深いかたちで相互に関係しあっている、その複雑さを論じます。第2部では、これまでの議論を手がかりに「ゲームとは何か」という問いを考える方向性を整理していきます。
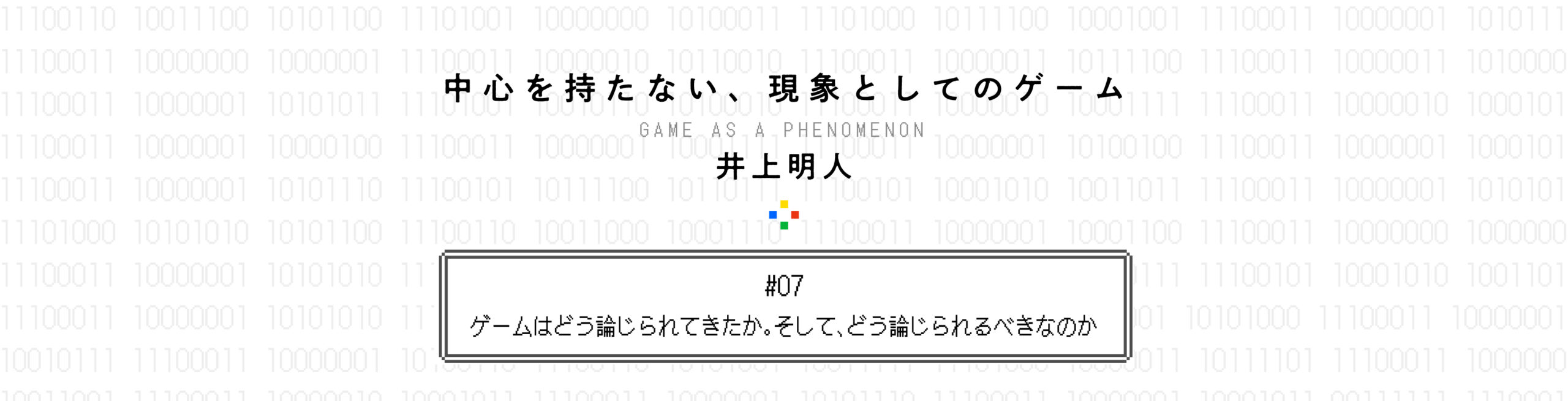
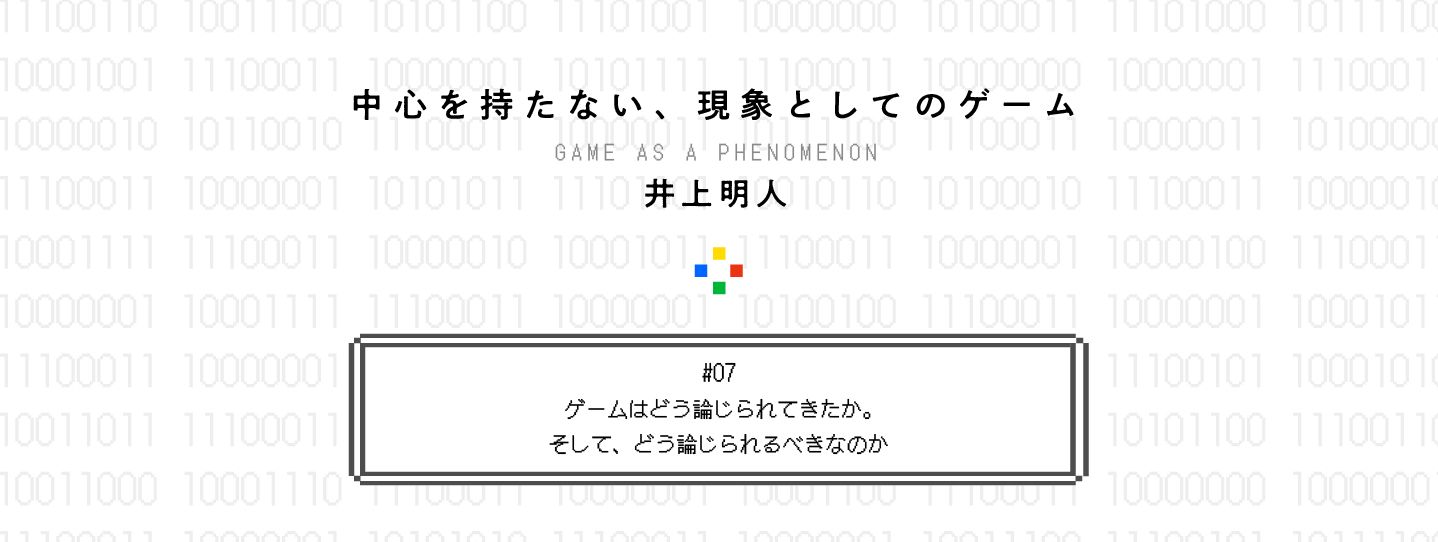 記事を読む
記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。
今回の研究会では、ゲストに招いたランドスケープ・アーキテクトの石川初さんによるプレゼンテーション、そして参加者によるディスカッションが行われました。テーマはランドスケープデザインの現在地と展望です。後編では、石川さんによるプレゼンテーションを踏まえた、参加者を交えたディスカッションの内容をお届けします。

 記事を読む
記事を読むデザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回は前回に引き続き『勇者王ガオガイガー』を分析します。玩具主導の勇者シリーズがロボットアニメへと転換した流れを読み解きます。

 記事を読む
記事を読むゲーム研究者の井上明人さんによる連載「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。「ゲームや遊びとは何か?」。この問いに答えるべく、ゲームや遊びに関わる多様な現象——ルール、コミュニケーション、非日常など——が興味深いかたちで相互に関係しあっている、その複雑さを論じます。第6回は、遊び手、作り手、実況者など第三者の相互作用により、ゲームの概念範囲を拡張し続ける過程を読み解きます。
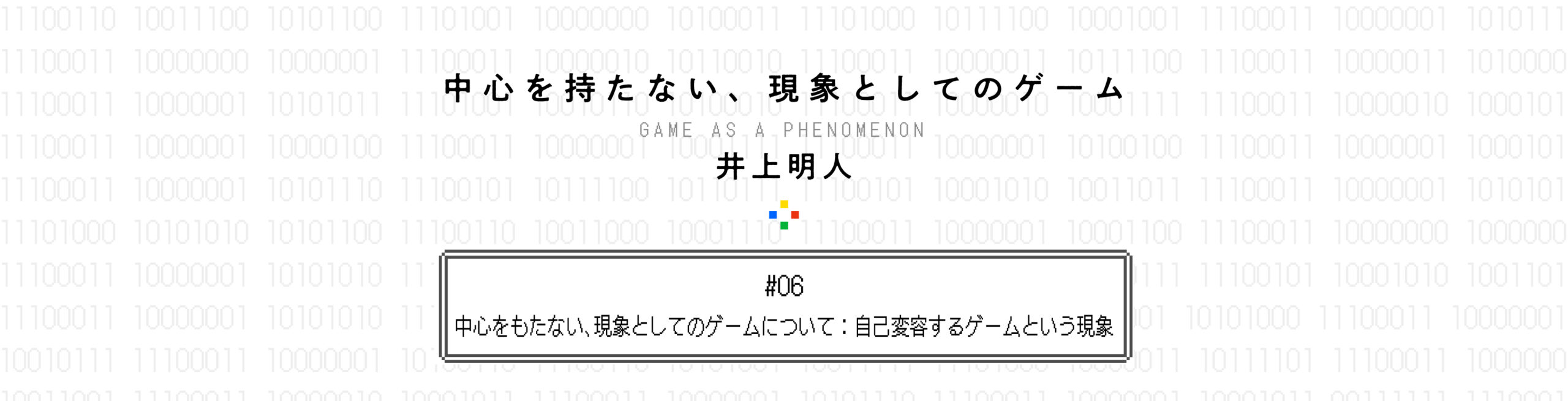
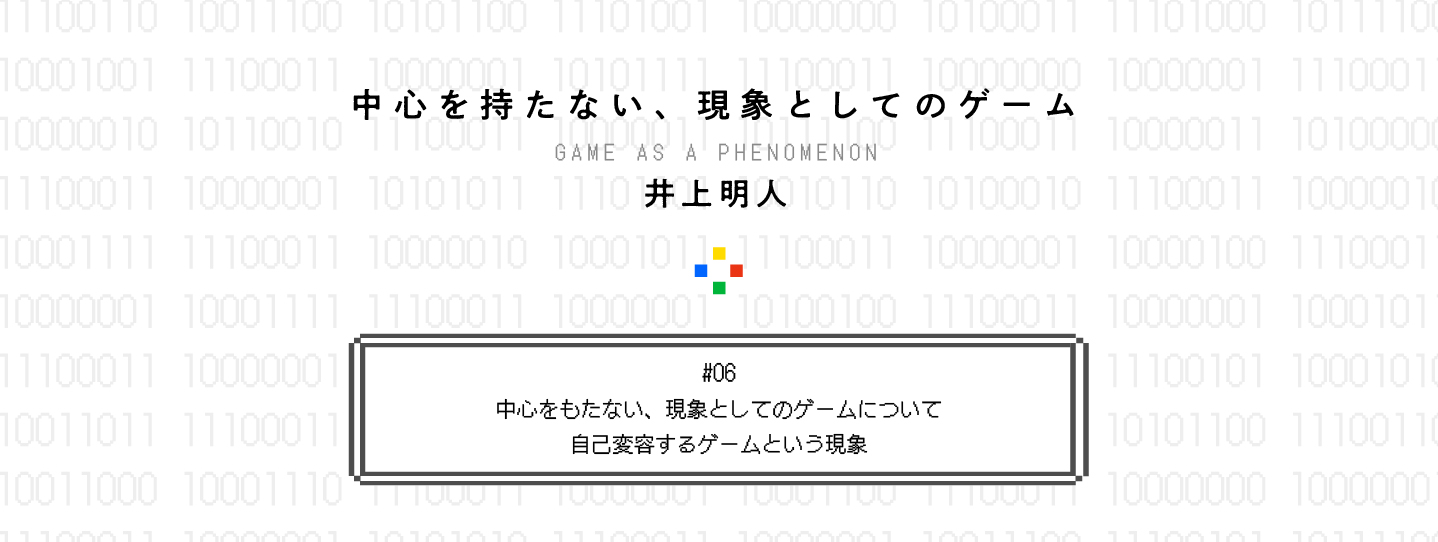 記事を読む
記事を読むデザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。勇者シリーズの最終作『勇者王ガオガイガー』は、歴代随一の人気作でありながら異端作だとも言われます。今回は、その「異端にして集大成」という二面性を読み解きます。

 記事を読む
記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。
今回の研究会では、ゲストに招いたランドスケープ・アーキテクトの石川初さんによるプレゼンテーション、そして参加者によるディスカッションが行われました。テーマはランドスケープデザインの現在地と展望です。前編では、石川さんによるプレゼンテーションの内容をお届けします。

 記事を読む
記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。
今回の研究会では、ゲストに招いた地域プロデューサーの古田秘馬によるプレゼンテーション、そしてそれを受けての参加者によるディスカッションが行われました。テーマは古田さんが近年精力的に活動する香川県・三豊市の事例から考える、これからの地域活性化です。
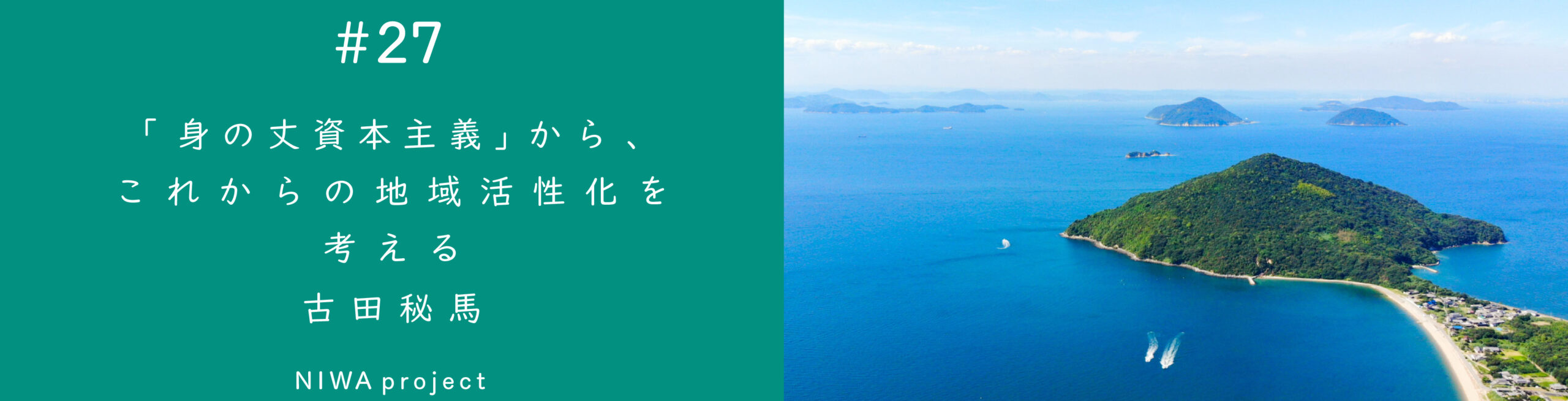
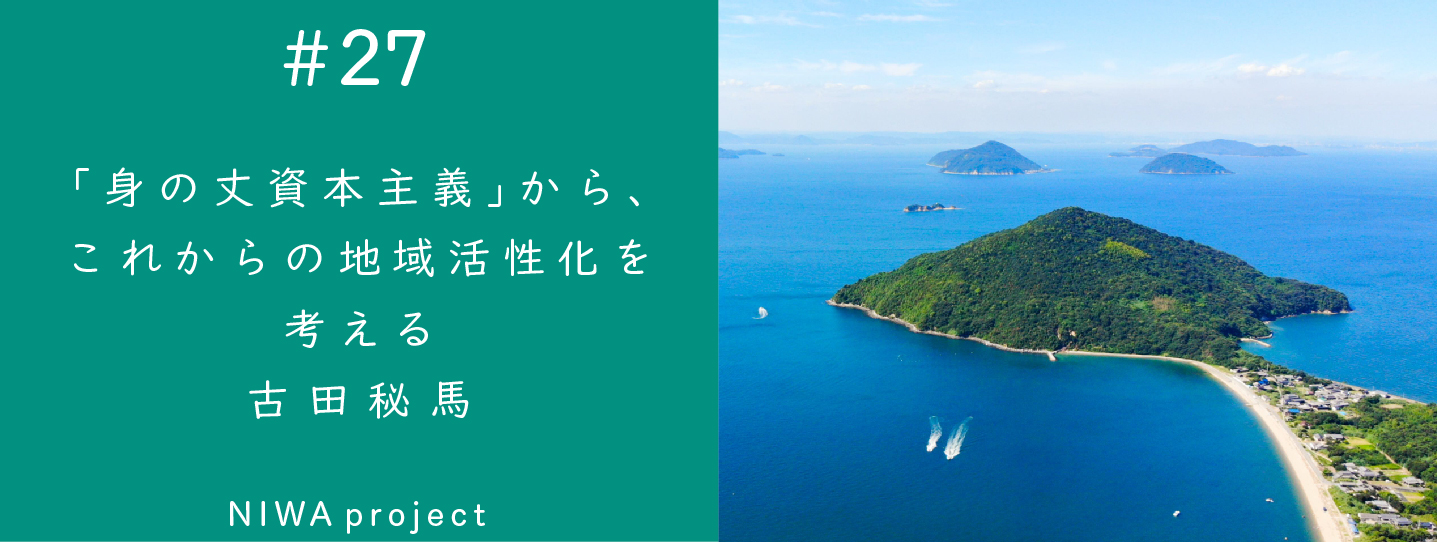 記事を読む
記事を読むデザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回は前回に引き続き『勇者指令ダグオン』を分析します。「絶対にして完璧な存在」となる誘惑を断ち切り「青春」を優先した主人公・大堂寺 炎。成熟のイメージという観点からは、どのように読むことができるのでしょうか?
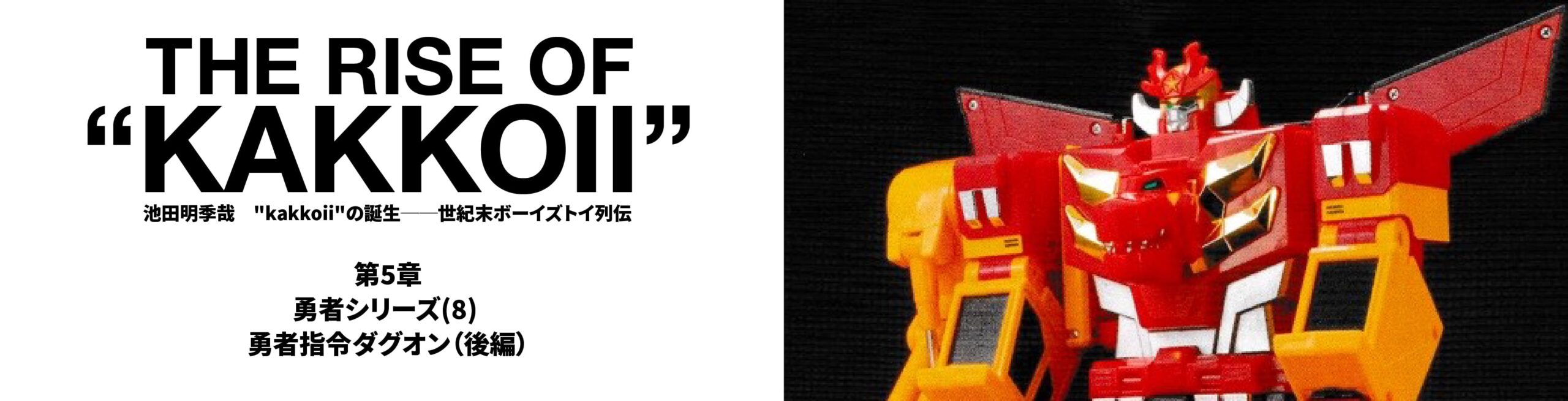
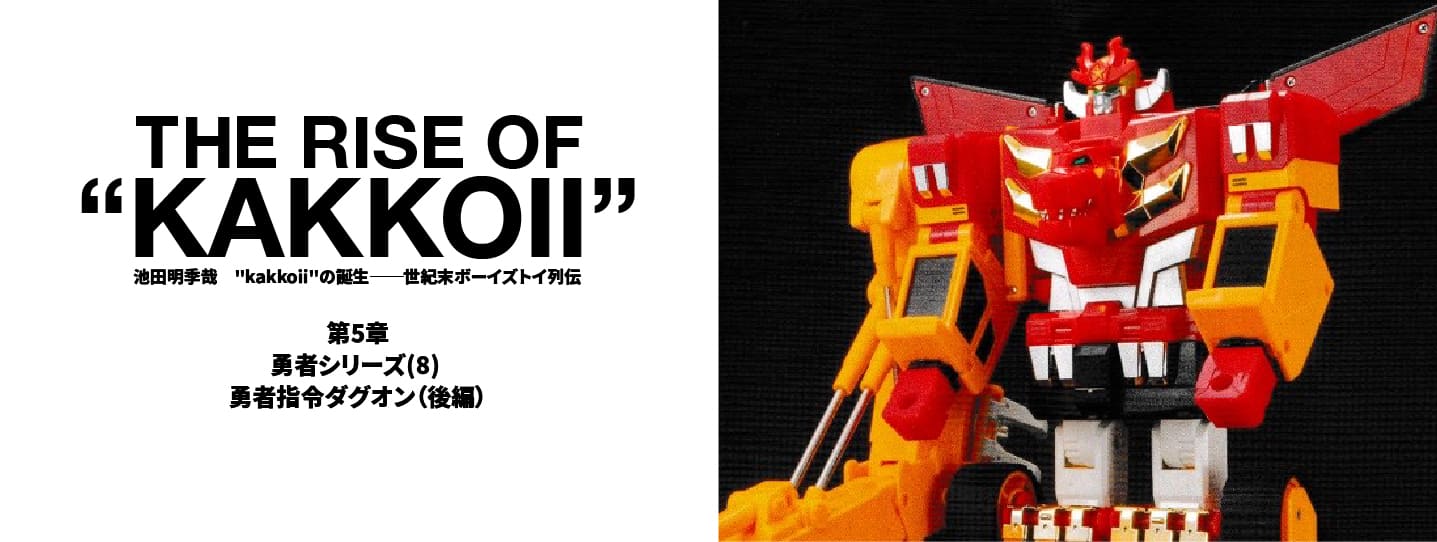 記事を読む
記事を読むゲーム研究者の井上明人さんによる連載「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。「ゲームや遊びとは何か?」。この問いに答えるべく、ゲームや遊びに関わる多様な現象——ルール、コミュニケーション、非日常など——が興味深いかたちで相互に関係しあっている、その複雑さを論じます。第5回は、音楽のリズムやファッションのセンス、さらには功利主義の思考までも“ゲームの快”へ組み替える〈変換〉のメカニズムに注目します。
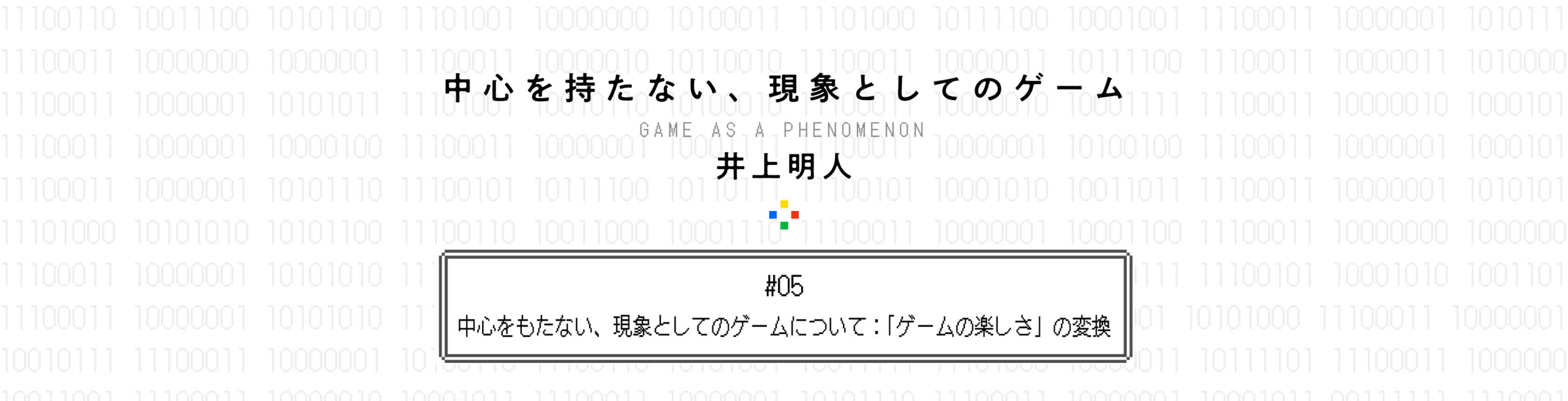
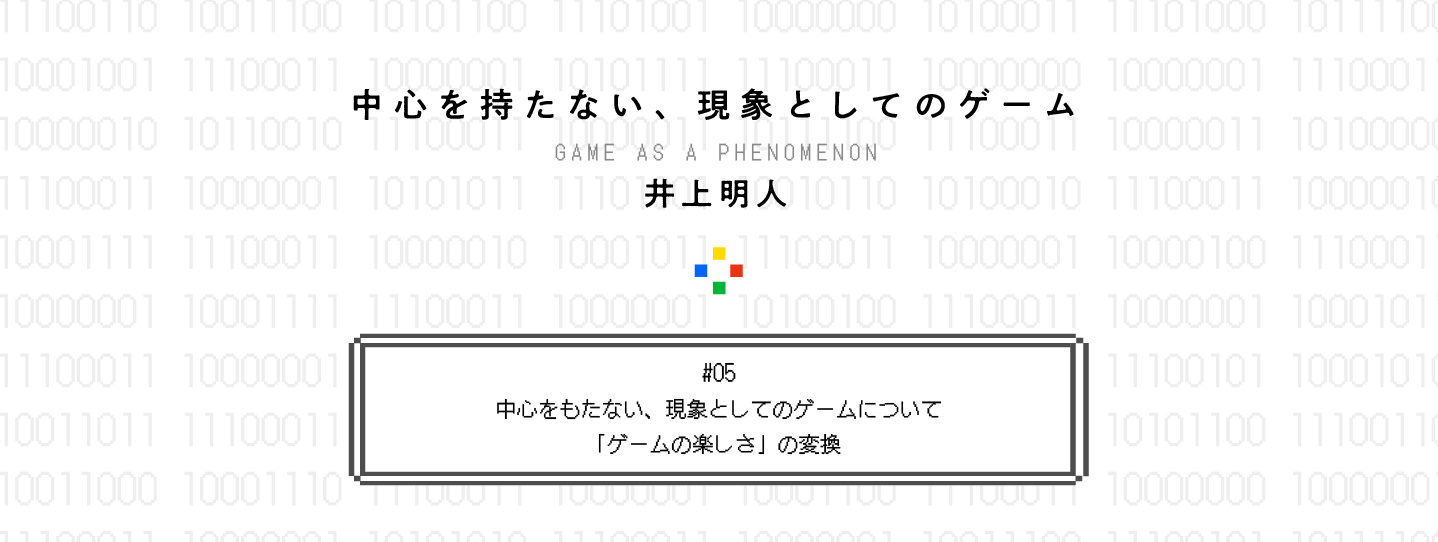 記事を読む
記事を読むゲーム研究者の井上明人さんによる連載「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。「ゲームや遊びとは何か?」。この問いに答えるべく、ゲームや遊びに関わる多様な現象——ルール、コミュニケーション、非日常など——が興味深いかたちで相互に関係しあっている、その複雑さを論じます。第4回では、プレイヤーをあえて受動的にさせる作品群を手がかりに、ぼんやりと風景を眺める“手持ち無沙汰”の時間がどのようにして新たな面白さと没入を生み出すのかを探ります。
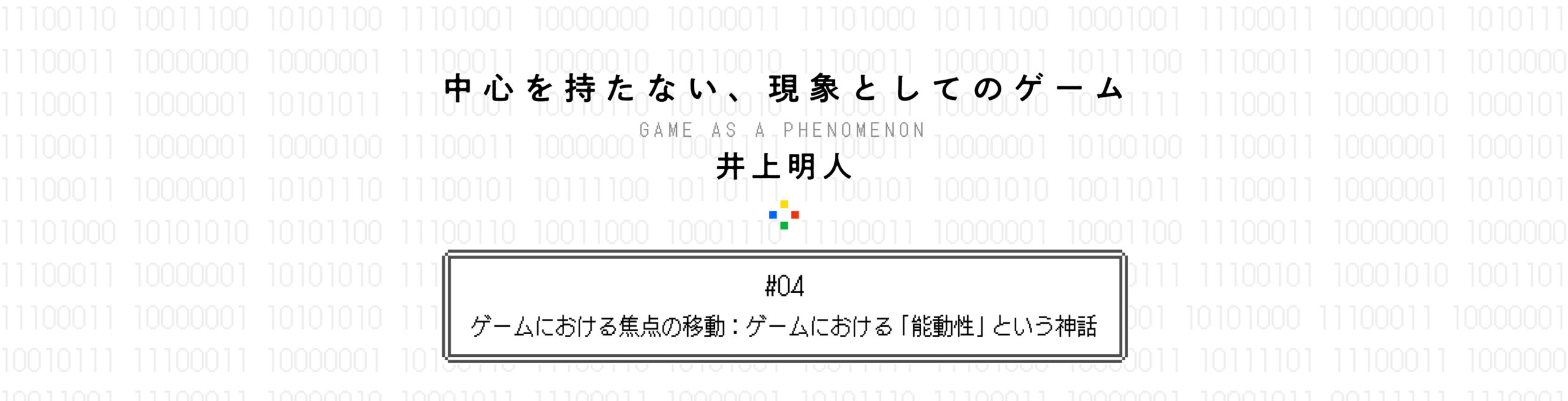
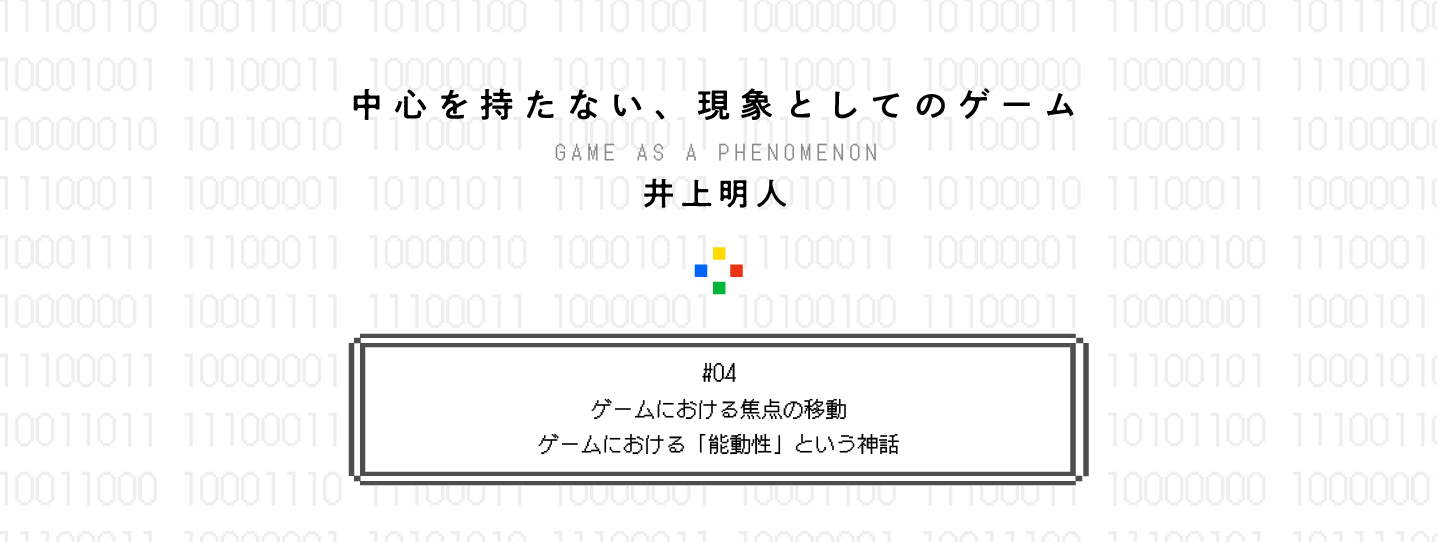 記事を読む
記事を読む