

「2020年8月」に公開された
選りすぐりの記事一覧です。






























この夏、内閣の経済・財政の最も根本的な運営の軸を定める「骨太の方針2020」が閣議決定されました。「新しい日常」のための徹底した行政のデジタル化を目玉に掲げつつ、決定直前に駆け込むように盛り込まれたのが、「中央銀行デジタル通貨」をめぐる2行の文言でした。これからの日本の行く末に関わるかもしれないその意味を、現役官僚・橘宏樹さんが読み解きます。

 記事を読む
記事を読むみんなで集まって一緒に遊ぶことが、いろいろ難しい世の中になってしまいました。これまでのように羽目を外せないことに、フラストレーションを溜めている人も多いかもしれません。けれども心配ご無用です。当代きっての遊びの達人・AR三兄弟の川田十夢さん、ゲーム研究者の井上明人さんをお招きし、本誌編集長と副編集長で寄ってたかって、世界がこうなってしまったからこその「新しい遊び」を、徹底的に考えました。さあ、一緒に(ならずに)あそびましょう!
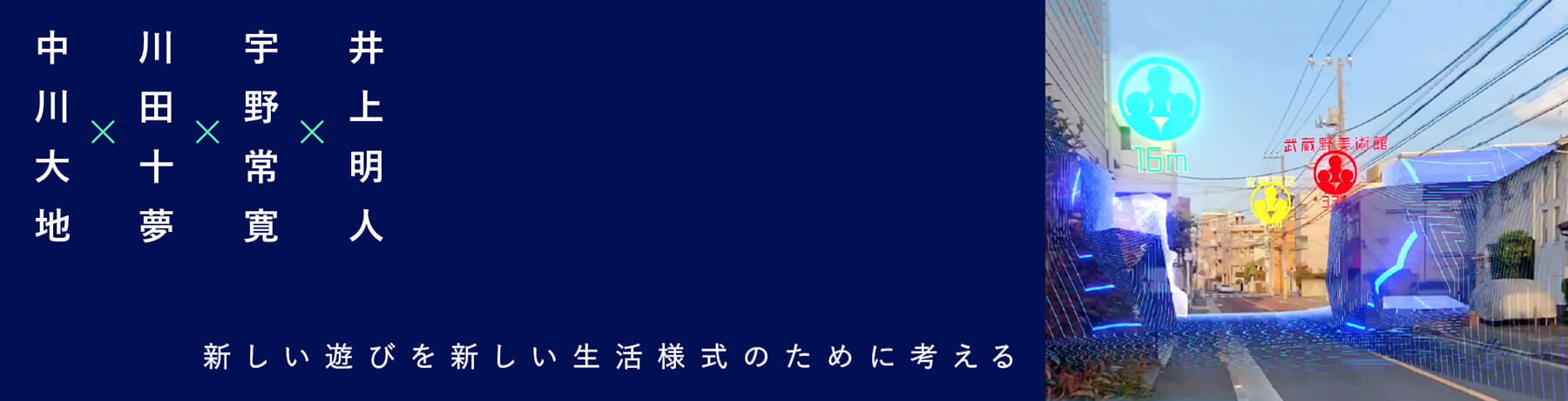
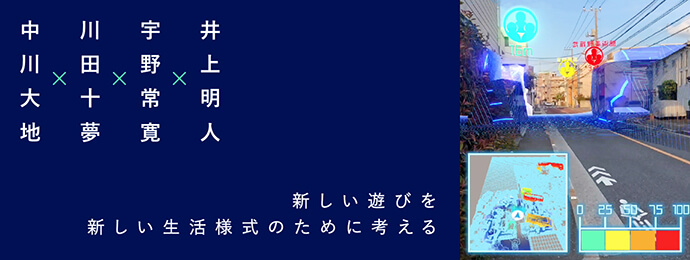 記事を読む
記事を読むアート集団チームラボ代表・猪子寿之さんと宇野常寛の連続対談「連続するものすべては美しい」。今回は2020年7月から福岡に新設された常設ミュージアム「チームラボフォレスト – SBI証券」がテーマです。「捕まえて集める森」「運動の森」という、デジタルテクノロジーでできた2つの森が、ふだん現代人が忘れている感覚をどのように解放するのか、語り合いました。

 記事を読む
記事を読む「不要不急」の外出がはばかられる状況はまだまだ長引きそうで、特に苦しい立場に置かれている業界のひとつが、音楽や演劇といったライブエンターテインメントの世界です。先々の公演予定が真っ白になっていくなか、この危機を逆手に、リモート環境で観客を物語世界に巻き込んでいく「イマーシブ(没入)」型のエンターテインメントがブレイクし、大きな注目を集めています。街からホームに撤退することで、かえって開かれた可能性について、牽引役の仕掛け人ふたりが語り合いました。

 記事を読む
記事を読む大人になって、「遊ぶ」ことがほぼ誰かと「お酒を飲むこと」になってしまって失望したことはありませんか? 本当に楽しんでいるときの遊びって、もっと自由に、まっすぐに、人目も気にせず夢中になれることなんじゃないでしょうか。もし昼の世界での肩書を捨てて、一人のプレイヤーとして真剣に「遊べる」ことができたら、それだけで世界の見え方はだいぶ変わるはず。そんな回路をこの社会に埋め込むため、全力で「遊び」を更新してきた〈遊び人〉の児玉健さんの活動と生き方を、改めてご紹介します。

 記事を読む
記事を読む今月から、僕がいま中高生向けに書いている本の、書きかけの文章をこのウェブマガジンに連載していきます。タイトルは『ひとりあそびの教科書』です。
みんなでワイワイ騒ぐのではなくて、孤独に世界と向き合うからこそ見えて来るものが、味わえる楽しさがある。この本は、僕が子供のころから続けてきた「あそび」を紹介することで、それらを伝えられたらと思っています。

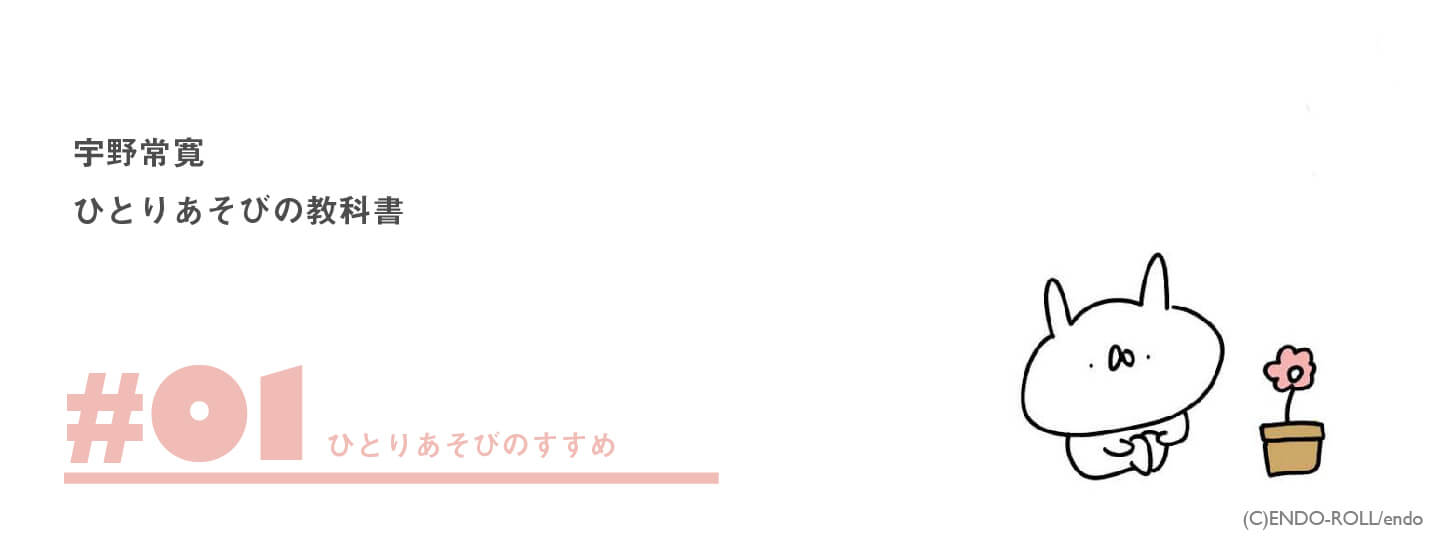 記事を読む
記事を読む都市集中型社会へのオルタナティブを作るプロジェクト「風の谷を創る」。この連載では、プロジェクトに関わる多彩なメンバーの横顔をご紹介していきます。
今回は、このプロジェクトを立ち上げたリーダーの安宅和人さんに改めて登場いただきます。科学者として、ビジネスマンとして「ニューロサイエンスとマーケティングのあいだ」で考え、実践してきた安宅さんがなぜ「風の谷」にたどり着いたのか。その原点から伺いました。
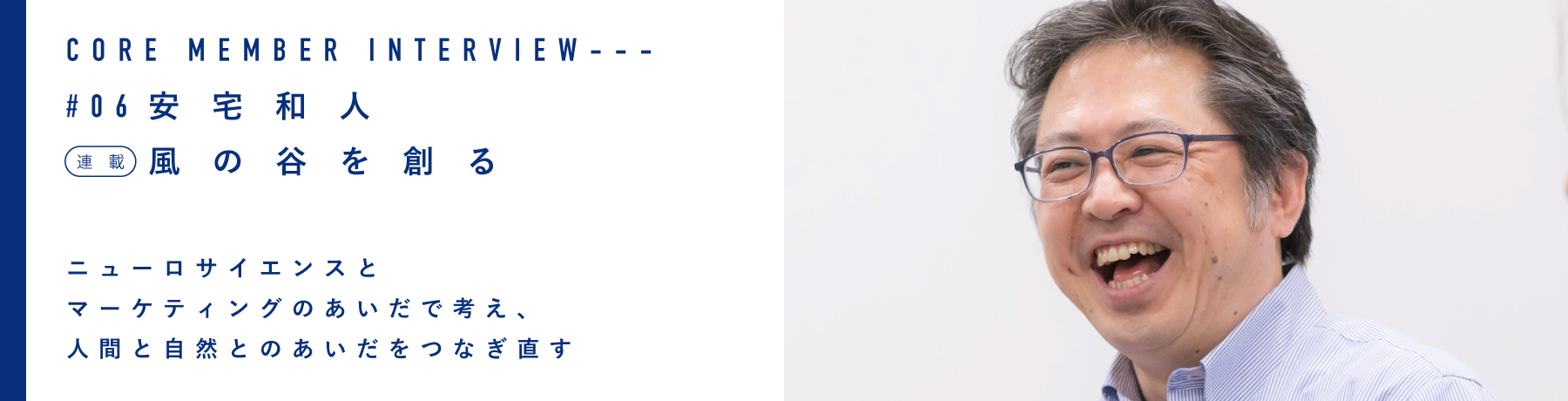
 記事を読む
記事を読むできるかぎり大きな視野で、できるかぎりゆったりした時間感覚で、「つくる」ということを考え直していくため、文筆家/キュレーターの上妻世海さんが、さまざまな知恵の持ち主たちを尋ねまわる連続対談。
都市史の探求から「生環境構築史」というアプローチに辿り着いた松田法子さんとの濃密な対話は、やがて地球全体の人口拡大が落ち着く未来に向けて、土地との関係を見直すことで、どんなライフスタイルや社会像が提案できるかの展望に向かっていきます。

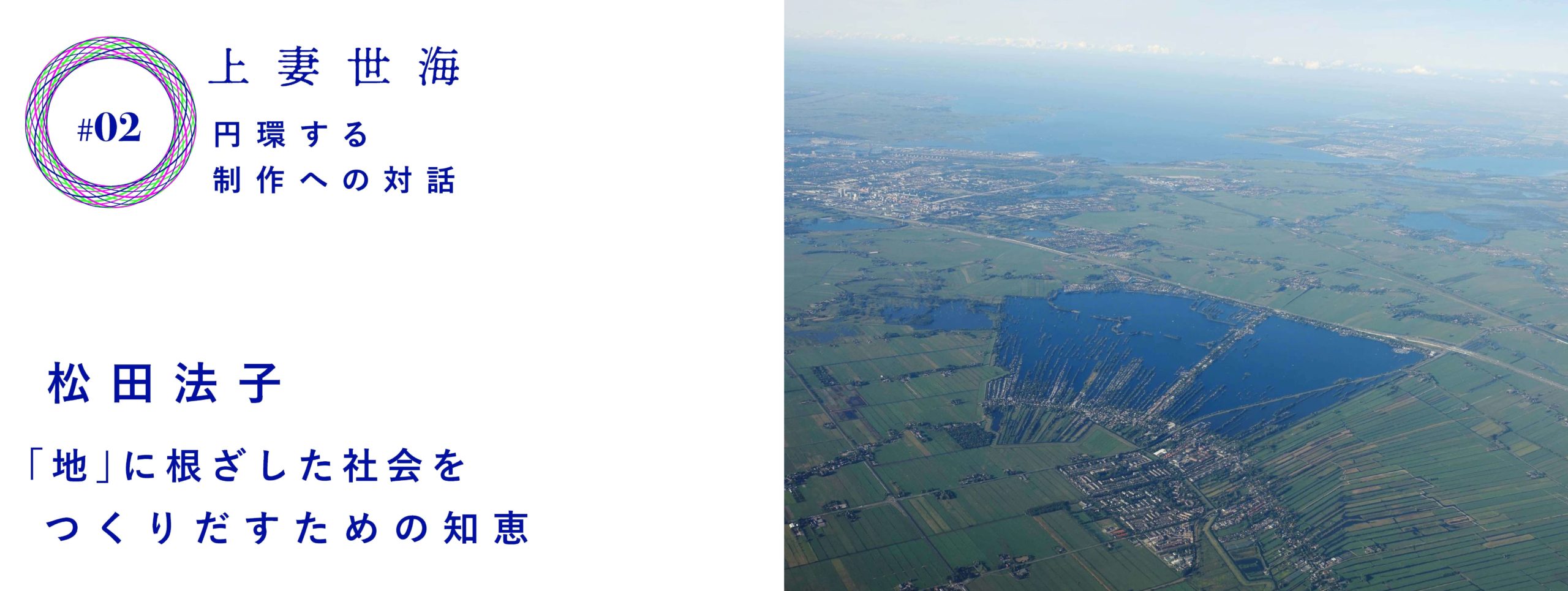 記事を読む
記事を読む今回取りあげるのは藤岡換太郎さんの『川はどうしてできるのか』です。世界中の川の成り立ちをわかりやすく解説した本書。川をよく下っているという井本さんならではの視点から、身近な「川」を知ることの豊かさを解説してもらいます。

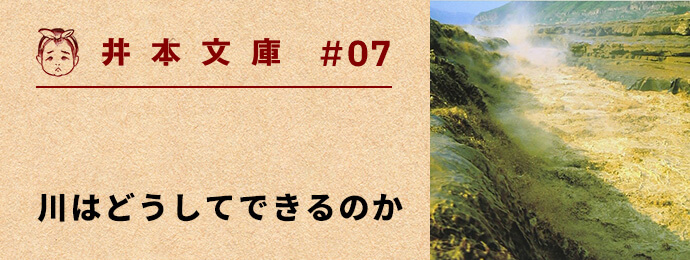 記事を読む
記事を読む