

これまでに更新した記事の一覧です。





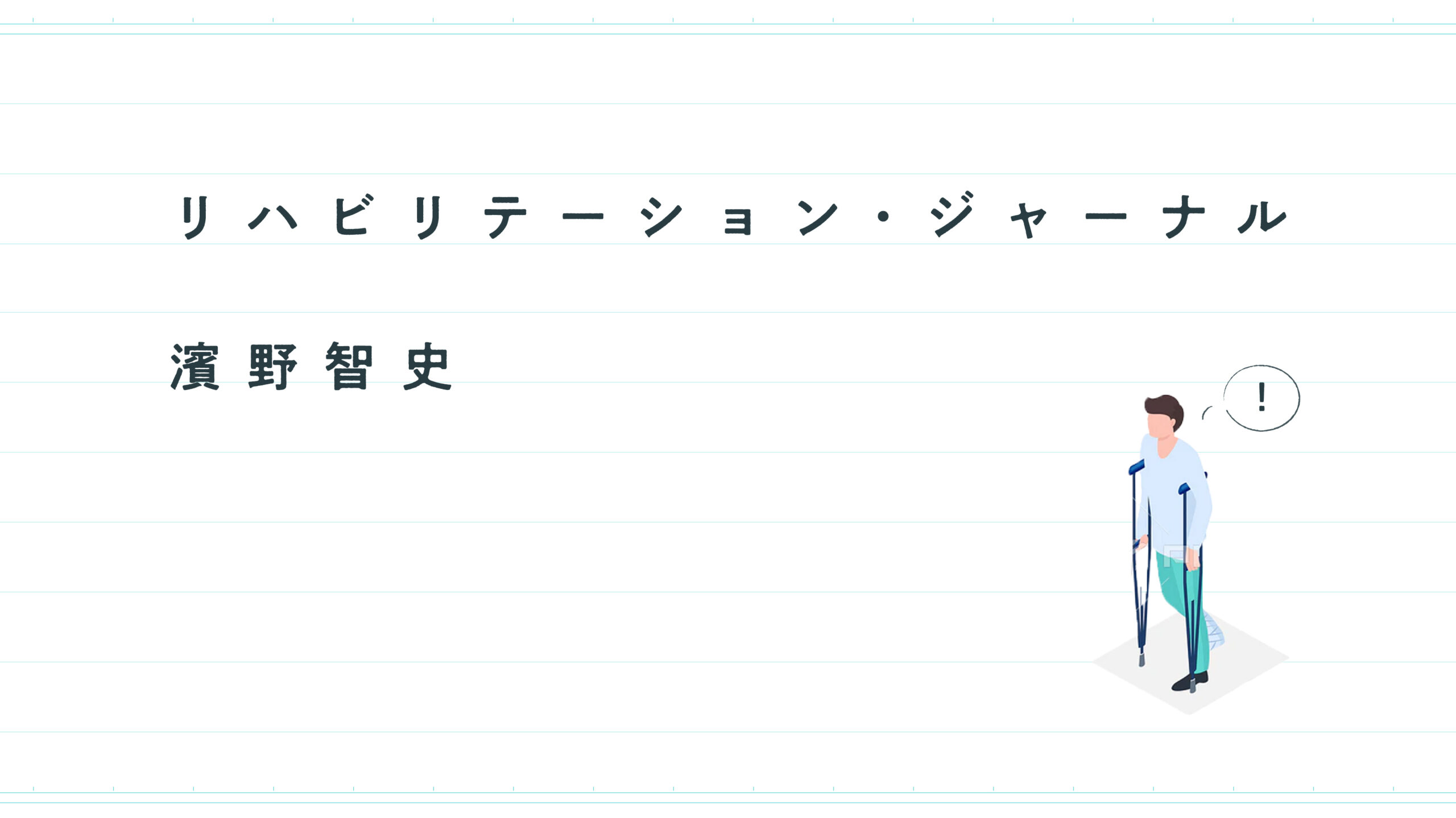

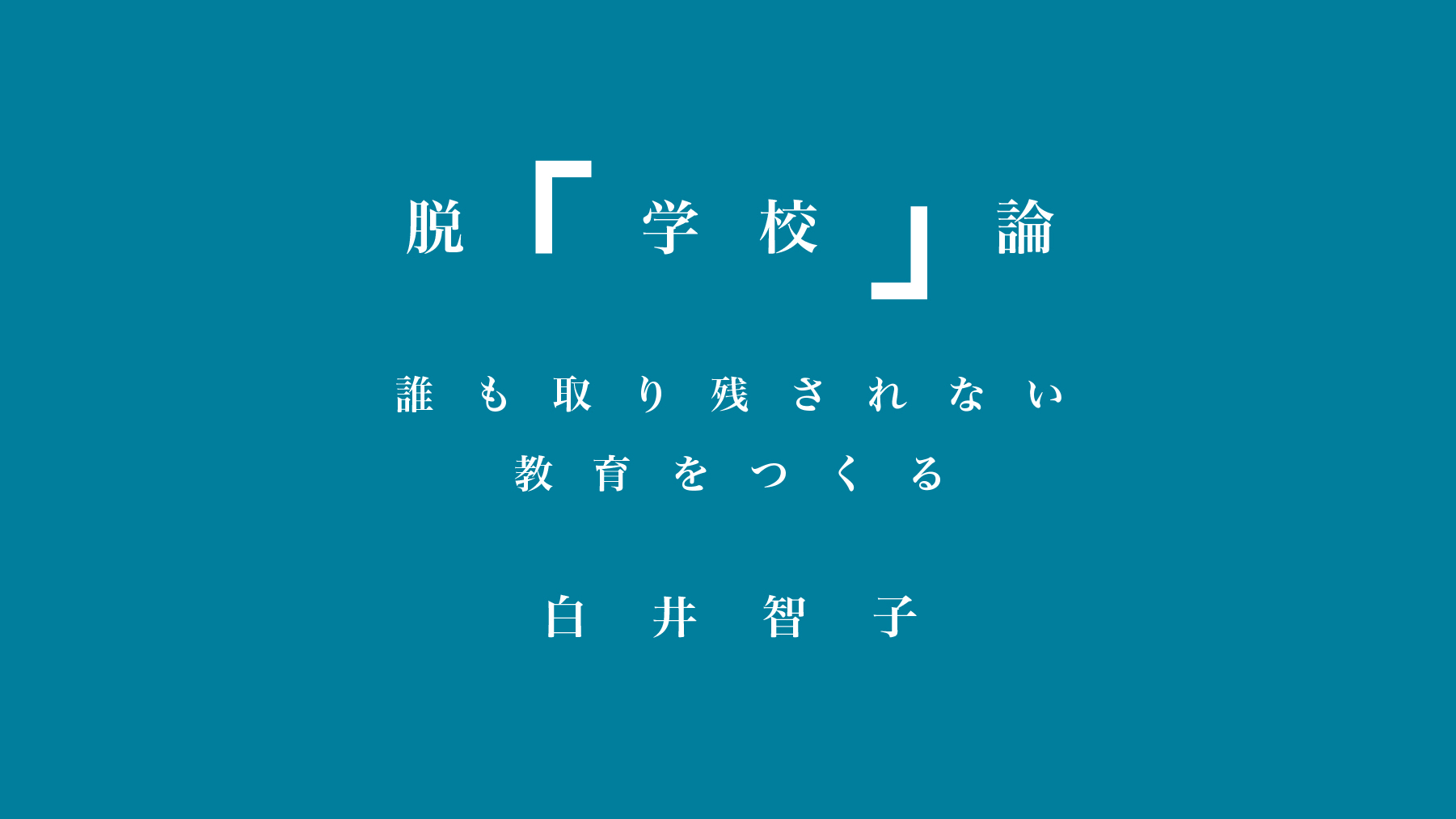






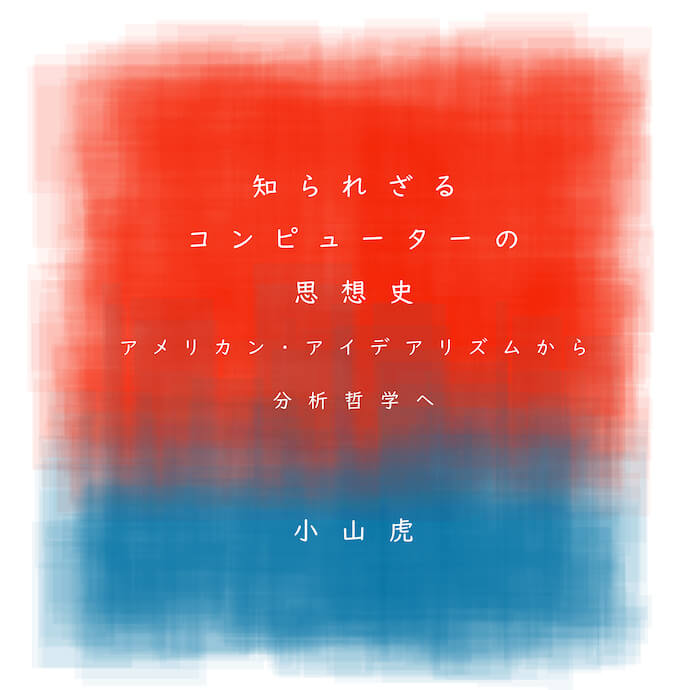



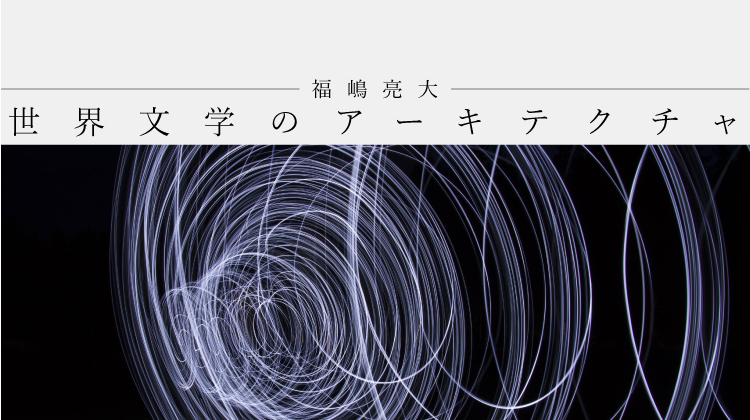
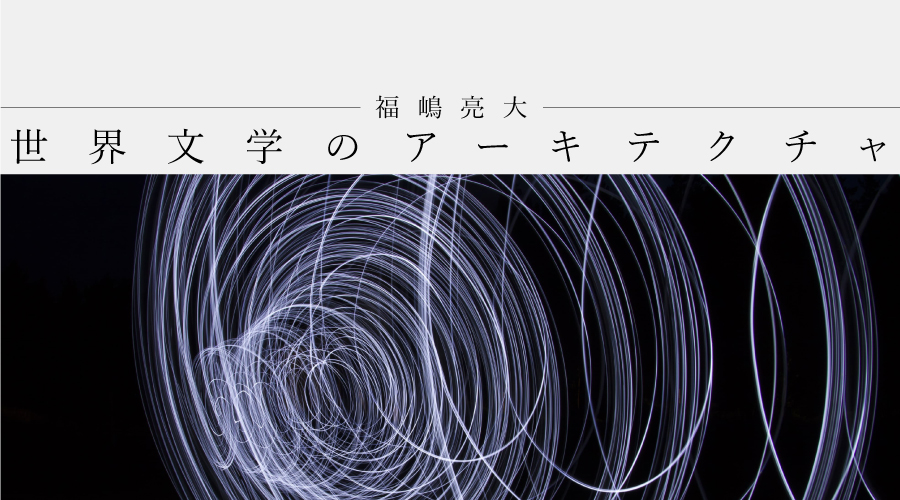

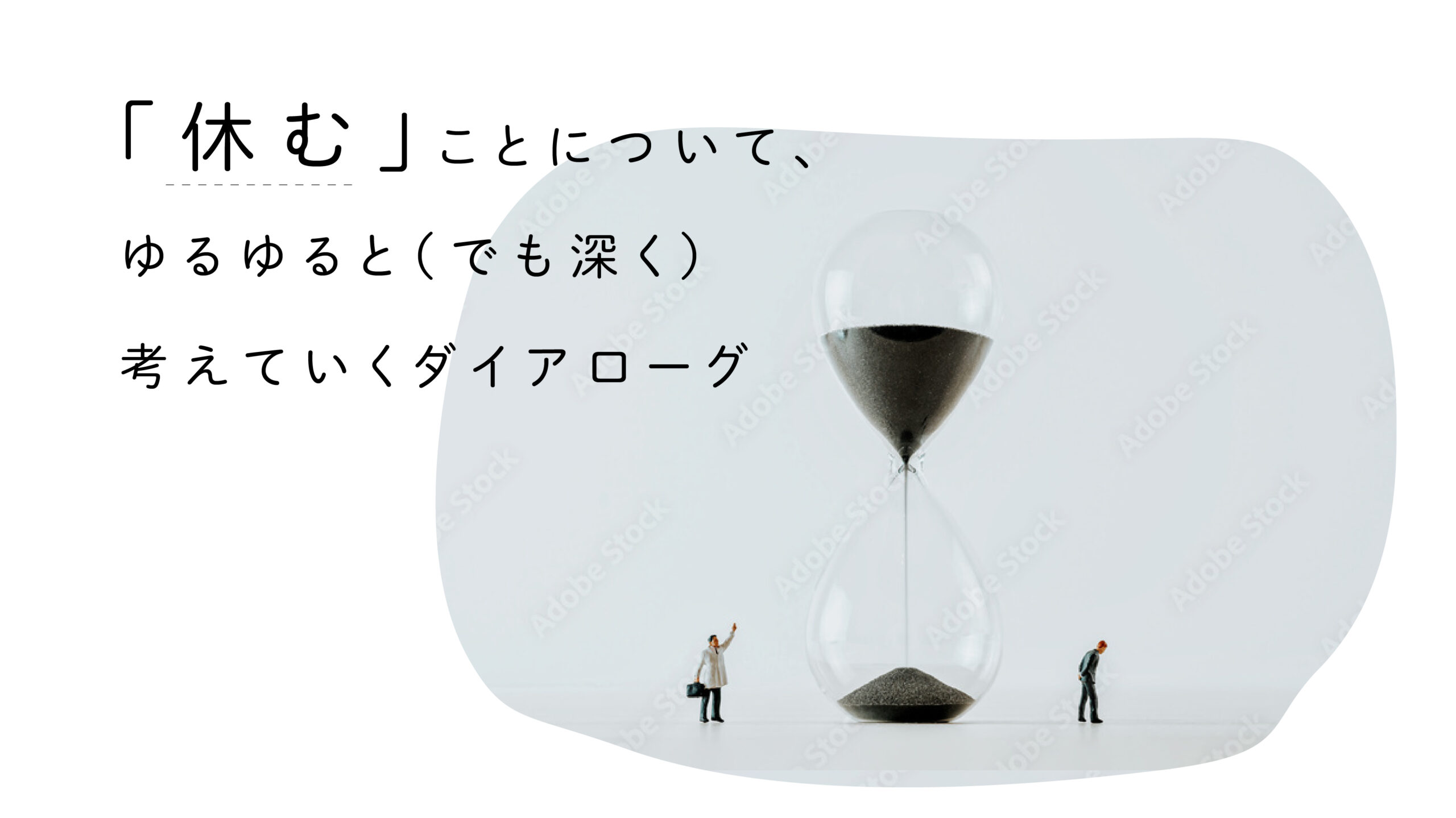




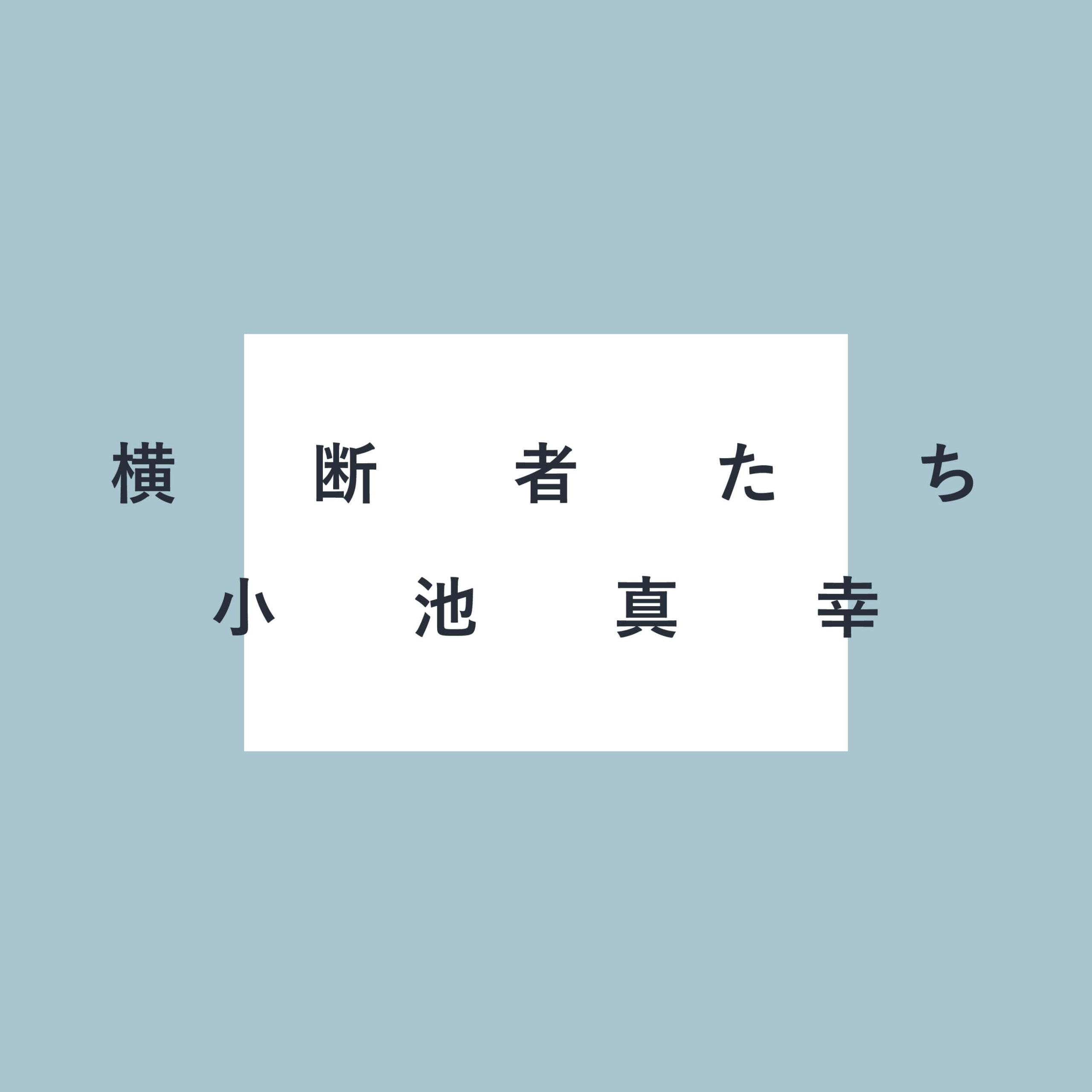
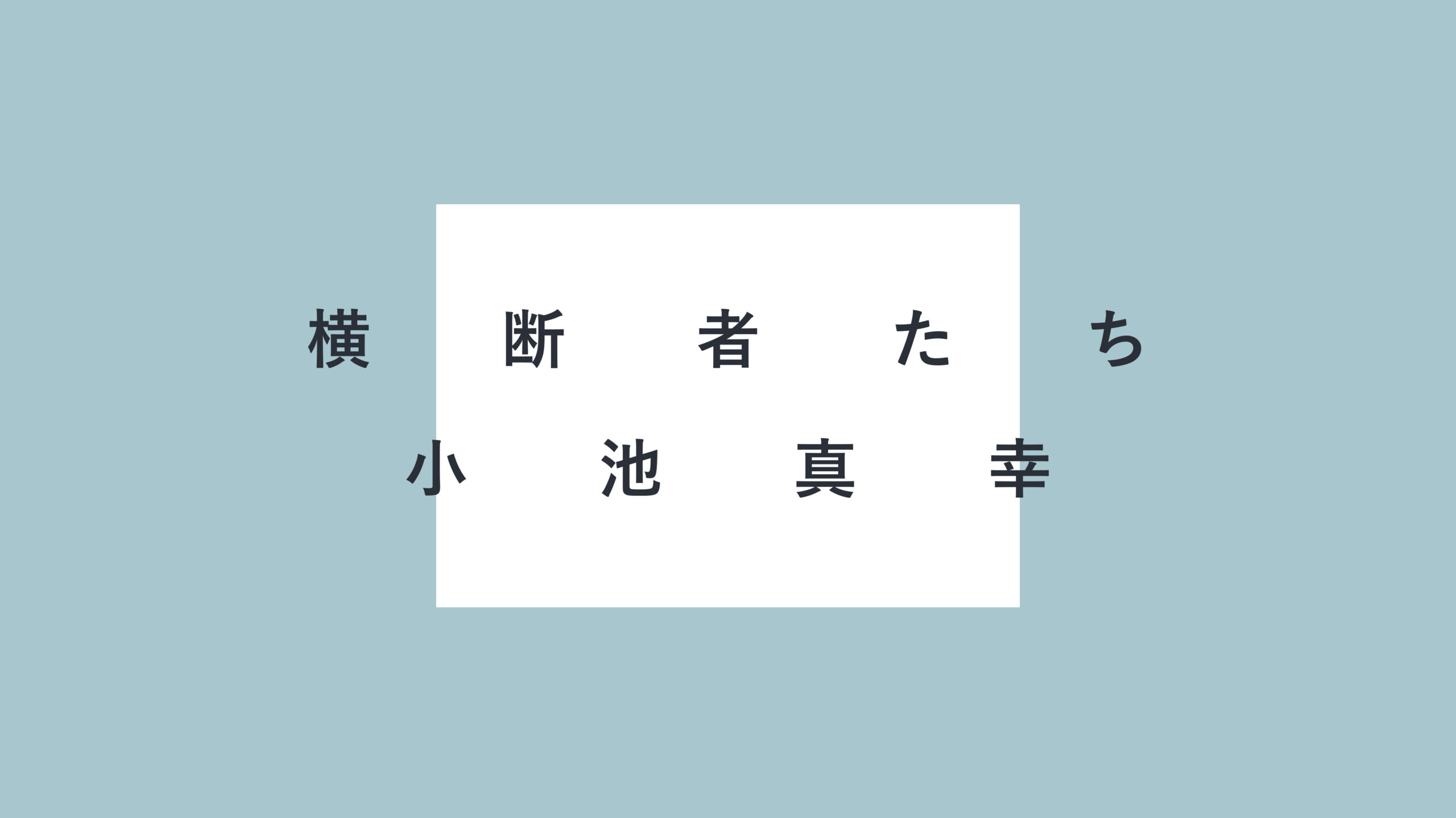


アート集団チームラボ代表・猪子寿之さんと宇野常寛の連続対談「連続するものすべては美しい」。今回は2020年7月から福岡に新設された常設ミュージアム「チームラボフォレスト – SBI証券」がテーマです。「捕まえて集める森」「運動の森」という、デジタルテクノロジーでできた2つの森が、ふだん現代人が忘れている感覚をどのように解放するのか、語り合いました。

 記事を読む
記事を読む「不要不急」の外出がはばかられる状況はまだまだ長引きそうで、特に苦しい立場に置かれている業界のひとつが、音楽や演劇といったライブエンターテインメントの世界です。先々の公演予定が真っ白になっていくなか、この危機を逆手に、リモート環境で観客を物語世界に巻き込んでいく「イマーシブ(没入)」型のエンターテインメントがブレイクし、大きな注目を集めています。街からホームに撤退することで、かえって開かれた可能性について、牽引役の仕掛け人ふたりが語り合いました。

 記事を読む
記事を読む大人になって、「遊ぶ」ことがほぼ誰かと「お酒を飲むこと」になってしまって失望したことはありませんか? 本当に楽しんでいるときの遊びって、もっと自由に、まっすぐに、人目も気にせず夢中になれることなんじゃないでしょうか。もし昼の世界での肩書を捨てて、一人のプレイヤーとして真剣に「遊べる」ことができたら、それだけで世界の見え方はだいぶ変わるはず。そんな回路をこの社会に埋め込むため、全力で「遊び」を更新してきた〈遊び人〉の児玉健さんの活動と生き方を、改めてご紹介します。

 記事を読む
記事を読む今月から、僕がいま中高生向けに書いている本の、書きかけの文章をこのウェブマガジンに連載していきます。タイトルは『ひとりあそびの教科書』です。
みんなでワイワイ騒ぐのではなくて、孤独に世界と向き合うからこそ見えて来るものが、味わえる楽しさがある。この本は、僕が子供のころから続けてきた「あそび」を紹介することで、それらを伝えられたらと思っています。

 記事を読む
記事を読む都市集中型社会へのオルタナティブを作るプロジェクト「風の谷を創る」。この連載では、プロジェクトに関わる多彩なメンバーの横顔をご紹介していきます。
今回は、このプロジェクトを立ち上げたリーダーの安宅和人さんに改めて登場いただきます。科学者として、ビジネスマンとして「ニューロサイエンスとマーケティングのあいだ」で考え、実践してきた安宅さんがなぜ「風の谷」にたどり着いたのか。その原点から伺いました。
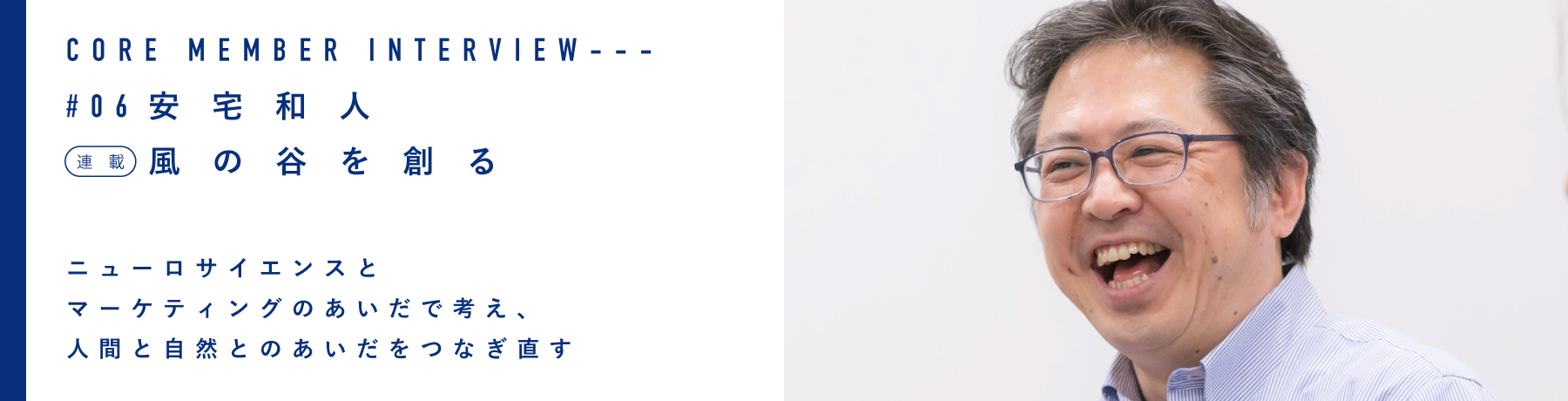
 記事を読む
記事を読むできるかぎり大きな視野で、できるかぎりゆったりした時間感覚で、「つくる」ということを考え直していくため、文筆家/キュレーターの上妻世海さんが、さまざまな知恵の持ち主たちを尋ねまわる連続対談。
都市史の探求から「生環境構築史」というアプローチに辿り着いた松田法子さんとの濃密な対話は、やがて地球全体の人口拡大が落ち着く未来に向けて、土地との関係を見直すことで、どんなライフスタイルや社会像が提案できるかの展望に向かっていきます。

 記事を読む
記事を読む今回取りあげるのは藤岡換太郎さんの『川はどうしてできるのか』です。世界中の川の成り立ちをわかりやすく解説した本書。川をよく下っているという井本さんならではの視点から、身近な「川」を知ることの豊かさを解説してもらいます。

 記事を読む
記事を読むできるかぎり大きな視野で、できるかぎりゆったりした時間感覚で、「つくる」ということを考え直していくため、文筆家/キュレーターの上妻世海さんが、さまざまな知恵の持ち主たちを尋ねまわる連続対談が始まります。最初の対話の相手は、都市や建築と大地との関係を「生環境」というアプローチから探求する松田法子さん。人類の文明やライフスタイルが、いかに地形や自然風土など土地そのものの力との相互作用でつくり出されてきたのかを、千年・万年単位の壮大な視野からとらえ直します。

 記事を読む
記事を読む20世紀末ボーイズトイデザインの変遷を振り返ることで、新たな“kakkoii”を探求する連載『“kakkoii”の誕生』。今回は『トランスフォーマー/リベンジ』以降の映画版トランスフォーマーシリーズが描こうとして挫折し続けてきた成熟のイメージを、「騎士」というモチーフを中心に論じます。

 記事を読む
記事を読む「もしよろしければ紹介しましょうか?」、「もしよろしければ紹介してください」と言ったものの、結局紹介に漕ぎ着けなかったことはありませんか?
今回はコミュニティ研究者の濱崎雅弘さんが、紹介・被紹介による「出会い」にまつわるコミュニケーションを考えます。紹介には、意外な心理的負担が隠されているようです。

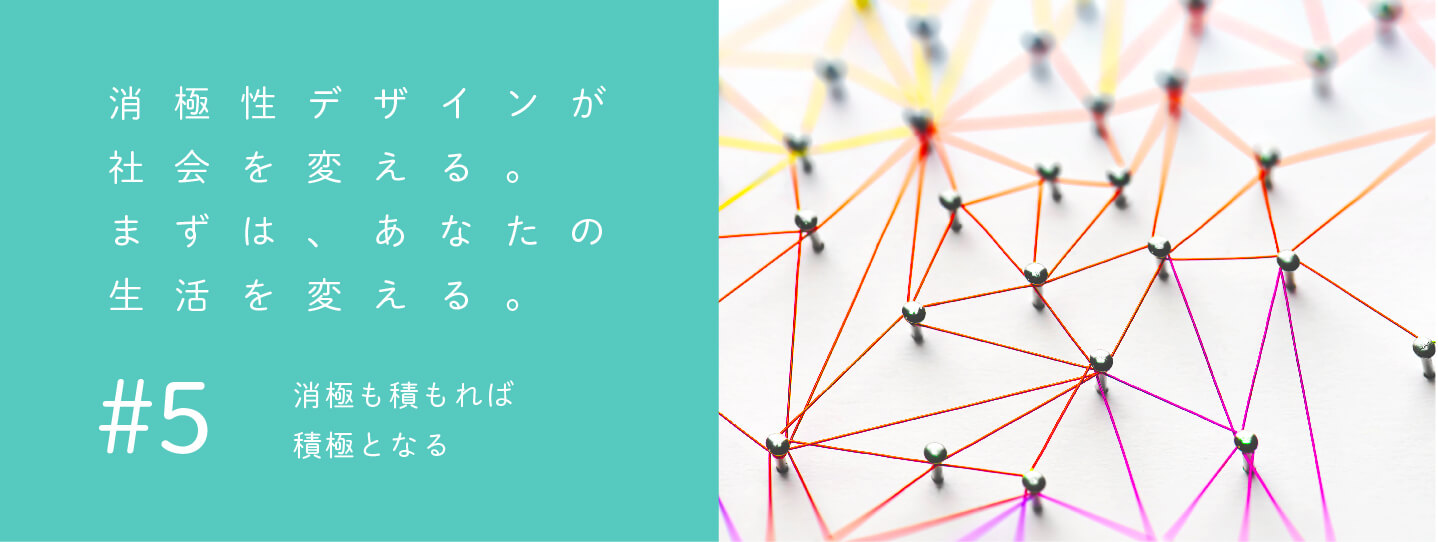 記事を読む
記事を読むさまざまな分野の知恵とテクノロジーを組み合わせて、人間が自然と共に生きるあたらしいかたちを模索するプロジェクト「風の谷を創る」。この連載ではこのプロジェクトに関わる多彩なメンバーたちの横顔を紹介していきます。今回は長年出版社でさまざまな編集に携わってきた岩佐文夫さんに、これまでのお仕事について、そして「風の谷」のこれまでの活動について伺いました。「編集者」から見た「風の谷」は一体どんな運動なのでしょうか?
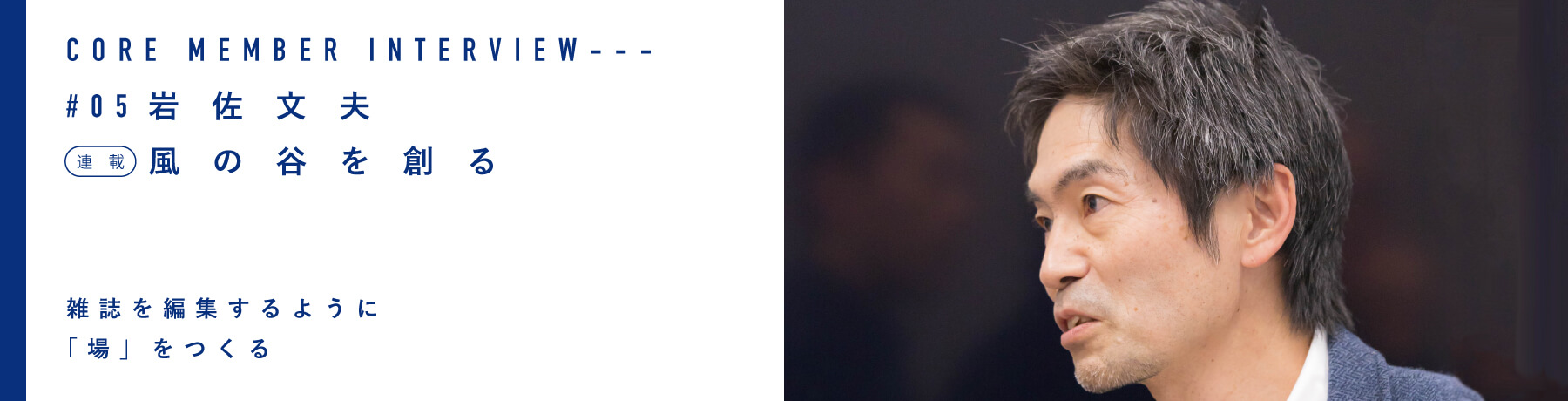
 記事を読む
記事を読む新型コロナウイルスの感染拡大によって、世界各国の社会体制が抱えていたさまざまな課題が、それぞれに顕在化しました。もちろん日本も例外ではありません。では、コロナ禍が浮き彫りにしたこの国の“ほんとうの問題”とは何なのか、LINEでの全国調査を手がけた宮田裕章さんに伺いました。どうすればこの危機を転機に変えていけるのか、諦めないための対話です。

 記事を読む
記事を読む